2024年12月16日、東京大学東洋文化研究所三階大会議室にて座談会「東アジアの思想文化を学ぶということ」が開催された。
この座談会は、同時期に東京大学大学院人文社会系研究科東アジア思想文化専門分野で学んだ卒業生である姜智恩氏(台湾大学国家発展研究所)、高山大毅氏(東京大学大学院総合文化研究科)、平澤歩氏(東京大学大学院人文社会系研究科)、田中有紀氏(東京大学東洋文化研究所)が集まり、「東アジアの思想文化」専門分野における学習と研究について語った。当時助教を務めていた水口拓寿氏(武蔵大学)もスペシャルゲストとして登壇した。開催形式はZoomを併用したハイブリッド型であり、当日の出席者はオンライン参加者を含めると50名を超えた。「東アジア思想文化」専門分野の学生たちも積極的に参加した。
司会の田中有紀氏は、「いま学生にお勧めしたい本の紹介」「影響を受けた研究」「博士論文までの道のり」という3つのテーマを設定して、対話を進めた。登壇者は自分の専門から、様々な思いや経験を語り、後輩である参加者たちにとっても非常に参考になった。
姜智恩氏は、教員が本を勧めるよりも、自分で本を捜して読むことが大事だと述べた。まず自分の興味があるテーマによって本を探して、参考文献の中の面白そうなものをピックアップして読む。絶対に読まなければならない本というものは存在しない。本を読む時、鵜呑みにするよりも批判的視線で見て、偉い先生であっても間違っているところを探し、自分に似ている考え方があれば自分の独自性はどこにあるかを考えるという方法を勧めた。
高山大毅氏は、三人くらい尊敬する研究者を見つけることを勧めた。そこから自分のオリジナル性が出てくるためである。日本思想を専門としているため、法学部との繋がりが強く、また西洋哲学の知識も必要となるため、特に両分野の本を推薦した。
平澤歩氏は、学生時代の様々な経験を語った。授業以外にも、先輩や同級生と学び合うことも大事である。漢籍コーナーで勉強している時に偶然出会った人からの指摘や、仏教やイスラム教など他の専門の先輩・友人とのお茶会なども非常に勉強になったという。研究室で先生と雑談した内容も博士論文の執筆へと繋がっていった。

田中有紀氏は、博士課程期間に北京大学に留学した経験を語った。学生の主催する読書会では、原文を読むのが早く、一回さらっと音読してからすぐに哲学的な議論に入ることに驚いたが、一生懸命準備することで、少しずつ自分の意見を発言する勇気が出てきた。中国の学生は、自分の中に「問い」を持っている人が多く、中国思想を現代社会に生かそうとする使命感を持つ人が多いなど、多くのカルチャーショックを受けながら、自分の研究に取り入れていったという。

スペシャルゲストの水口拓寿氏は、古典に依拠したもの・堅実で優れた先行研究・指導教員が若い時に出した単行本の研究書という三つのグループの本を読むことを勧めた。そして、一対一の形式に限られない多元的な議論の場にたくさん参加することの重要性を指摘した。
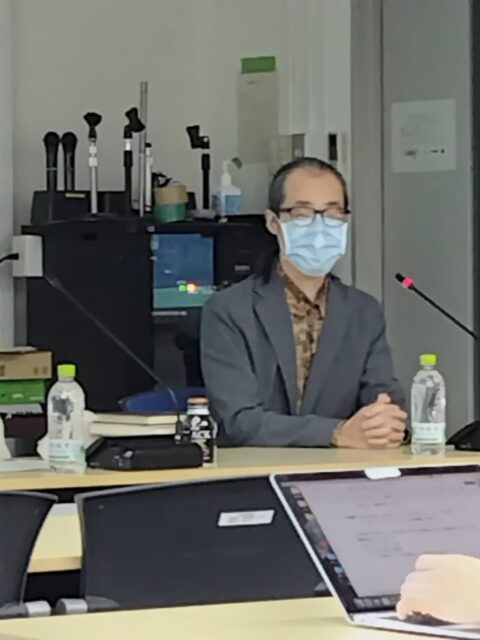
「博士論文までの道のり」についての議論では、先に計画を立てて器を満たすように博士論文を書くタイプと、とりあえず面白い問題だけを書いて、後ほどその問題に通底する共通性を見つけて博士論文にまとめるタイプが紹介された。博論執筆にあたり、どちらも可能な道である。
今回の座談会で、東アジアの思想文化専門分野の先輩たちによる、学習の様々な経験・感想を聞くことができた。参加した学生たちにとって、先輩の学習の道や悩みを解決する方法を知ることは、自分の勉強・研究に貴重な示唆となる。先輩から後輩へ、知識だけではなく、学問の伝統が受け継がれていくことを改めて感じられた。
奉告者:呉雨桐(EAAリサーチアシスタント)








