「石牟礼道子の世界をひらく」というイベントタイトルを見返したとき、言葉に素直であろうとすれば、いくつもの問いが浮かんでくる。「石牟礼道子の世界」とは、あらためてひらかれねばならないものなのか。それは閉ざされているのか。そもそも「石牟礼道子の世界」とは何か。いわゆる「作品世界」のことなのか、それとも別の意味があるのか。「世界」とは何を意味しているのか。私たちにとって「世界」とは何か――。
こうした根本的な問いが問われるに至ったのが、今回の「石牟礼道子の世界をひらく」というオンラインワークショップであった。最後の問いは実のところ、総合討論においてEAA院長の中島隆博氏(東京大学)から発せられたものである。そしておそらく、こうした問いも含め、あらためて言葉を交わし思索することが、「世界をひらく」ことになるのだ。ここで「ひらく」というのは、閉ざされたものを開放するというより、むしろ「世界」なるものを引き受けつつ、語り直し作っていくという、「開拓」のイメージに近いだろう。私たちの現在地点をそのようなレベルで確かめる、それほどの意義がこのワークショップにはあったと思う。

ウェビナー画面(上段右:張政遠氏、左:宇野瑞木氏/中段右:石井剛氏、中央:中島隆博氏、左:髙山花子氏/下段:右・前島志保氏、(中央:鈴木将久氏)、左:山田悠介氏)
初めに中島氏から開会挨拶として、石牟礼道子の作品をどう読むかについては、これまで駒場で何度も取り組みがあったこと、そして今般のCOVID-19の流行に接して、水俣病事件という未曽有の事態を私たちにとっての根本的で普遍的な問題として捉え言葉にもたらした石牟礼の作品から学ぶことは、ますます必要となっているのではないかということが語られた。
そもそも今回のオンラインワークショップは、突発的に開かれたものではなく、6月以来5回の研究会(詳細はこちら)を経て開催されたものである。その研究会と今回のワークショップを中心となって企画・運営してこられたEAA特任研究員の宇野瑞木氏(東京大学)、髙山花子氏(東京大学)からは、世界文学としての石牟礼の文学の普遍性と、同時にその翻訳の不可能性を引き受けながら、どのようにそれを読み広げていくことができるかという、一貫した関心の在り処が語られた。「石牟礼研究」として専門的に読み解くというより、様々な専門から寄り集まって、共に考えるということが主旨である。「ひらく」という語には手遊びのイメージも込められている、という説明が印象深かった。
――基調講演(張政遠氏)――
この「ひらく」ということに関して、また冒頭で触れた「世界」に関して、張政遠氏(東京大学)の基調講演は示唆的であった。「道の研究――わき道・被災した道・巡礼の道」と題された講演は、まさに交錯したいくつもの道を辿るように、様々な場所・話題に触れつつそれらをつなぐ道を示すものであった。これが、石牟礼の作品を単に分析するのではなく、私たち自身そのテクストを読んで思考するための導きになったと思う。
「わき道」に関しては、和辻哲郎の『古寺巡礼』から思索が展開された。和辻にとっては哲学が「本道」、文化研究や小説の創作などが「わき道」となるのかもしれないが、しかし一方が他方の上に位置づけられるといった序列化はおそらく不適当であって、重要なのは「精神」「感覚」などと明確に分けられる以前の、根源的な感覚のレベルを彫琢することなのだ。
道を歩み巡礼するということは、そうした次元での思索、そして実践に参与することである。ここで見逃すことができないのは、私たちは道において様々な他者と関わる、ということだ。そこには過去の他者も含まれる。巡礼には、土地に眠る記憶を繰り返しよみがえらせるという意義があるのだ。それがとりわけ、被災地を歩くときに際立ってくるということを、張氏はご自身の「巡礼」の体験から語られたのだった。
石牟礼にとって、あるいは石牟礼の作品を読む私たちにとって、この「道」の問題は非常に大きな意義を持つ。今日の私たちは道を、単なる交通経路としか見なさないかもしれない。実際、そのような道が整備されたことは、チッソの隆盛とともに水俣の自然が破壊されていったことと軌を一にしている。だが石牟礼は、道の本来の姿を「花の道」という言葉のもとで見て取ろうとする。石牟礼の生まれた家がそもそも石工であり、道路整備にたずさわっていたわけだが、かつては道が華やぎの場だったのだ。そして、石牟礼にとっては文章を書くこともまた、様々な人が行き交い語り交わす「道」をつくることだったのではないか――そのような考察が展開された。
そうだとすれば、私たちが石牟礼の作品を読むということは、道を歩むことと類比的に考えられるだろう。張氏は、巡礼のパフォーマンス的側面に着目して “performance philosophy” の潮流を紹介されていた。その「パフォーマンス」は作品を読むことにも敷衍されうるだろう。ただし石牟礼の「道」は、単純に「花の道」なのではない。なぜなら石牟礼を含めて私たちはすでに、近代的な「道」と無縁ではいられないからだ。それは業のようなものですらある。だがおそらく、コメンテーターの前島志保氏(東京大学)が指摘されたように、様々な道が開かれている、ということが重要なのだ。一つの道ではなく、わき道を探りながら歩むということが、私たちにとって重要な意義を持つ。そうした可能性に開かれているということが「世界」の豊かさを確保するのだと言えよう。

――パネル発表――
続いての三名の発表は、いずれも特に「言葉」の成立条件ないし「言葉」の限界といった事態に注意を向けつつ、石牟礼のテクストを検討するものであった。ここでも、私たちはどのように石牟礼の記した言葉を読み、それに応答して語ることができるか、という反省的な問題意識が全体を貫いていることは、あらためて指摘しておくべきだろう。
髙山氏の発表では「声が歌になるとき――『苦海浄土』の音響世界」と題して、音・声・歌がどのように『苦海浄土』で言葉にもたらされているかが論じられた。石牟礼自身があるエッセイで人々の「歌う心」に関心を寄せ、それが失われつつあることを嘆いており、たしかに『苦海浄土』にもそうした「歌」に耳を傾ける姿勢が見て取れる。なかでも第二部のクライマックスでは、チッソの株主総会に患者たちと共に乗り込んで「ご詠歌」を唱和し、一種荘厳な舞台を現出させるのであるが、ここで私たちが気を付けねばならないのは、石牟礼が単に「歌う心」とその喪失とを対比しているのではなく、近代的な「騒音」も含めて、なにか新しい音の響き合いに対する聴覚を自ら持とうとしていることである。そこには、異他的な音声を重ね合わせる、仏教的な「声明」のような側面があると言えるかもしれない――これは総合討論を通じて展開された点でもある。『苦海浄土』のなかにそうした多声性を見出すことが髙山氏の読解方法であるわけだが、それはまさに、テクストによって可能になる音や声の響き合いに耳を澄ませる、という態度なのであろうと思われる。これは私の勝手な連想に過ぎないが、「反対するものが協調する、そして異なる(音)から最も美しい音調が生じ、万物は争いによって生まれる」という古いヘラクレイトスの箴言が予言のように思い起こされた。
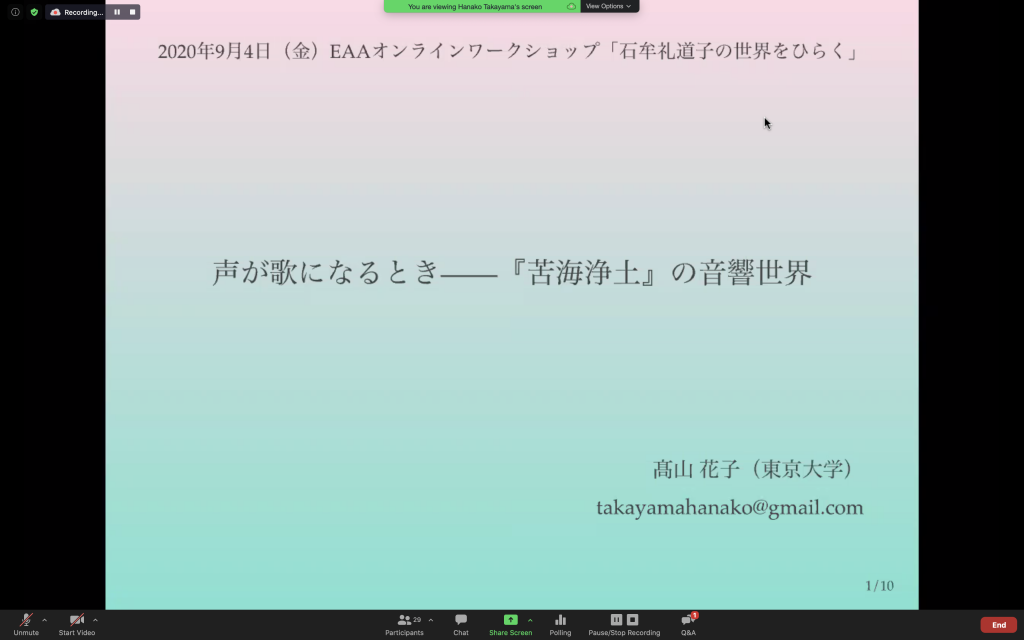
山田悠介氏(大東文化大学)には既にエコクリティシズムの観点から石牟礼の文学を取り上げ、特に「反復」のレトリックに着目して分析された著書があり(『反復のレトリック:梨木香歩と石牟礼道子と』水声社、2018年)、これまでの研究会でもそこから学ぶところが大きかった。今回の「「多重化」のレトリック――石牟礼道子『あやとりの記』から」と題された発表では、『あやとりの記』(幼少期の石牟礼の体験をもとにした物語であり「クリエイティヴ・ノンフィクション」とも呼ばれる)を題材に、その語りの構造と、場所の語られ方について綿密な分析を展開し、どのようにして物語が成立しているのかが論じられた。とりわけ興味深く思われたのは、自然の対象や場所についての表現が、テクスト上で様々な語り手の口をわたるように継承されているということ、そして自然ないし「場所」が、もはや単なる「背景」でも「客体」でもなく、むしろ物語の中心を占めて語り手たちを従えているという構造である。私たちはここに、言葉を介して「世界」につながるという可能性を見出せるのではないか。その場合、「世界」とは空虚で形式的な容れものではなく、自然と人間との関わりが具体的な記憶として蓄積した、固有の場所として考えられねばならない。山田氏がさらに提起された、石牟礼文学において「むかし」を語るとはどういうことか、という問いは、創造的でありながら回顧的でもある、そのような「世界」との関わり方を示唆しているように思われる。
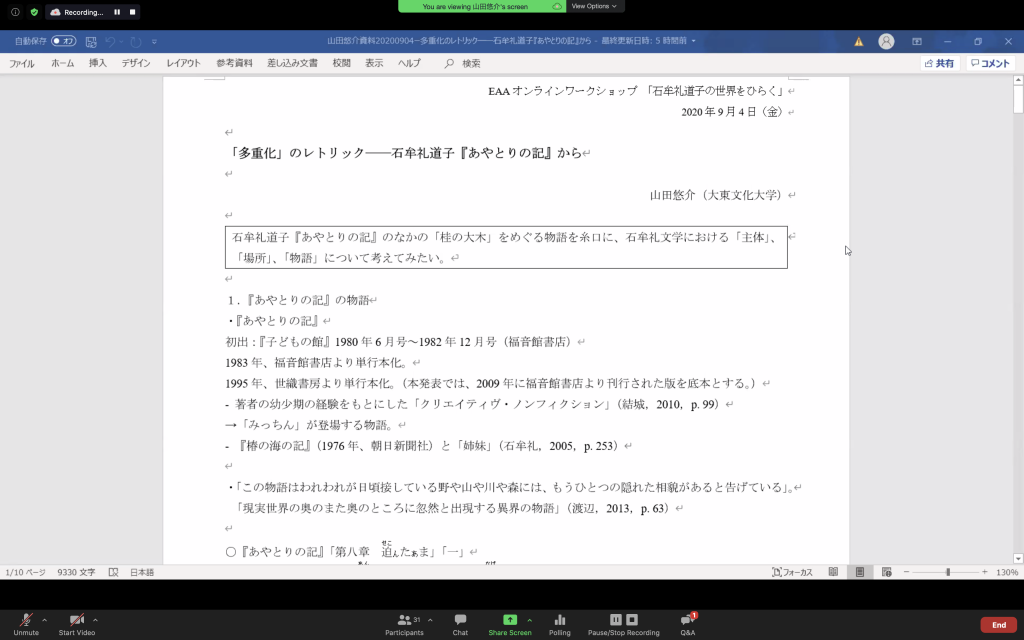
宇野氏の発表は「『苦海浄土』における古代的形象の意味」と題して、その題の通りテクスト冒頭にあらわれる「椿の古樹」から末尾の「古代の巫女のよう」と形容される女性の姿にいたるまで、『苦海浄土』においてどのように古代的なものがあらわれ、意義を担っているのか、それを考察するものである。ただし重要なのは、テクストの内在的な分析のみならずその成立史を踏まえて、どのように石牟礼の「古代的なもの」との関わりが成り立っているのかを検討している点であろう。たしかに石牟礼は自ら、水俣病患者の魂が「わたくしの中に移り住んだ」と記すように、巫女的な語りをものする。ただ一方では、『苦海浄土』の成立以前に水俣病事件の発生と経過を年代的・論理的に記録した文章を書いており、また古老の話を聞いてそれを郷土史に練り上げるという主旨の連続座談会にも参与している。いわゆる巫女的な語りが石牟礼の特徴であったとしても、それは数あるなかから自覚的に選び取られた方法であると考えられるのだ。またそこには、中近世の「語り物」との親近性も見いだされる。それは石牟礼が『苦海浄土』という作品を、自らに語り聞かせる「浄瑠璃のごときもの」と述懐していることにも認められるが、同時に彼女の目指すところが、死者たちや言葉を奪われた者たちの声を生者の世界に響かせることであったことを顧みれば、それが琵琶法師の語りに非常に接近することは疑い得ない。これは髙山氏が論じられた「音」の問題にも関わる。石牟礼は、死者の声をよみがえらせつつも、決して生者の秩序に取り込むことなく、むしろ異他的なものとして響かせるのである。こうした「多声性」についての洞察は、テクストの分析にも絡んでくる。水俣病患者との最初の邂逅ともいえる場面において、作品冒頭で海や古樹に託して語られた風景が、「わたくし」の語りとして反復的に語り直されるのである。
多声性は、しかも最後に、読者である私たちに開かれる。『苦海浄土』第一部の最後は、両親を急性劇症型の水俣病でなくし、やはり水俣病による歩行失調を抱える弟を世話する女性が「草いきれのたつ古代の巫女のように、彼女はゆらりと立ちあがる」と形容され、遅ればせの見舞いに訪れたチッソ社長の手土産のようかんを切り分け「はい、どうぞ」と差し出す場面で終わる。その台詞のあとに地の文はなく、いかにも唐突に終わった感がある。しかしこれはおそらく、読者の私たちに「はい、どうぞ」と何かを託す言葉でもあるのだ。
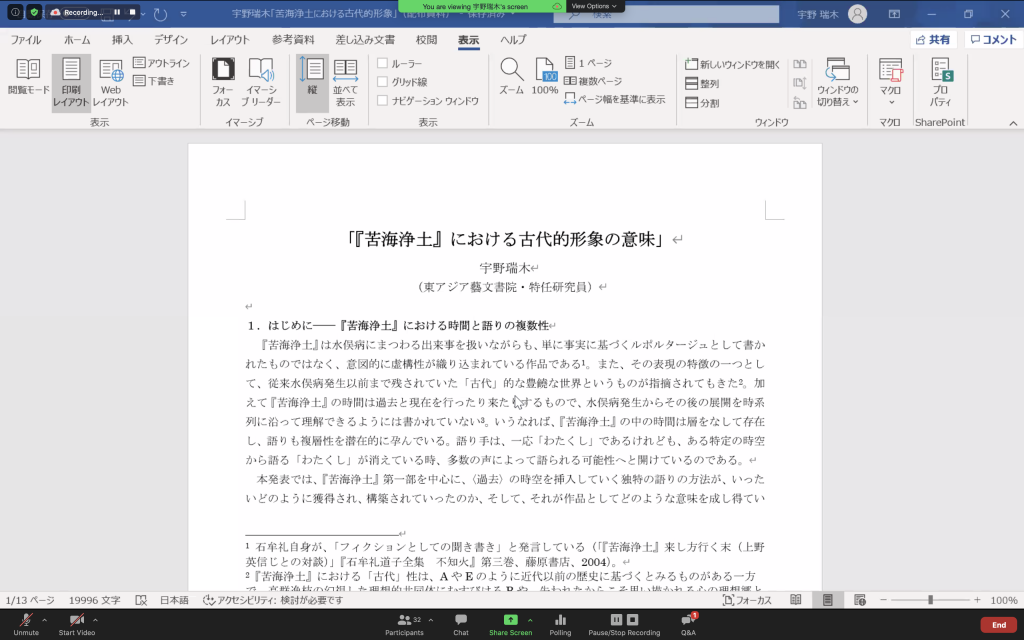
既に質疑の内容も踏まえた形でまとめてしまったが、コメンテーターの鈴木将久氏(東京大学)、前島志保氏(東京大学)からのコメントをあらためて振り返り、そこから展開した話題を簡単に補っておきたい。
鈴木氏からはまず、石牟礼の表現の導きとして、谷川雁の存在が大きかったであろうことが補足された。しかし谷川の求める集団性と、石牟礼の考えるそれとの間にはおそらく差異がある。このあたりに注意を払わねばならない。そのうえでの問いとして、第一に言語以前の「音」の経験を、それでもなお言葉に(とりわけ文字に)するということはどのような意義をもつのか、第二に「むかしを語る」ことと、何らか人間の関係性をつくるあるいは取り戻すということにはどのような関わりがあるのか、第三に「古代」というとき、時間的な広がりのみならず、国境線をやすやすと超えるような空間的広がりをどのように考えるか、といったことが挙げられた。特に「古代」に関して宇野氏から、それが「古典」という権威的なものとは区別されているようだ、という応答があったが、この点も非常に興味深い。

前島氏からは、ご専門がジャーナリスティックな文章を扱うものであることを踏まえて、そうした言葉が扱いきれないような事態に面し、どのような伝え方が可能であるのかということが石牟礼の作品を読むなかで考えさせられることである、ということに加えて、次のようなことが指摘された。第一に、声や音の問題はまさに今日の私たちの生き方を見直す観点となりうる、例えばちょうどNew York Public Libraryでは、コロナ禍以前のサウンドスケープを公開するという企画を行っていたが、ひょっとすると私たちはまさに新たな聴覚の涵養を求められているのかもしれないということ、第二に『あやとりの記』における語りの主体の多重性の分析は、おそらく『苦海浄土』に関しては、患者の言葉にならぬ言葉を聞き取るという営みに通ずるものであろうということ、第三に石牟礼の語りの「語り物」的性格は、しかし一方で中世の語り物とは異なる点があるだろう、それはまさに多声性のあり方に関わっているのではないか、といったことである。実のところ、『苦海浄土』第一部末尾の台詞については、前島先生の指摘から、私たちへの問いかけとしても受け止められるだろうという話が展開されたのだった。

*****
コメンテーターの先生方への再応答、その後のフロアとの質疑も含めて、報告しきれぬほど話題は広がりと深まりを見せた。この報告の冒頭に「石牟礼道子の世界をひらく」とはいかなることであるのか、という問いに触れたが、これに関して、司会のEAA副院長である石井剛氏(東京大学)が会の最後にコメントされたことを紹介しておきたい。即ち、石牟礼は彼女の言葉によって、私たちに対してある世界を開いてくれている――それが『苦海浄土』第一部の「はい、どうぞ」という結びに示されている――のだが、私たちはここで、石牟礼から贈り届けられたものを受け止め、あらたに世界を開きつつある、道を作りつつあるのである。世界をひらくとは実に、道を歩むことに他ならない。それは単に定められた道に従うことではないが、しかし放縦に新奇なものを作ることでもない。むしろ先蹤を認めながら、わき道を発見しつつ行き交い、そのような交流の道筋をつけることなのであろう。私としては石井氏の司会をはじめとする「導き」のおかげで、この会のあいだ複雑な道を歩みながらも、道に迷うことなく共に歩みおおせたように思う。ここでの報告もすでに、そうした導きのもとで追思考したことに他ならない。もちろん、同道しながら何を考えていたかということは、それぞれ別個に抱えるべきものであろう。
報告:宮田晃碩(東京大学大学院博士課程)








