2020年7月20日(月)15時より、Zoom上で、第3回石牟礼道子を読む会が開催された。発表担当者は宮田晃碩氏(東京大学大学院博士課程)で、石井剛氏(東京大学)、鈴木将久氏(東京大学)、前島志保氏(東京大学)、張政遠氏(東京大学)、山田悠介氏(大東文化大学)、宇野瑞木氏(東京大学EAA特任研究員)、建部良平氏(東京大学大学院博士課程)、報告者(髙山花子、EAA特任研究員)の計9名が参加した。
宮田氏の選んだサブテクストはつぎの3つである。
・佐藤泉(2013)「『苦海浄土』のさまざまな「栄耀栄華」:「聞き書」の主体とはだれであるのか」『敍説Ⅲ』09.
・早川敦子(2019)「越境する「命」の神話:石牟礼道子と翻訳の不/可能性」『津田塾大学紀要』第51号.
・水溜真由美(2005)「石牟礼道子と水俣:ゆらぐ〈共同体〉像」北田暁大、野上元、水溜真由美編『カルチュラル・ポリティクス 1960/70』せりか書房.
まず、佐藤論文の丁寧な読解にもとづいて、『苦海浄土』が近代の経済成長の価値観になじまない筆致で描かれており、発表当時の文壇の政治と文学をめぐる議論から渡辺京二によって「私小説」と位置づけられると同時に個人的な「私」の概念の問い直しが生じており、『サークル村』の集団的な活動と「聞き書」自体が聞くことと語ることの単純に二分できない行為によって成り立っている、という論点整理がなされた。直後の質疑応答では、近代ジャーナリズムの成立以降の報道の文法と文学との分離との関連や、漢文学が排除されてゆくなかで「文学」と呼ばれるものが一体どういったものを指すようになったのか、について文学史的な質問がなされた。さらに、報道におけるフィクションの登場と関連して、「わたしたち」という概念に包摂されている同質性の前提が指摘され、そういった「わたしたち」と思えるものを越えてゆくものはないのかと問いかけがなされた。また、当時のアジア・アフリカ文学への世界的な関心と同期していることや、必ずしも日本人としての集団ではない集団の問題が描かれていること、文学の脱政治化の不可能性、経済的共同体のようにグローカルな国家を越えるものとの関連が指摘された。
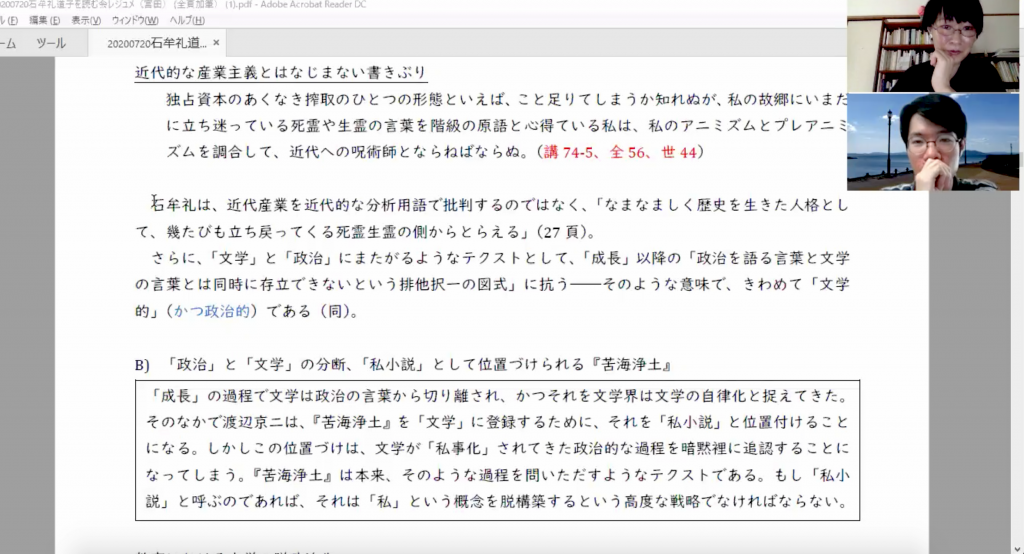
その後、早川論文にもとづいて『苦海浄土』英訳における翻訳の問題が具体的な訳出例とともに整理され、水溜論文にもとづいて水俣の「共同体」の性格が必ずしも「中心/周辺」、「都市/自然」といった二分では描き出せない流動的なものであることがコンパクトに確認された。
発表全体をとおして提出された大きな問いのひとつは、『苦海浄土』の語りの主体が一体誰なのか、ということだろう。宮田氏は哲学を専門とし、ハイデガーと和辻を主軸として研究をしているため、議論では最後まで、「主体性」や「間主体性」、「共同体」、「風土」といった概念についても問い直しがなされたのが印象的であった。
今回の第3回で、いったん『苦海浄土』第1部にもとづく集まりは一区切りとなるが、これまでたびたび話題にのぼってきた、「聞き書」の反復のレトリックや翻訳不可能性の議論にも深く立ち返る契機をあたえる充実の時間であった。
報告者:髙山花子(EAA特任研究員)








