2023年6月29日に第11回藝文学研究会が開催された。塚本麿充氏(本学東洋文化研究所)に、「無準師範と円爾、清拙正澄の「遺偈」――死の作法と造形――」という題目でご講演いただいた。
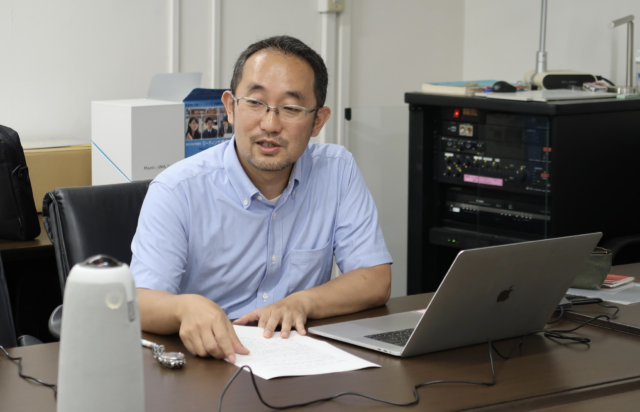 (講演者:塚本麿充氏)
(講演者:塚本麿充氏)

塚本氏は「遺偈」、すなわち高僧が臨終のとき、門弟や後世のためにのこす教訓などを記したものを、東アジアにおける「死」を前提とする「書」、もしくはこれを表現する「書」として捉えた。こうした書道作品においては、テクストの内容のみならず、その「かたち」こそが思想を伝達する上で重要となる。そこには作者の生前の字姿の痕跡が残り、またそれによって宗教的な真正性(authenticity)が生じると考えられる。亡くなった人の書を重視することは、中国においては皇帝御書を鑑賞する伝統が挙げられる。そのような例にかんがみれば、書のテクスト以上に、かたちに重きが置かれることが了解される。そもそも「遺偈」の成立には、宋代以降の「尚意」書風の成立、すなわち「かたち」が人格や精神性をつたえるという発想が前提に置かれていると指摘された。
具体的には、塚本氏は無準師範(1177-1249)の「遺偈」(木版、淳佑9年〔1249年〕頃、東福寺)と、清拙正澄(1274-1339)の「遺偈」(毘嵐巻、暦応二年〔1339年〕、根津美術館)を引き合いに出して議論を展開した。作品から確認できる、たとえば肉筆と拓本の関係や流通の仕方、また文字の書き足し・修正の痕跡とそこから察しうる生命が尽きようとしたときの線的変化といった、いわゆる「臨場感」などがピックアップされた。美術史研究では一般的に重視された様式論的分析は、遺偈に関しては行えない場合もあるが、それが作者によって執筆されたものだ、という認識が一種の前提として受けいれられ、そのうえで、作品のもつ宗教的真正性がどのように担保できるのかについて、拓本や模本の在り方からも考察されていた。
討論でも指摘されたように、人間の生の在り方を暴き出す貴重な契機という意味で遺偈は注目すべきものである。また仏教思想の視点からも、そのテクストの内容に関してコメントが寄せられ、真正性の意味の重層性などが議論された。
報告者:丁乙(EAA特任研究員)







――山内久明先生への手紙――(工藤庸子)







