11月24日、第3回の「訳者と共に読む『中国における技術への問い』読書会」が開催された。今回扱ったのは、『中国における技術への問い』の第7節から第10節途中までである。発表担当者は、後期ハイデッガーを専攻している鹿伝宇氏(東京大学人文社会系研究科哲学研究室・修士課程)で、前回に引き続き、EAAリサーチ・アシスタント3名(伊勢康平氏、ニコロヴァ・ヴィクトリヤ氏、上田有輝氏)、本記事執筆者の汪牧耘(EAA特任研究員)、そして数人の学生が参加した。
はじめに鹿氏が内容のまとめを報告し、それに基づいて参加者の間で意見が交わされた。大きな論点となったものとして、著者のユク・ホイ氏が取り扱っているハイデッガー論とハイデッガー研究の射程の異同や、テクネーという人間の暴力性と自然の暴力性との関係などが挙げられる。具体的な箇所に関しては、「有機・総合」といった言葉の哲学的文脈と、本書における用法の比較が行われた。
今回の議論を通じて筆者は、伝統の再発明を通じて現実問題に新しい発想力を注ぐという本書のアプローチに面白さを覚えた。第10節で取り上げられた中国の技術哲学にあった「道器合一」は、その再発明の手がかりだといえる。一方、本書の前提にあった宇宙技芸の多様性を踏まえて考えた際に、道の内なる多様性はどういった次元において捨象可能であろうか、という疑問が浮かび上がる。さらに言えば、たとえ新しい宇宙技芸が再発明されたとしても、それは必ずしも既存の宇宙技芸の間にあるヒエラルキーを転覆できるとは限らない。そういう意味では、技術に纏わる制度的・物理的条件を考慮することも、本書の序論で提起された技術の「物質性」に向き合うために不可欠だと考える。
筆者がいる開発・援助の分野において、技術の再発明を通じて近代の暴力を洞察したり、抵抗したりするような実践が少なからずある。日本の場合、「技術」というものの生産過程における役割を考える手がかりが浮かんでくるまで、四年間も作業現場で「経験」を身につけることに没頭していた中岡哲郎はその先駆者である。国際社会をみれば、E・F・シューマッハーが打ち出した「中間技術」はその代表であろう。ローマ・クラブの『成長の限界』が代表するような自然・環境・資源への危機感が溢れていた1970年代において、中間技術を名乗った活動は、世界中で展開されていた。しかし、それは結局、経済成長、利潤増大、支配力増大等の流れの中で圧しつぶされ、埋もれてしまった。こうした技術思想の浮き沈みがある中、本書が提示した中国の宇宙技芸が、現代社会を覆い尽くしつつある資本主義に横取りされない保証を哲学的に示してほしいという願望を抱いているのは、筆者だけであろうか。
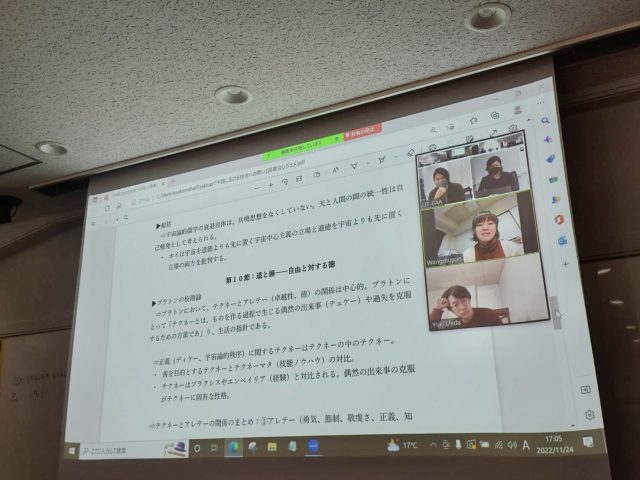
報告者:汪牧耘 (EAA特任研究員)








