ゲストとしてフランス文学者の千葉文夫氏(早稲田大学名誉教授)をお迎えして、2022年6月15日(水)に駒場キャンパス900番教室で行われた映画『籠城』上映会アフタートークの記録を公開いたします。

髙山:これまで3月までの上映会では制作チーム内でトークすることが多かったんですけれども、先日、映像作家で映像人類学者である太田光海さんをお呼びしたように、外部の方からのお言葉をいただけないかということで、クリス・マルケルをはじめ映画について非常に多くを書かれていらっしゃるだけでなく、1949年生まれでいらっしゃいまして、ちょうど世代的に、旧制第一高等学校であるとか、システムが新しく変わっていったその後の時代であるとかを知っていらっしゃる千葉文夫先生に批評していただけないかということで、きょう来ていただきました。それから、小手川将さんはタルコフスキーを中心とする、ロシア・旧ソ連の映画の研究をしていらっしゃいまして、今回はふだんの研究とはまったく違う対象に果敢にアプローチいただきまして、集団で制作する中心的な役割を果たしていただきました。それではお二人にお願いしたいと思います。
小手川:はじめまして、小手川将です。本日はありがとうございます。みなさんもお越しいただきありがとうございます。早速ですけれども、『籠城』という、文字通り閉じた……籠城している映画ですけれども、外部からの視点を千葉先生に持ってきていただいたということで、どのように見ていただいたかをお訊きしてもよろしいでしょうか。
千葉:千葉です、よろしくお願いいたします。2017年に、私、早稲田大学を選択定年で辞めまして、もう隠居生活なんですけれども、うちで翻訳したり、原稿を書いたりという。コロナがありまして、滅多に外に出なくなっちゃったんですけれども、ちょっとまずいことに、急速に右の耳が、聴力が落ちてきまして、ちょっとうまい対応ができるかどうか心許ないところはあるので、よろしくお願いいたします。
いきなりどうでしょうかって訊かれたんですが、最初に高山さんからこういった映画あるというお話があって、上映会の後にトークがあるから、そこに参加してくれないかと言われたときに、ちょっとうろたえまして。というのは、その主題が旧制一高、とくに駒場に移転してからの旧制一高を話題にする映画だということで、いったい自分とどういうつながりがあるんだろうかということで、内心、非常に不安だったんですけれども、その前に髙山さんから別の件で依頼を受けたときに、僕はにべもなく断ってしまったことがあって、どうも二回立て続けに断るというのは忍びない。自分の人格を疑われるんじゃないかというような気もしまして、あえてそういった不安がありながらお引き受けしたということです。そして、いろいろ資料をいただいたりして、実は今日観る前に一回、自分のパソコンでちらっと観てはいたんですけれども、いただいた資料などを拝見したりしながら、やっぱりいろいろなつながりがあるものだなということは思い始めました。
後でちょっとそのことを話題にすることになるかもしれませんが、旧制高校の話で、ちょうど駒場に移転したのは、本郷から来たのが1935年か1936年ぐらいだということですよね。それから10年ぐらい、駒場に「一高」の建物、校舎があったということです。要するに、第二次大戦がずっと迫ってきて、その危機のもとにある学校生活ということで、とくにそのあたりのことで、自分にとって──たとえば自分の父親がそういった世代だったということもあって、とくに自分の父親との関係で、自分に宿題が高校生ぐらいのとき与えられたことがあって、それをうまく処理できずに今に至ったということであります。これはいったい何のことだということは、後でもうちょっと具体的に申し上げますが、そういうことも含めて今日、小手川さんが監督なさった映画というものを非常に興味深く拝見しました。
一つは、映画そのものに入る前に、ここに来られた方、それぞれ世代的にもいろいろな世代の方がいらっしゃるし、いろいろな場所からここに集まられてきたわけで、それぞれさまざまなご意見、あるいは、この映画を観に来る動機もさまざまに違った動機がおありだと思うんです。
それで、自分はまず、やはり自分の仕事の関係で、早稲田大学を辞める前のだいたい10年間、2008年ぐらいから始まっているんですが、新しい学部と新しい学科を立ち上げようという話になりまして、これが大きく言うと……場所は早稲田の戸山キャンパスなんですけれども、文化構想学部というものをつくりました。これはゼロからつくったに等しいようなものなんですけれども……もちろん文学部が同じ場所にあって、その教員も含めていろいろな遺産を活用しながら、ということなんですが、いわゆる学問体系の組み替えということで、要するに細かい専門に分かれるんじゃなくて、それを大きくつなげて、ある意味では自由に移動できるような、横断できるようなスタイルでやろうよ、ということで。自分は表象・メディア論系というところで──表象というのが、ここ〔駒場〕の表象文化論の表象なんですけれども、そういうものをつくって──その立ち上げから軌道に乗るまで参加したということなんです。そこで一つ、最終的に、そのカリキュラムの仕上げとして、映像とか映画の制作ということがあるんじゃないか、ということを考えてやってきたんですね。
自分はとくにイメージ論というものを中心にして仕事をするようになりまして、それは、それまでやってきたフランス文学とやはり大きな違いということがあったんです。要するに、いろいろな文献を読むだけじゃなくて、やはり自分でイメージ制作に、学生たちが共同で参加しながらつくり上げていく。これを最終的には仕上げとして設定することはできないかということを考えて、僕から見て若手ですが、映像人類学の金子遊さんとか、非常に独自の映画制作をされている七里圭さんとか、まだひょっとすると20代か 30歳になったばかりなんですけど、若手の女性アーティストで石原海さんという方がいるんだけれども、そういう人を呼んできて雰囲気づくりをしようというところで、実は終わっちゃっていたんですね。だから、映画制作まで至らずに終わっちゃってたということがあって、きょうは、自分としてはそういう延長で──別に自分が教えたわけじゃないんだけれども──向こうの方で似たようなラインでやっている人たちがいたんだということで、非常に頼もしく思ったということが一つあります。
謳い文句としてどこかで読んだんですけれども、「リベラルアーツとしての映画制作」という……リベラルアーツというのは、やっぱり文章を書くとか議論をするとか、そのあたりでふつうは収束しそうな気がするんだけれども、それ以上に、映画制作を掲げてやったということで、そのあたりに自分としても反応するようなことがありました。だから、『籠城』という作品そのものの話に至る前に、リベラルアーツとしての映画制作という話題で、自分の方としては……そうですね、これはもうちょっと後の方で質問しようと思っていたんですけれども、それに臨む時の姿勢とか、要するに、東京の映画祭に出品するという考えがあるという話も聞いたんですけれども、それとは別に、単なる能書きなのか、それ以上の……リベラルアーツとしての映画制作という意味合いをどういうふうに捉えたのか。
そしてまた、今後……今回、大きなプロジェクトですよね。結構お金をもらったということで、いろいろな……なんていうのかな、全体的に非常に洗練された技術知の、つまり、撮影であるとか音楽であるとかサウンドデザインであるとか、断片的なテキストを読む声の重ね合わせとか洗練されたところがあるんだと思うんだけども、そういったことも含めて、何かリベラルアーツとして関係するものとして本当に捉えることはできるのか。そしてまた、今後の展開であるとか、これは大きなプロジェクトだけども、駒場の──僕が早稲田でひょっとしたらできるかなと思ってそこまで至らなかった──日常的な実践として学生たちが集団で作業をする、そういった映画制作みたいなことで、何か見えてきたということはあるのか。つまり、本題に入る前なんですけれども、そういったことからちょっとお訊きしたいなと思ってますんですけれども、いかがでしょうかね。

小手川:率直に言うと、今回の映像プロジェクトは、リベラルアーツとして映像制作をやろうというふうに始まったわけでは必ずしもなくて、最初にこの映画について、リベラルアーツとしての映画制作とは何かという問いが立ったのは、映画の完成する直前の2月末に、渋谷のスクランブルホールで行われたイベントのタイトルをつけて初めて、そうして問いが明確になった。完成する前の作品のプロセスについて公に語るという非常に貴重な機会をいただいたわけですけれども、そこで初めて、この映画制作がリベラルアーツとして考えられるのではないかということを制作チームで共有したということになります。
そこでプロセスについて語る、しかも完成する前の作品について、制作チームによってこの映画制作が何だったのかということを記録して公に発表するというのは、それそのものに、大学で映画作品をつくるということの実践としての価値があるのではないかというふうに今は思っています。ただ、率直に言って、まだ完成して3ヶ月と少しで、はっきりとした答えがあるわけではなくて……こうして上映会をして、制作チーム内でも3月に何度かトークしましたし、外部の方からの視点をいただいて──とくに今回は早稲田大学で長く教えてらっしゃった千葉先生に作品について語っていただきながら──、この映像制作について語るという場を設ける。映画そのものではなくて、大学で映画をつくるということや、そのプロセスについてこうやって話すということ自体が──議論の場を作るということですね──リベラルアーツとして今、実践している最中なのではないか、というのが率直な印象です。
千葉:ありがとうございます。一つは、今の小手川さんのお話に出てきた──正確なタイトルはちょっと僕は覚えていないんだけれども──、2月になさった、この制作に関わった人々が、それぞれいろいろお話をされるみたいな討論の場ですよね。これは映像化されていて、それを私はいただいて見たんですけれども、これで非常にいろいろなことがよくわかりました。
今日ここに来られている方で、それをご覧になっているという方は少ないんじゃないかと思うんですけれども……この話が分かりますか、2月の、制作スタッフが集まって、いろいろな議論をされたという、ほとんどご覧になっていないですよね。これを見ないとわからないという部分はすごくありました。リベラルアーツ云々というのは、たとえば、自分は表象・メディア論系の中ではイメージ部門、というとちょっとあれなんですけれども、学科の謳い文句として三つのプログラムを絡めて構成する。メディアと身体とイメージだ、っていう。後で気がついたんですけれども、ハンス・ベルティング(Hans Belting)というドイツのイメージ人類学者がいて、それがまさに、メディア・身体・イメージで、大風呂敷を広げると世の中のすべての現象が分析できるみたいな三つの重要な柱だということを言っていました。期せずして我々はそう謳っていたんですね。
自分が早稲田の中でやっているときは、たとえば身体っていうのは、身体を扱うさまざまな芸術があって、ダンスだとか演劇であるとか、だいたいそういうふうに考えちゃうわけなんですけれども、2月のトークを映像で拝見して、たとえば、撮影の一之瀬さん、それから作曲の久保田さん、とくにこの二人の話を聞いた時に、この身体ということが非常に関係していた。自分の知り合いの先生で、身体知──知というのは知識の知なんですけれども──「身体知」と「概念知」という二つを対立させて、うまいこと説明をしている先生がいる。身体知の方はもっと感覚的な言葉ですよね。お二人の仕事って、まさに身体知、つまりある種の身体的な技術をもって、作曲の技術であったり、ピアノ演奏であったり……そういった無機質な知識ではない、身体に入り込んでいる知というものを問題化しないとできない世界がある。その話が非常にうまく出ていたということで、僕もハッとしたということであります。
これはある意味では地味な世界で、一之瀬さんの映像と、それから久保田さんの音楽を漠然と聴いているだけではそこまで意識しなかったかもしれない。それがトークの中で、ある種の苦労話であるとか、久保田さんが途中でお父様に連絡して、お父様がたまたま、一高ではないんですけれども駒場の学生だった頃に寮歌を歌っていたという。要するに、卒業して非常に年月が経っているにもかかわらず出てくるみたいな……つまり、身体の中に蓄積された知として入っていて、これも一つの身体知ですよね。一之瀬さんの映像も、駒場という環境を、非常に洗練された映像だと思うんだけど、建物の肌触りであるとか、そういうものを捉えている。これはやはり、むしろ肌の感覚に近いところで何かやっているものが入り込んでいる。こういうものが入り込むことによって、まさに本当の、無機質な意味でのリベラルアーツではなくて、実践的で能動的なリベラルアーツの可能性があるんじゃないかという気がするんですよね。
だから、今後の……小手川さんはたぶん、やはり将来、映画監督になろうというふうに意欲的な野望を持たれていて、そっちの方が強いのかもしれないけれども、駒場の普段の学生の営為の中で、──非常に小さなデバイスとかで簡単に映画が撮れるような時代に入っていますから──そういった可能性があるんじゃないかということを考えた、ということが一つ。
それから、もう一つは、小手川さんの最後の、今日の場がどういう場か、という話で、まさにそこも自分が考えることが一つありまして。大昔にパリ大学に留学した時にドゥサンティ(Jean-Toussaint Desanti)先生という方がいて──拙い論文を書いて副査で読んでくれた人なんですけれども──、ドゥサンティさんと、それからモンザン(Marie-José Mondzain)というイメージ学者がいまして──モンザンの翻訳が最近出たみたいですけれども──その二人が共同して、この本はフランス語のタイトルでVoir ensemble (Gallimard, 2003)というんですね。「一緒に見る」という意味なんですけれども、この本のことがすっと頭に浮かびました。というのは、まさにVoir ensemble、一緒に見るというのは、逆に言うと、一緒じゃないと見ることはできないという発想なんです。
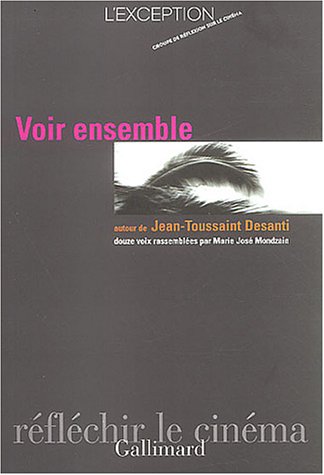 ここにたくさんの人がいて、いろいろなバックグラウンドがあって、いろいろなところから来ている、いろいろな視点を持っている。そのことをドゥサンティはsiteという言葉で言っている。これは英語だとsiteなんですけれども、皆さんいろいろなsiteを持っていて、そのsiteから見ている。そして、見えるものと見えないものがある。今日もそうだと思うんですね。今日も、よく分からないものってすごくあると思うんです。分かる部分もあり、そして自分がこういうものを求めて観にきたとか、そういう違うがいろいろある。でも、この場で一堂に介している、ということの意味がすごくあるんだというのが、ドゥサンティが言っていることの意味です。
ここにたくさんの人がいて、いろいろなバックグラウンドがあって、いろいろなところから来ている、いろいろな視点を持っている。そのことをドゥサンティはsiteという言葉で言っている。これは英語だとsiteなんですけれども、皆さんいろいろなsiteを持っていて、そのsiteから見ている。そして、見えるものと見えないものがある。今日もそうだと思うんですね。今日も、よく分からないものってすごくあると思うんです。分かる部分もあり、そして自分がこういうものを求めて観にきたとか、そういう違うがいろいろある。でも、この場で一堂に介している、ということの意味がすごくあるんだというのが、ドゥサンティが言っていることの意味です。
要するに、映画作品〔の上映〕があって、その後が付け足しかというとそうではなくて、ここから本当に映画を観るという行為が場合によっては始まるんじゃないかというのが、ドゥサンティとモンザンの考えです。我々はここで喋っていますが、皆さんが何かここでひとこと言うってこと自体の方がひょっとすると重要かもしれないというのはドゥサンティの考え方です。そうすると作品とその後との切れ目がなくなっちゃって、全部がプロセスみたいなことになってくるということですよね。そこに非常に近い発想かなと思う。
これがまさにリベラルアーツと非常に関係あるんじゃないかな、ということです。ドゥサンティは哲学の先生で、モンザンはイメージ学者なんですけれども、拡大ゼミみたいなことをやっていて、他に全部で10人ぐらい参加していて、そのうち5人ぐらいがなんとシネアスト、映画監督なんですね。オリヴィエ・アサヤスとかブノワ・ジャコーとかがいて──こういう人たちとドゥサンティとどういう関係があったのかなと思ったりしたんですが──、ドゥサンティの言ってることのラインと自分の距離を測りながら参加しているということがあった。これは見事な、リベラルアーツと謳っていないですけれども、こういうものが理想的なリベラルアーツかなというふうにだんだん考えるようになりました。
もう一つだけ、例として、それを裏打ちするようなことがあります。自分が仏文学と別個に映画論の論集みたいなものに参加したんですけれども、そのうちの一つが、ストローブ=ユイレが──ジャン=マリー・ストローブとダニエル・ユイレという二人の夫婦なんですけども──共同制作した映画の論集〔『ストローブ=ユイレ シネマの絶対に向けて』森話社、2018年〕をつくるっていうものに関係した。そのときにいろいろ映画を観たり材料を見たりしたんですけれども、ストローブ=ユイレは映画を何か……どうも完結したものとして考えていないんじゃないかと思ったのは……そんな大規模じゃないんです。これくらいか、もっと小さい規模で上映と討論をやる。これがすごい侃侃諤諤な討論で、場合によっては罵り合いに近いような批判的な意見がぼんぼん出てくる。それを好んでやるんですね。これがセットになっているような気がしているというのが一つ。つまり、作品として完結していないという感じかもしれないですよね。
それからもう一つ、ジャン・ルーシュという、アフリカの民族誌を映画でやった人なんだけれども、マリ共和国のドゴンっていう人々がいて、シギの儀礼という壮大な儀礼があるんですけれども、その記録フィルム〔『シギの祭:ボンゴの洞穴』(1969)〕を撮ったときに、完成した段階でドゴンの人々に現地に持っていって見せるんですね。そうするとまた侃侃諤諤の議論がある。それは映画を正しく受けとめるとかそういう話ではなくて。要するに、ドゴンの人々にとっては、うちのおじいちゃんやおばあちゃんが出てくるみたいな。ジャン・ルーシュが、ドゴンの神話とか、いろいろナレーションをする、解説をするんですけれども、あれうるさいから消してくれ、うちのおじいちゃんの言っていることが聞こえないよ、というような……ある種のノイズですよね。でも、そういうものとして成立するということも受け止めないと、そういうことはできないということかなって。ごめんなさい、話がどこに行くか分かんなくなっちゃったと思うんですが、そこでちょっと戻します。
小手川:今の話をお聞きしていて思い出しましたけども……制作プロセスの中で、基本的には去年の9月から12月ぐらいにかけてが制作のコアな期間だったんですけど、コロナの影響もあってほとんど全員で会うことは叶っていなかったんです。ただ、オンライン上で、SlackとかメールとかZoomとか、皆さんも普段使っているようなツールを使って、随分と制作途中の作品について議論をしていた。撮影中もそうでしたし、撮影が終わった後の編集でも、編集途中の完成していないものを共有して全員から意見をもらってつくっていたりとかしたんです。そこでもかなり白熱したというか、激しい……激しいというと言い過ぎかもしれませんけど、随分批判的なコメントも多くて、それに応答しながらつくっていったということを思い出しました。
あと、もう一つは、一之瀬さんも久保田さんもそれぞれの分野、身体知においてプロフェッショナルの方で、そうした方が制作に参加してくださったというのは恵まれたことなんですけど、基本的に、限られた一部を除いて、制作チームは映画制作の経験がない人ばかりで、僕自身も専門的な教育を受けていたわけではないですし、プロの映画撮影の現場に集中して参加したことも一度もないので……そうしたことを考えました。
今では誰でもiPhoneひとつで映像も撮れれば音も録ることができるわけで、今回の映画の音も随分と自分たちの手作業で録音した素材を使っている。つまり、僕たちは録音のプロではないんですが、たとえば、セリフのほとんどは自分たちで録音したんですね。久保田さんの音楽はプロの方に録音していただいたんですけれども、そうした技術的な……技術的な環境ですかね。新しい技術的な環境においては、何というか、早稲田の何ら専門的な教育を受けてない人でも〔映画を〕つくれる可能性は十分にあるというふうに思います。千葉先生が関与していたという、金子監督や、七里さん、石原海さんとかをお呼びしたというのは、それぞれ監督のプロフェッショナルというか、映画制作の現場を重ねてきた方々だと思うんですけど、そこではどのようなことが目指されていたのか、というのはお伺いしても良いものでしょうか。

千葉:まずね、3人とももちろんすごく違っていて、金子さんというのはエスノグラファーですよね。いろいろなところを飛び回っていて……エスノグラファーというふうに決めつけるのは難しいんだけれども、人類学的に何か試みの一環としてフィルムがあるみたいな。とにかく学生時代からフィルムを回すとかで出発している人だけれども、文章もいろいろ書くんですね。サントリー学芸賞も貰っているし、文章も立派なものを書く人で、非常に幅広く、文芸評論からいろいろなことをやっている。おそらく、皆さんの関心とも重なる、ジョナス・メカスとかクリス・マルケルとかの論集や本も書かれている方で、だから理論的な部分と実作者として、両面を持っているという方ですよね。
七里さんというのは独特で、フィクション映画として非常にわかりにくい……音楽としての映画とか、建築としての映画というテーマを立てて、非常に禁欲的な、そんな長いものをつくらないと思うんだけども、映画をつくっているこだわりの人ですよね。喋らせると、金子さんは非常に整理したことを喋ってるんだけども、七里さんは非常にこだわって収拾がつかなくなっちゃうというところがあって、まさに現場の感覚を持っている人。大学の中での話って、だいたい分かりやすくしないと保たないというのはありまして──つまり、起承転結をはっきりさせるとか、今日はこういうものを学習して皆さん帰りましょうみたいなことがどんどん増えちゃったんだけども──、七里さんはその対極にくる人で、それをもってきたということは面白かったですね。それを学生がどう受け止めるのか。大教室の、大人数の教室での授業ではなかなか難しいんですけれども、大学院のゼミなんかでぴたっとはまるということはありました。
石原さんは、最初に早稲田に呼んだときは23歳ぐらいかな。早稲田大学の招聘講師として出すときに、書類の形式が非常に古くて、今もそういうことをやっているのかどうか分からないんだけども、招聘講師の年齢を書く欄があって、21歳とか22歳とか学生じゃないかっていう。学部の学生じゃないかということで、ちょっとこっちは青ざめてたんですけども。藝大の学生だったんだけども、すでにアーティストとして活躍していて、非常に若いんだけども、立派に喋ることができる……いやこれがいけない、差別的な用語で……たとえば、何を話してくれたかな、ベルギーの女性監督で自殺しちゃった人……70年代後半から仕事している人……〔会場から声が上がって〕そうそう、シャンタル・アケルマン。アケルマンが一つのレファレンスだと言って、喋って、そういう見事な話があって、自作を絡めてやるというような。
みんな他の映画と自作を絡めるみたいなことで、たんに映画評論家が喋る話とは全然違う。とくに若い学生にとっては石原海さんのような存在というのは……あれはやはり肌で分かるという感じなんだと思うんだけども、こっちはちょっと頭で理解しようとするんだけども……そういう感じがありましたね。
だから、これはそういうところで動かさないといけないという感覚はありましたね。映像みたいなもの──ある意味、今日の音楽の、あるいはサウンドの使い方っていうのは非常に洗練されているわけで、全体の話は分からないということはあるかもしれない、構成とか分からないってことはあるかもしれないけれど、そういうところで反応する人はいるっていうことはあり得るんだと思ったんですね。これは、時間はどれくらいあるんでしたっけ。いや、今日、会場の皆さんが発言することは大事だということを言っちゃいましたから、そういう時間を残さないといけないということで、あとはちょっと端折って言いたいことを言います。
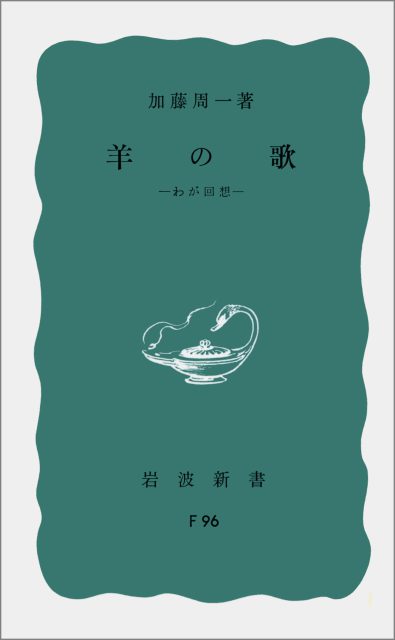
一つは、旧制高校という話題がここで関係しているので、これは先ほど言った宿題みたいなことなんですけれども、自分は、駒場だと小林康夫先生……辞めちゃったけどね、もちろんもう辞めているわけで、彼とまったく学年が同じだと思うんですが、そうすると旧制高校というのは高校生ぐらいのときはもちろん直接見えないわけですよ。ただし、自分の祖父であるとか、父親というのは、まさに旧制高校から両方とも帝大に入って、両方とも東大行ったような人だったんだけども、自分の父親の場合は一中、それから水戸高、東大ということで、普通だと一中、一高、東大というのがある。一高を迂回したのは、どうも一中のときに病気で留年しちゃって、一高に行けなかったということはあったみたいです。その父親から、僕は中学から高校くらいのときに、中学の同級生だといって教えてもらったのが加藤周一で、その『羊の歌』という有名な本があって。これには一高の話が書いてあるので、久しぶりに、もう何十年ぶり読み直して付箋しましたけれども、ご存じない方は、今日の映画を観て、この本の一高の部分を読み直すと、非常によく概略が分かるんじゃないかと思います。父親なんかの世代がそうですから、周りにいろいろそういう人たちはいるわけです。高校のときの先生も、英語の先生が一高だった。ただ一高というと、すごくエリートみたいな意識があるんだけれども、どうもその高校の先生はそういう感じは全然なかったです。高校の先生で、もうちょっと前向きにいろいろなことを生徒に訴えかけるかというと、それはなくて、非常にアイロニカルな人で、却ってそれで記憶に残っているんですね。懐が深いというのかな。今はああいう先生はいないんじゃないか。
1969年5月に三島由紀夫がここ〔900番教室〕で全共闘とやった、そういう場所だっていうので、初めて足を踏み入れました。僕はその時、1969年4月に東北大学に入りまして、東北大学がまさに無期限ストに入っちゃった頃です。そういうことをやっているということは知っていましたけれども。東北大学へ行ったときに、これは〔かつて〕旧制二高だったんですけれども、そういうものは一切、影も形もない。もちろんそういうものを求めていたわけじゃないんだけども……最初にキャンパスに事務登録のために歩いていたら、木造の平屋建ての白っぽい家があるんですね。要するに、占領軍、進駐軍っていうことですから、その宿舎になっているところだっていう。つまり、旧制二高をアメリカの占領軍が塗りつぶした。その後、1、2年して建物の建てかえが始まった。これは高度経済成長のときで、大学の建物をどんどん近代化して建て直す。占領軍の記憶を削いでまた潰しちゃうみたいな。
だから、旧制高校の記憶は二重に消されたという感じの時代なんですが、ただ2000年以降ですね、いろいろな学会などがあって、熊本大学へ行ったのは、──熊本は五高なんですが──五高の記念館があった。金沢に旅行したら──あれは四高ですよね──四高を建て直して、それを石川四校記念文化交流館とかいうものになっていたんですが、そういう回顧の時代に入っていったんですね。ある意味ではベンヤミンの用語で言うと展示価値の時代ということになって、記憶と記録の時代に入ってきたわけですよね。
小手川さんのこのプロジェクト、皆さんのプロジェクトは、まさにそういう中でリンクしているんだと思います。どこかでリンクしているんだと思うんですよ。リンクの仕方は違うと思うんだけど。熊本五高の場合は純粋に懐かしいみたいなことかもしれない。金沢の場合、土地柄もあるし、歴史を文化財として再活用しようということがあるかもしれない。このプロジェクトは、そういったことでいうと、どういうことになるのかなという。あまり意識してないかもしれないけれども、そういう問いを投げかけたような気もするのですけれども。
小手川:千葉先生が旧制一高、というか一高の世代とは二重に上塗りされているとはいっても、かなり僕からすれば近い距離、近い世代にいましたよね。僕は、今回の制作が始まるまで、2020年11月ぐらいですかね。一高というのをほとんど知らないと言ってもいいぐらいの距離があったんです。いろいろあって、一高をテーマに映画をつくる、それを自分が監督することになって、一高というテーマについて、自分がどういう位置を、ポジションを取るか、一高というテーマとの距離というのを決めなければいけないという意識は強く最初にあったことです。制作が本格的に始まるまでに資料を読んだり、あとは、ありがたいことに、まだ一高の卒業生の中には存命の方もいらっしゃって、実際にインタビューに行くことができた。それで、語りやテキスト、声、言葉を聴く、そうしたポジションに自分を置くことで、さまざまな世代の一高についての語りだったり、言葉だったりに、ほぼ何も知らないような自分の距離感、そうした距離感である自分がどのように迫れるか、ということを自分に課したということがあります。
その中でも特権的な語りとしたのが、今回、原案としても声の出演者としても参加していますけれど、高原さんという一高の研究者の方です。僕よりちょっと上の世代ですけど、でも同じ身分の大学院生で、自分と近しい世代の人間がどうして一高というものに向かって研究を進めるのか、欲望を持てるのか、ということを高原さんの語りを中心に自分の中で考えるというのが、今回の監督としてのポジションだったと思います。
この映画は非常に断片的なテクストを用いながら、さまざまな声があふれているような映画ですけれど、すべては一高への、旧制一高という今はないものへのある種の欲望をテーマにした映画だと考えています。一高にどのように接近できるのか、そういう欲望を現在──現在といっても、今は2022年で、そして2021年制作という、そうした時代というものに特定されないような現在──という位置から、すでに終わった日付もわかっている一高というものにどうやって欲望が向けられるのか。そういう構造を映画の中でつくろうと思ったというのが、今、千葉先生のお話を聞いて、振り返って思うところです。
千葉:旧制高校の中の一高であってね、旧制高校自体の問題というのがあると思うんだけど、もう今とは圧倒的に全然違うわけですよ、世界がね。つまり、男子の世界であって、寮生活であって、そして、旧制高校であれば帝大へ無条件で基本的に行くことができる。一高のほとんどの人は東大に行くというような、特別な世界ですよね。だからそこは旧制と新制で違うわけで、時期的にはもちろん僕は旧制の方に近いけれども、ただし、高校からたとえば早稲田に行くとか、高校から京大に行くとか東大に行くとか、今は同じじゃないですか。旧制高校の時代は違うんだよね。帝大と他と違うという、圧倒的に教育制度の違いがある。

最後の一つ、僕の宿題だと思ったことと、今回の複数の声ということがあって、そのあたりがうまくリンクするかどうかわからないんだけども、最後の一つの質問につなげていきたいと思います。加藤周一の『羊の歌』の、とくに旧制高校の部分を読み直して、ある意味では──これはちょっと不遜な言い方ですが──よく書けすぎているというくらいよく書けているなと思ったんです。あと、もう一つ持ってきたのは、林尹夫という人の『わがいのち月明に燃ゆ』という、筑摩書房から1967年の春に出た本がありまして、今これはちくま文庫で出ています。林尹夫というのは──一高でないんですけども──三高から京大に入った人で、18歳 から 21歳にかけての日記を本にした、お兄さんが中心になって本にしたんです。この人は戦死しています。特攻隊に入って──僕も特攻隊で死んだんだと思ったんだけども、──実際には米軍の戦闘機に四国の沖で撃墜されて、ほとんど終戦間際に死んだ。三高から京大に入って、そして特攻隊に入るというのは、もう有り得ないくらいレアケースだと思うんだけども……どうしてそういうことになったかと色々詮索があるんですが、これが宿題だというのは、これを僕が高校3年生になったときに、父親から読めって言われて渡されたんですね。
父親はまさに……今日、自分は25歳で若くはないという主人公のナレーションが入りましたけれども、父は25歳のときにトラック島に行っていた。つまり、生死の境。そこでさまよっているわけで、そういった経験をその世代が持っていて、君たち──つまり我々が高校生だったとき、1960年代末の高校生──は非常に平和を享受していたから、自分たちの世代はこういうものだったということを知ってほしいということが一つあったんだと思う。それが僕にはぴんと来なかったというか。もちろん読めば、同感するとか共感するということはあるんですが、すっとそこに入り込めなかった。そして今、読み直してみてやっぱりこれは悶えるというか、どう捉えていいのかよく分からない。というのは、すべてを勉強に捧げる、そういう時代であるということと……でも、その勉強というのは、傲岸不遜な言い方をすると、やっぱり狭いんじゃないか。
林尹夫というのはすごい秀才で、たとえば、家の父親は一中のときに矢内原伊作という人と同級だったって言うんだけども、確か京大に行った人なんですよね。その名前が出てきたり……後は、東大の駒場でフランス語を教えていた平井啓之さん──我々はケイシさんと呼ぶんですが──、そういう人と三高で同期で、とにかくすごいできる、フランス語なんか滅茶苦茶にできる。ただ、それが何か痛々しい、悲しい。それは時代のせいもあるかもしれないけれども、これを今、どういうふうに受けとめていいのかよく分からない。
時代が違うと簡単に言えるんだけども、これを……『籠城』の中で使われたテクストというのは、寮の規則であるとか、一高のディシプリンに関係するものであるとか、それを断片的に朗読してバラバラにしていくわけで、この一人称の記録とは非常に違うわけなんだけれども、だから、歴史的なそういった環境の中にあるテクストをどういうふうに扱えるのかというのは、自分で解決できなかった宿題である。
声の扱いのやり方とか、重ねていくとか、サウンドを何重にも多層にレイヤーを重ねていくやり方。そして、そこに写真、静止画像であるとか、一之瀬さんの現在の画像を合わせていくやり方とか、非常に洗練されていると思うんだけれども、何かテクストとして広がりが感じられないところがある。それはよく分かる。ナレーションをかぶせていって、説明的にやると、一人称の声になっちゃう。たとえば、主人公がべらべら喋ってね。そうして一高を解説しちゃったりすると、物語的なものに回収されちゃうからあえてしないんだ、いろいろな歴史的な写真をぱらぱら映すようにテキストを分けて、女性の声を絡めているって意図的ですよね。つまり、男子生徒の社会に対して、それを切り崩す、解体していくみたいに声が入り込む。こういう意図はすごくよく分かるんだけども、ただ、このテクストの扱いがこれで良かったのかどうかよく分からない。
ただ、僕が答えを持っているわけじゃなくて、何かしら自分が抱えた宿題と、この時代の資料を扱う……寄り添って、距離を持って、っていう、こういうことだと思うんだよね。距離を持っていたら語ることはできるかもしれないけれども、何の心もこもったものにならない。ただ寄り添っちゃったら同期しすぎてしまってという、その辺の感覚だと思うんだけども、このあたりの課題というのはあるなと思ったんですけども。これが一番大きな質問かな。
小手川:はい、そうですね、先ほど欲望の問題を考えていたというふうにお話ししたんですけど……対象に近づき過ぎると距離を取っていられないし、そもそも同じ経験はできないわけですよね。一高の当時の人々もそうだし、私と千葉先生も同じ経験はできないんですが、書かれたものにはそういうふうに〔同じ経験ができるかのように〕錯覚させる何かがある、あると思う。つまり、書かれて残ることで、それを読むことができるようになり、そうして何か共通するものがあるような、そういう幻想をつくり出す力がテクストにはあると思うんですね。一高の歴史自体もそうして書かれて、書き継がれて、規則や寮日誌や、さまざま学内外に発表された生徒たち自身のテクストによって残っている。一高生自身もかつての、駒場移転前の一高生のテクストを読み、批判的に読み継いでいったという、そうした歴史として私は見たということが一つ。
それと、歴史的なテクストをどう扱うかという課題なんですけれども……書かれたものという点で、個人的には、あらゆるテクストがとても歴史的に見えるというか……率直に言って、言葉自体に違いを見ることが非常に難しい時がある。それは対象との距離感の問題とかかわっていると思うんです。ただ違う〔違いを感じられる〕のは、今回、引用しているセリフもあり、断片的に構築したセリフもありますが、すべて声にして読んでもらっていて……書かれた文字、言葉というものを読むことで初めて、そこに時間の感覚が、それぞれの声の出演者によって異なる質が生まれて、そしてそれが初めて歴史との距離を生むことになるのではないか、というふうに思っていましたね。それが同じテクストを複数の話者で読んでもらった意図の一つです。








