2024年6月6日(木)、駒場キャンパスのEAAセミナー室にて、酒井直樹氏(コーネル大学)と石井剛氏(EAA院長)の対談が行われた。シリーズ「EAA Dialogue」の第12回にあたる本イベントは、日本思想史・比較文学・翻訳論・ナショナリズム論で知られる酒井氏から話を伺う貴重な機会となった。

対談の冒頭ではまず石井氏から酒井氏に、生い立ちおよび学問の道に進む前の経歴を尋ねた。第二次世界大戦の直後に生まれた酒井氏は少年時代にアメリカによる占領下の民主化と高度経済成長を経験してきた。そして1960年代から70年代初頭に東京大学に在学していた間、東大闘争やミシェル・フーコーの東大訪問をきっかけに、知識と制度の関係に関心をもちはじめ、フーコーやデリダの著作に触れた。大学卒業後はイギリスに渡り、そこの会社で勤めたのち、自ら会社を設立したこともあるという。1979年、シカゴ大学の博士課程に入学し、そこではハリー・ハルトゥーニアン、テツオ・ナジタ、マサオ・ミヨシらの指導を受けながら博士論文を執筆し、博論はのちにVoices of the past:the status of language in eighteenth-century Japanese discourse(1991)として刊行された(日本語訳:『過去の声――18世紀日本の言説における言語の地位』)。

酒井氏は自身の研究だけではなく、韓国語、中国語、英語、日本語による多言語学術誌『TRACES』の創刊と編集にも携わった。そこで逢着したのは、国民・国家を単位とする国際社会という前提、そして翻訳という問題である。翻訳への問いは『過去の声』の問題意識に通底している。酒井氏は国語としての日本語およびそれを単位とする翻訳という制度が成立した前の近世日本に遡り、朱子学と対決して「情」の意義を掬い上げた伊藤仁斎、言語の歴史性を強調し、三代を神聖視した荻生徂徠、そして古学派の方法を取り入れ、「声」の本質化をさらに推し進めた本居宣長をめぐって議論を展開した。そこでは発話行為の物質性を重んじる仁斎と音声言語を正当化する国学との対照性が浮き彫りになっている。
酒井氏の議論を受けて、石井氏は清代考証学にも過去の「声」への関心があるとし、とりわけ古学派に近い位置にある戴震の小学が古代の「音」を復元しようとする欲望を内包していることを指摘した。その上、黒住真氏と葛兆光氏の論述を引き合いにしながら、明清交代の歴史的インパクト、近代東アジアのナショナリズムとの関連性にも言及した。さらに、酒井氏の著書『希望と憲法──日本国憲法の発話主体と応答』(2008年)と『日本思想という問題――翻訳と主体』(1997年)を取り上げ、「情」との出会いに基づいた翻訳の可能性、翻訳と主体の関係について問題を提起した。それに対して、酒井氏はたとえ自己言及という形での翻訳にもつねにすでに差異が発生しており、そういった仕方でわれわれが他者に出会うが、いわゆる主体性はこうした他者との遭遇においてしかありえないと応答した。
対談の最後は憲法を中心に議論が交わされた。憲法第九条にある、国民主義を内側から乗り越える希望に関する石井氏の問いに対して、酒井氏は戦後日本の歩みとアメリカの対日政策を振り返りながら、日本ないしアジアにとっての憲法の意義を語った。その後、話題がさらに「恥」の情、普遍性と単独性、魯迅における「希望」へと展開された。
本対談は翻訳への原理的な問いを通じて、近世から近代にかけて確立した国語・国民国家・国際社会といった枠組みを批判的に捉える視座をあらためて提示したものであり、対談者にまつわる「情」に出会う場でもあった。
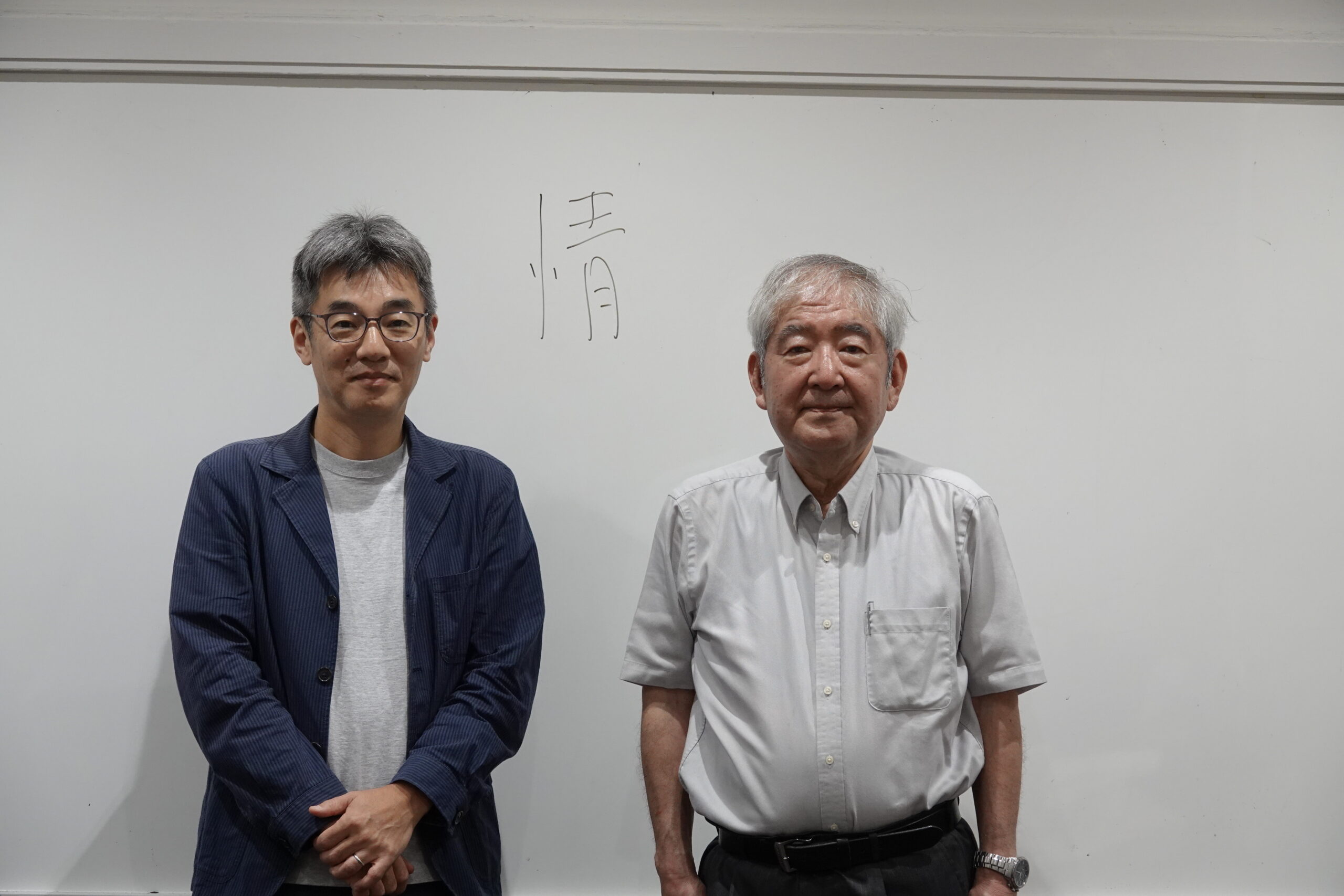
報告・写真:郭馳洋(EAA特任助教)








