2021年3月31日(水)14時より、東京大学本郷キャンパスEMPラウンジにて、第8回EAAダイアローグが開催された。今回のダイアローグは宮本久雄氏(東京大学名誉教授)と中島隆博氏(EAA院長)によって行われた。EAAのダイアローグは幼年時代の思い出を聞く場面からはじまる。中島氏による問いかけに対して宮本氏は胎児時代の話を澱みなく始めた。1945年2月に生まれた宮本氏が母親のお腹にいた頃、激しい空襲から逃れるために防空壕で孤独を過ごした母親は、世界が終わるのではないかという感情を抱いていたという。そしてその終末観、世界が没落するのではないか、という感情を自分が受け継いでいるのではないか、と宮本氏は言うのである。それから紹介されたのはBC戦犯としてシンガポールで絞首刑になった彼のおじの存在である。これらが幼年期の二つの基本としてまず提示された。転校を繰り返しながら新潟で生まれ育った彼がやがてアウシュヴィッツについて書くようになった背景には、そうした二つがあり、それらが発端となって、戦争をめぐる議論をドイツから学び東洋に持って来れないかという問題意識がいまになおつづいていることが明かされた。

高校時代にマルキシズムとキリスト教を二者択一とするのではなく、両者をまとめられないかと夢を抱いて、しかし周囲からは答えを得られず苦しんだ過去も語られた。その後、東大に入学したことによって、葛藤し苦しんだ問題がだんだんと解決していった過程は、あとで中島氏によって確認されたように、大学の外での出会いや体験に多くを負っていたように思われる。ザビエル寮での徹夜の議論、新宿でバーを開く神父、押田神父による長野の共同体、クリスチャン禅……。駒場時代のクラスメイトに炭鉱争議にコミットしたメンバーがいた回想のあとに明かされたのは、本郷の哲学科に進学し、語学を相当勉強し、とりわけ加藤信朗氏の導きによってトマス・アクィナスで卒論と修論を書いた経緯である。それから大学紛争のあと、氏はドミニコ会の門を叩くことを決め、カナダのオタワの神学大学に進み、フランス語で学業を修め、ヘブライ語を習得し、いったん帰国する。五島列島の隠れキリシタンの頭領と知り合う出来事を経、宮本氏はまた海外へ向い、イスラエルの聖書学考古学研究所で学ぶに至った。このように宮本氏自身の旅の経験のスケールの大きさが桁違いであることが感じられるエピソードが静かに矢継ぎ早に現れていったことが印象的であった。エジプトのシナイ山にも行き、カタリナ寺院では料理長を務めたという。フランスに渡ったあとはドミニコ会の共同体で神父たちと衣食住を共にした経験も語られ、東大に教員として戻るまでに世界の各地を経巡ってきた歩みがあったことが静かに振り返られた。
駒場時代に宮本氏に学んでいた中島氏は、かつて、学生として、冬の真っ暗闇の2号館にてギリシャ語で聖書を読んだりもしたという。宮本氏は翻訳についても旅先で仲間と訳した思い出を語っており、どこにあっても、誰かと言葉を交わしつづけてきた姿が想像された。最近の著作についての受け答えのなかで、近著の『パウロの神秘論』(東京大学出版会、2019年)に描かれるソーマの問題は、中島氏が学生のときにすでに話されていたことがわかるなど、本質的な大きな問いについての思考が熟成されるように時間をかけて深まってきたことも推察された。
報告者のわたしの心に残ったのは、自分にとっての問いを探究するために旅をしながら自らのテーマを深めそしてさまざまな語学を習得されていった氏のダイナミックさと、専門がなんであるのかを聞かれるのは好きではない、という言葉である。宮本氏は現在、ヘブライ的な脱在論としてエヒィエロギアをテーマとしているが、聖書学であれ、教父哲学であれ、日本の哲学であれ、どれも8割は行かない成熟度であったとしても、時間をかけて、すべてのレヴェルをあげて全部を投入することをやってきているという。それが根源悪の問題を乗り越えてゆくための態度でありつづけていることに驚いた。数十年かけてなお、極めて大きな高みを目指すために時間をかけて全力投球を続けている姿には、学徒の一人として大きく励まされるものがあった。
報告者自身は昨年の石牟礼道子を読む会をきっかけに初めて宮本氏に出会ったが、今回のダイアローグを聞くことで、彼の石牟礼文学の読解の底に貫かれている近代を批判的に眼差す姿勢が、終わりなき旅をする心、それも交通機関に頼らずに自分の足で歩いてゆく時間、そうした経験によって支えられていることを諒解した。夏の気配さえ感じられるほどに暖かな春の午後のひとときであったが、全体主義への警戒が再び感じられる、移動の制限されたいまこのときに、どうやってインターネットでは到底辿り着けない世界の「つらいところ」に近づいてゆけるのか、自分とは本当は何者なのかを問うてゆけるのか、これからの世界を生き、創るための激しく厳しい課題を突きつけられたように思う。そのためには極めて遠くの未来と遙か昔を見通しながら、目の前の現実をどれだけ正視できるのか、目を逸らさずに閉塞した現実を受け止めることが求められるように感じている。
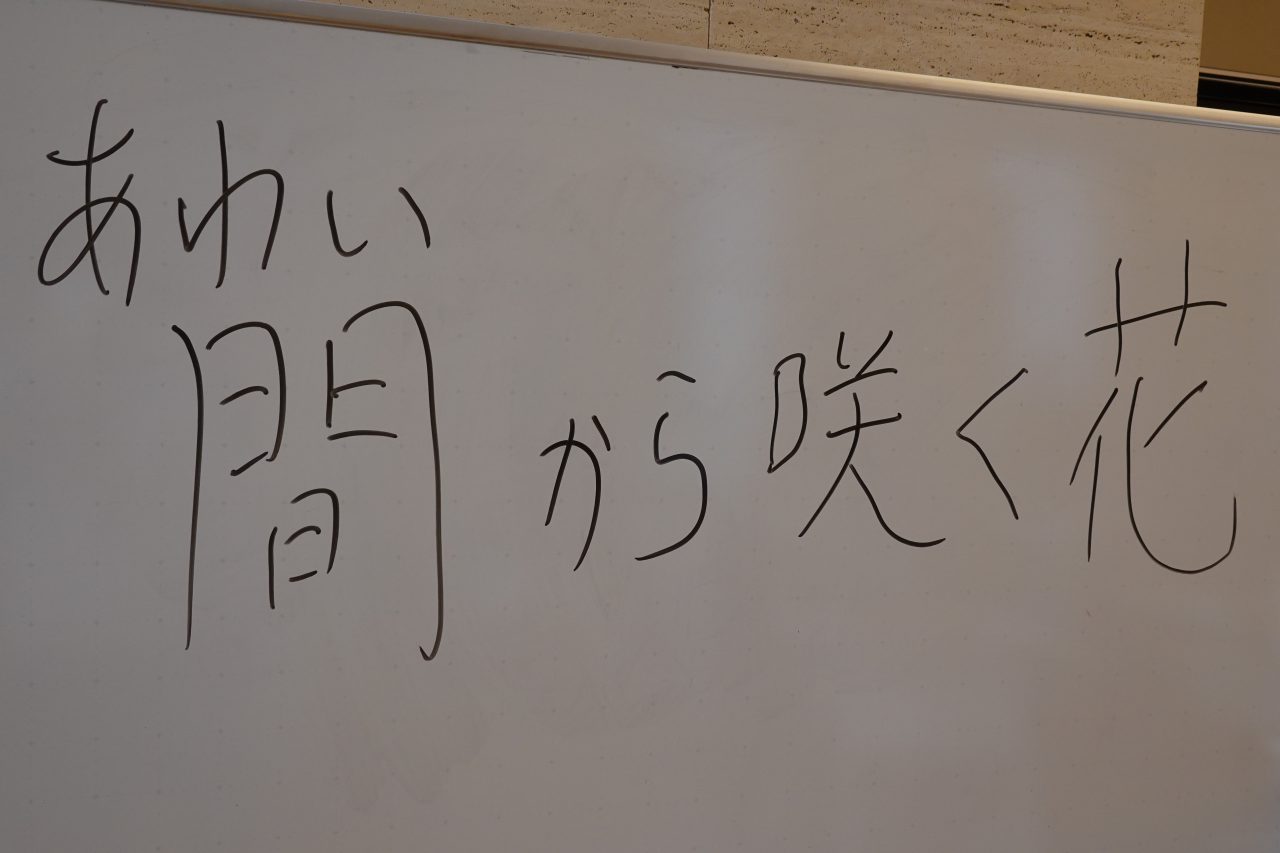
報告:髙山花子(EAA特任助教)
写真撮影:立石はな(EAA特任研究員)











