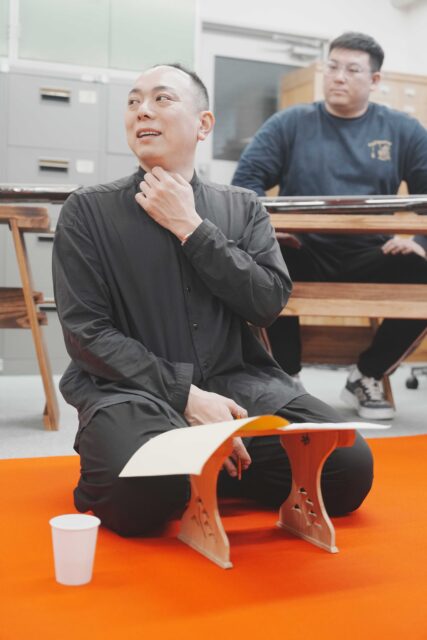2025年3月9日(日)12:30より、シンポジウム「「音楽を記す」行為の普遍性―東アジアの楽書・楽譜・物語からみる音楽への希望―」及び「吟樂琴 「南風」―『宇津保物語』に描かれる古琴」が、東京大学伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホールにて開催された。日本各地から、あるいは海外からの聴衆も含め、来場者は100名を超えた。
聴覚藝術である音楽を「書き記す」事には常に矛盾がつきまとう。それでも私達はなぜ「音楽を記したい」という欲望を持つのか。「音楽を記す」目的は、その音楽を後世へ伝えるためだけではなく、好ましい音律、演奏の背景にある精神性、人々と音楽の理想的な関わりなど様々な「希望」を表現する事でもある。さらにその記述を受容した人々の間で「書き記した」本人には予想もできない展開をする場合もある。本シンポジウムは、「音楽を記す」人・受容する人双方に目をむけ、そこから「音楽とは何か」という普遍的な問いへと繋げてゆく。
また、現代の私達自身が「書き記された」音楽に向き合い、新しい音楽を「書き記す」ことで、どのような思想的営為が生まれるかをも視野に入れ、中国の伝統楽器である古琴をテーマにした音楽劇「吟樂琴「南風」―「宇津保物語に描かれる古琴」」を同時上演した。
まずはシンポジウムである。千野裕子(学習院大学)は「平安朝物語文学に描かれる音楽―『うつほ物語』から平安後期物語へ―」と題し報告を行った。耳で音を聴き、その感想を抱き、批評するという行為は『うつほ物語』に初めて「書かれた」ものだった。『うつほ物語』は音楽物語であり、俊蔭一族によって奏でられる音のすばらしさが語られるが、もしも聴衆の耳が鈍感であったなら、俊蔭一族の音は価値を認められることはなかった。しかし一方で、俊蔭の娘を見初める藤原兼雅は、いくら鋭敏な耳を持っていても一族の音楽伝承の系譜に入ることはないのである。
続いて原豊二(天理大学)が「遣唐楽人の史実と虚構」という報告を行った。「遣唐楽人」と一口にいっても、その身分や役割は異なり、実際には中位や下位に挙げた人物たちは長安までは赴いていない。つまり彼らが習得した音楽が、長安の音楽そのものではなく、権威化されたであろう長安の音楽を模倣した沿岸部の音楽を摂取したと考えるべきである。このような音楽摂取事情が平安時代の 『うつほ物語』や『源氏物語』などに、直接的・間接的、時には大きく屈折して反映されているだろうと原は述べた。
唐代の音楽は日本音楽史を考える上で非常に重要な存在であるが、それでは、唐代の音楽とは一体何なのだろうか。中国の音楽史ではどのようなものとして位置付けられてきたのだろうか。
中純子(天理大学)の報告「宋代類書による唐代音楽像形成」では、宋初の類書、たとえば『太平広記』『太平御覧』が唐の音楽故事として引く資料は、中・晩唐以降の資料が多いことを指摘する。『新唐書』礼楽志には、玄宗期の音楽故事から、音楽と政治の関係を意識した物語を構築しようとする態度が見出せる。これらがさらに、宋代において陳暘『楽書』など音楽事典や『碧鶏漫志』など詞余理論書へ引用されることで、唐代音楽像が確定され、さらには日本雅楽の源流とされる唐代音楽理解に、類書が貢献している可能性もあるという。
現在、私たちがイメージする唐代音楽は、さまざまなレンズを通して描かれたものである。それでは、唐代の音楽文献には、何が書かれているのだろうか。田中有紀(東京大学)の報告「『楽書要録』が記す音律の世界」では、則天武后撰『楽書要録』における七声の理論をとりあげた。宮・商・角・徴・羽の相対音高を五声と呼び、これに変徴・変宮の二
変を加えて七声と呼ぶ。隋や宋代の七声をめぐる議論と『楽書要録』を比べると、たとえば音のグラデーションを日々の推移(暦の変化)と重ね合わせるなど、二変を、五声をより充実させるものとして捉えたことがわかる。また『楽書要録』は、音律に君臣秩序を読み込む志向は持っているが、清濁(高低)とは切り離す。 つまり、隋の鄭訳と同じく七声を主張するが、その理由は異なり、ある意味宋代の議論を先取りして回答を示しているようにもみえる。中国では失われ、読まれなかった『楽書要録』が描く音律論が、日本では、この音律論が「中国の音律論」として読まれるに至ったが、むしろ、その後の宋代の音律論のいくつかを先取りする内容があったのではないか。中国音楽のイメージが、先取りされるように日本にて形成され、中国の音楽論もそれに追いつくようなかたちで、同じようなイメージを形成していったといえるのではないだろうか。
「音楽を記す」行為は楽書や物語、楽譜に留まらない。とりわけ近代に入り、西洋音楽と向き合うよ
うになると、自らの伝統音楽をどう記していくか、さらに興味深い展開がみえる。
鍾鈺婷(清華大学、東京大学東洋文化研究所訪問研究員)は、音楽と言葉の関係を考える上で非常に重要な、詞楽を専門としており、「中華民国における詞楽研究の世界観:新発見の張寿『詞源校記』を中心に」として報告を行った。宋末から元初にかけて張炎が著した『詞源』は、戯曲研究史上、非常に影響力のある詞論である。これまで蔡楨『詞源疏證』が『詞源』の最初の完全な注釈本であると考えられてきたが、中華民国の張寿がそれよりも4年前に『詞源校記』を編纂している。校注が拠る版本は豊富であり、また張寿自らの考えも示され、さらには音律に関する注釈で西洋の音律論を用いるなど近代化の特色も有している。
近代に入り、様々な国や地域の音楽が否応なしに交流しあうようになり、また録音技術の誕生により、「音楽を記す
」行為が持つ意味も大きく変化する。金志善(東京大学)の報告「植民地期朝鮮における教育書やメディアなどで描かれる音楽」では、まず植民地期朝鮮において「検定」された音楽教育図書、たとえば認可教科書の『近世楽典教科書』と『高等女学校楽典教科書』を取り上げ、それらで紹介される楽典用語を紹介し、西洋楽典が和製漢語を通じて翻訳される過程を明らかにした。また、『京城日報』に現れる音楽関連広告や京城放送局開局日の音楽番組からは、朝鮮歌や長唄、西洋クラシックなど様々な音楽が紹介され放送されていたことが窺える。
東アジアの音楽はこのように、常に自分たちの音楽とは何かを意識しながら、それを記す行為を続けてきたが、現在の演奏家たちはどのように考えているのだろうか。
最後の報告者である王文(四川音楽学院、東京大学東洋文化研究所訪問研究員)はピアニストでもあり、「五線譜における中国音楽の韵律」と題して報告を行った。まず中西音楽の文化的・音楽的違いについて述べた後、中国の作曲家がどのように五線譜で中国音楽の韻律を表現するか、リズムと拍子(中国音楽は特別な記号を使用してリズムの弾力性と自由さを表現する
)、音高(中国の民間音楽や劇音楽で使われる微分音を、五線譜上では小さな矢印やスライド音符で表現する)、音価(中国の伝統音楽では感情の変化に応じて音符の音価が自由に延ばされ、たとえば無限回反復記号などが用いられる)、奏法(唱法)(琵琶の楽譜では古琴の「減字譜」に似た指使いや把位の記号が使われるなど、五線譜において中国の伝統的な記譜法を借りて演奏技法を記すことがある)の四点に分けて詳しく説明した。東西音楽の交流と融合が進む中で、各自の音楽文化の特徴を保持しつつ、どのようにして異文化間の音楽表現と創新を探求するかが、今後の音楽研究および創作における重要な課題となるだろうと述べた。
以上をふまえて、改めて「音楽を記す」ことを考えると、記された音楽は、その当時のありのままの音楽を思いがけなく描く場合もあるし、逆に、のちの時代のイメージによってもとの時代の音楽の姿が改変されたりする場合もある。しかしそのどれもが、書き手がどんな音楽を理想とし、どんな音楽を希望していたかを表現している。
いま、私たちはどのような音楽を理想とし、希望するのか。続いて上演した「吟樂琴『南風』:宇津保物語に描
かれる古琴」は、平安時代に生きた人々が音楽に託して描いた、人々の交流と伝承に関する希望の物語であるともいえる。この物語を再び私たちが現代に蘇らせることで、私たちはさらにどのような希望を音楽の中に見出すのか。
東京公演では、クアラルンプール公演とは出演者が少し異なり、語りを歌舞伎役者の中村橋吾が務めた。また琴の演奏には、劉勇剛(広州逍遥古琴工作室)、単立(広陵琴派)、邱爽(香港鳳宜齋古琴工作室)、井口玉燈(日本古琴振興会)が加わった。そのほかの出演者・スタッフについてはクアラルンプール公演の報告ブログを参照してほしい。中村氏は歌舞伎座での公演の合間に本公演のリハーサルに参加した。今回は日本語での語りのため、演奏家たち(大半は中国語話者)は琴の演奏の入るタイミングを覚えてうまく調整する必要があり、短い時間の中で集中して練習する必要があった。また原豊二氏は前日のリハーサルから参加し、日本文学の専門家の視点から様々なアドバイスを行った。
本番では、うつほ物語や平安時代の文学の専門家も多数来場した。東京公演では舞台の背景には何も設けず、音響や照明も最低限にし、語りと琴のみのシンプルな舞台となったが、中村氏の迫力ある声と、微かな音色でありながらもダイナミックな変化をつけた琴の技術がうまくかみ合い、最後の曲「大胡笳」が演奏されると、主人公清原俊蔭の家族を思う心と、曲の内容とが重なり合い、会場は感動に包まれた。
公演の様子は日本東方新報にも紹介されました。
http://www.livejapan.cn/static/content/news/news_chn/2025-03-10/1348713720234655744.html
報告:田中有紀(東洋文化研究所)