2022年6月9日、第7回 EAA「民俗学×哲学」研究会「異人論を再考する」が、EAAセミナールームとZoomでのハイブリッド開催で行われた。講師は、民俗学や日本思想史、社会学などを研究しながら、まちづくりや災害復興についての研究活動もしている関西学院大学教授の山泰幸氏。山氏は今回のテーマの異人論について、自身の研究人生を振り返る形で、語った。
異人論との出会いは学部生の頃に遡るという。その構造分析の手法が、シャープでクリアなものであり、魅力を感じたそうである。日本で異人論を最初に論じたという岡正雄から、山口昌男、さらには赤坂憲雄、小松和彦へと話は及び、日本における異人論の展開が振り返られた。とくに小松によって説かれた異人殺し伝説は、貨幣の浸透とともに旧来の共同体が解体していく物語として語られたというが、山氏は、共同体は本当に解体したのかという点に関心を持つ。貨幣経済浸透後に、異人(ボランティア、研究者…)はどのように扱われるか。また共同体内部のアウトサイダーともいうべき内なる他者に目を向けるべきだという。山口昌男の提唱したトリックスターという概念からすると、内なる他者がそれとして活躍できていると言えるとして、どうして活躍できているのか。山氏によれば、彼らを理解しサポートする者が内部に必要という。その上で山氏は、内なる他者を媒介的知識人という形でとらえようとする。共同体の内にいて、外からやってくる知識を共同体に媒介する存在として。そのような人物は、普段は付き合いづらいこともあるが、危機的な状況においては活躍をし、まさに共同体内部のアウトサイダーとして存在しているという。最後に、山氏が媒介的知識人という発想を得たのは、若い頃に江戸末期の憑きもの落としの事件を分析したのがけっかけであり、それに対応した平田国学系の地域の神官の話を展開しながら、それを民俗宗教的な事件ととらえるか、国学学問史としてとらえるか、立場によって異なってくるだろうとし、前回の本研究会で、梶谷真司氏(総合文化研究科教授)が提示した専門知と民衆知の接点ということに及んだ。
コメンテーターである報告者からは、自身が研究している旧制第一高等学校につき、特に地方から上京して一高に通っていた生徒は、帰郷すれば異人になりえただろうこと、日清戦争後、一高には中国から留学生が来ており、一高の中にも異人というべき存在がいたことに触れた上で、いくつか質問をした。まず、異人論の分析の鮮やかさに魅力を感じて、民俗学に入っていったというが、民俗学は、その方法あるいは対象、どちらから特徴づけられると考えられるか。山氏は、対象から入っていく傾向が強いとしつつ、アカデミックであるためには方法化が必要であるとし、コンテンツ重視の中で、分野に縛られずに適用できるという点で構造分析は魅力的であったとした。また、知識人というのは、異人的であらざるをえないだろうか、と問うた。かつて、シャーマンのような人は霊能者であり、医者でもあり、物語を制作する、総合的な知識人であり、知識人の原像であった。それが宗教者と学者というように分化していく。また現在でも大学教授ということで地域に入ると、その専門分野に限らず、なんでも知っている人かのように扱われる。外から来たというだけで知識人の相貌を持つのではないか。お雇い外国人はまさにそのようなものであった。それがやはり分化して、外来者が一方で貴ばれ、他方で蔑まれたりするという分化が生じてくるのではないかと、山氏は答えた。
Zoom参加者からも質問があった。秋光信佳氏(アイソトープ総合センター教授)からは、最初は異人でも時間が経つに連れて、異人でなくなるときがあるのではないか、またそうなるのを早める方策はないかとの質問があった。山氏は、内部に保証人を確保し、その人と義理の関係を結んで、メンバーシップを得るというのが古典的であり、また同じ釜の飯を食うというのはこれまた古典的であるが、長く付き合い、繰り返し会うこと、ともに食い 飲み、泊まることが重要であるとした。また、コミュニケーションのためには、内と外の人が出会うための中間的な場所が必要であるとし、それを受けて梶谷氏からは自分が地域に入るにあたっては、学校がそれにあたるとされた。通訳者というのも必要で、仮に日本において、日本語が通じる対象地であっても、コミュニケーションの間に何人かが挟まれることが必要であるとされた。
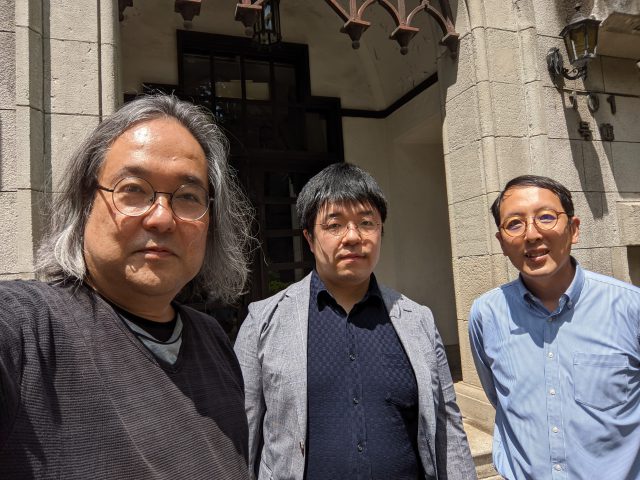
報告者:高原智史(総合文化研究科博士課程)








