2022年3月30日(水)15時から、EAAとの共催イベント「未来哲学研究所第4回シンポジウム 霊魂論の未来──情念・鎮魂・他者」が対面とオンラインのハイブリッド形式で開催された。会場からは、司会の山内志朗氏(未来哲学研究所副所長. 慶應義塾大学)、発表者の末木文美士氏(未来哲学研究所所長)、中島隆博氏(EAA院長、未来哲学研究所副所長)、オンラインで平野嘉彦氏(東京大学名誉教授)、佐藤弘夫氏(元東北大学教授)が登壇した。
初めに、末木氏より開催趣旨として、4回目となる今回のシンポジウムは、ウクライナ侵攻という事態もふくめ様々な意味で危機的状況にある現在において、霊魂という問題を今一度、文明圏を横断して考え直すための場であることが述べられた。また司会の山内氏からも、企画の意図として、21世紀が9.11の同時多発テロから始まり、今まさに世界大戦が起きかねない情勢のなかで、「怒り」の時代にあることと、この霊魂観の問題とが結び付けて考えられる可能性に思い至った経緯が示された。近代合理主義に突き進む中で周縁に追いやられた霊魂の問題に光を当てた時に、それぞれの時代、地域、言葉の違いの中にいかなる諸相が見出せるのか、そこを出発点として現代と未来への道筋をいかに考えることができるか、といった問いが投げかけられた。その上で、4名の発表へと移った。

山内志朗氏
最初の発表は、平野嘉彦氏による「ドイツにおける心霊思想、もしくは超心理学──デュ・プレルとシュレンク=ノッツィング」と題されたものであった。平野氏は、近代的自我の周辺に浮かび上がった夢遊病や脱魂、死霊という領域について、19世紀末から20世紀初めにかけてのドイツで展開された心霊の議論をめぐってデュ・プレル(1839−1899)とシュレンク=ノッツィングを対比させながら論を展開した。氏によれば、心霊思想に依拠するデュ・プレルは、死後においても霊魂の同一性を保持すると考えたのに対し、超心理学を標榜していたシュレンク=ノッツィングは、自我や意識は分裂し多重化すると考えていた点で、その霊魂観には重大な差異が存在した。但し、シュレンクの考えには「無意識」が前提されていた一方で、「霊魂」という語は殆ど用いられなかったことも指摘された。

平野嘉彦氏
続いて中島隆博氏は、「中国における霊魂論」と題して、中国哲学に蓄積されてきた「霊魂論」、そしてそこに深く関わる「鬼神」「精神」「心」「気」をめぐる論点を整理した。特に、危険で不安定な鬼神の暴力性が他者に及んでいくことを制御することが求められた中で、霊魂に対して交流を求めていく方向性と断絶する方向性とが拮抗する様を、『老子』『礼記』『国語』等とその注釈、范縝の『神滅論』をめぐる論争や朱熹の鬼神論等具体的なテクストに触れながら論じた。儀礼は双方の中間において特定の魂との交わりを肯定しようとするものであったが、それは、動植物や天地という人を超えたあらゆる魂との交流の可能性へと中国哲学を開く想像力でもあったと結論づけた。

中島隆博氏
三番目の佐藤弘夫氏の発表は、「語らう死者たちの誕生──日本列島における鎮魂の系譜」と題し、日本の東北などにおけるフィールドワークに基づき、日本列島における霊魂観や鎮魂の思想・儀礼の変遷をたどった。佐藤氏は、まず死者は身近にとどまるという柳田國男の霊魂観が古代以来のものではない点を指摘した。供養絵額(遠野)やムサカリ絵馬(山形盆地)といった地方に見られる死者表象に仏などの中世以来の宗教的救済者が存在しない点に着目し、中世から近世への世界観の転換を論じた。特に近世以降の「墓」参りの一般化は死者をケアする主体が仏ではなく遺族に移行したことを意味した。さらに、江戸後期から幕末には誰でもカミになれる認識が共有されるようになったとし、「ヤスクニ」の問題へとつながる議論を展開した。

佐藤弘夫氏
最後の発表者である末木文美士氏は、「心という回路――仏教哲学への一視点」と題し、仏教における霊魂は「心」を核心とするとして、この問題に対峙してきた南方熊楠や妻木直良の真如=霊魂論(『霊魂論』1906)などにおける問題意識を辿り、仏教の「真如」に関する議論につなげた。『華厳経』十地品を源泉とする仏教の「心」の理論は、理性による哲学とは異なり、三昧といった心を鎮める実践をもって悟りへと向かい、知恵を獲得していくものである。そこで玉城康四郎(1915-1999)の『心把捉の展開』(1961)における作為から自然へ、世界への開かれへと向かう議論(人為的に心に一切を映す心の修行から人為的心が消えていき、世界そのものに開かれる)を参照し、心を通して他者へ開かれる道筋を親鸞、道元にも見出した。最後に、インドの瞑想世界、神智学、ロマン・ロラン、中村元・井筒俊彦へも言及し、瞑想によって世界に開かれる東西の統合の可能性を示した。
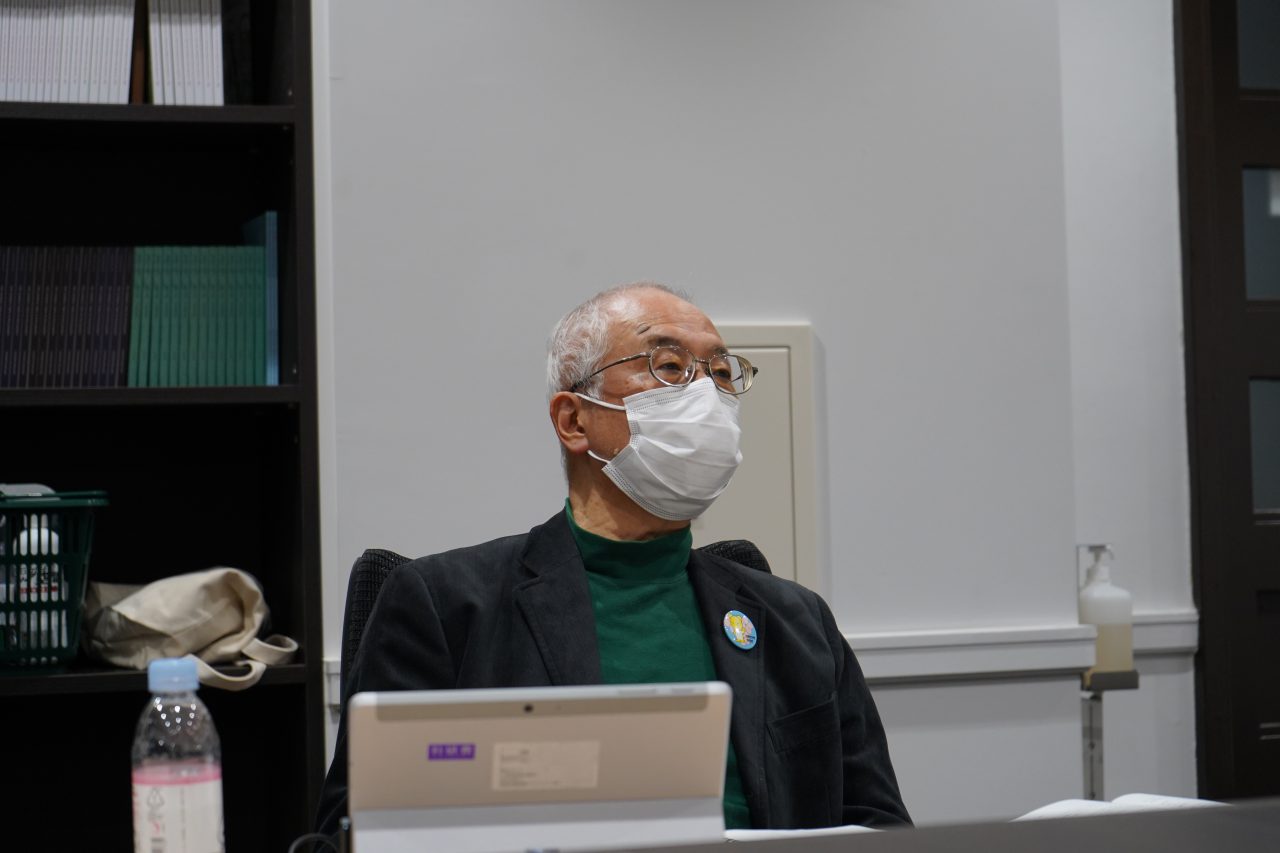
末木文美士氏
休憩を挟み、質疑応答及び登壇者同士の討議の時間に入った。朱熹の鬼神論の現代性、霊魂の個体性と普遍性の問題、そこからさらに霊魂の交わりだけではなく変容と倫理の問題を考える必要性や個体的な心から普遍性へ拓かれていく可能性、現在の戦争や政治との関わりなど、霊魂をめぐって古今東西に亘る諸相に触れながら議論がとり交わされた。
以上、近代合理主義以降に後景化したかにも見えた「霊魂」というテーマは、しかし古来東西にわたり重要な思想の系譜をなしており、そして現在の喫緊の課題を照らす可能性を有するものであることが改めて明らかになったと思う。
そして、司会の山内氏も触れていたように、今回の登壇者である末木氏と中島氏の2001年の共編著『非・西欧の視座』(大明堂)での異なるフィールド同士の交わりから20年の時を経て、末木氏編で出された中島氏も対話者となっている『死者と霊性――近代を問い直す』(2021年8月、岩波新書)まで、粘り強い思索と対話の糸が繋がっていることを感じた。『死者と霊性』では、3・11の東日本大震災と原発事故や収束の全く見えないパンデミックという近代合理主義では解決のつかない事態を前に霊魂の問題が浮上してきたことが示されていたが、今回のシンポジウムでは、ロシアのウクライナ侵攻による戦争の現状をもって、より差し迫ったものとして挑まれたように感じられた。
本シンポジウムは、日本仏教、中国哲学、民俗学的フィールドワーク、そしてドイツ近代にわたる霊魂・鬼神観の変遷や問題の所在を眺められる貴重な機会となった。それらを突き合わせることは、すぐに見通しの良い理論や解決法を見出すことを目的とはしていなかった。無理にそれぞれを繋ぎ合わせることは危険であるし、それよりも各フィールドで浮かび上がってくる問いの場所について、対話を交わしながら、注意深く、時に大胆に揺り動かすことによって、現在に結びつけることが重要なのであろう。そして、なによりも私達ひとりひとりの問題として受け止め、この個別性から出発して普遍へと開いていく努力が必要であろう。その回路として実践と「心」の領域を提示された末木氏の発言は、どの分野においても大きなヒントとなると感じた。自身のフィールドでも、この問題を粘り強く考え続けていきたい。
報告者:宇野瑞木(EAA特任助教)








