2022年3月19日(土)日本時間14時より、第9回東アジア仏典講読会を開催した。今回は佐久間祐惟氏(東京大学大学院・日本学術振興会特別研究員DC)より「虎関師錬の修証論」と題する研究報告がなされた。
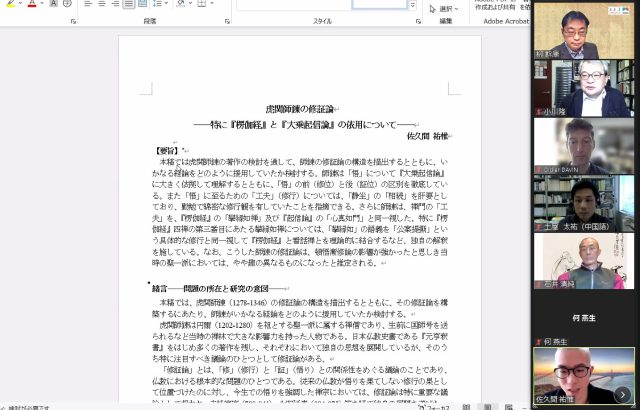
虎関師錬(1278-1346)は鎌倉後期から南北朝期にかけて活躍した禅僧であり、当時の禅林に大きな影響力を及ぼした。日本で初めての仏教史書『元亨釈書』を著したことで有名であり、先行研究も多く為されているが、これまで見落とされてきた重要な問題がある。それが修証論である。
修証論は「修」(修行)と「証」(悟り)との関係性をめぐる議論であり、仏教の根幹に関わる重要なものである。近年、中国禅宗における修証論の展開が解明されつつあり、それにともない虎関師錬の思想を新たに読み解くことが可能になったという。佐久間氏によれば、その修証論を考えるうえで参照すべき人物に、(1)馬祖、(2)宗密、(3)延寿、(4)円爾、および(5)円爾門下の禅僧らがいる。(1)馬祖は本来仏である己の心に気づくことを「頓悟」とし、それに気づいた後はただあるがままに時を過ごせばよいとしたが、(2)宗密はそれを批判し、仏である心に気づいた後も長期に亘る修行(漸修)により煩悩を除去すべきであるという「頓悟漸修」論を説いた。その後(3)延寿は両者の議論を承けつつ、馬祖の立場を「頓悟頓修」――仏心の自覚のもと“仏として”ありのままに過ごす理想的境界――と捉え直し、そこに至るための一段低い実践として宗密の「頓悟漸修」論を排した。のち(4)円爾は延寿の説を承けて「頓悟頓修」「頓悟漸修」の双方を説いたが、(5)その門下では「頓悟漸修」により悟る前の修行を「イタヅラ事」とし、実践を軽視する弊害が現われたという。
このようななか、禅宗の伝統を遡り、独自の修証論を構築したのが、虎関師錬であった。虎関師錬は円爾の法孫であるが、円爾の修証論が延寿の主著『宗鏡録』に基づいていたのに対し、自身は『楞伽経』『起信論』に依拠する。『楞伽経』はインドから中国に禅を伝えた西天(インド)28祖、東土(中国)初祖の達磨が弟子の慧可に授けたとされる経典であり、『起信論』は西天12祖の馬鳴が著した『楞伽経』の注釈書とされる。『宗鏡録』よりも遙かに時代を遡る禅宗祖師と関連の深い両書に依拠した点に、虎関師錬の伝統回帰の志向が見いだせる。
両書に基づき虎関師錬が構築した修証論は、「修位→契悟→証位」と次第に深化する直線的な構造が基本となっている。うち「修位」(悟りに至るための修行の段階)は主に『楞伽経』と『起信論』に依拠しており、南宋期に大成された看話禅(公案の参究により悟りを得る実践法)もそこに取り込まれている。「契悟」(悟り)の理解は『起信論』に大きく拠っており、汚れが除去された清らかな心に契合することだとされる。そして「証位」(悟りを得た後の段階)として示されるのが、『楞伽経』に説かれる如来禅(衆生を救済する仏の禅)である。この修証論からは、綿密な実践を貴ぶ勤勉な修行観を読み取ることができるという。
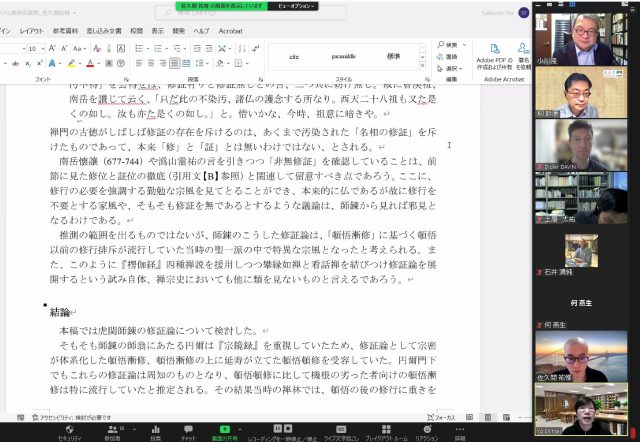
如上の佐久間氏の発表に対し、参加者からは虎関師錬の公案に対する理解、公案と坐禅の関係、禅と密教の関係などについて質問がなされ、活発な議論が行なわれた。佐久間氏が述べる通り、虎関師錬は従来注目されながらも、その「修証論」という重要な思想は分析されていなかった。それが今回、中国禅思想の展開の延長線上で解明されたことは、非常に意義深いことである。同氏の今後の研究により、虎関師錬の思想の全容が解明されていくのが楽しみである。
報告者:柳幹康(東洋文化研究所)








