
2022年3月9日(水)日本時間15時より、第2回EAA研究会「東アジアと仏教」を開催した。この研究会は、人と仏教の交錯から東アジアの歴史や文化、思想、芸術などを照らし出そうとする試みである。第二回となる今回は一色大悟氏(東京大学大学院人文社会系研究科助教)が、「仏教思想として日本の近代仏教学を再考する:輪廻批判・縁起説論争・仏教研究法」と題して研究発表を行なった。なお司会は柳幹康(東洋文化研究所准教授)が務めた。
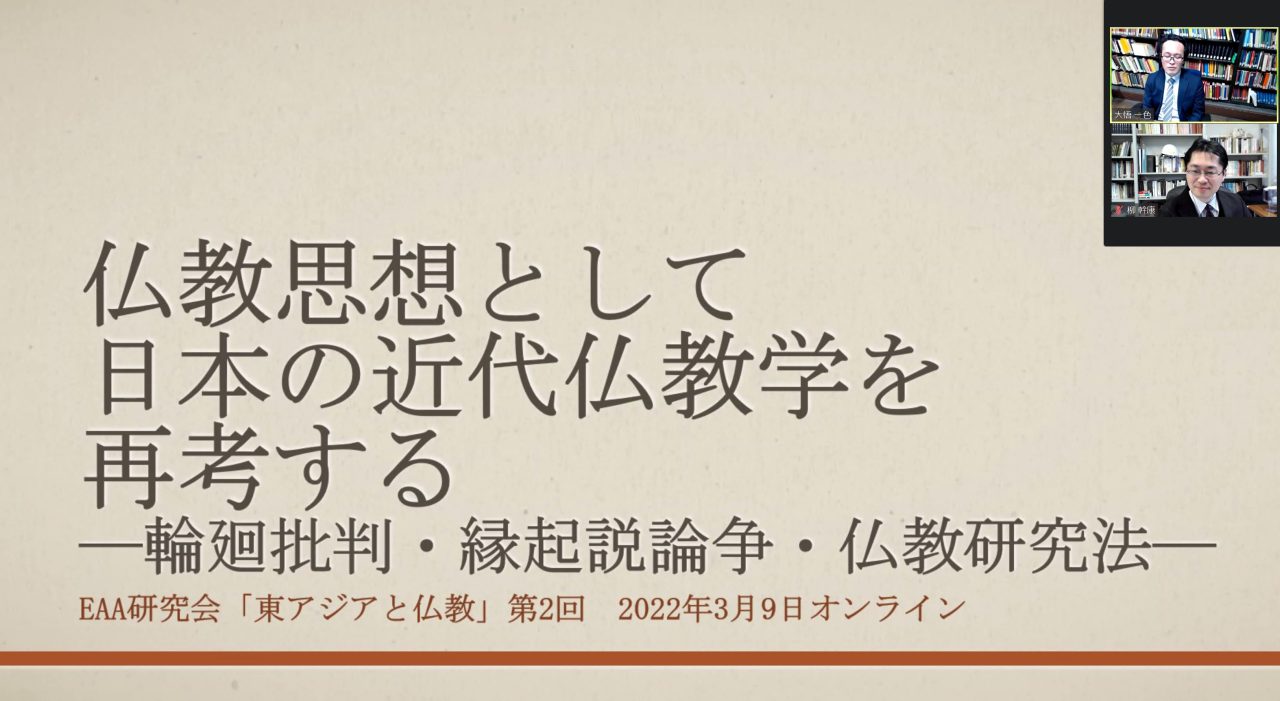
一色氏は「アビダルマ」と呼ばれるインド仏教の解釈学を専門とする仏教学研究者であり、近年では日本の近代仏教学を仏教思想として考察する研究を進めておられる。氏によれば「アビダルマ」の理論体系と近代仏教学とは、仏教の初期経典を資料とする解釈学としての側面を共有しており、「アビダルマ」と同様に近代仏教学も仏教思想の一種として考察することが可能であるという。そのような企図のもと今回は、近代日本において、多くは僧侶でもあった仏教学者たちが、西洋から伝来したインド学という新たな知識体系を参照しつつ、どのように仏教思想を近代的に再解釈しようとしたか、あるいはどのように仏教聖典を読みこなすことで再解釈が可能になると考えていたかを分析していただいた。その内容は大きく以下の2つ――(1)明治期に仏教学においていかなる課題が生まれていたのか、(2)仏教の再解釈が問題となる大正期においていかなる理解が示されたのか――である。
(1)明治期に仏教学が直面した課題として氏が着目するのが聖典解釈論(仏教研究法)と輪廻批判の二つである。仏教では伝統的に輪廻説をその前提とし、聖典の増加・多様性を認めるものであった。それに対し西洋由来の文献学では、文献の比較により教説の真偽を見極める、文献の新旧の弁別を通して仏教本来の姿を求めるなどの削減の論理を有していた。また死んだ後に新たな生を得るという輪廻説は、一生涯という期間に限定された人間に経験されえない事柄であり、その論拠は古来聖典に依存していた。西洋由来の聖典削減の論理が広まった明治20年代を分水嶺として、輪廻説も非科学的なもので真理ではないと批判され、やがて知識人・研究者により語られることがなくなっていった。かくして、聖典・輪廻の二点において伝統的な仏教観とは大きく異なる近代仏教学が成立するにいたったのである。
(2)このような「科学的」な仏教研究に対し、大正期になると複数の仏教学者から疑問が呈され、伝統的な仏教教理の再定位が試みられるに到る。一色氏はそれを行なった重要な人物として木村泰賢と宇井伯寿の二人を挙げる。両者は帝国大学印哲研究室の二代目・三代目教授であり、ともに曹洞宗の禅僧であった。
木村は業と輪廻、あるいは行為が人生をいかに変えるかというテーマを生涯にわたって問い続け、伝統的には輪廻を前提に解釈されていた「十二縁起」を、「生きようとする意志」に端を発する人間形成の過程として新たに解釈した。また木村は輪廻を、積極的な人生を可能たらしめるものと解釈する。すなわち木村によれば、人は輪廻を「確信」することによって、「運命に安んじながらも喜んで善と正義とに固執して、人のために尽くすこと」ができるのだという。一色氏はこれを菩薩道の観点からの輪廻説、聖典解釈論とみる。
一方、宇井は文献学的手法によりその限界を示すことで、自身の信じる「仏陀の根本思想」を語る余地を生み出している。すなわち仏教の原点たる仏陀自身の思想を知るための根本資料となるのが原始仏教の経(仏陀が語った教え)と律(仏陀が制定した規則)であるが、そのいずれも不足しており、その原点に文献学的に遡ることはできない。そこで宇井が採用する手法が、不足している経・律に加え、仏陀の重要な事蹟と当時の一般的な思想とを合わせ見ることで、「最も確実にして何人も疑わない」ような「仏陀の根本思想」を推論するというものである。このような宇井の戦略について一色氏は、禅宗の「教外別伝」(教えの外で別に伝えるという)説の影響の可能性を見る。文献学の手法を教(経・律)に限定し、それを超えた真理を推論に委ねることで、学術領域の客観性と自身の信念を両立させようとしたのではないかと考えるのである。
以上の分析ののち、人文学を含めたいわゆる「総合知」の概念が提示され、学術の価値創造が強くうたわれる昨今の日本学術界の動向を参照したうえで、「仮にここで仏教学が、その解釈論の枠組みを見直そうとするならば、現在を規定した近代仏教学が研究される必要があろう」と述べ、講演を結んだ。
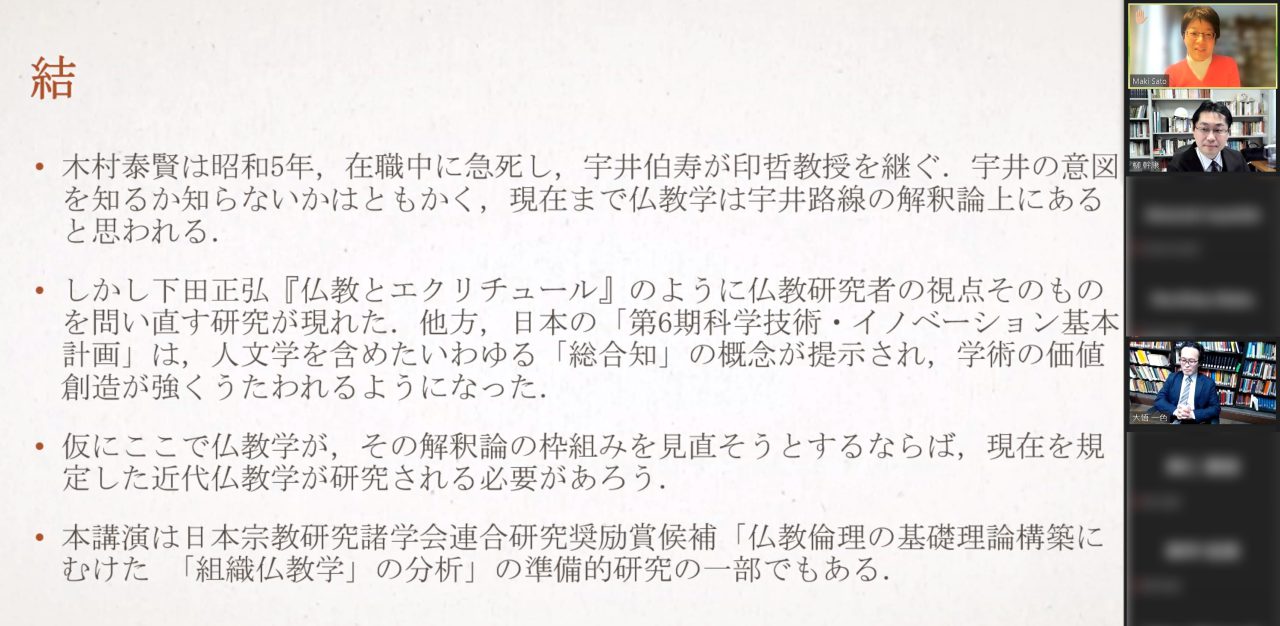
その後、参加者より様々な質問が寄せられた。たとえば、「木村の十二縁起の解釈と輪廻への確信はどのような関係にあるのか」「宇井に見られるような禅的な解釈が木村にも認めうるのか」「西洋の仏教学の同時代的な影響はあるのか」「仏教学者の学説を批評する際に、その出自に注目することは適切なのか」「そこに近代の文脈だけでなく、研究対象である古代インドの文脈も合わせて見る必要があるのではないか」などである。これらの質問に対し一色氏によりそれぞれ返答がなされ、活発な意見交換が行なわれた。
当日は平日昼間の開催であったにもかかわらず、貴重な時間を割いて約30名もの方にご参加いただきました。この場をかりて改めて篤く御礼申し上げます。
報告者:柳幹康(東洋文化研究所)








