2022年1月26日(水)日本時間15時より、EAAシンポジウム「仏教と哲学の対話」を開催した。このシンポジウムは仏教と哲学の双方に通じ、独自の新たな研究をなさっている守中高明氏(早稲田大学法学学術院教授)と下田正弘氏(東京大学大学院人文社会系研究科教授)のお二人をスピーカーにお招きし、馬場紀寿氏(東京大学東洋文化研究所教授)の司会のもと開催されたものである。
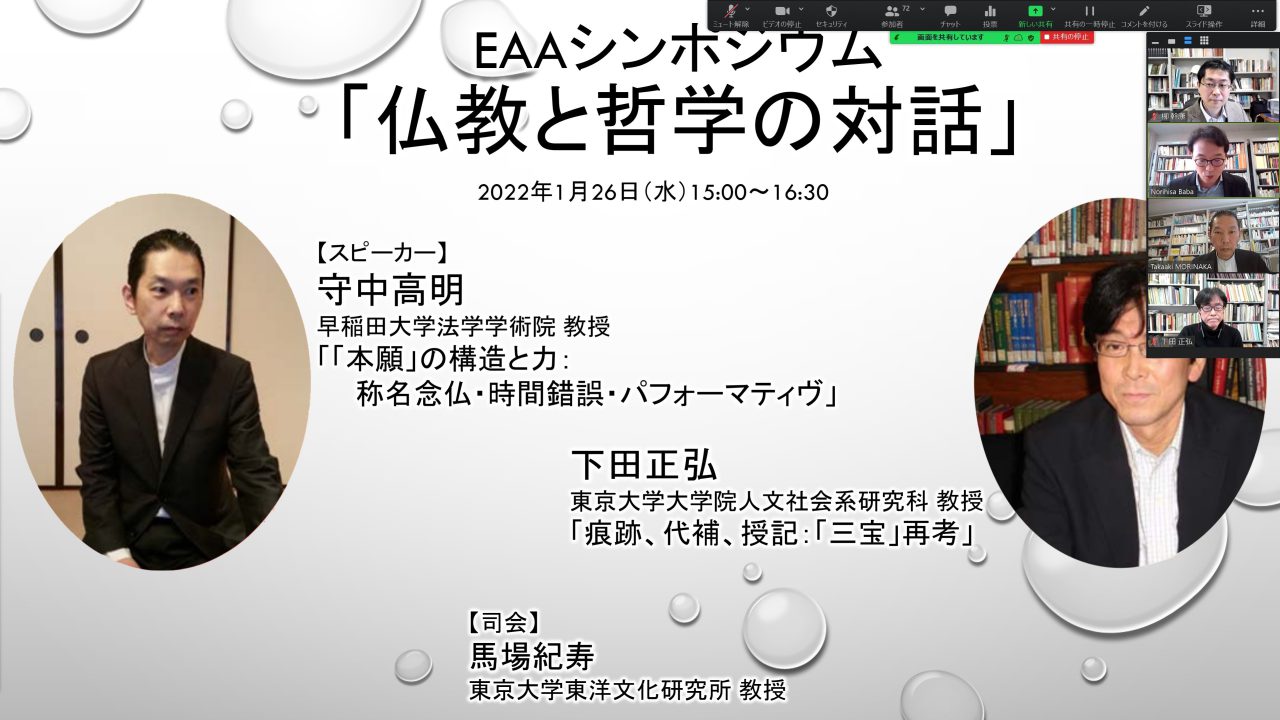
守中氏はフランス現代哲学・詩学の研究者であり、ジャック・デリダやジル・ドゥルーズなどの思考を援用しつつ仏教における他力・浄土の教義に深く切り込んだ『他力の哲学』『浄土の哲学』を出版されている。
下田氏は大乗経典を研究する仏教学者であるが、その起源の分析にあたってジャック・デリダの哲学を導入し、新たな議論を展開しておられ、『仏教とエクリチュール』を出版されている。
それぞれご自身のなかで仏教と哲学の対話を重ねておられるお二人をお招きし、このシンポジウムにおいて新たな対話をしていただき、さらには聴講に来ていただいた参加者も交えながら議論を深めたいという企図のもと、本シンポジウムが企画された。
当日はまず守中氏より、「「本願」の構造と力:称名念仏・時間錯誤・パフォーマティヴ」というタイトルでご講演いただいた。それは今日も日本で行なわれている称名念仏(口に仏の名を称える実践)をとりあげ、その行いが背後に秘めた高度に錬成された論理――人々を常に別なる生へと解放する現実的効果をもつ論理――の構造と力を分析するものであった。
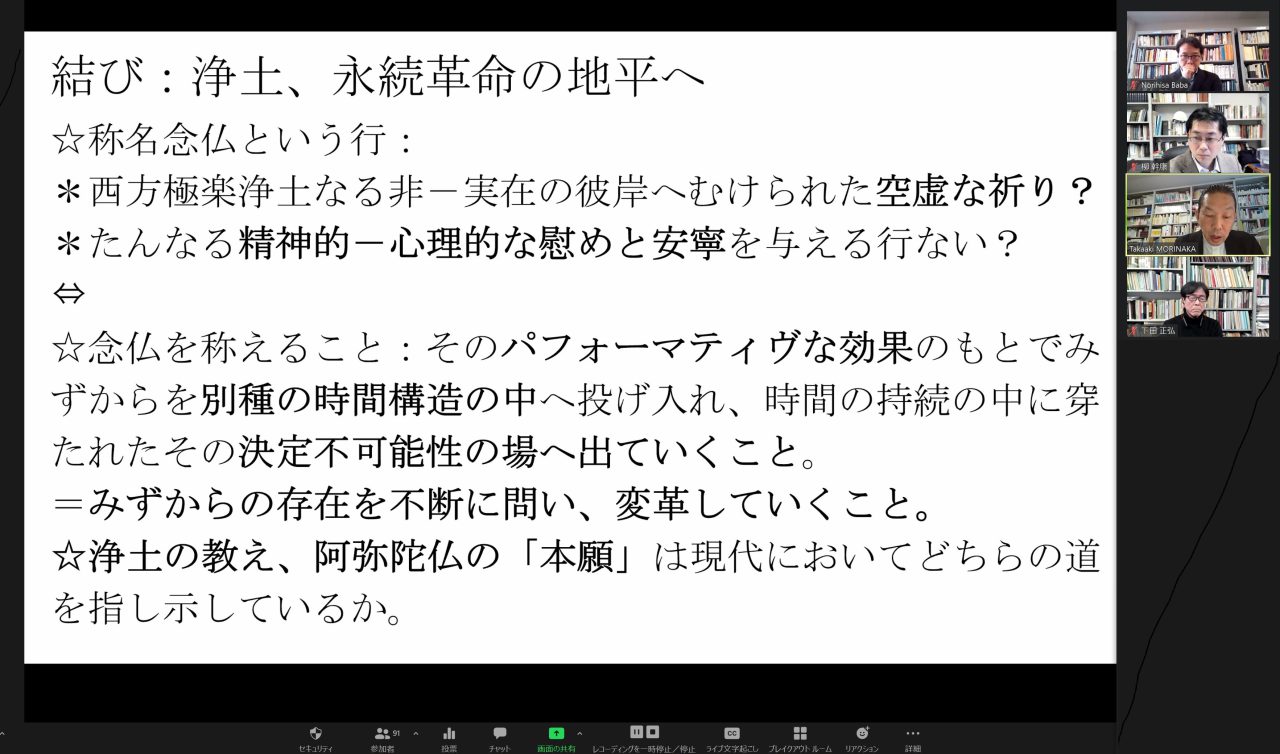
「南無阿弥陀仏」と称えることで、末法を生きる誰もが西方極楽浄土へ往生できるとする「称名念仏」は、中世の法然が提唱した教えであり、それは仏教を歴史的にも思想的にも大きく変革するものであった。
歴史的にみればそれは一種の宗教的階級闘争であり革命的な力を及ぼした。浄土教の平安的パラダイムでは、戒律を守り厳しい修行ができる僧侶や、経済力を背景に仏教を外護する貴族など一部の人にのみ救済の道が開かれていた。それに対し法然の「称名念仏」は、ながらく排除されていた数知れぬ庶民たちをも平等に解放する教えであった。
また思想的にみればそれは、以下の二点で劃期的であった。
第一に、「称名」に行を集約した点である。従来の「念仏」には、仏の十種の名を心に強く思う、瞑想において諸仏の顕現を得る、雑念を払って仏の姿を観察するなど様々な実践があったのに対し、法然は中国の道綽・善導の解釈を承けつつ、「念仏」を「阿弥陀仏の名を称すること」へと組み替え焦点化した。
第二に、阿弥陀仏の「本願」に基づき救済の理路を確立した点である。法蔵菩薩は悟りを開いて阿弥陀仏となる前に四十八の誓願を立てたが、それらはすべて「たとえ私が仏になることができたとしても、~ならば私は正しい悟りを得た仏にはなるまい」という構造をしている。そして法然が中心にすえた第十八願はこの条件と仮定を「私の名を称することわずか十回であっても、もし浄土に生まれることができなければ」としている。しかるに、かつてこの誓いを立てた法蔵菩薩がすでに悟りを得て仏となっている以上、この誓いは実現しており、それゆえ念仏する衆生の救済もまた、つねにすでに約束されていると法然は説いたのである。
この法然の「称名念仏」による救いは、前近代的の神話的物語に還元されるものではなく、現実的な出来事であるという。このように言える理由として守中氏は以下の二点を挙げた。
第一に、「南無阿弥陀仏」、すなわち「南無:帰依」+「阿弥陀仏:無限者」=「帰依‐無限者に」という一句は、パフォーマティヴな発話である。それは、そのつど一回かぎりの状況を遂行的に産出する。「帰依‐無限者に」と口に称えることは、帰依しているという「事実」を確認しているのではなく、帰依という行為そのものを発話によって遂行しているのであって、無限者への帰依という場面をそのつど新たに作り出す。「称名」とは、法蔵菩薩の誓願を範例として、それを自身も反復することにより法蔵菩薩と同様に仏となることを願う言表である。そのとき「衆生」は法蔵菩薩=過去の阿弥陀仏の分身となる。称名念仏する者は、社会的属性・能力・資質など一切の差異と関係なしに、その言表の行為体として「平等」となるのだという。
第二に、称名念仏により一種の時間錯誤、すなわち「未来完了」という特異な構造が開かれる。「未来完了」とは、「それは‐あった‐ということに‐なるだろう」ということを示す時制であり、みずからの成仏を仮定のもとに約束する法蔵菩薩の誓願の時間構造は「私は‐仏となった‐ということに‐なるだろう」という「未来完了」に他ならない。称名念仏を実践する者は、「過去において“いまだ”仏となっていない」と「未来において“すでに”仏となった」という二つの時のあいだに宙づりにされる。このような「いまだ」と「すでに」のあいだに刻まれる「現在」を欠く決定不可能な時とは、「生ける現在」がそこから派生してくる前‐起源的な「痕跡」ないし「間隔化」とデリダが呼んだ場面であり、その時刻を告げる「南無阿弥陀仏」とは「決定不可能命題」(ゲーデル)であると言ってよい。しかし、決定不可能な場面に身を投げ入れ生きることは、曖昧な無力さにとどまることを意味しない。根源的な時間の変容を引き受け、閉じざる未来完了という別種の「無限」を生きることは「革命的な決定の場」(ドゥルーズ&ガタリ)を産み出すことを意味する。称名念仏の反復によってこの経験領域を不断に押し広げていくことこそが、この穢土を浄土へと生成させていくことであり、「往生」とはそのようなリアルな出来事なのだという。
以上の議論を踏まえたうえで、守中氏は以下のように話を結ばれた。「称名念仏という行を、西方極楽浄土なる非実在の彼岸へ向けられた空虚な祈りだと理解し、たんなる精神的・心理的な慰めと安寧を与える行いと捉えるか。それとも、念仏を称え、そのパフォーマティヴな効果のもとでみずからを別種の時間構造の中へ投げ入れ、時間の持続の中に穿たれたその決定不可能性の場へ出て行くことによって、みずからの存在を不断に問い、変革していくか。浄土の教え、阿弥陀仏の「本願」は現代において、果たしてどちらの道を指し示しているでしょうか」。
つづいて下田氏より「痕跡、代補、授記:「三宝」再考」というタイトルでご講演いただいた。
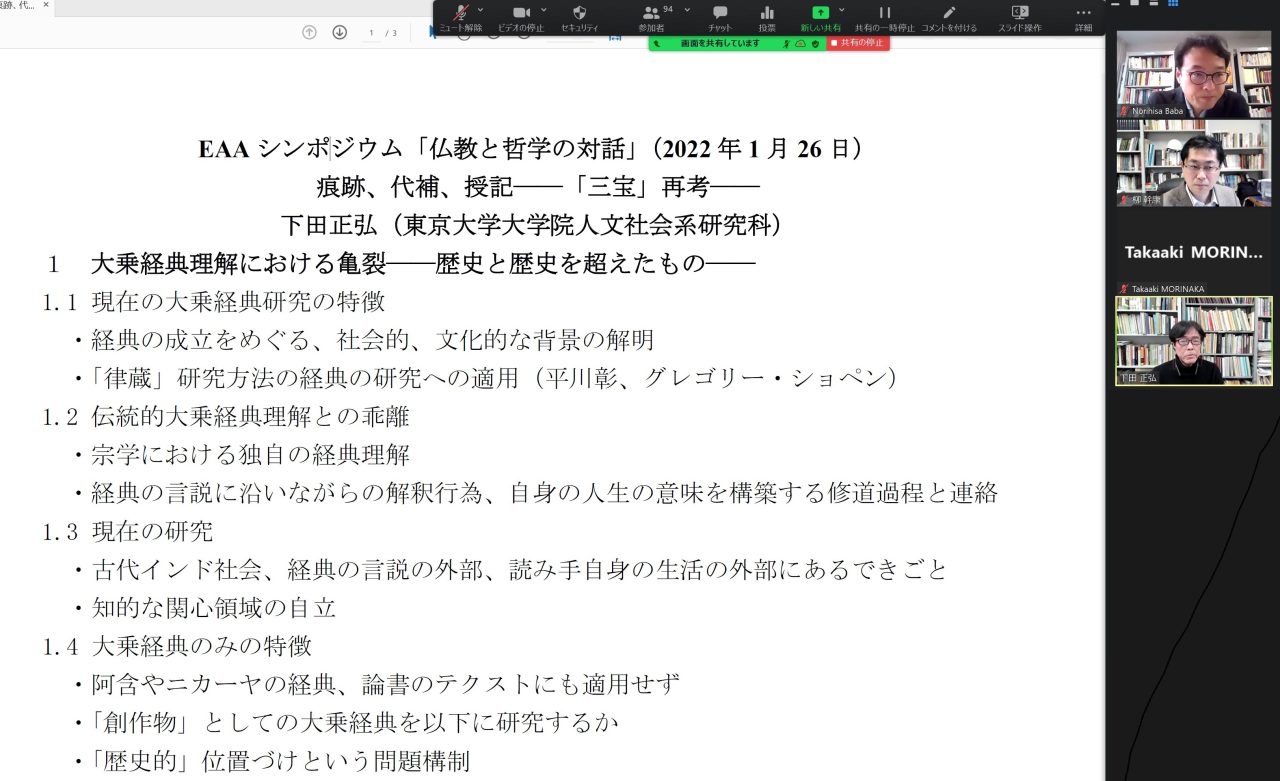
まず最初に、仏教研究に対する危機意識を述べたうえで、講演の趣旨説明がなされた。大乗経典をめぐり、近代仏教学は伝統的理解と乖離しており、両者の間には亀裂がある。大乗経典に対する伝統的理解とは、おもに各宗派で継承されてきたものであり、それは自身の修道と連関する形で、経典を解釈するものである。それに対し近代仏教学は、大乗経典を歴史的に位置づけることを目的とし、その社会的・文化的な背景の解明に傾注してきた。近代仏教学では経典を読み手自身の生活の外にあり、自身の生き方に関わらない、古代インドの歴史に限定された過去のものと見るのに対し、伝統的理解ではそれを自己の人生の意味を構築するもの、今も意味を産出しつづけるものと見る。これは、思想と歴史の研究態度に関わり、近代以前と近代以後の狭間に現われた重要な差異であって、ここにポストモダンの思想家たちの思索を参照すべき所以があるという。
このような問題設定の後に、歴史において「起源」を問うことの問題に考察が加えられた。テクストの聖典として幾世紀にもわたり発揮してきた役割とその歴史的特性に注目するウィルフレッド・キャントウェル・スミス、「遅れて」の解消不可能性というフロイトの発見を論じるジャック・デリダの議論を参照したうえで、聖典というテクストの起源は、それが誕生した歴史的状況の光景に求められないことが指摘された。そのうえで、「無意識のテクストはすでに純粋な痕跡、差異によって織りなされている。そこでは意味と力とが一体化しており、これはつねにすでに転記であるような複数の古文書によって構成された、どこにも現前しないテクストであり、起源的な版画である。すべては複製によって始まる。換言すれば、つねにすでにまったく現前したことのない意味の貯蔵庫である。というのも、この意味が指し示す現在は、つねに遅れて(nachträglich)、事後に、代補として再構成される」というデリダの議論を踏まえ、大乗経典が常に新たに産出されつづける起源は、釈迦仏という「充実した起源」や「現前する起源」にあるのではなく、その起源を否定しつつ「代補」する「差延」という作用にあると述べられた。
下田氏によれば以上の痕跡・代補・差延は、大乗経典の理解に留まらず、三宝という仏教の核心の問題理解に深く関わる。三宝とは「仏」(ブッダ)、「法」(ダルマ)、「僧」(サンガ)という仏教を構成する三つの宝であり、その重要性は各地に展開した仏教において一貫して承認されてきた。近代仏教学、具体的には仏教全体の歴史を描いたヘルマン・オルデンベルクの『ブッダ――その生涯、教理、教団』(1881年)以降、仏が生まれ、彼により説かれた法が出現し、それが弟子たち、僧に伝えられたことで仏教が成立したという、仏から僧までの直線的な展開による三宝理解が定着している。これは三宝の意義の起源を、釈迦仏という歴史的な「充実した起源」に求めるものである。ところが古代から継承されてきた仏典では、三宝をめぐり、これとは異なる精緻な考察がなされている。そこからは、三宝のそれぞれが、差延を起源とし、時間の中ときどきに代補として展開してきていることが明らかになるという。
たとえば教団の規則全体の「起源」を記したとみなされる、パーリ律蔵「大品」の冒頭は、三宝の出現と展開という観点から解釈されるという。この「起源」は「仏の悟り」にある。仏は悟った当初、悟りの経験を自身のうちで無言のまま享受しており、この段階では悟る主体の仏と、悟られる対象の法とは一体となっている。「梵天の勧請」に応答して仏が法を説いたとき、仏と法とは個別化されると同時に、法は所証法(悟るべき対象としての法、真理)と所説法(語るべき対象としての法、教説)とに分岐する。このうち所証法は仏の体験として存在する「法の内部」であり、所説法は衆生・僧に言語をとおして接する「法の外部」である。たしかに、法が内外へと分岐したとき、仏と僧とは成立している。けれども、ここで法を二方向に分岐せしめた「起源」は、仏と僧を同時に発現せしめた「起源」でもある。すなわち、三宝のいずれの宝も、自立したものでも、時系列をなして展開するものでもなく、差延による代補として成立している。
かかる三宝は、仏の入滅を経て、更に複雑化する。その現われは、三宝のうちいずれを中心とするかによって異なる「起源」の様相を呈する。仏を中心とすれば、釈迦が入滅しその肉体が失われた後、法・律の教法(法身)と、その身体の痕跡(遺骨)を納めた仏塔(色身)がそれに代わる。そこにおいて、仏という、歴史に実在する起源と見えていたものは、いま現に存在する教法や仏塔から事後的に再構成される代補である。また、法を中心とすると見えるものに、法こそが仏を生み出す根拠であると主張する経典がある。けれどもその経典の法は、仏によって説かれつつ出現するものであり、説いている仏の事後的な代補としての起源となっている。最後に、僧を中心とすれば、釈迦の入滅により、仏と法が僧に移譲されたことで、以降、仏と法は、見かけのうえで僧に包摂されているため、僧の歴史の「起源」が仏教の歴史の「起源」となる。けれども僧の存在意義は、あくまで仏と法の実現にあるのであって、歴史上のいかなる僧も、仏と法からの差延として、それらの代補としての起源となっている。
仏教の「起源」を問う際、近代仏教学はそれを釈迦という歴史的人物にのみ求めてきたが、それは、しばしば現前する歴史的事象に展開した歴史全体を還元する過ちを犯す。そこでは、「起源」からの歴史はいまも連続しているという視点が落ちてしまう。そのような視点から「起源」を問うにあたり重要となるのが、上述の三宝の展開、および「仏」の誕生に関する「授記」であるという。授記とは、仏が修行者に対して「将来の成仏の確約」(記)を「与えること」(授)であり、釈迦もまたはるかなる過去世において修行者であったころ、燃灯仏という仏により将来仏になるという予言を受けたとされる。これによれば仏教の起源は、過去において釈迦が他者より「未来に仏になる」と開き示されたところにあり、釈迦が悟りを開いて「仏」となったのは、この過去における授記という行為の、未来における完成なのである。
三宝により織りなされてきた仏教の歴史は、この授記を視野に収めることで、その起源、差延、代補として現われてくるのだいう。また下田氏は最後に、仏教を理解する基盤が文献学であることは過去も未来も変わらないが、「それにより何がどう読み取られていくのか」という問題を明らかにしていくこと、研究対象とともに研究者の意識をも分析することが必要であり、そうすることによって、資料に厳密に向き合うことの意味が、歴史の事実に根を下ろしながら明らかになってくるという見方を示された。
以上の両氏のご講演の後、馬場氏の司会のもと、未来の成仏を過去に決定する「授記」の動態的な時間構造や、その構造の反復により織りなされる時間と、近代仏教学が前提とする歴史的な時間との相違、その二つの時間にどのように向き合うのかという問題を巡って守中・下田両氏の対談がなされた。また参加者からは授記(開かれた未来に対する言及)と無記(世界などの起源について言及しないこと)の関係や、未来完了という特殊な時間構造に人を投げ込む称名念仏の理路などについて質問が寄せられ、活発な意見交換がなされた。

シンポジウムは平日の昼間に開催されたものであったが、幸いにして90名以上もの方々にご参加いただけた。素晴らしいご講演をいただいた守中先生と下田先生、司会をご担当いただいた馬場先生、貴重な時間をさいてご参集くださった皆さまに心より感謝申し上げます。
報告者:柳幹康(東洋文化研究所)








