2021年12月28日(火)、29日(水)、共に13時より、EAAセミナールームにて、ホロコーストに関わる証言を集めた長編ドキュメンタリー映画「SHOA(ショア)」(1985年)を観た。本作は第1部から第4部までの全編あわせて9時間半近くあるため、2日間に分けて2部ずつ上映会を行った。参加者は、髙山花子氏(EAA特任助教)と報告者(宇野)であった。
本読書会では、これまで水俣病患者を撮り続けた映画監督・土本典昭の作品をはじめとしたドキュメンタリー映画の上映会を開催し(第10回・第11回・第26回)、議論を重ねてきたが、今回、土本監督が対談をしたこともあるクロード・ランズマン監督の本作を観ておきたい、ということになった。年の瀬ということもあり、参加者が少なかったので、ここに報告文として備忘録を残し、後ほど会で共有できたらと思う。
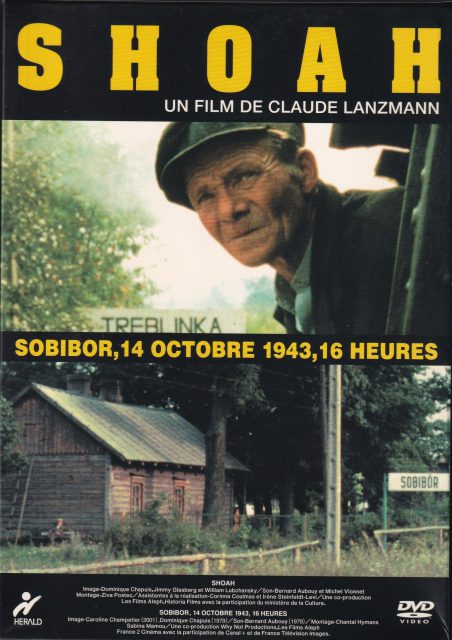
DVDボックスの表紙
「ショア」はヘブライ語で「絶滅」を意味し、第二次世界大戦中にナチスがユダヤ人を計画的に大量虐殺した「絶滅作戦」をめぐるインタビューで構成されている(その虐殺されたユダヤ人の人数は約600万人にも及ぶと言われている)。ランズマンは、1979年より本作に着手し、作品は1985年に公開となった。日本で初上映されたのは、それから10年後の1995年であった。
インタビューの対象は、絶滅収容所からの生還者やワルシャワ・ゲットー蜂起の戦士、そして加害側のドイツ人の元ナチス(収容所の親衛隊(SS)伍長等)だけではなく、傍観していたポーランド人、さらに歴史学者なども含まれ、断片的な証言や語りによって、二項対立的な見方ではない様々な立場の当時の生々しい空気を伝える。撮影は、ポーランドのいくつかの絶滅収容所跡(トレブリンカ、アウシュヴィッツ、ベウジェツ、ヘウムノ等)だけではなく、その周辺地域やユダヤ人移送経路にある駅周辺、さらに強制連行されてきたユダヤ人たちの住んでいた町や、ワルシャワの中心部にあったゲットー、ドイツに占領されたギリシアのコルフ島などに及び、いかに入念な準備の上に撮影がなされたかが窺える。言語も、ポーランド語やドイツ語、フランス語、英語の他にギリシア語など多言語であり、ポーランド語とギリシア語については通訳者の翻訳を待つために二倍の時間がかけられた。通訳を待つ煩わしさよりも、その翻訳過程も記録されることが重視されたのであろう。
意外に思われたのは、この映画では、9時間半の間、怒号も泣き叫ぶ声も哀願する声も、銃声一つ響かないことである。映像においても、インタビューされる人の表情が克明に映される他は、廃墟と化した収容所やゲットーの跡、殺戮とその隠蔽に使われた森、近くを流れる川や収容所近隣の畑や町のたたずまい、移送に使われた貨車や中継された駅周辺を静かに映していくだけである。決して映画のために仮のセットを作って再現的な撮影をすることはしないし、BGMの演出も一切ない。すなわち、全ては時間が経過してしまって痕跡と化した風景と年を重ねた人間とで構成されているのである。しかし、だからこそ、この映画は、大量虐殺を現実にあったこととして受け止めて、何よりも「決して忘れられてはならない」「なかったことにしてはならない」「曖昧にしてはならない」という強い警告を発するものになっていたように思われる。
ランズマンのインタビューは、終始穏やかでフレンドリーな雰囲気さえ醸し出していたが、一方では、相手の発した言葉の曖昧な点や、口籠ったり、ごまかしたりした部分について、細かく突き詰めていくような態度がたびたび見られた。元ナチスの人物(絶滅収容所のSS伍長など)に対しては、執拗にその当時の細かい過程やその都度感じたことについて問い詰めるような場面もあった。これは、無論、劇場的な見世物を意識したのではなく(むしろランズマンは、そうしたまやかしの高揚感をいかに避けるかに細心の注意を払っている)、真実はディティールにこそ表れると考えているからだと思われた。
その証言のディティールからは、いかに人間の大量殺戮を行う過程が工場の作業工程のように効率化を検討され、徹底的に遂行されていたかが、明らかになっていく。そして有名なアウシュヴィッツ以外にも様々な収容所があり、殺害や遺体の処理の方法も、収容所によって、また時期によって、さらに対象によって異なっていたことも詳細に語られていく。小さな収容所では、ガス・トラック内で移送中に殺害する方法も取られ、また効率的に移送できない老人や病人、付き添いの孫は、赤十字を装った野戦病院行きの車に乗せられて、森のなかの死体用の穴の前でひそかに銃殺された。焼却施設がない収容所では、こうした死体の穴に大量の死体を遺棄していた。生還者の一人は、収容所に焼却炉ができた後に、大量の死体を穴から素手で掘り起こさせられ、そこで4ケ月間地中に埋まっていた親と子供の遺体と出会った時のことを語った。死体の穴は、その後、木を植えて隠蔽された。
こうしたユダヤ人の虐殺と遺体処理の作業を収容所で強制されていたのは、移送されたユダヤ人の中から選ばれた特務班員たちで、証言をした生還者の殆どが彼等であった。例えば、トレブリンカでは、200人ほどが収容所で働いていたというが、彼等は共に話すことは禁じられ、口をきくことは死を意味した。そもそも彼等は証言をしてはいけないがために、全員死ぬ運命を背負っていた。皮肉なことに、新たなユダヤ人の移送が途切れることも、また彼らの死を意味したのであった。この巧妙な沈黙と隠蔽の服従構造の中で、ユダヤ人にユダヤ人を虐殺させ、証拠を隠滅させる作業が日々続けられたのである(「移送」が始まったのは、1942年秋。アウシュヴィッツがソビエト軍によって解放されたのが1945年初頭だった)。
しかしアウシュヴィッツ収容所では、1944年秋頃から、ひそかに蜂起する準備も進められ、わずかだが脱出に成功した者がいた、という知られざる事実も語られた。
インタビュー中、生還者は、同胞の虐殺に加担せざるを得なかったこと、忘れなければ生きていけないと思っていたこと、あるいは想像を超える現実に自分でも理解ができないことを語る行為に対して躊躇や中断を示すことが見られた。しかし、ランズマンはそうした時にも、繰り返し続きを語ることを求めた。そうして記憶をたどりながら語りだす生還者の声の調子や沈黙、そして表情に瞬間的に浮かび上がるものこそ、真実に他ならない。このようにして人類の歴史の闇に葬り去られようとしていたものが、当人が「忘れる」ことを望んでいたとしても、決して葬り去ってはいけないものとして、この映画では表象されていた。
全編にわたって、ランズマンの編集は安易な感傷や理解を齎すことを注意深く回避しているが、しかしドラマ的な要素や映画的な美しさが皆無なわけではなかった。それは自然発生的なところがあるが、演出も含まれているように思われた。特にシモンという当時13歳でヘウムノ収容所に入れられた生還者に関しては、人間の悲哀と慈しみと不条理と歴史と残酷さの全てがないまぜになったような印象深いシーンとなっている。当時、足首に鎖をつけながら餓死寸前の姿でSSに教わった歌を舟の上で歌っていたという13歳の少年シモンについて、ヘウムノにある教会から出てきたポーランド人の老男女に尋ねると、みな口々に彼を覚えているといい、元気でよかったと声をかけた。この教会は当時ユダヤ人たちが強制的に運び込まれ、そこから次々とガス・トラックに乗せられていった場所であった。当時は傍観せざるを得なかったという彼等の声の渦の中で、シモンは終始柔和な表情を浮かべつつも、時々平静を保とうとしてか煙草を口にやって、表情をゆがめる瞬間をカメラが捉えていた。そして、その中のポーランド人の一人が、当時ラビ(ユダヤ教聖職者)が、SSの前で、この災難をユダヤ人がかつてキリストに侵した罪の贖いとして受け止めよう、と演説したという話をした。ユダヤ人の根絶という前代未聞の政策の根底には、ホロコースト以前からの根深い反ユダヤ的な思想の歴史の層が横たわっていることが透かし見えるシーンでもあった。
このような印象深いシーンはいくつかあった。しかし、物語の断片は、決してひとつの感動的な物語にまとめあげられてはいかない。そして、時間軸と場所も細切れに行ったり来たりするのである。決して「わかった」と言わせない複雑さを残し、断片の答えは用意されないままに進んでいく。
それは映画の終わりに語られた不可解な言葉にも象徴的に表れていた。ワルシャワ・ゲットーで、仲間が皆殺しになった後、たった一人生き残った戦士が「自分は最後のユダヤ人だ」と一種の安らぎを覚え、「朝を待って、ドイツ兵のもとへ行こうと思った」と語る言葉である。あの言葉は一体なにを意味するのか。この映画の中で語られたことは、何も解決していないし、回収されていない。
では、この映画体験はどのようなものなのか。先述のように、この映画は徹底して物語化が回避されたものであるが、生還者の人々の記憶をたどりながら語る声と、その表情の深い何かによって支えられており、9時間半もあったにもかかわらず苦痛と感じることはなかった。むしろ、この映画を二日に分けて観たことで、一日目を終えて、一晩寝て、次の日を迎え、続きを見るという、この長くも短すぎる時間の間、証言の内容や表情を反芻し、情景を思い返すことになった。映画には、極めて普通に生活を営む人間の姿が映されており、それによって語られた当時の出来事もまた、いかに日常の中で起こったことであったかが、むしろ深く刻まれていた。したがって、通常の非日常を体験できるような映画とは別の体験として、この映画は私の体内に残った。この映画で出会った人たちの表情や解することのできない言葉は、今もひたひたと残り続けている。そして、この映像の繊細な手触りや、言葉の不可解さにひかれて、私はまたこの映画を観るだろうと思う。
戦争の悲惨さを伝える映画は、一般に、衝撃を受け感銘を受けながらも、同時に二度と見たくない、と思わせるものが多い。一方で、極限状態にある人間の荘厳さや日常のかけがえのなさや人生の意味を確信できるようなドラマがあれば、もう一度見たいと思うのかもしれない。しかし、この映画は、どちらにも当てはまらない。この映画は、そもそも戦争の悲惨さという次元で理解されるべきではない問題を提示していた。
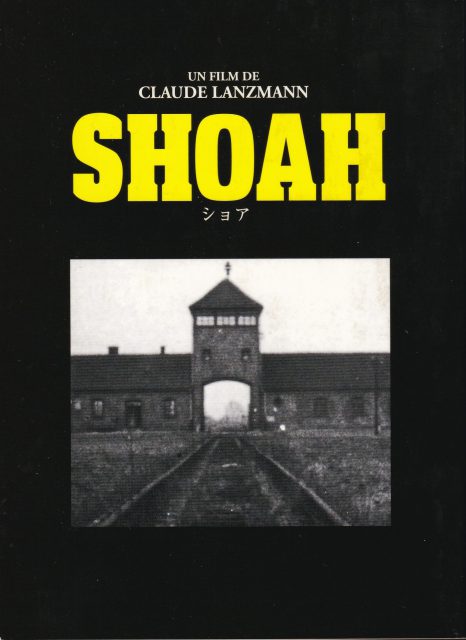
付録の小冊子
石牟礼道子は、水俣病事件について『苦海浄土』という長い小説を書いた。思えば、この長さが、読書する者において大事な体験であったはずである。そして、それが様々な立場の人たちの異質な言葉のつぎはぎによって成り立っていたことを改めて思う。さらに水俣病患者が味わった苦しみと重い澱のような日常のディティールが丁寧に刻まれていたことも共通している。また、水俣病の原因がチッソの工場排水であると内部発覚した後も、その事実を隠蔽し排水を垂れ流し続けた絶対的な悪について、利益追求する組織の誰に責任があるのか曖昧なままであった構造も、この映画が突きつけた問題と類似していた。
加害者側の元ナチの親衛隊(SS)伍長は、トレブリンカ収容所での自身の責任を決して口にせず、懺悔もしなかった。また1941年よりワルシャワ・ゲットーにユダヤ人を隔離し、非人道的な状況の中で街の真ん中で餓死させた責任者の一人のドイツ人は、自身に決定権はなかったと繰り返していた。アイヒマン裁判に見られた構造と同じもどかしさである。組織で行われる凶悪な犯罪は、責任の所在の曖昧さの中でなされてしまう。組織の部分と化した人間の人間性、知性、良心とは何か、厳しく突きつけられる。
こうした類似性がみられる一方で、この映画は事実に基づくドキュメンタリーにおいて、「物語」を語ることの危うさを厳しく突きつけてもいる。その徹底したランズマンの方針は、一見『苦海浄土』と正反対の態度を示しているように見える。しかし、実際はどうであろうか。石牟礼は、「聞き書き」というフィクションに踏み込んだ時に、この問題に正面から向き合ったはずで、だからこそサブタイトルも「わが水俣病」とし、石牟礼はそれを自身の罪業としても背負うことを覚悟したのであった。有機水銀に侵された水俣病患者は、神経系が破壊されるために、うまく話すことができない。ましてや、生まれながらの胎児性水俣病患者という存在は自身で証言することもできないのである。この違いは決定的であるのではないか。そしてこの問題は、石牟礼が次第に、儀礼と身体の次元へと向かっていったことともかかわっているのであろう。さらに言えば、「チッソは私であった」というところまで行きついた水俣病患者のように、「ナチスは私であった」というような地平を想定することは(倫理的に、そして歴史的に)可能なのだろうか。そもそも、そのような問いを立てることが許されるのか。
近々、土本監督とランズマン監督との対話も合わせて参照し、本作が喚起する問題から石牟礼の問題に立ち返って議論できたらと考えている。
報告者:宇野瑞木(EAA特任助教)








