12月25日(土)日本時間 15 時より、第10回日中韓オンライン朱子学読書会が開催された。これまで同様、EAA のほか、清華大学哲学系、北京大学礼学研究中心との共催である。今回は趙金剛氏(清華大学)が司会を務め、許家星氏(北京師範大学)が、2021年3月に出版した『経学与実理:朱子四書学研究』(中国社会科学出版社)について、発表を行った。
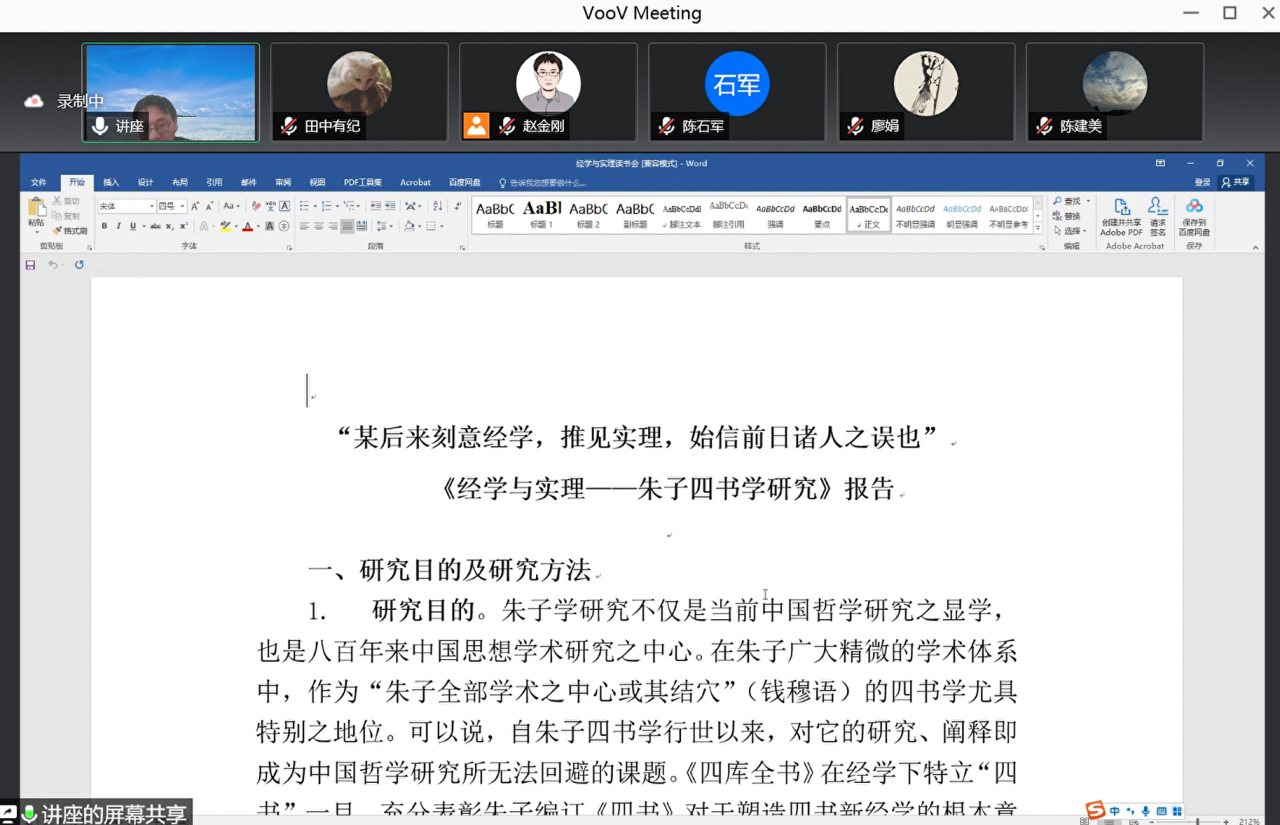
漢代や唐代の学問が経書の訓詁に偏重したのに対し、北宋の理学家たちは道を明らかにせんとして自説を創り出し空疎に流れ、朱熹もこの学風の影響を受けていたが、やがて「経学を追究することに努め、実理を推察して、初めてこれまでの人々の誤りを確信した」(『朱子語類』巻一〇四、「自論為学工夫」)という。本書は朱熹によって朱熹を解釈する。特に彼の経学の精髄である『四書集注』をとりあげる。第一章では、朱熹の四書学に関する研究をふりかえりながら、その研究史を概括する。第二章は、朱子の道統論について「十六字心法」をとりあげ、人欲と人心の関係を論じる。第三章は、経学と実理について、『論語』における「学而時習」章や「克己復礼」章の解釈、管仲の評価の問題、『孟子』「浩然之気」章の解釈、『大学』の格物・誠意の説に対する理解、『中庸』首章の解釈について分析する。第四章は、四書を通して朱熹が儒家の聖賢の人格についてどう認識していたかを論じ、孔子の弟子たちへの批判や顔回の人格に対する評価についても論じる。第五章は、朱熹の四書テキスト詮釈の方法・態度・理念についてとりあげる。第六章は、『四書集注』のテキストについて、朱子後学において、異なる版本における文字の差異が、朱熹晩年の重要な思想の理解の仕方に影響を与えたことのほか、中華書局本への疑問についても論じる。第七章は、朱子の四書学の後世への継承と発展についてである。
許家星氏は最後に、伝統的な学術それ自体にしっかりと向き合うことで、古の人々の学問に対する態度や学問の方法を理解できると強調する。しかしそれと同時に、朱熹の哲学命題や思想が、今日においてもある程度の合理性を有するのに対し、彼の採用した「注経」という方法は、今日の哲学を表現するにあたりふさわしいかどうか、常に疑問に思っていると述べた。西洋の「哲学」と、中国固有の伝統学術「経学哲学」の間には、表現という形式面においても、距離があるのだ。
そもそも朱熹や中国前近代の思想家にとって、「経を注すること」はどのような意味を持っていたのだろうか。このことに関して、たとえば垣内景子氏は「経書の注釈という形式に限定された儒者の自己表現に、大きな制約があることは見やすいところであろう」(『朱子学のおもてなし:より豊かな東洋哲学の世界へ』、ミネルヴァ書房、2021、p.200)と述べた上で、以下のような興味深い指摘をしている。「孔子のように経書を『信じて好む』という態度によってしか見えない世界があるのではないか」(同p.201)「(経書という)枷がなければ、人の『心』は本当に自由になれるのであろうか」「今日の私たちに無条件で信じる経書が存在しないということ、そしてそもそも無条件で信じるということそのものに懐疑の目を向けてしまうということは、私たちの『心』を永遠の不安に陥れ、別のどこかに閉じ込めてしまうのかもしれない」(同p.208)…
学問的態度としても、自身の生活信条としても、はっきりとした自覚の上で、「何かを無条件に信じること」は、案外難しい。何かを疑い、それを自身の見識や自身の心の実感に基づいて判断することが良しとされる環境でずっと生きてきたからだろう。その一方で、「何かを無条件に信じる」人々が、私よりも自由であるように見えることがある。
たとえば朱熹はどうか。本書が具体的に論じてきたように、朱熹の「実理」は「経学」に徹底的に支えられている。「経学」は確かに朱熹にとって「枷」ではあるが、彼ほどになると、この「枷」を自覚的に利用し、自身の心の実感に確固たる基盤を与えようとした、ともいえるだろう。もちろん私たちもまた、何らかの制約のもとで自身の思考を展開している。しかし、経書のような「枷」を自覚的に自身に与えることはできない今、まず私たちは自らの思考が、不安に陥ることなく本当に自由であるかを考えてみたい。「枷」の中に自覚的に入り込み、限定された範囲の中でひたすらその作法に習熟し、それを積極的に利用する。限定された範囲の中でしか、見えないものもあるということを、中国の経学は教えてくれるのではないか。
報告者:田中有紀(東洋文化研究所)








