2021年11月12日(金)、第2回EAA批評研究会「戦後日本の『批評』と『大衆』」が開催された。本研究会は、様々な概念・事象・テクストから「批評」そのものを問い直すとともに、「批評」を広く世界史・文学・哲学の文脈に向けて開き、新たな知のプラットフォームの構築を目指す試みである。第2回の研究会では前回の内容(第1回の報告はこちら)を振り返りつつ、そこから浮上した「大衆」というキーワードにあらためて焦点をあてるとともに、主として竹内洋の著書『大衆の幻像』(中央公論新社、2014年)の第1〜3章を取り上げた。
まず前回行われた議論への一つのレスポンスとして、報告者(郭馳洋:EAA特任研究員)は近代以前の批評、すなわち明治期におけるcriticismとしての「批評」概念成立以前の「批評」について、江戸時代の評判記、中国の小説批評・注釈(金聖歎の水滸伝批評)、目録学的な批評(『漢書』藝文志)の例を挙げながら簡略に補足した。近代以前の「批評」に関心を抱いたのは、単なる歴史に関する実証的な趣味ではなく、かつて存在した複数の批評の様式を蒐集して今日流通している「批評」概念を相対化し位置付けるためである。
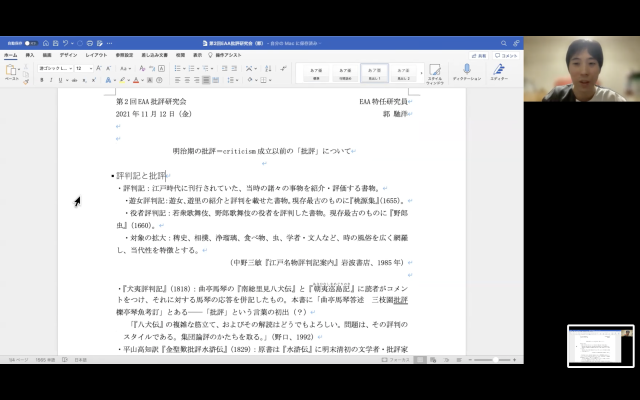
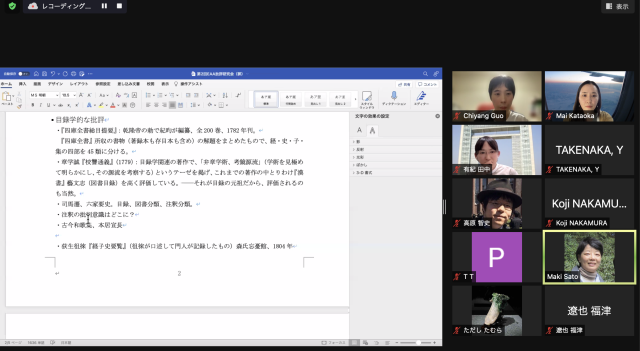
そして今回の本題として、片岡真伊氏(EAA特任研究員)は竹内洋『大衆の幻像』の前半部分の内容を詳細に整理したうえで自身の考察を加えた。前回取り上げられた大澤聡著『批評メディア論』(岩波書店、2015年)は、1920年代後半〜1930年代のメディアにおける批評の様式そのものに注目し、戦前に生成しつつあった批評メディアの生態図を描き出したが、そこで繰返し強調されているのが大衆社会化という時代背景である。それに対して今回の取り上げた著書は、歴史社会学の視点から主に戦後から現代に至るまでの「大衆」・「大衆社会」の変容およびその帰着を考察している。
「大衆」はもともとmassの訳語として大正期に登場、1920年代後半に流行しており、「大衆社会」(mass society)はカール・マンハイムが1934年に提起した概念で、1951年に清水幾太郎がそれを「マス・ソサエティ」という表記で導入した。著者の竹内は日本の大衆社会に二つの構造転換を看取している。つまり大正時代から1960年の安保闘争までは間歇的初期的大衆社会化の時期(「大衆社会の構造転換I」)であったが、1970年代後半にいわゆる新中間大衆(村上泰亮)が前面に出て、恒常的大衆社会を形成した(「大衆社会の構造転換II」)。大衆は、エリートに対する下位者・追随者あるいは理性的討論で社会を築く自律的個人としての市民よりも、むしろ消費者・納税者として世論を通じて政治や報道機関に強い圧力をかける存在となっていた。このような「大衆高圧釜社会」では、政治家が「国民のみなさま」、マスコミが「視聴者のみなさま」をつねに意識せざるをえなくなっている。そして大衆圧力が一層増幅し、大衆がもはや実在のものではなく想像されたもの(超大衆)として担ぎ上げられている現在において、大衆社会は想像された多数者からまなざされる「大衆御神輿ゲーム社会」になっている。この社会における支配的な存在は実体としての大衆でも理念型の大衆(吉本隆明の「大衆の原像」)でもなく、想像された大衆すなわち「大衆の幻像」である。そこでは、大衆の代理として政治を行う者の意識が「受託者」(trustees)から(大衆の意向に従わなくてはならない)「委任者」(delegates)に変化し、これまでシェルターで守られてきた学問・芸術も「大衆目線」を求められるようになった。知識人の性格はテレビが普及してから従来の「公共知識人」から「文化人」に変わり、「文化人の芸能人化」と「芸能人」の文化人への「昇格」という現象が発生した。
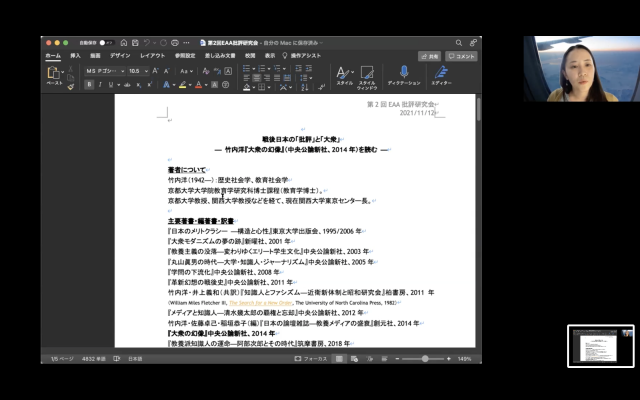

こうして本書(第1〜3章)の内容をまとめたあと、ネット時代の大衆社会と批評を考えるためのヒントとして、片岡氏は著者と山折哲雄がかつて行った対談(http://www.kokoroforum.jp/report/toyokeizai1211/)の興味深い一節を紹介した。山折は「批評対象の最も優れたところを選び出して褒めていくこと」を小林秀雄的な批評の核心とし、「まず他人を刺す前に、自分自身の背中を刺せということ」を鶴見俊輔的な批評スタイルと捉え、現在の論壇ではこの二種類の批評法はともに失われていると述べている。その話を受けて竹内は「教養というもの自体が、自己批評があるか、自分を見つめる力があるか、自省があるか、自己中の反対がどれだけあるか、ということ」と、教養と自己批評の関係を強調している。
その後のディスカッションで佐藤麻貴氏(EAA特任准教授)は、本書で言及されたノブレス・オブリージュというものの必要性を説きつつ、SNSでの情報に日々接する若年層における懐疑精神・批評精神の欠如、「自己批評」「教養の度合い」(竹内)の不在、それが知識人層にも見られることを指摘した。この状況において一方では大学のマス化、他方では専門知と実社会との乖離が起き、哲学の実践、社会への批評の仕方が問題になっているという。佐藤氏の見方では、批評とはより良い高次のレベルの世界を開くためのツールであり、そのためには権威主義、エリート主義あるいは「大衆」を脱構築的に論じる必要があり、その際は相手への単なる否定ではなくある種の昇華のほうが重要となる。
田中有紀氏(東洋文化研究所)は中島隆博氏(EAA院長)の新著『危機の時代の哲学』(東京大学出版会、2021年)での議論を援用し、批評=批判とは切り分けることによって新しい思考空間が開かれるような実践だと捉えたうえで、竹内の著書で論じられた「大衆の幻像」への迎合、さらにはこうした大衆社会論それ自体の背後に、新たな世界を切り開こうとする理念・理想的世界像が果たしてあったのかどうかと問いかけた。そして現代の大衆迎合とは異なる民衆との向き合い方を、かつて陽明学を説いた町人学者に見出した。田中氏によれば、(東アジア藝文書院の名前の由来でもある)『漢書』藝文志はまさに複数の学問ジャンルを分けることによって新しい学問ないし世界の形を浮き彫りにしたものであり、中国の目録学・注釈では一種の社会変革志向が強く働いていたのであるが、こうした志向は「大衆の幻像」時代の批評においてむしろ薄れている。


田中氏の発言を受けて、高原智史氏(EAAリサーチ・アシスタント)は、新たな世界を切り開きこうとするような大きな目的もしくはグランドデザインが欠如しており、大衆の一人一人が自分の思う通りに社会を支配したいというのはまさに大衆社会の重要な側面であると述べた。高原氏は竹内著における「委任」と「受託」の議論に触れながら、大衆が政策・意思決定を代議士や専門家のようなプロフェッショナルに任せようとしなくなっていることを指摘した。つまり、任せられないにもかかわらず自分の思う通りにして欲しいという大衆的欲求が迫り上がっているという。この「任せられない」状況において批評がどう成り立つか、大衆がSNSを通して政治的・社会的事柄に反応していくなかで批評家の立ち位置をどう捉えるかという問題を提起した。
SNS時代における批評の(不)可能性あるいは難しさを考えるにあたって、田村正資氏(EAA特任研究員)は時間間隔・時間的距離感という視点を提示した。田村氏によれば、本来なら「任せられる」政治の場合、ある政策の評価はその結果が出るまで一定の期間を待ってからフィードバックを踏まえて行うべきであって、つまりタイムラグがあるからこそ、批評的な眼差しが可能になり、作品批評についても同じである。しかし「任せられない」状況においては、例えば「いまこの瞬間」に与えられたものに対して大衆がリアルタイムで反応し、SNSで炎上するため、政策も朝令暮改になってしまい、そこにやはり時間間隔が欠如しており、このことが批評の難しさにつながるという。
最後に参加者たちの議論を聞いた報告者(郭)による当日の発言およびその後の感想を簡単に綴りたい。
批評精神を懐疑の精神と理解すれば、あらゆる権威は批評・相対化の対象になる。しかし一方で、学的言説の権威が失墜し、専門知に対する不信感(「任せられない」状況)が増大している今日の大衆社会において、批評は軽薄化する言論に呑み込まれて機能しなくなっているようにも見える。つまり権威を相対化するのは批評の一つの役目だが、権威の全く存在しないところに批評も成り立たなくなる。では、単に権力や資本に依存しないような権威をどこに求めればよいのか。もし価値のあるものに権威を認めるとしたら、私たちにとってどのような価値が必要なのか。こうした問題はつねに批評に絡んでくる。
言論の生成・拡散のスピードがかつてないほど加速化する現代において、批評の質を担保する時間間隔が限りなく縮まり、「想像された大衆」がリアルタイムで現前している。それに対して、古代ではむしろ「書く」という行為それ自体が身体性、ときには儀礼性をさえ伴う(「読む」についても同じことが言えよう)。そのように書かれたもの、すなわち「文」は実に重みのあるものであったし、その伝達にも一定の時間を要した。だとすれば、今日における言論の批評性を回復するには、何らかの身体性・儀礼性を再構築することが大事なのかもしれない。
報告者:郭馳洋(EAA特任研究員)








