9月25日(土)日本時間 16 時より、第9回日中韓オンライン朱子学読書会が開催された。これまで同様、EAA のほか、清華大学哲学系、北京大学礼学研究中心との共催である。
今回は田中有紀(EAA、東洋文化研究所)が司会を務め、福谷彬氏(京都大学人文科学研究所)が、2019年に出版した『南宋道学の展開』(京都大学学術出版会)について、特に第六章の「消えた「格物致知」の行方——朱熹「戊申封事」と「十六字心法」をめぐって」をとりあげ、発表を行った。
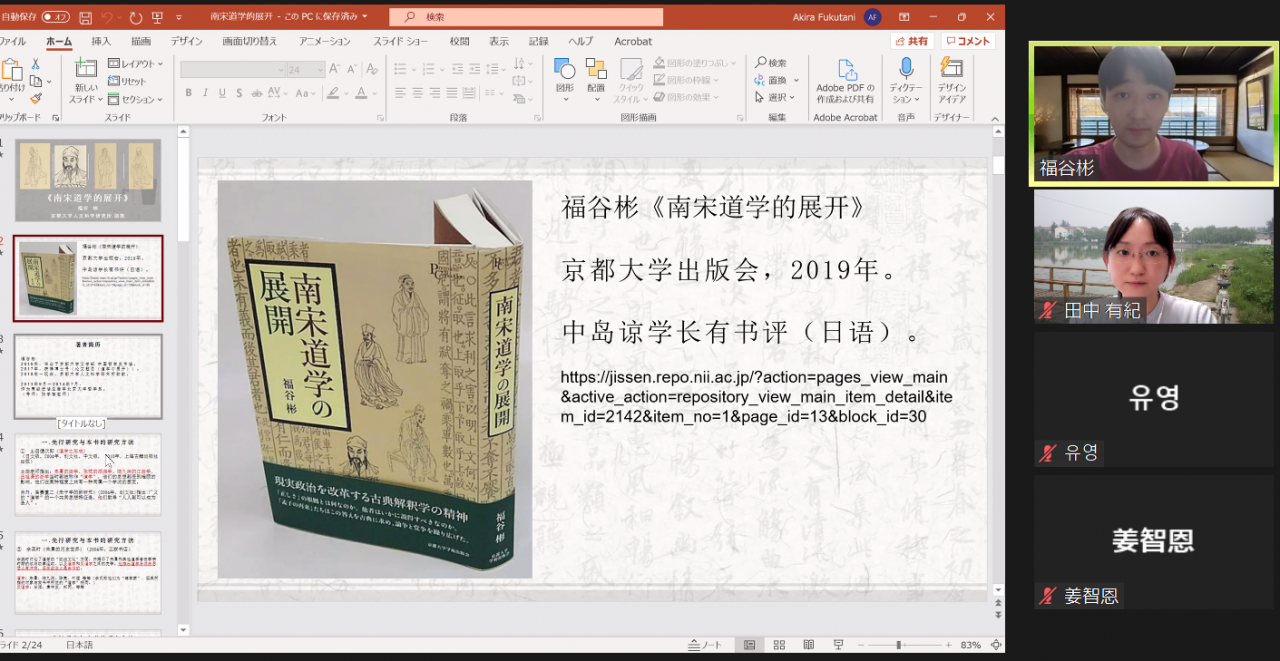
該章は朱熹の封事(上奏文の一種)にみえる「十六字心法」の解釈の変化から、朱熹の君臣論を分析するものである。「十六字心法」とは、『尚書』大禹謨「人心惟危、道心惟微、惟精惟一、允执厥中」という記述を指す。朱熹は人生で3回皇帝に封事を上奏したが、この「十六字心法」の実践を通して皇帝に政治意識の改革を求めることがあった。朱熹の早期の封事では「惟精惟一」を「格物致知」の解釈に、「允执厥中」を「誠意正心」の解釈と結び付けたのに対し、「戊申封事」では両方とも「誠意正心」を述べるものとした。朱熹の工夫論においては、「格物致知」を完成させてから「誠意正心」が実現できるはずだが、「十六字心法」からは「格物致知」が消えてしまったのである。これは一体何を意味しているのだろうか。朱熹の「十六字心法」解釈の転換は、陳亮の「王霸・義利」論争が関わっている。陳亮は王朝が政治的に成功するかどうかは、君主が政治的独立性を発揮できるかどうかにかかっていると考えた。それに対して、朱熹は、より重要なのは君主が政治的独立性を発揮できるかどうかではなく、「十六字心法」に基づき正しく独立性を発揮できるかどうかだと主張した。同時に、朱熹は当時の皇帝孝宗が側近ばかりを重用し、士大夫の建議を聞かずに独断で政治を行っていたことに対し、「賢臣」の建議を聞くよう主張していた。『戊申封事』において、朱熹は皇帝に「十六字心法」の実践を説き、皇帝は「私心」を取り除き、側近に頼る政治をやめるべきだと主張した。「十六字心法」は聖王が自己の私欲を取り除くための修養法であり、この修養法を実践するためには、天理と人欲をはっきりと区别する賢臣の諫言を受け入れる必要があるとした。天理と人欲をはっきりと区別するための修養が「格物致知」である。つまり「格物致知」は士大夫がなすべきことで、皇帝は士大夫に「格物致知」を任せるべきだとするのである。朱熹は「十六字心法」から「格物致知」を取り除き、士大夫の皇帝権力に対する牽制作用を確保しようとしたのである。ただし、このような士大夫を登用するかどうかは皇帝の意思次第であるという点で、皇帝の主体性もまた確保されているといえよう。
報告後、参加者からいくつか質問が出た。書評を執筆したこともある中嶋諒氏(明海大学)は、「福谷氏の著作は、道学者の政治的側面をとりあげ、陸九淵や陳亮は思想的な対立のみならず、政治的にも対立していたことを明らかにした点が優れている」と述べた上で、「南宋時代に出てきた朱陸折衷論についてどう考えるか」と質問をした。福谷氏は「宋末に、朱熹と陸九淵は対立するものではなく、どちらの長所も吸収しようという姿勢が出てくる。どのような哲学的態度で吸収しているのかというと、「自分に対し厳しい目で修養する」場合は朱子学を取り入れ、「人に接する」場合は「自分と他者がともに探求していく」ような、陸九淵的な考え方を取り入れたのではないか」と応答した。
また他の参加者からの「八条目は時間上の順序ではなく、演繹上の順序であり、「格物致知」と同時に「誠意正心」も進める必要があると朱熹は考えていたのではないか」という質問に対し、福谷氏は「全くその通りであり、だからこそ、皇帝は「誠意正心」、臣下は「格物致知」と分けているように見える朱熹の態度に違和感を覚え、この研究へと繋がった」と返答した。「朱子学の排他性、ただ一つの理論しか認めない態度は、朱熹の哲学のどの部分から導き出されるのだろうか」という質問に対しては、福谷氏は「たとえば朝鮮朱子学における内部の激しい対立の原因は、朱熹の性格および朱子学自体にあり、もともと対立を激化させるような性質を持っている。「存天理、滅人欲」というテーゼにみられるように、他者の道理に妥協点を見出そうとせず、「自分と異なる考え方の人に流されてはいけない、徹底的に攻撃せよ」と考えてしまうからではないか」と応答した。このほか「南宋における道学形成において王安石学派との論争はあったのか、その焦点は何なのか」などの質問も挙がった。
「格物致知」を人に任せ自分で実践しないということは、たとえ皇帝にのみ許されたことであったとしても、結局、誰かがなした「格物致知」に拠ることができると、認めることになるだろう。報告者は音律学を研究しているが、朱熹にとって音律学はまさに重要な「格物致知」の一つである。抽象的な音律学を論じる一方、朱熹は毎日楽器を弾き、「自ら」音楽を奏でて実践する努力を大切にした。理論として理解するだけでなく、自分自身が経験することを重視した朱熹の態度と、本報告のような「消えた格物致知」をどう理解したら良いのだろうか。あるいは、たとえ矛盾していたとしても、皇帝には「誠意正心」を説かねばならないほど、朱熹は政治に対して切迫した思いを持っていたといえるのかもしれない。
報告者:田中有紀(東洋文化研究所准教授)








