2021年6月12日(土)日本時間14時より、第2回東アジア仏典講読会を開催した。この読書会は、禅を中心に仏教の研究を行っている日本・中国・韓国・フランスなど各国の研究者が集い、文献の会読や研究発表・討論を行うものである。
今回は小川隆氏(駒澤大学)による『大慧普覚禅師宗門武庫』第四段「暹道者」の講読とそれに基づく議論が行なわれた。当該の一段には「嗣法」に関する暹道者の逸話が記されている。
「嗣法」とは「法を嗣ぐ」意であり、禅宗では歴代の祖師により釈尊の法(真理)が代々継承されてきたとされる。禅僧は各地を行脚して法を伝える各地の禅師に参じ、開悟を経て一寺の住持となる際に自ら嗣法の師に対し報恩の香を焚き、それによって自身の嗣法関係を決定・公表することになっていた。師承関係の決定権は師でなく弟子の側にあったのである。
『武庫』に記される一段によれば、暹道者は長らく雪竇重顕のもとで修行していたが、その後継者と目されるや二首の偈頌を壁に書き付けて出奔し、晩年に開先寺に住するにあたり徳山慧遠を嗣法の師として香を焚くとともに、その旨を伝える書簡を雪竇に送った。雪竇の門前の婆子は暹道者が徳山に嗣法したことを聞くや、その不義理を詰ったという。婆子は禅籍において、無名ながらも禅僧顔負けの力を具えた者として登場するのが常であり、当該の一段においても禅門の本義を代弁、更には雪竇側の輿論を代表する役割が担わされている。雪竇重顕と徳山慧遠はともに雲門宗の禅僧であるが、雪竇は70余人もの法嗣(嗣法の弟子)を輩出し、後に雲門宗中興の祖と尊称されたのに対し、徳山の法嗣は10人にも満たない。通常なら、一門の名望や権勢を顧慮せずそもそもの開悟の師の法を嗣ぐことは称賛されるべきことであるが、この故事が暹道者が雪竇の法を嗣がなかったことを非難する婆子の言葉で結ばれていることは、おそらく雪竇山側の不満を表現するものであり、と同時に、暹道者に対する評価と期待が本来いかに高かったかを反面から示すものともなっている。小川氏は、他の事例を挙げて、禅僧の嗣法においては、「誰の法を嗣ぐか」ではなく「誰の法を嗣がないか」ということに意味がある場合があることを指摘しつつ、暹道者にとっては雪竇の法嗣という権威ある輝かしい地位は受け容れがたいものであったろうという解釈を示した。
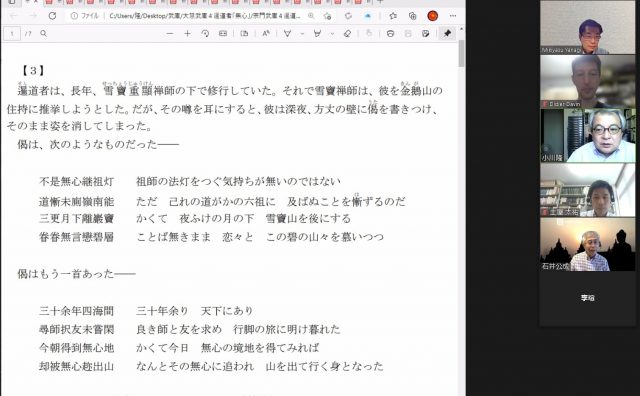
参加者による議論では、暹道者が書き残した偈頌の解釈や詩の格律・修辞などが取り上げられた。また後に日本の禅宗で有名となる釈尊成道の語「明星出現の時、我と大地有情と同時に成道す」が元は徳山慧遠の語であることが指摘されるとともに、中国ではこの語が殆ど注目されなかったことなども確認された。
禅籍は禅問答に代表されるように簡潔かつ難解な表現が多く、その読解は非常に困難である。本講読会には、禅宗史・仏教学・中国文学など様々な専門分野の研究者が参加しており、今回もそれぞれ独自の視点から様々な議論が為された。ひとつの文献を前に参加者が各自の知見を寄せ合いつつ、新たな読みを摸索していくことは会読の醍醐味であるし、新たなリベラル・アーツの可能性を模索するうえで重要な基礎となるものと考える。
報告者:柳幹康(東洋文化研究所准教授)

《企画》座頭と瞽女の説経(節)の語り——兵藤裕己氏をお迎えして







