2021年5月18日(火)15時より、Zoomにて第17回石牟礼道子を読む会が開催された。参加者は、佐藤麻貴氏(EAA特任准教授)、髙山花子氏(EAA特任助教)、建部良平氏(総合文化研究科博士課程)、宮田晃碩(EAAリサーチ・アシスタント)及び報告者の宇野瑞木(EAA特任研究員)の計5名であった。
今回は、来週に控えている第18回(5月25日)の石牟礼道子の新作能「不知火」の鑑賞会、つづく第19回(6月15日)の最後の琵琶法師・山鹿良之の語り物の鑑賞およびその記録者・兵藤裕己氏の講演会にむけての事前勉強会としてセッティングされた会である。共有されたテクストは、下記の通り。
◎メインテクスト:
- 石牟礼道子「『詩篇・苦海浄土』(テレビ台本について)」
- 石牟礼道子「ひがん花」
(共に、『石牟礼道子全集・不知火』第一巻(藤原書店、2004年)所収の「わが不知火」の一部、326-335頁)
◎サブテクスト:
- 兵藤裕己「語り物享受と共同体――平家物語と〈国民〉文学論」『語り物序説――「平家」語りの発生と表現』(有精堂、1985年)
- 兵藤裕己「座頭琵琶の語り物伝承についての研究(一)」『埼玉大学紀要』(教養学部)26(1990年)
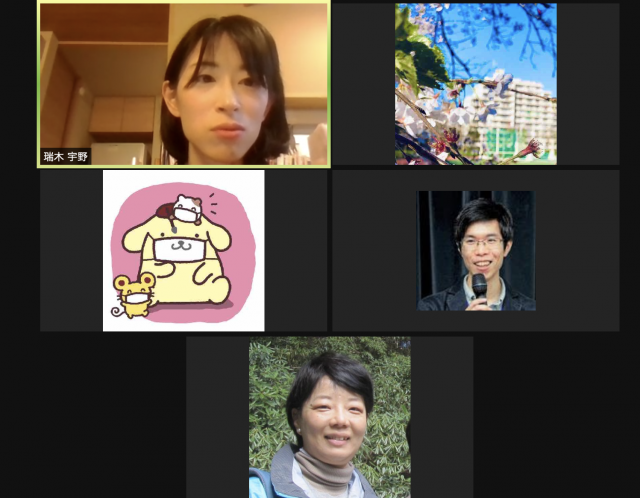
まず、発表者(宇野)は、石牟礼道子における琵琶語りの芸能者や、その周辺の「かんじん殿」と呼ばれた人々への深い関心の在り処を確認するために、1と2のエッセイを取り上げた。
1の「『詩篇・苦海浄土』(テレビ台本について)」では、石牟礼がテレビ用に台本を書いたドキュメンタリー作品「詩篇・苦海浄土」(ディレクター:木村栄文、制作:RKB毎日放送、1970年芸術祭大賞を受賞)の撮影時のことが綴られている。中でも興味深いのは、作品の主人公である胎児性水俣病患者の杢太郎の家に、漂泊の瞽女に扮した女優・北林谷榮が「門つけ」にやってくるシーンで、杢太郎の婆さまが庭先に突如現れた琵琶を背負った瞽女を本物だと信じて疑わなかったと述べられている点である。石牟礼が活写した婆さまの慌てて米や銭を喜捨しようとする姿は、かつてこの土地に、確かに漂泊の瞽女がいたということを物語っている。
加えて、発表者は、瞽女が「門つけ」に向かう道中、心のうちに深く誦える「生死のあわいにあればなつかしく候」と始まる石牟礼自身が創作した「詩経」が、のちに『苦海浄土』第三部冒頭に掲げられる「序詩」の原型となったことも指摘した。すなわち、この瞽女の心象に響く詩(声)は、石牟礼にとって、第三部の構想の一つの核となるほど重要なモチーフであったことを意味するであろう。
続いて、2の石牟礼の幼少期における「かんじん(勧進=乞食、あるいは狂人)」との交流を綴ったエッセイ「ひがん花」では、先の瞽女の誦えた「詩経」の世界観と共鳴するような、盲目性、人間の「言葉」への嫌悪に象徴される未分化の世界、花の匂いに酔い狂う虫の世界への憧憬が表明されている。さらに、そこに連なるような「かんじん殿」たちの魂や境遇への思慕が、彼らとの交流の思い出とともに描きだされていくのである。そして注目すべきは、こうした人々は、かつての水俣あたりの地域共同体にとって「遊行する人びと」としてなくてはならない存在であったと石牟礼が述べている点である。その一方で、女性の「かんじん殿」の過酷な現実についても描かれている点は見逃せない。
以上のように、石牟礼の2つのエッセイからは、幼少時の心象に深く刻印された「かんじん殿」たちの姿やその共同体における位置づけが、石牟礼作品中の「漂浪(され)き」という言葉や、他者の心への寄り添い方の基盤になっていること、また、そうした存在の共同体の浄化作用と差別を併せ持つ構造が、石牟礼において明確に認識されていることが確認された。また、石牟礼の「かんじん殿」という「漂浪き」の系譜への思慕・親密さの大本には、自身の盲目の祖母「おもかさま」の存在と共に、父の「おなごは三界に家なし」という因習的“教訓”があったと石牟礼自身が述べている点も興味深い。
さて、今回は、能と琵琶語りを鑑賞する連続企画のきっかけともいえる、石牟礼自身が「自分自身に語り聞かせる浄瑠璃のごときものであった」(改稿版講談社文庫のあとがき、1972年11月)と第一部を振り返って述べた言葉が、一体なにを意味するのかを検討する作業でもあるといえる。それはすなわち、石牟礼のいう「浄瑠璃」とは具体的にどのようなものであったか、ということになるであろう。
実は、この「浄瑠璃のごときもの」という石牟礼の実感は、熊本に伝わる芸能の特殊な歴史的状況というものが深く関わっていると考えられる。なぜなら、熊本は琵琶を持つ浄瑠璃語りが最後まで残っており、中世的な芸能の内容や活動形態が残存していた特殊な地域であったからである。熊本で1980年代まで活躍していた座頭琵琶の山鹿良之のもとに通い、語りを記録する活動をしていた平家物語研究者の兵藤裕己氏(学習院大学名誉教授)は、その実態についてまとめた論考(4)において、この地域の座頭琵琶の特徴・歴史的位置を次のように指摘する。第一に、肥後琵琶とは琵琶を用いた浄瑠璃で、すなわち古浄瑠璃との関係が深いこと、第二に、盲人の語り部が中世から近世にかけて琵琶から三味線へと持ち替えていく中で、九州地方だけは琵琶を持ち続けたことである。それは九州では近世以降も座頭琵琶が宗教儀礼を司り続けるという中世的な芸能者の在り方を継続させていたからであり、琵琶は法具としてみなされた。さらに、天草は、制度的に管理されていない、放浪する芸能者が最も多かった土地でもあったという(山鹿の最初の師匠も天草の座頭琵琶)。
すなわち、奇遇なことに、石牟礼が生まれ育った天草・水俣の辺りは、全国的に見ても中世的な漂泊の口頭芸能の姿が濃厚に残っていた特別な土地であった。兵藤氏は、盲目の座頭琵琶・山鹿氏の語りの特徴に、オーラルな伝承の記憶の仕方と、その語りの生起のしくみを見出しており大変興味深い。それは、近世以降の正本テクストにおける、分割されインデックス的に部分の取り出しが可能な在り方とは異なるものである。即ち盲目の芸能者が伝承するために、日常言語とは異なる七五調で(それは方言とも異なる)、フシ回し・リズム様式に結び付いた「声」による一定の成句として「記憶」され、継起的・入れ籠的に、いうなれば芋づる的に生起する語りであるという点である。
また、同じく兵藤氏の研究の原点に位置づけられる『語り物序説』(1985年)の中から一篇の論考(3)を取り上げた。本論考は、当時の国文学研究における『平家物語』の「国民文学」としての位置づけ、そして近世に刊行された正本テクスト中心主義に対して、そもそも中世の「平家」語りは共同体の外部を漂泊する被差別民により伝承されたものであり、その盲目の語り部の身体・主体・声・社会的位相において捉え直す必要があると異を唱えたものである。その上で、兵藤氏が強調したのは、漂泊の盲僧の琵琶語りの機能が共同体の浄化作用でありながら、語り手自身は不具性=穢れを負い続ける者であり、その生存のリアリティの上に迫真の語りがなされていたという点である。こうした問題意識の背景には、現代の琵琶法師・山鹿氏との出会いがあった。それと同時に、ユージン・スミスの写真集『MINAMATA』についての言及があるように、水俣病患者の存在を文学者はどのように語ることができるのか、そこから目を背けて「国民文学」などと語ることはできないのではないか、という問いがあった。兵藤氏の「平家」語りの研究の根底は、はじめから水俣にも繋がっていたのである。
***
以上を踏まえて、議論では、まず同じ芸能とはいっても、能と門付けの位相は大きく異なっているのではないか、という疑問が呈された。能は、神仏や死者等に奉納する芸能であり、そこに居合わせなかった者にとっても催されたという出来事自体が意味を持つ一大イベントとしてあるのではないか。これに対し、例えば「門付け」のような偶発的にはじまる語りは、それとは異なる出来事としてあるように思われる。
この点を考える上で、「不知火」の上演が、不知火海の大量の汚染魚をドラム缶に詰めて埋めた場所でなされたということが改めて注目されるだろう。その痛ましい出来事に対して、汚染されてしまった土地自体から沸き立ってくるような複数の思いや声をどのように聞き、そしてある種の救済や浄化をすることができるのか。そこには儀礼的な節目としての出来事が必要であり、しかも人類の経験したことのない未曽有の事件であったがために、その世界を新たに創る仕事は石牟礼道子が担わねばならなかったと想像される。そこに、能をほとんど見たことがないという石牟礼が作能に踏み切った一つの背景があるのではないか。
さて、その一方で座頭琵琶にも「夜ごもり」のように、わざわざ家に招いて、夜通し語り物を聞くような一大イベントもあったようだ。しかし、これは一晩中続くことを考えても、ずっと集中して聞くのは異なる鑑賞形態であったであろう。参加者の中に、兵庫にいた祖父から聞いた話として、芸能者を家に招き、何夜も続けて「平家」語りしてもらった時のことを披露してくれた方がいた。それは一晩中、語り物に集中するわけではなく、酒食を楽しみながら、名場面になると皆集中して聞き涙するといった楽しみ方であったという。この語り物は段物だと非常に長いものとなることが兵藤氏によっても指摘されているところだが、長い語り物を皆で聴くというかつての娯楽が、共同体の浄化作用として機能したことの意味を考えさせられる。それとともに、兵藤氏が指摘するように、共同体の外からやってくる芸能者が、共同体を浄化するけれども自ら浄化されることがない、という差別の回路の構造もあったのであろう。
もう一つ重要なことは、石牟礼が、兵藤氏がラフカディオ・ハーンについて指摘したのと同様に、「耳」の人であった点である。石牟礼の生まれ育った土地が、偶然にも中世的な語り物の形態を残しており、彼女はそうした声と音の響く世界を原体験として持っていた。そして、石牟礼はそれを敏感に聞き取る「耳」を持つ人であった。それは、彼女にとって共同体の外側を漂浪(され)き、人間の言語の分断の世界から離れた盲人や狂人の「あわい」の主体への限りない憧れにも繋がっていた。
しかし一方で、石牟礼自身は「声」で語る芸能者ではなく、あくまで表現としては「書く」人であったことを改めて考える必要がある。石牟礼は、『苦海浄土』第一部を刊行して間もない時期に、テレビ台本により盲の瞽女の語り手を現出させてみた。しかしテレビというメディアにのせて女優が演じるという在り方に拭いきれない違和感を抱いたのではないか。「書く」という表現だけでは果たしきれない何かを達成するために、そこから身体・声・場所を伴う次元を求めていったのが、第二部以降の「巡礼」であり「御詠歌」という実践でもあったのであろう。そして、さらに「不知火海」という場所性の問題とともに、死者に正面から向き合うにふさわしい儀礼的な芸能として、そこに能舞台を設けて奉納することへ向かったようにも思われる。こうしたそれぞれの芸能の持つ位相の違いも含めて、次回の石牟礼の新作能「不知火」鑑賞会では、能の専門家の高橋悠介氏と倉持長子氏を迎えてさまざまに議論できたらと思う。
報告者:宇野瑞木(EAA特任研究員)








