2025年3月24日(月)、EAA主催の2024年度第2回RA研究発表会が開催された。本年度EAAリサーチ・アシスタント(RA)を務めている新本果氏(人文社会系研究科博士課程)と張子一氏(総合文化研究科博士課程)がそれぞれの研究について発表を行った。張政遠氏(総合文化研究科)がコメンテーターを、髙山花子氏(EAA特任講師)がモデレーターを務めた。石井剛氏(EAA院長)も同席した。
まずは新本果氏から「宋代の家族観を考える:『周易』家人卦の解釈をてがかりとして」と題する発表がなされた。宋代の儒学を研究している新本氏は『周易』家人卦に関する王弼、程氏兄弟、および朱熹の注釈を比較することによって、宋代の士大夫における家族観とりわけ夫婦観を明らかにしようとした。宋儒の解釈における「修身斉家」から「治国平天下」への連続、「正身」「正位」の重要性、役割分担についての規範と実態の差などが論じられた。
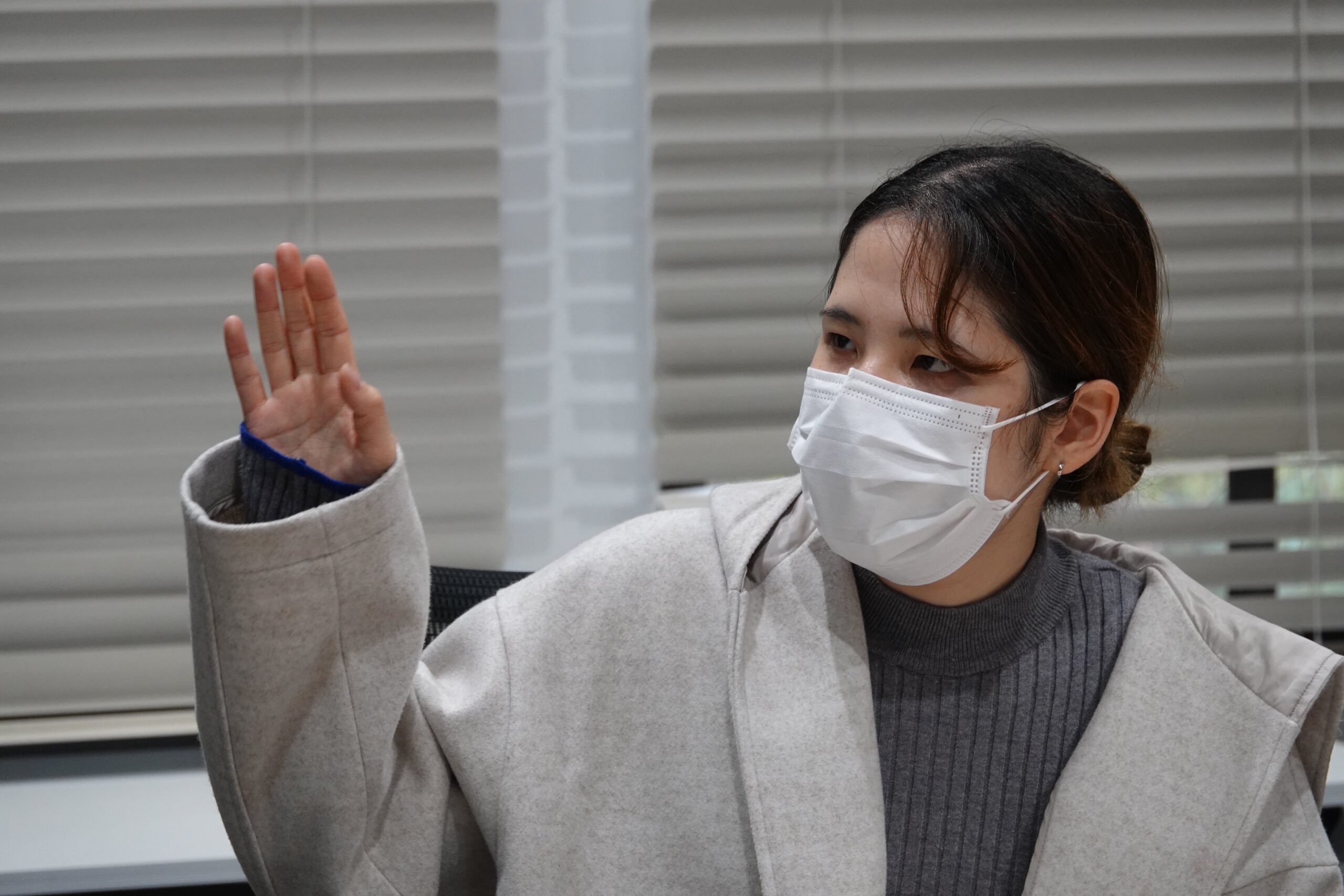 (新本果氏)
(新本果氏)
続いては張子一氏が「戦時下の皇典講究所華北総署と「神社問題」」と題する発表を行った。近代神道史を研究している張氏は大陸における神社の動向を視野に入れることで、従来の「神社問題」と異なるアプローチを試みた。具体的には行政と思想の両面から、戦前の「満洲国」における「惟神道」の言説、皇典講究所華北総署の刊行物における神道論を考察し、「皇道」と「王道」の関係性、「惟神道」の位置づけ、神社の(非)宗教性などが検討された。
 (張子一氏)
(張子一氏)
以上の二つの発表について、張政遠氏、石井氏、そして髙山氏がそれぞれコメントと感想を述べた。議論は漢文の翻訳、考察対象となる文献の選定・収集といった研究手法に関わる問題から、儒教の女性観と現代的なジェンダー観との緊張関係、近代における「礼教」への反発、日本と中国における「天」の意味合いの差異、戦前日本の大陸政策における「満洲国」と「華北」の位置づけの相違、さらにはAI時代の人文学研究の直面する課題などへと広がり、新たな展開の可能性を見せた。
二回にわたって行われたRA研究発表会は、新進気鋭な大学院生による専門的な研究とEAAの目指す新しいリベラルアーツとをつなぐ貴重な場になった。一つの専門分野で研鑽を深めつつ、その知見を今日よりよく生きるための「教養」に「翻訳」していくことに、EAAという場所に集まる意味があるといえよう。
 (左から:石井氏、張氏、髙山氏)
(左から:石井氏、張氏、髙山氏)
報告・写真:郭馳洋(EAA特任助教)







