2021年1月10日、「痛みの研究会」第8回研究会がオンラインで開催された。「痛みの研究会」は2017年に発足した研究会であり、小川公代氏(上智大学教授)、伊東剛史氏(東京大外国語大学准教授)、南谷奉良(報告者:日本工業大学講師)、田中浩喜(報告者:東京大学大学院博士課程)をコアメンバーとして活動している。本研究会の目的は、依然として人文学のなかで充分な研究量を欠いている「痛み」という対象に注目し、文学、歴史学、宗教学などの人文知を用いて多角的にアプローチすることにある。本研究会はこれまで主に西洋地域に焦点を当ててきたが、東アジアにも視座を広げることを目指しており、今回EAAと初めて共催して研究会を企画する運びとなった。
研究会は南谷を司会に、前半の合評会と後半の研究報告の二部構成で進められた。前半部では、サンダー・ギルマン『肥満男子の身体表象——アウグスティヌスからベーブ・ルースまで』(小川公代・小澤央訳、法政大学出版局、2020年)の合評会が行われた。同書の訳者には本研究会の小川氏が名を連ねていることから、本研究会で「痛み」の観点から同書を合評することとなった。後半部では、貝原伴寛氏(社会科学高等研究員博士課程)による研究報告が行われた。貝原氏は現在、近世フランスにおける猫の歴史をテーマに博士論文を準備しており、その成果の一部を「痛み」に関連させて報告していただくこととなった。
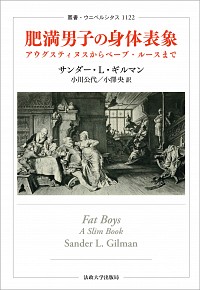
書誌情報は以下を参照:https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-01122-1.html
前半の合評会では、まず小川氏が「肥満のスティグマを覆そうとするギルマンの試み」という発題を行った。その目的は、理性と非理性の対立という観点から、ギルマンの『肥満男子の身体表象』を読み返すことにあった。小川氏によると、西洋では18世紀以降、神経医学の発達とともに理性と非理性を対立させる言説が発達し、肥満には非理性的な身体というスティグマが与えられてきた。ただし、ギルマンは肥満のスティグマの例外となる事例を多数取り上げている。実際、18世紀の医師ジョージ・チェイニー(1672–1743)や、「腹で思考する肥満探偵」の表象の系譜は、理性と非理性、痩身と肥満の近代的対立を相対化している。ここには、肥満のスティグマを覆そうとするギルマンの試みをみることができるという。
小川氏の発題に続いて、研究会メンバーから『肥満男子の身体表象』へのコメントがなされた。南谷は、肥満が、ギリシャ世界以来の〈訓練〉(askesis)を土台とした、健康で理想的な男性の身体と対照を成す形で、悪徳や醜悪さと結び付けられてきたというギルマンの指摘を取り上げた上で、肥満表象には、痩身/非肥満との対照が分かちがたく関連していることに注目した。この主題を掘り上げるため、続けて、クリント・イーストウッド監督の映画『リチャード・ジュエル』(2019)を取り上げ、英雄や主人公というステータスが顕在している間は肥満という身体は前景化しないことを指摘し、「肥満に意味を与えることによって醜くしている」というギルマンの議論を応用した。
田中は、痛みと肥満の表象の歴史的展開の類似性を指摘した。肥満の表象はともに近代化による医療化と世俗化を経験している。肥満の場合、前近代には神聖な霊魂の堕落の象徴とみなされたが、近代になると神聖な身体の管理不足の象徴とみなされるようになる。痛みの場合、前近代には救済をもたらすものとして積極的な宗教的意味が与えられたが、近代になると除去すべきものとして否定的な医学的意味を与えられるようになる。さらに、20世紀後半以降、肥満と痛みの表象はともに脱医療化を経験している。医療に独占されていた痛みと肥満の表象は、医療制度批判の高まりとともに人文学にも対象化されるようになった。肥満の表象の脱医療化は、ファット・アクセプタンス運動の高まりにもみることができる。
村上克尚氏(東京大学准教授)は、日本文学の観点から『肥満男子の身体表象』にコメントした。リアリズム的傾向の強い日本文学では戯画的な肥満表象が忌避されてきたのではないかとの見解を示したあと、村上氏は大江健三郎の『父よ、あなたはどこへ行くのか』(1968)を取り上げた。この小説では、大江自身を思わせる肥満した主人公が、同じく肥満した父の伝記を書けず煩悶している。この肥満した父は戦時中の食糧難にあっても食欲旺盛で、周囲から狂人とみなされていた。ここには、ギルマンの示した狂気と肥満の表象上の繋がりをみることができるという。村上氏はさらに、肥満した身体を志向する大江と、強靭な身体を志向する同時代人の三島由紀夫との間には、身体表象の対称性がみられることを指摘した。
後半の研究報告では、貝原氏が「痛みをもって痛みを制する——18世紀フランスの医療における薬物としての犬と猫」と題した発表を行った。この発表の目的は、薬物としての犬と猫の利用が19世紀初頭に放棄されるに至る過程を、歴史学的に解明することにあった。貝原氏によると、近代以前のフランスでは、犬や猫が薬物の材料として用いられてきた。例えば、17世紀の薬師レムリ(1645-1715)は、仔犬から抽出したオイルが神経痛に効くと述べている。猫の場合、17世紀の医師リヴィエール(1589-1655)は、猫の耳にひょう疽の患部を挿し込むと痛みが取れると主張しているほか、ルイ14世時代の医師エルヴェシウス(1661-1727)は、生きたまま切り裂いた猫の体をあてると腹部の痛みに効くと主張している。
しかし、犬と猫の薬物利用は19世紀以降の正統医学に批判されるようになる。実際、19世紀初頭の医学教授クロケ(1787-1940)は、犬と猫の薬物利用は残酷な民間療法であるとして、その効果を全面的に否定している。貝原氏によると、犬と猫の薬物利用が忌避されたことには三つの背景がある。まずは「薬学革命」である。薬学は革命を経て中央集権化され、近代的な医学と前近代的な医療の区別が強調されてゆく。次に「嗅覚革命」がある。臭いは瘴気論などと結びついて近代以降に忌避の対象になるが、犬と猫の薬物利用は臭いへの忌避感と結びついて、正統医療でも忌避されるようになった。最後に「感情革命」がある。18世紀後半以降、動物には痛覚があるという言説が広がり、犬や猫の薬物利用が「残酷な」(cruel)、「痛ましい」(pitoyable)行為として批判されるようになるという。
貝原氏の報告のコメンテーターを務めたのは、動物史を専門とする伊東氏である。伊東氏は、近年の動物研究の動向に貝原氏の研究を位置づけた。伊東氏によれば、およそ1980年代以降、キース・トマスの『人間と自然界——近代イギリスにおける自然観の変遷』(1983年)など、動物を歴史叙述に組み込む研究が蓄積されてきた。しかし近年では、人間による動物表象の歴史ではなく、動物の視点からみた人間世界、あるいは動物の行為主体性に着目する研究がなされるようになっているという。この「動物論的転回」(animal turn)は日本でも人類学などの分野で次第に注目を集めているが、歴史学ではまだ研究蓄積が少ない。それゆえ、貝原氏の研究は「動物論的転回」を踏まえた日本人による歴史研究として、大きな研究史上の意義を有していると伊東氏は指摘した。
合評会と研究報告後には、フロアとの質疑応答を通じて活発な議論が行われた。例えば、合評会後の質疑応答では伊達聖伸氏(東京大学准教授)が、フランスでは聖職者が「肥満男子」として表象されるケースが多いが他国ではどうなのか、大柄な男性の表象には近代批判(ガルガンチュア的な巨人)と医療化(肥満)という二つの契機があるのではないか、という問いを投げかけた。また、研究報告後の質疑応答では坂本葵氏(作家)が、近代以降に犬と猫の品種改良がなされるようになったことに触れながら、犬と猫の薬物利用の歴史は品種改良の歴史とどのように関連しているのかという問いを投げかけた。
南谷が冒頭の挨拶でも述べたように、2020年には国際疼痛学会(International Association for the Study of Pain)によって「痛み」の定義が41年ぶりに更新された。新定義において、1979年時の定義にあった「このような損傷を表わす言葉を使って述べられる」という文言が取り払われたのは、不快な情動経験そのものに重きを置き、苦痛を訴えることのできない患者や、人間の言語では語らない動物の痛みを取り込む目的であったが、第8回研究会ではこの「痛み」という主題の裾野の広さと個々の事象の複雑さを確認することができた。
報告者:田中浩喜(東京大学大学院)・南谷奉良(日本工業大学講師)








