2021年1月20日(水)、姜涛氏(北京大学中文系准教授)による講演「「新たな抒情」――何其芳『夜歌』における「心境」と「仕事」」がオンラインで行われた。同講演はEAA連続ワークショップ「中国近代文学の方法および射程」の第二回目に当たり、今回は50名の参加があった。

姜涛氏(北京大学中文系准教授)
何其芳(1912-1977)は、繊細な表現による初期の詩作から明朗な調子をもつ延安時期の創作への変化によって知られており、その転換は「何其芳現象」とも呼ばれ、これまで議論の対象となってきた。今回取り上げる『夜歌』はその転換の過程を示す重要なテクストであり、1930年代の何の「抒情」の延長線上にあると同時に、魯迅芸術学院を含めた延安における集団的な環境の影響も見られる。
『夜歌』には、「快活」という表現が散見される。『夜歌』の自由で伸び伸びとした文体は子どもの発話のような活力を帯びており、それは当時の何其芳の思想的な「成長」と連関したものだった。初期の詩作を特徴づける「寂寞」というテーマは、ここに至って延安の共同生活の中で生み出される情熱へと変化し、更に革命同志の間で交わされる同志愛の表明へと繋がっていった。こうした明朗さや情熱は中国の新詩の系譜において全く新しいものであり、「新たな抒情」とでも呼ぶべきものである。
「抒情」は中国の新詩にとって極めて重要な用語であり、初期の新詩の理論的な起点でもあった。そこでは詩歌はある抒情主体の表現であると見做され、「抒情」は主体の内面や自我を造り上げる一方で、社会を動かす「情動」でもあると理解された。日中戦争以降も、徐遅の提唱する「抒情の放逐」に対して穆旦が「新たな抒情」を主張するなど、新詩における「抒情」の系譜が継承されていった。但し穆旦の主張は「新たな抒情」と銘打っているものの、実際には自我と自然・社会・国家とを対峙するものとして捉える二元的な「旧い抒情」の原型を留めており、また当時の延安における詩作もそうした「旧い抒情」の面影を残していた。しかし何其芳の詩作においては、そうした二元的な抒情の代わりに革命同志間の親密な人間関係が描かれており、この点は魯藜や艾青など同時代の詩人とは異なる何其芳独特の「新たな抒情」であったと言える。
このような「新たな抒情」の傾向は、何が自身の「心境」を整理した結果でもあった。何が後に『夜歌』の標題を『夜歌と昼間の歌』と改名したことに明らかなように、当時の何は夜と昼、新たな自我と古い自我、寂寞と情熱、個人と集団、仕事と文学といった「心境」上の数々の矛盾を抱えており、『夜歌』にはそうした相反する「心境」の襞が書き込まれていた。そして当時の知識人の思想上の動揺や矛盾が描かれた『夜歌』のテクストは、延安の革命従事者に自身の「心境」を整理するべく促すことで、彼らの日常的な「仕事」や生活において意義を獲得していった。
革命に従事する「仕事」と詩人という身分との矛盾もまた、当時の何其芳が抱えていた矛盾の一つである。魯迅芸術学院で働いていた何は、弁の立つ優れた教師というよりも、とにかく「仕事」熱心な人間として人々に記憶されていたようである。そして『夜歌』で描かれる数々のもまた、そうした「仕事」の現場で起こった出来事に他ならない。その意味においては、実際の「仕事」は文芸創作に対立するものというより、寧ろ何の創作を刺激する存在であったと言える。『夜歌』で示された「新たな抒情」は、そうした「新たな仕事」の倫理において次第に広がっていったのである。
「新たな抒情」というキーワードに導かれつつ、何其芳の延安時期のテクストがもつ独自性に焦点を当てた本講演の内容は、以上のように多岐にわたるものであった。講演後に設けられた質疑応答の時間では、王徳威・陳国球による「抒情」論や伝統中国における「情」との関連性、国統区の「抒情」と解放区の「抒情」の差異、更には近年研究上の流行となっている「社会史的視野」の議論との接続性など、さまざまな問いかけがオーディエンスから提出され、講演は盛況のうちに幕を閉じた。
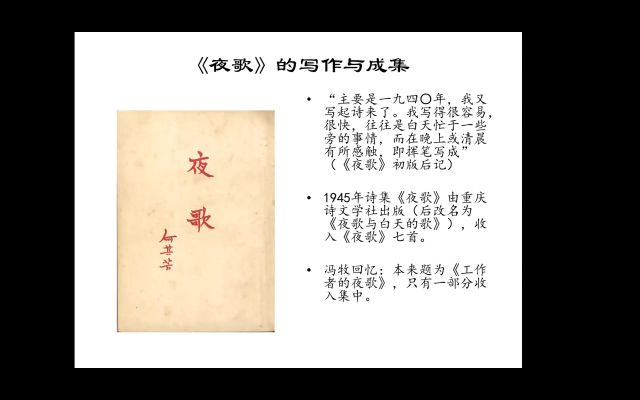
報告: 田中雄大(東京大学人文社会系研究科博士課程)

「18世紀の対話篇を読む/論じる/翻訳する」







