
『世界哲学史』(全8巻+別巻、ちくま新書)
2021年3月9日、「世界哲学・世界哲学史を再考する」と題した連続シンポジウムの第1回「世界哲学史の可能性:中国とヨーロッパを付き合わせる」がZoomにて開催された。この連続シンポジウムは、2020年にちくま新書から全8巻および別巻が刊行された『世界哲学史』シリーズの編者である納富信留氏(人文社会系研究科)をオーガナイザーとして迎え、「世界哲学(史)」というコンセプトのさらなる可能性を探究する試みの一環である。
第1回となる今回のシンポジウムには、オーガナイザーの納富氏に加えて、編者を務めた中島隆博氏(EAA院長)、論考を寄稿した石井剛氏(EAA副院長)が参加して、それぞれの発表者が「中国」と「ヨーロッパ」の関係を「世界哲学史」的な射程で捉えなおすためのアイデアを持ち寄った。議論の糸口を提供するため、崎濱紗奈氏(EAA特任研究員)と本報告の執筆者である田村正資(EAA特任研究員)が加わり、それぞれの観点からコメントを行った。
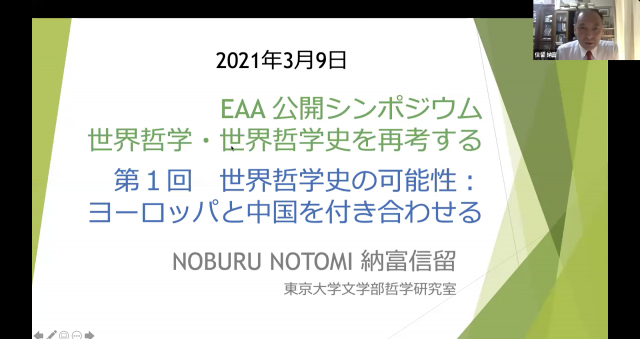
納富氏は、この連続シンポジウムの趣旨説明に続けて「世界哲学史の軸としての中国とヨーロッパ」と題する報告を行った。報告では図式化の弊害にも目配りを行いつつ、「世界哲学(史)」を構想する際のひとつの基軸として「ヨーロッパと中国」というテーマがありうると指摘がなされた。ヨーロッパから中国への影響だけではなく、中国がヨーロッパに与えた影響や、西洋を相対化する視点として中国を研究することの意義を説いたうえで、そのテーマに関する日本独自の業績があることも紹介がなされた。
続いて中島氏は「中国古代からの視点」という題で報告を行った。ある概念はしばしば翻訳されて変容し、またもとの地域に逆輸入されていく。世界的な枠組みで哲学を考えるときには、このような概念の遍歴を問うべきではないかと中島氏は問題提起をした。中国にはヨーロッパの「神」よりも古い歴史があり、「古代中国」への独特な視線がある。また、中国には世界の成り立ちを論じる複数の経書が存在し、テクストの複数性がそのまま世界の複数性と向きあう態度を醸成してきた。場としての中国をめぐる哲学的な概念の変遷を問うこともあるいは可能であるだろう。
石井氏は「中国近代からの視点」という題で報告を行った。報告では中国における哲学的言説のあり方について近代中国で展開された議論が紹介された。とりわけ戴震をめぐった中国哲学構築の試みに触れて、中国においてはつねに、ヨーロッパ発祥の「哲学」を問うことが自らのアイデンティティを問い直す契機になってきたと指摘した。加えて石井氏は、清代考証学を例に挙げて、中国思想において文献研究が重視されてきた歴史にも触れた。中国思想の文献学的な特徴は、ヨーロッパの哲学的な伝統とも重なり、その意味でも「中国とヨーロッパを付き合わせる」際のひとつの視点となりうるだろう。
3人の報告の後、まずは田村が「哲学の普遍性と言語」という観点から、崎濱氏は「世界‐哲学‐史」という複合語と「他者」「周縁」の関係を問いなおす観点からそれぞれコメントを行った。田村は『世界哲学史』第5巻に収録された新居洋子氏の論文「イエズス会とキリシタン」の内容を紹介し、「世界哲学」なるものがあるとすれば、それは言語的な隔たりを乗り越える営みであることを存在の条件とする必要があるのではないかと問題提起を行った。崎濱氏は伊波普猷をめぐった沖縄思想史を専門としている。同氏は、沖縄という日本を経由して近代が流入してくる場から見たとき、「世界哲学(史)」的なコンセプトについてどのようなことが言えるか、という視点からコメントを行った。
総合討論では、研究員のコメントに対して各報告者が応答し、そこにまた研究員が問いを重ねていくかたちで議論が展開された。「世界哲学史」という主題は、「世界」という言葉の拡がりによって様々なバックグラウンドを持つ人々の参加を促しつつも、「哲学(史)」という言葉の歴史的な負荷を避けられない。それゆえに「世界哲学史」とは、つねにジレンマをはらむコンセプトであると言える。議論のなかで、自らの状況に向き合う人々の「アイデンティティ」と、その思考のなかで呼び求められる概念の「普遍性」の関係が話題になった。自らのおかれた立場や考えを他者と分かち合い、問題を解決していくためには一定の普遍的な枠組みがなければならないが、その言葉はつねに特定の人間の喉から絞り出されてくるのでなければならない。普遍的な言葉を希(こいねが)う個人の思考を、私たちがいかに拾い上げてきた/いくのか。その探究の営みとして「世界哲学史」を考えることもできるのではないかと、登壇者のひとりとして感じた。私たちは「世界哲学史」にどんな言葉を希うのか、今後のシンポジウムの展開が楽しみになる幕開けであった。
報告者:田村正資(EAA特任研究員)
|
第1回シンポジウムの参加者からいただいたご質問・コメントの一部を紹介させていただきます。回答はシンポジウム発表者個人の意見です Q1 world philosophyの語にはいわば「多様のなかの統一」(worldliness?)という含意が込められていて、その点で「画一性」を示唆しかねない“global” philosophyを採らなかったというお話でした。他方、歴史学のほうでみると、宗教的普遍主義を含意するuniversal history、脱キリスト教的普遍性を含意するであろうworld history、これに対して西洋中心主義を批判し多元性を重視する“global” historyという流れがあるようにも感じます。その点では、両分野で“global”という語の受け止め方が異なる部分があるのではないでしょうか? さらに“world”概念への眼差しが歴史学ではより批判的だということはないでしょうか? もしあるとすれば、哲学の側でそれにどう応答するかも問われるかもしれないと思われます。 A(納富) ご指摘ありがとうございます。world, global, universalといった言葉の使い方と概念には分野ごとの歴史と微妙な違いがあるようで興味深いところです。例えば、哲学に関してuniversal philosophyという表現は見たことがありません。哲学はその存立自体が普遍性にあるからでしょう。私自身は普遍性は多元的に追求できると考えています。ただ、タイトルにそれほどこだわるつもりはありませんので、global philosophyといった表現を使う海外の研究グループとも協調していきます。 A(中島) ご指摘のように、world, global, universalの概念的な働き方は分野によっても違いがあり、それをどう考えるかが重要です。カント的な意味での普遍史universal historyは明らかに西洋中心主義的で、東洋はいわばアネクドートのような扱いでした。京都学派が受容した当時のヘーゲル的な世界史world historyにも西洋と東洋のヒエラルキーが厳然としてあり、その上での転倒を試みたのだと思います。それに対して、近年のglobal historyはそれらの限界を超えていこうとする試みだと思います。それは従来の歴史の主体を批判する意義を有していると思いますが、主体をずらしたり消したりするだけでは、多元性が担保できない可能性は残ります。世界哲学world philosophyとあえて使ってみるのは、世界という概念を鍛え直しながら、哲学における普遍性を問い直したいという思いがあります。
Q2 世界哲学という概念の提起は結局どんな問題を解決したいですか? この言い方自体はどんな目的と意義がありますか? 世界史とのつながりはどんなことですか? A(納富) 世界哲学は具体的な問題解決を目指すプロジェクトというより、哲学のあり方を再検討することで本来の哲学の営みを取り戻し、そこで現実の諸問題に対していく共同作業の場です。それを通じて、地球環境や文化対立や格差などの問題にも新たな視野が期待されます。また、世界哲学史は世界史(歴史分野)ともより綿密な連携をもって議論していきたいと思っています。
Q3 概念の世界的循環と概念の再発見というお話は興味深かったです。ですが他方で、概念の世界的循環で言われているところの「世界」が(抽象的な議論が交わされる)学問の世界に強く制約されすぎていないか心配になりました。ここら辺のことはどうお考えになるのか興味をもちました。 A(中島) 世界は学問的な抽象には収まらない具体的な現実にも関わっていると思います。悩ましいのは、その現実が成立するのにも諸々の概念が深く関与していることです。そのダイナミックな構造を理解するためにも、概念の世界的循環を見ていくことができればと思っています。 A(納富) 哲学や哲学史の議論を進めていくのが研究・教育の場であるため、どうしても学問的な抽象性を帯びてしまうのは仕方ないかもしれません。ただ、「世界」が学問の領域を超えた現実を指す以上、より広い範囲の人々との連携を図っていくべきでしょう。その際の語り方が難解で専門的にならないような配慮が必要となります。
Q4 よく「世界の解像度を上げていく」というようなことが言われますが、人間の成長と呼ばれる過程が正にそれであるとすると、認識に枠組みを付与していく過程に於いて付与される枠組みというのは、その人が生きる社会に依拠したものになってしまうのでは、と思い、究極の「普遍性」は生と死のその一瞬にしかないのでは、ということを今までは考えていました。しかし、本日のシンポジウムを経て、個々の集合体としての社会、として捉えると、確かに普遍性を見つける事も出来るな…しかし、その個々でさえも社会によって形成されたものだとすると…という循環が生じるようにも思え、先生方はその循環のどこに、何を基準にして切り口を見つけるのだろうか、ということが気になりました。 A(納富) 私たち一人ひとりは自身の視点や背景をもち、経験や他者との関わりをつうじてそれらを変容させています。その中で人々とともに語り考える可能性を模索する場が「普遍性」でしょう。普遍性はすでに持っている特性ではなく、議論や対話をつうじて確認され共有されていくべきもので、その限りで批判的な考察の対象でありかつそれを成立させる背景です。
Q5 崎濱さんが述べられたように、当事者性(「わたし」の特殊性)には、知の営みの普遍性を覆い隠してしまう側面があります。これに対して、中島先生の「自分は距離をとってAとBを比較する」方法に対する批判は、当事者性が(問う人に属する問題意識の次元のみならず)普遍性を確保するうえで必要であることを示唆しているように感じました。「普遍性の確保」という視点から、われわれが概念の循環に参加してゆくことの意味を語ることはできるでしょうか。 A(納富) それぞれの「わたし」は実は単一の固定された視点や主体ではなく、その内に多様な視点や考えを持ち葛藤をかかえた複雑な存在です。さらに、他者との関わりにおいて視点を移動させていくことも重要です。それが哲学に参画するという営みです。概念はそういったダイナミズムにおいて自然に循環するはずだと期待しています。 A(中島) 当事者という概念は翻訳しづらい概念です。だからこそ、それは「わたし」というあり方を鍛え直してくれると思います。それは、従来の主体と客体といった対立を問い直し、「わたし」がより複雑に世界に関与していること、他者と関わっていることを考えさせてくれるのではないでしょうか。
Q6 ヨーロッパ思想史と中国思想史は世界の歴史において二つのメインの思想史だと言えると思われますが、最近(とくにアメリカなどで)80年代からのヨーロッパ中心主義批判に続き、「中国中心主義」も注目されるようになってきました。中国思想は西洋思想の「対等と言える他者」としてヨーロッパ中心主義批判には使われるのですが、最近になってこの「ヨーロッパと中国」というペアリング自体が「書記言語中心的、歴史意識中心的、文献学的、どちらもドミナント・カルチャーである」、哲学の枠を広げるにはヨーロッパ中心主義(西洋)の他者(東洋)ではあるがそれは「同類の他者」であり、「他の他者」ではない、という批判の的になってきているのですが、このような指摘(批判)に対してどうお考えでしょうか。 ちなみに、このような批判は、アメリカでは「比較哲学における中国哲学の中心性」、その政治性の欠陥、と言った形で、主にデコロニアル哲学派(アフリカ、ラテン・アメリカ、その他のクリティカル政治哲学)から出ているものです。批判の要は、「ヨーロッパ、アメリカ、中国」哲学という枠はそれぞれ「哲学脱植民地化」(decolonizing philosophy)を目標とするアフリカ、ラテンアメリカなどの批判哲学との対話を避け、新しい「東西世界優位」を成立するものであり、「南北問題」を問題化していないが、「世界」を語る現在最も必要な課題は(思想においてもの)ドミネーションをテーマとする「南北問題」なのであり「東西」ではない、という点です。(アメリカ、特に今中国が経済的にトップにでた世界経済事情から出て来ている背景が比較哲学の分野にも影響し、それに対する批判が哲学内で起こっている、ということです。) A(納富) 貴重なご指摘をありがとうございます。「東・西」や「ヨーロッパ・中国」という対立軸が周辺や他文化を見えなくしてしまう恐れはつねに心しておくべき点です。世界哲学はどのような仕方のものでも「〜中心主義」と呼ばれる偏向を排除する試みです。他方で、世界哲学史では、おそらくその二つの哲学伝統が大きな役割を果たしてきたことを認めて、それを権威化することなく批判的に見ていく必要があるはずです。シンポジウムで指摘したように、哲学営為の連続性と伝統、その展開の範囲と文字資料の伝承という点でこの二つの伝統は突出しているからです。その遺産をどう活かしつつ乗り越えて新たな哲学を構築するかが現代の課題であり、そのためには両伝統に深く関わる日本という視点は有効だと感じています。
Q7 「哲学」という枠組み自体の変化への質問です。今までの「西洋哲学」を超える捉え方、という点は共通していると思いますが、言語、特に「書かれた言語」を超えた「哲学」を考えることは可能だとお考えでしょうか。もしもそうだとすると、それはどのようなところまで広げることが可能だとお考えでしょうか。 例えば、もう議論はされているかと思いますが、世界という場所を考えた場合、アフリカや中南米やアボリジニーその他の口承文化にみられるコスモロジーや信仰や世界像や人間像に「哲学」という表現は使えるか、踊りや武芸など言語でない表現に対して「哲学」は使えるか、また、もう少し広げると、漫画、お笑い、フィルム、SNSなどの最近の媒体には使えるか、その「哲学という表現を使うか」と問うのは誰で(私達哲学者ですが)、その思想的根拠や軸となる概念などは決めることができるか、それともそれ自体対話者や研究対象やテーマにより根本的に動くものだとし、その都度考察されるべきなのか、というような質問です。 A(納富) 哲学が「言葉」を離れて成り立つか、その「言葉」において語りと書くこととの違いはどうなるのかという点は、古代以来の問題です。古代ギリシアでは書き物を残さなかった哲学者が多くいますし(ソクラテス、ピュタゴラス、シノペのディオゲネス、ピュロン、エピクテトスら)、インド哲学・仏教の伝統では言葉を語らないという哲学の方途もあります。しかしこの点は西洋の神秘主義でも同様で、かならずしも「東洋」の特徴ではありません。 現代で哲学という思考・議論を遂行するのは学問が培ってきた言葉ですが、哲学的に考察される対象は、日常の言葉や各種の文化活動や非言語的営為も含まれます。それを、身体や絵画や音楽などで表現するのではなく、言葉で論理的に遂行するのが哲学の共通手段だと思います。どのような「哲学の言葉」が可能か、ふさわしいかは、世界哲学がこれから考えるべき基本問題です。
Q8 議論の最後の方に石井先生が取り上げてくださったインペアメントの視点が特に示唆に富んでいると思いました。インペアメントというのは、実際のところアイデンティティを成している「一部」のはずですが、「一部」だけによってこそつなげたり議論をしたりすることで、アイデンティティそのものの解放が初めて可能になるかもしれません。また、このような解放の前提として、「全部」を以って「一部」を切り離す生成があるのだとすれば、それは自覚を必然とする営みでなければならないはずでしょう。言い換えれば、学問/友情という生成ほど主体的でなければならない営みがないでしょう。しかし、自覚であれ主体性であれ、実践とかかわる問題としてその難しさを考えた場合、当事者問題と同様に、そして中心と周辺の問題と同様に、極めて慎重な態度を取る必要があると感懐しました。「世界哲学」はこの難しさとどのように向き合い、どのような方法論を提唱するのかは、「世界」に一番期待されているところなのではないかと理解しています。 A(石井) たいへん鋭いご指摘であると思いますし、わたしもご意見に共感します。アイデンティティは人が生きていくために大切な立脚点であると同時に、それが時に人を生きづらくしてしまう現実もあります。それを乗り越えていくためには、何らかの共感に頼る必要があると思います。Chinese philosophyを中国哲学から中国語哲学へと読み替える運動について紹介しましたが、わたしはさらに中国語内部の多様性と非中心性に注目するためにSinophone philosophyへと進む必要があると考えています。Sinophone(中国語系言語の総称)の領域では、多様なバックグラウンドを有し、「中国」という包括的なアイデンティティには到底収まらないような人々による「世界」の分節が絶え間なくくりかえされていると思います。
なお、今回シンポジウムにご参加いただいた有坂陽子先生が参加されているドイツ・ヒルデスハイム大学「世界哲学史プロジェクト」のウェブサイトもぜひご覧ください https://www.uni-hildesheim.de/en/histories-of-philosophy/ |








