2025年3月5日(水)14:00から駒場キャンパス101号館EAAセミナールームにて、第2回水と空気を考える会が開かれた。
はじめに企画者の張政遠氏(総合文化研究科)から趣旨説明がある。「風土変化(風土チェンジ)」をテーマに、特に水と空気の問題を考察することを目的としている。第1回(2023年)に続き、今回はより具体的な事例を検討し、環境変化が地域社会や文化に与える影響を深掘りする。特に、福島原発事故後の風土変化や、災害と宗教・文化の関係を取り上げ、単なる自然現象ではなく、歴史・社会的要因を含めた総合的な視点で議論する。今後の研究の方向性を探り、学際的な連携を促進することを目指す。

山泰幸氏(関西学院大学)は『東アジア災害人文学への招待』(山泰幸・向井佑介編、臨川書店、2025年3月)の出版をきっかけに、研究者・住民参加の防災論を風土論から再考する。桜島噴火や台風慣れなど、多様な災害要因と地域特有の自然環境が、家屋や家族を守る伝統的感覚を形づくり、実際の避難行動を左右する。寺田寅彦や和辻哲郎の議論を引用し、個人重視の防災モデルとコミュニティ単位の価値観の齟齬を指摘。さらに地域ごとの文化や災害史を丁寧に踏まえ、住民との対話を通じて最適な防災策を模索する必要を提案する。
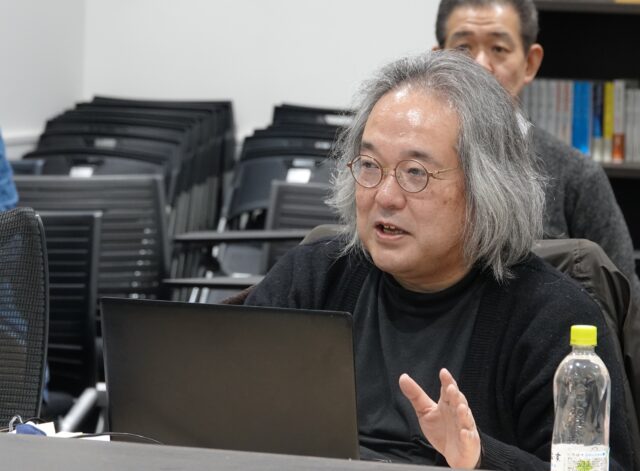
加藤泰史氏(椙山女学園大学・一橋大学)は、和辻哲郎の風土論におけるリベラルなトランスカルチュラリズムの側面を指摘し、それが梅棹忠夫の生態史観を経て亀山純生や桑子敏雄の「風土的身体性」に発展した系譜を概観する。また、寺田寅彦の「解釈的自然科学」とカント哲学との比較を試み、現代の防災やパンデミック対策に通底する問題を検討しつつ、想定外の事態への対応を哲学的観点から再評価する必要性を提起する。

桑山裕喜子氏(UTCP)は、空気汚染で少女が亡くなったロンドンの事例や、マイナス25度からわずかに気温が上がるだけで「暖かく」感じる体験を例示し、人間が環境を単なる客体としてではなく、身体・情動を通じて深く結びついていることを指摘。さらにダニエル・スターンの「情動的空気」概念を紹介し、呼吸や気の流れを含むコミュニケーションの重要性を強調する。現代文明がもたらす環境との摩擦を再考するうえでも、この身体性と「間」の視点が不可欠だと提起した。

張政遠氏は「風土チェンジ」の概念を軸に、大気汚染や都市開発、災害の影響などがどのように環境と人間の関係を変容させるかを論じた。台湾、日本、アメリカなどの具体例を示し、風土は固定されたものではなく、歴史的・地理的文脈や人間の営みによって動態的に変化すると強調する。とりわけ大気汚染などの実例は、風土チェンジが一部の地域では深刻な環境問題を誘発しうることを示唆し、環境との共生や持続可能性の視点が欠かせないと問題提起した。
譚家博氏(グラスゴー大学)は「風土」と「異文化交渉」の関係に焦点を当て、香港の歴史的変遷と国際的役割を通じて、文化の形成と風土の影響を考察した。特に「風土」の概念を用い、都市開発や気候変動が地域文化や社会構造をどう変化させるかを論じた。また、日本や中国との比較を通じ、異文化交渉が文化の発展に与える影響を考察し、風土が単なる環境要因ではなく、人間の意思によって変容することを強調した。異文化の融合や対話の重要性を示し、新たな哲学的アプローチの必要性を提起した。

ディスカッションでは、「風土チェンジ」の概念を中心に、居住地域の変遷、環境問題、異文化交渉の影響が議論された。アイヌや台湾の事例を通じ、風土が固定的なものではなく、人間の移動や社会構造の変化によって再編されることが指摘された。また、災害時の地域共同体の対応が議論され、祭りや消防団などの伝統的組織が防災と結びつく点が強調された。さらに、企業の「組織風土」にも触れ、職場文化の変化とその影響についての議論が展開された。

報告:張子一(EAAリサーチアシスタント)
写真:新本果(EAAリサーチアシスタント)








