私は一応、建築や都市の歴史を専門としている。しかし、興味の赴くままに研究をやっていたら、いつしか近接領域に首を突っ込んでばかりいるようになった。
建築学にとっての—少なくとも、私の考えでは—近接領域の1つとして、最近私が夢中になっている文化人類学を挙げることができる。文化人類学の方法論は、昨今のような変化の時代に一筋の光を投げかけてくれる。それらは、EAAが重視する古典への再訪と同様に、変化の観察者たるべき自分自身を、なんとか変化に押し流されないよう懸命に特定の視座へと定位させることを可能にする。
2023年度学術フロンティア講義「30年後の世界へ—空気はいかに価値化されるべきか」における人類学者小川さやか氏のわかりやすい解説によれば、学問としての文化人類学は、方法論上3つの特徴を持っている。1つ目は参与観察。2つ目は相対主義。普遍的な議論はその先にあるものと理解される。3つ目として、価値判断はしないという原則がある。自分たちの価値基準だけで他者の事象を評価しようとすれば、その背景にあるもの(例えば、価値システムなど)の総合的理解が妨げられてしまうからだ。
この三本柱に異存を唱える人類学者はおそらくいないであろう。他方、私は門外の研究者だからこそ、ここにあえて4つ目の特徴を付け加えてみたくなる。それは、上記3つの特徴によってかたちづくられる文化人類学独自のモノの見方それ自体である。
2023年6月3日から4日にかけて県立広島大学広島キャンパスにて開催された日本文化人類学会第57回研究大会は、人類学者たちがいかに文化人類学独自のモノの味方を演繹的に運用しているかについて披露し、語り合う場であった。少なくとも、門外の私の目にはそう映った。私は、それらの中から空気の価値化プロジェクトや個人で進めている研究を推し進める上での視点や切り口を得たいと思っていた。実際、色々なことを学ばせて頂いた。
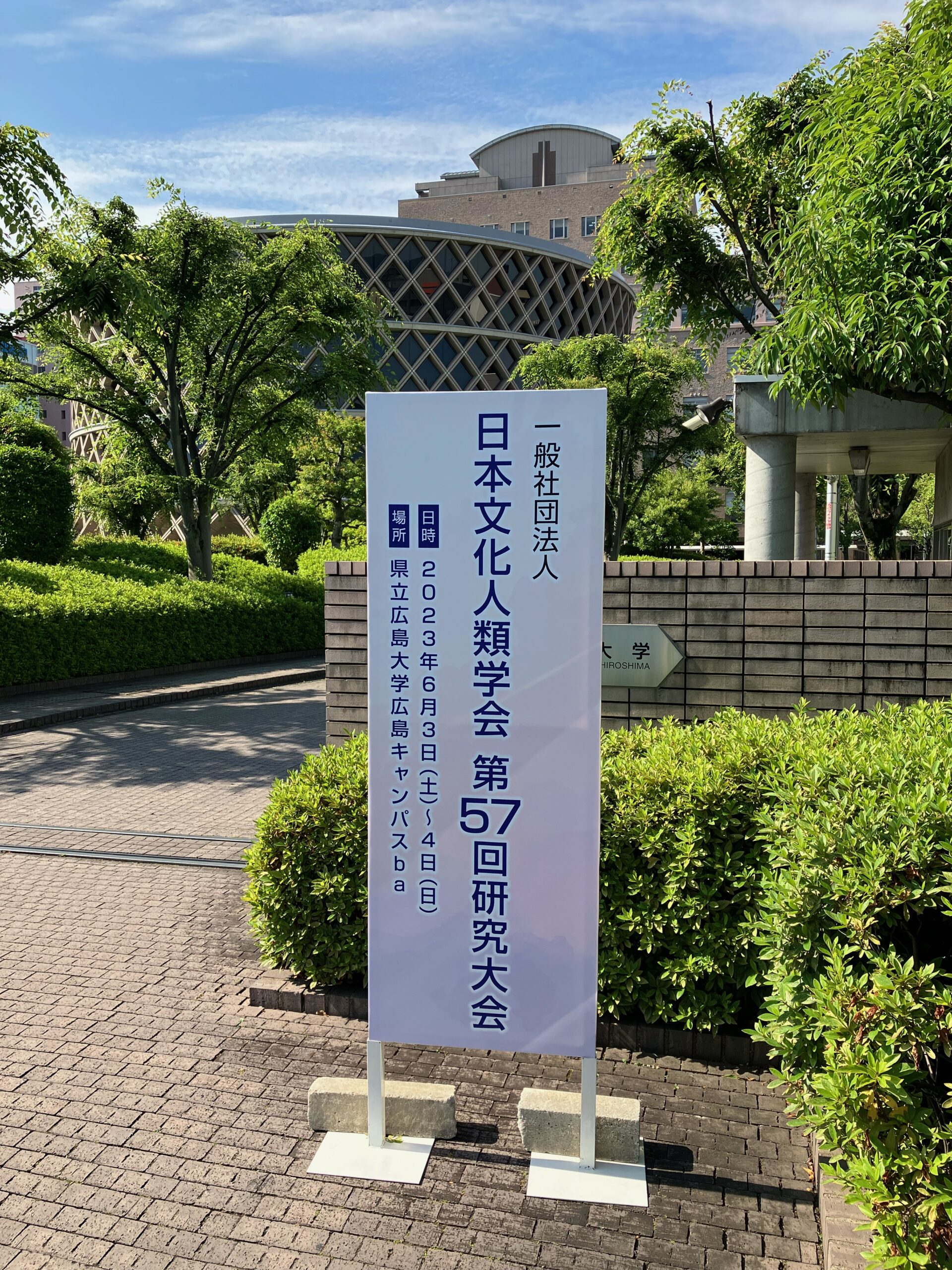
私が個人的に興味を持った研究発表は、概して2つのキーワードによって分類され得る。
1つ目のキーワードは、景観である。景観とは、目の前にある環境の眺めのことであるが、「背景」に置き換わらないところに「景観」という概念の存在意義がある。「景観」という場合、それは何らかのかたちで誰かに意識された環境の眺めであることを含意する。併せて、環境との間にある何らかの関わりという意味合いもまた包含している。よって、景観は環境の眺めという実態としてのみならず、記憶やイメージとしても語られる。景観に関連する研究発表として、古川勇気氏(新潟県立大学)「変わりゆく生活景観—ペルー、カハマルカ県山村の鉱山開発と河川」、阪田菜月氏(早稲田大学)「メラネシアの活火山から考える人新世」、合原織部氏(京都大学)「「先祖の田」の生成—宮崎県椎葉村における住民–景観関係の動態に着目して」などが興味深い話題を提供していた。
以上の研究発表は、それぞれペルー、パプアニューギニア、宮崎という全く異なる文化圏の全く異なる事象を扱っているが、共通して景観を巡る1つの構造を浮かび上がらせていたように見える。いずれの研究発表においても、景観が汚染や噴火、あるいは獣害などといった乗り越えるべき困難を通じて意識されるものとして描かれている。汚染や噴火によって目にみえるかたちで引き起こされる環境上の変化は、認識上「前にあった景観」と「後からできた景観」を生み出す。それらの間に時間軸が成立する。はたまた、「望ましい景観」が議論されるようになる。
空気の価値化プロジェクトとの関連で言えば、このような景観を認識することと出来事の関係は、そのまま空気を認識することと出来事の関係にも当てはまるように思える。私たちは日頃、空気に対して、絶えず強い意識を持ち続けることはない。花粉の多い空気を吸い込んでくしゃみをしたり、新型コロナウイルスが蔓延していることを知らされたりして、はじめて空気を認識する。そして、望ましい空気のあり方が議論されるようになる。私はかねてより都市や農村の景観に興味を持っていたが、景観を理解することが空気を理解することにつながるとは思ってもいなかった。これも偏に文化人類学のお陰である。
私が興味を持った研究発表を分類するもう1つのキーワードは、レジリエンスである。レジリエンスとは、ダメージに対する復活力や回復力と定義される。本学の関谷雄一教授が主催された分科会「レジリエントな社会モデルの構築—公共人類学の向かう先」では、東日本大震災からの復興というレジリエンス発揮過程を参与観察して得られた4つの研究成果が報告された。
それらの発表から導き出される示唆は、1つ目のキーワードである景観に係る議論と結び付けて理解できるように思われる。それは、震災復興におけるレジリエンスの発揮は、「前にあった景観」への文字通りの回復を必ずしも意味しないという点である。例えば、内尾太一氏(麗澤大学)の「持続可能な養殖漁業と国際エコラベルに関する文化人類学的考察—宮城県南三陸町の復興過程を通じて」は、南三陸のとある漁村において牡蠣養殖を営む漁師たちが、震災を契機に従来よりも持続可能な養殖法に取り組んでいく過程を明らかにした。生業を復興する過程で養殖に係る新しい技術や知見が摂取された結果、震災前とは異なる養殖筏の設置が実践されることになった。
牡蠣養殖という生業に着目すれば、それは漁師たちのレジリエンス発揮によって元に戻ったとみなされるであろう。他方、景観の概念を用いてこのプロセスを参与観察してみると、回復の仕方に付随する質(感)へとアプローチすることができる。「前にあった景観」への回復が目指されつつも、南三陸の海には実質的に「後からできた景観」がもたらされることになった。
アフターコロナの景観もまた、「前にあった景観」への回復を意味しないのであろう。大会初日の夜には、とある大学の文化人類学コースが主催したかなり大規模な懇親会に入り込んで「参与観察」を行った(ということにしておきたい)。4年ぶりの本格的な対面開催となった本年度の大会。研究発表のみならず、懇親会も大いに賑わいを見せた。ここで私が目撃したものは厳密には「後からできた景観」なのかもしれないが、やはり同じ場の雰囲気を共有し合いながら研究者たちと語り合うのは楽しい。
東京へ向かう新幹線に乗る直前、私は少しだけ平和記念公園に立ち寄った。2日前の荒天が嘘のような晴天の下、世界各地からやってきた大勢の人々が、この分断の時代における明日の平和を祈っていた。

報告:野澤俊太郎(EAA特任准教授)








