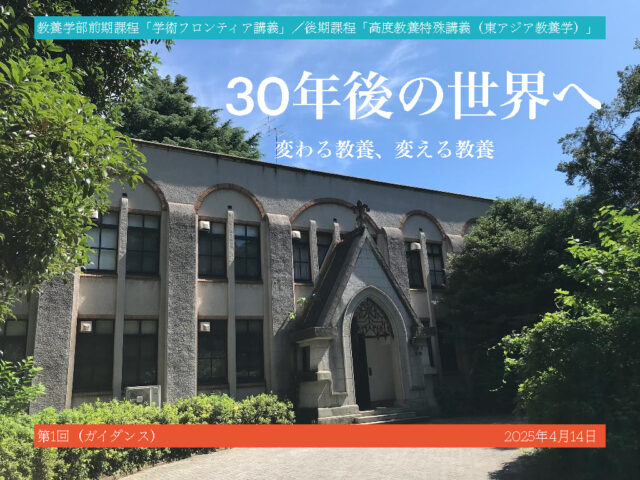
2025年4月14日(月)、2025年度学術フロンティア講義「30年後の世界へ——変わる教養、変える教養」第1回がオンラインで行われた。初回はガイダンスとして、コーディネーターの石井剛氏(EAA)が趣旨説明また各回の担当講師の紹介をした。
冒頭で、石井氏は101号館の由来およびEAAの組織について簡単に紹介し、EAAで求める新しい教育像について話した。EAAは、学部授業でクラシックテキストの精読を行いつつ、新しい視点を取り入れた教育を展開している。また、社会連携にも力を入れており、リカレント教育といった取り組みを通じて、「新しい大学モデルの創出」が図られている。これらの教育活動を通じて、いかに新しい未来を創造するのか、そしていかに共通の学問の価値を築いていくかが大きなテーマとなっている。
続いて、今年度のテーマである「変わる教養、変える教養」について、石井氏は受講者とともに改めて「教養」を考えた。受講者に対して、「「教養」とは何か?」、「「教養」を身につける方法は?」そして、「教養学部は皆さんに機能しているのか?」といった問いを投げかけ、意見交換が行なわれた。受講者たちは教養について、「生きやすくするもの」、「現代社会を読み解く力」など、幅広い知識を身につける素養であると捉えていた。一方、教養学部について、すでにここで1年を過ごした2年生たちの中には、教養学部に対する理想と現実との間にギャップを感じ、十分な満足を得られていないという声も見られた。
一般的に、「教養」は「カルチャー(Culture)」あるいは「クルトゥーア(Kultur)」として理解され、「躾け」とも関連づけられ、身につけるべき修養と捉えられている。リベラルアーツに含まれる「アーツ」は、単なる知識にとどまらず、技術や実践的な能力も含む広い意味を持つ。中世ヨーロッパでは「自由七科」という形で、また東アジアの伝統においては、「六芸」が教養の古典的なあり方として存在していた。近代以降、「教養」という概念は再構成され、とりわけ現代社会においては、その重要性が再び問われている。教養のあり方は、時代や空間、さらには政治・経済的な条件に応じて絶えず変化してきた。現代における急速な社会変化を受けて、「新しい教養(New Liberal Arts)」の目標もまた進化している。
現在では大学進学率が50%を超え、より多様な学生が高等教育を受ける時代となったが、従来の「教養の時代」は亡くなったとも言える。時代が急速に変わる中で、これからの教養は従来の枠組みでは捉えきれないものとなっている。そうした背景を踏まえ、「変わる教養、変える教養」というテーマのもと、今年度の講義では、あらためて教養のあり方を問いなおす。
最後に、石井氏は今年度の学術フロンティア講義の各回を担当する講師陣を紹介した。文系・理系を問わず、さまざまな分野の講師に加え、海外からの講師も招き、学術の最前線に触れ、いろんな背景の先生方から「教養」に対するお考えをうかがう。
それでは、今年度の学術フロンティア講義を楽しみにしましょう!
報告者:席子涵(EAAリサーチ・アシスタント)







