2024年11月17日(土)・18日(日)の2日間にわたり,“Contemporaneous East Asia: A Joint Forum by Graduate Students from China, Korea and Japan 2024”が,北京の清華大学を会場に催された。同フォーラムは,毎年,日本・東京大学,韓国・成均館大学,そして中国・清華大学の3大学による持ち回りにて催され,主に近現代東アジアにかかわる人文学を専攻する大学院生がつどい,おおよそ専門とする研究領域や年代ごとに区切られたパネルでの発表とコメンテーターを交えた質疑応答を通じて,自らの専門とする研究を見つめ直し,「東アジア」の幅広い視座へと開いてゆく機会となっている。本年度は,3大学より8名の教授陣と18名の大学院生が北京につどい,東京大学からはコメンテーターとして,三原芳秋氏(総合文化研究科),逆井聡人氏(同),発表者としては鄭徳峘(人文社会系研究科),清宮優衣(総合文化研究科),張暁然(同),川上智大(同)の4名の大学院生に加え,ポスドク研究員の黒沢祐人(総合文化研究科),かつて東京大学に留学していた劉文欣(北京大学)が現地に参加し,英語にて発表と質疑応答,議論を行った。
フォーラムの初日は,橋本悟氏(ジョンズ・ホプキンス大学)による招待講演 “Afterlives of Letters: Origins and Examples of Modern Literature in East Asia” に続き,清華大学のメンバーの案内によるキャンパスウォークが催された。清朝の康熙帝時代に離宮の庭園として造られ,王朝末期のアロー戦争後に英仏により破壊された旧円明園が敷地の一部になっているというキャンパス(ちなみに,破壊された廃墟が遺されていることで有名な円明園遺跡公園はキャンパスの西に隣接する)は,風光明媚な(!)自然を有しながら,随所に中国史の片鱗を想わせもする。自然豊かで美しいキャンパスを歩きながら,3大学の学生同士,教授同士はもとより,学生と教授がそれぞれの専門領域について訊ねあったり,教授から学生へ研究の助言をしたりする姿もみられるなど,さまざまに交流が行われた。

午後からはPanel 1ならびにPanel 2において,主に東アジアの近代を中心的な研究領域とする大学院生の発表が行われた。Panel 1では,袁先欣氏(清華大学)をコメンテーターに,5名の院生が発表した。東京大学からは,鄭徳峘が”HUANG Ying’s View of Chinese Folk Songs”と題し,大正末期から昭和初期にかけて日本・中国の文学者と交流をもち,日本詩壇で活躍した中国出身の詩人黄瀛をテーマに発表した。黄瀛は,1920年代の中国歌謡運動が強調した客観的保存方法とはアプローチを異にし,中国歌謡の言語と構造を日本の詩に適応させ,詩の聴覚的本質を捉える手法を通じて,詩作において日中両国の文化を融合させた詩人である。歌謡の感覚的および感情的側面を強調し,新たな詩的表現を探求しながら独自の文学スタイルを形成した黄瀛が,日中両国を越境する文化の媒介者であったことを,黄瀛による日本語の詩作や、彼が翻訳または詩作に取り入れた中国語歌謡の実例を示しながら議論した。
Panel 2では,黄鎬徳氏(成均館大学)をコメンテーターに,5名の大学院生が発表した。東京大学からは川上智大が,“The Origins of Hagiwara Sakutaro’s Coined Words in the Poetry Collection Hyoto”の標題にて,萩原朔太郎の詩集『氷島』の擬古典調の漢文体について,しばしば朔太郎の「造語」とみなされてきたいくつかの漢語表現の典拠となる用例が,中国古典にみられることの意味について議論した。従来,朔太郎は口語自由詩の確立を以て「日本近代詩の父」と称されるが,「郷土望景詩」や『氷島』の文体は,詩人の「退却」ないし「保守化」とみなされてきた。一方,発表では毀誉褒貶の議論を巻き起こした『氷島』詩語を,東アジアの近代におけるトランス・テクストのネットワークのなかに置き直すことで,朔太郎が漢語を取り入れた「新しい日本語」を模索し,「新しい口語藝術」を創り出そうとする革新的な試みとして再評価する可能性を提起した。Panel 2では,劉文欣も “The Spread of Left-Wing Culture in Campus of Northern China” のタイトルで発表した。
2日目のPanel 3およびPanel 4では,主に東アジアの現代を中心的な研究領域とする大学院生が発表した。Panel 3では,逆井聡人氏をコメンテーターに,4名の大学院生が発表した。東京大学からは,清宮優衣が “The Named Subject: Takahashi Takako’s The Tempter”のテーマにて,高橋たか子『誘惑者』(1974)の分析を通し,狂気的だと見なされる人物主体に対し,他者の記憶がもつ可能性を模索した。ウーマンリブとの共通点を持ちつつ,死にゆく存在に焦点を当てた本作では,覇権的な物語を無意識にずらしながらも,「抵抗」的ではない存在の応答可能性が描かれる。そして,作中で批判的に描かれる男性的主体は,女性を排除しながら,敗戦直後の「政治と文学論争」で「近代的主体」となろうとした男子学生である。「狂気」的な主体の構築は,男たちの戦争責任をめぐる「近代的主体」への批判とも解釈できるものであり,東アジアの枠組みからの幅広い批評へと開かれ得ることが議論された。

Panel 3ではさらに,張暁然が “The Wavering ‘Made in Nippon’ — A Study on Yukio Mishima’s Nippon Sei” として,三島由紀夫『にっぽん製』(1952-1953)における恋愛モチーフについて議論した。作中,戦後日本の「独立」や「新しさ」が揺らぎながら崩壊し,いわゆるデザイナー言説による主体性も恋愛に翻弄されながら失われることから,「ジュドー・ド・パリ」のデザインや銀座という都市に,敗戦の記憶や帝国の残渣が刻まれていることを示した。発表では,『にっぽん製』は真の自立に至らない戦後日本を象徴し,恋愛を通して,戦後日本の「新しさ」を,「不純」な政治的アイロニーとして示唆していると結論づけたが,質疑応答はもとより,とりわけ休憩時間などでの清華大学や成均館大学の大学院生との「非公式」な交流を通じて,本発表が「戦後日本」の枠組みに限定されており,戦前・戦後の東アジアにおける言説や視座へと議論をひらいてゆく必要性が痛感された。

Panel 4では,三原芳秋氏をコメンテーターに,より現代的な諸問題について議論が交わされた。ここでは,黒沢祐人が“Colonialism, Violence and Dissociation in Postwar Okinawa: Imagining the Perpetrator’s Bodies in Matayoshi Eiki’s Fiction” と題して発表したほか,「日帝鉄杭断脈説」(いわゆる「日帝風水謀略説」)から,中国における「ショート動画」プラットフォーム,あるいは韓国における「インスタトゥーン」(Instagram + cartoon)といった極めて21世紀的なトピックまで,各国から多種多様なテーマがContemporaneous East Asiaの議論の俎上に載せられた。
フォーラムはClosing Round Tableを以て総括された。現地参加の教授陣とともに,東京から鈴木将久氏(人文社会系研究科)がオンラインで加わり,各氏が大学院生らの発表に対してそれぞれの専門領域から応答したうえで,次年度以降のフォーラムに向けた将来的な展望についても議論が交わされた。やがて,各大学の大学院生を巻き込みながら更に議論は活発なものとなり,フォーラムの締めくくりとしてふさわしいラウンド・テーブルとなった。

COVID-19の日本国内の感染症法上の分類が「5類」に移行されてから早2年,本フォーラムもいわゆる「コロナ禍」のあいだは各国の防疫上の理由からオンラインで行われていたが,2023年より東京大学・清華大学2校による対面に戻り,今回は対面での開催が復活して2回目,成均館大学も合流し3校開催の再スタート初回となった。日本で「不要不急の外出自粛」が求められ,中国ではいわゆる「ゼロ・コロナ」政策による厳格なロックダウンの体制が布かれていた頃,人々はオンライン・ツールの利便性に(なかば強制的に)慣れさせられ,かつてほどの「人流」は戻らないと考えられていた。しかし,あれから5年を経たいま,人とは「会いに行く」生きものだったのだと,多くの人々が気づかされていることだろう。このほど北京に渡航した大学院生のなかには,かつて本フォーラムにオンラインで参加した経験のある者もいる。自らの研究について対外的に発表し,コメンテーターを交えた質疑応答をするだけであれば,Zoom上でも事足りていたかもしれないが,一抹のもの淋しさは否めない。対面フォーラムには,人と人とが出会い,面と向かって議論を交わす空間としての「場」があり,会食の際や廊下での「非公式」な交流によってもたらされる次なる研究の「種」の数々もがもたらされる。それらは確かにフォーラムの「主目的」にはなり得ないかもしれないが,とはいえ「必要不可欠な『副産物』」ともいうべきものでもあったことに,失ってはじめて気づかされることとなったのである。
末筆ながら,このほどの北京への渡航に際しては,様々な形で関係各位の多大なるご支援をたまわった。この場を借りて御礼を申し上げたい。(参加院生一同)
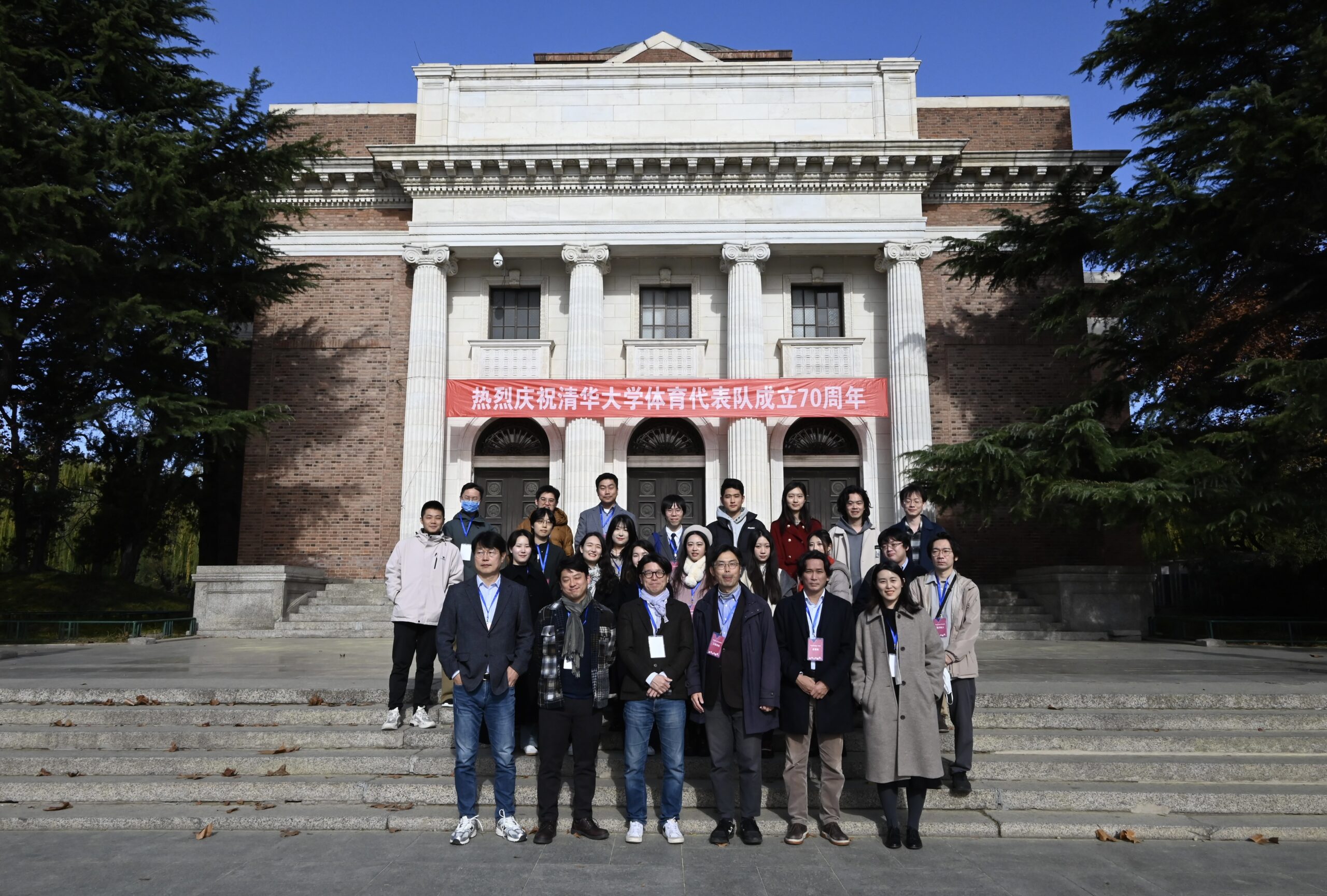
報告:川上智大(東京大学総合文化研究科修士課程)、張暁然(同)、清宮優衣(同)、鄭徳峘(東京大学人文社会系研究科修士課程)
※写真は主催校より提供されたものです。








