
2024年7月5日(金)、EAA主催の学術フロンティア講義「30年後の世界へ——ポスト2050を希望に変える」第12回が駒場キャンパス18号館ホールで開催された。岩川ありさ氏(早稲田大学)が 「パンデミックを銘記する」というテーマで講義を行った。
COVID-19によるパンデミックは、社会で周縁化されてきた人々の存在を可視化するとともに、社会や世界の不均衡を明らかにした。パンデミックの記憶が薄れ始めた今日、これらの周縁化された人々をどう記憶し銘記していくべきなのか。そして、どうすれば差異を持った人々が共に生きられる「共通世界」を、私たちは想像できるようになるのだろうか。これらが、今回の講義の主な問いである。

岩川氏がこの問題を考える手がかりとして挙げたのは、ジュディス・バトラーの論とバトラーの論が念頭におくエイズ危機の社会運動である。1980年代、アメリカ政府は未知のウイルスであったエイズを、ある特定の人々の集団と結びつけ、「ハイリスク・グループ」に指定した。この表象は既存の同性愛嫌悪を助長し表面化させた。「ハイリスク・グループ」とされた人々は、差別と無支援の中で、自ら声を上げなければ殺されてしまうという危機感を共有し、社会運動を行っていった。
ジュディス・バトラーは、生の条件として「前未来形」と「悲嘆可能性」を設定する。子どもが誕生した時に、その子が将来にわたってその生を全うできるだろうと思える「前未来形」、その子の死は嘆かれ得るという「悲嘆可能性」。すなわち、その生が尊重され、その死が哀悼されること無くして、人は生きられないのである。しかし、エイズ危機とパンデミックの事例からは、この「生の条件」がいかにマイノリティの人々から奪われやすいのかが見えてくる。パンデミックを銘記することによって、そのような状況をも銘記し記憶することが重要なのである。
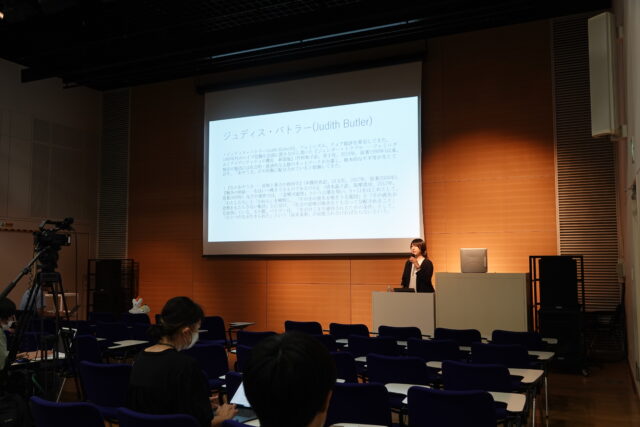
最後に、岩川氏は「共通世界」を想像する方法の一つとして、言語表現や物語を見出すことがあるのではないかと提案した。例えば、マイノリティの物語、言語表現が増えること、社会にある理不尽、暴力、支配関係などを問い直す言葉を見つけること、そうした表現によって社会の規範そのものを変えていくことなどである。岩川氏が提示したこれらの方法は、社会の不均衡を変えるために私たち一人一人が個人の力で実践できる方法であるように思われる。講義の終盤には会場から活発に質問・感想が出され、「共通世界」を想像し実践するために、自分ができることは何かを模索しようとする思いの感じられる、熱い議論が交わされた。
報告・写真:新本果(EAA リサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)貴重なご講義ありがとうございました。エイズ危機の時に、正常な人たちとハイリスクな人たちを区別し、前者の一部によって、「ハイリスクな人たちは自滅すればいい」というような言説があったと聞き、確かにコロナの時にも身近で同じような言説を聞いたことを思い出しました。例えば、「高齢者はいなくなっても良い」のようなものです。人は皆歳をとり、いつ自分がハイリスクな立場になるかわからないのに、排他的な言説が身近でされており、恐怖を覚えました。確かに過去の記憶がないと、同じことが繰り返されてしまいますが、ただ記憶するだけでも、このような人間の危機時の排他的な言動は無くならないと考えます。ハイリスクな人々を保護する制度などが必要だと感じました。ジュディス・バトラーの考えについて、過去と現在と未来をすべてつなげて考えるべきということは、確かに地球温暖化対策などの文脈で多く語られており、重要だがなかなか実行することが難しく、どのようにすれば人々の思考の際に当たり前なものとなるか考えなければならないと思いました。また、「悲嘆可能性」という概念は初めて聞き、とても興味深く思いました。確かに私自身も知らず知らずのうちに生に差をつけてしまっているのではとハッとしました。コロナと性について、一緒に考えたことはなかったのでそのような研究があることに驚きました。ぜひ詳しく知りたいです。本日は過去、現在、未来を考える上で重要な考えについてご講義いただき、大変興味深かったです。ありがとうございました。教養学部後期課程・3年(2)復興の技法を文学や言語表現に見出す・問い直す言葉を考える、という先生の言葉に非常に感銘を受けた。先生は特にマイノリティ問題に焦点を当て、同問題で見られる理不尽なこと、暴力、支配関係を問い直す言葉の必要性(そうした言葉の登場によって社会の規範そのものが変わっていくことを期待)を議論していたが、これはマイノリティ問題に限らず、多くの社会問題において共通しているのではないだろうか。川口さんの詩に関するお話、そして先生がいかに現在における未来の変容を切実な問題として考えるようになった過程を聞いた上で、様々な社会問題における各個人の当事者意識を強化することが極めて重要であり、そのために言語表現が大きな役割を持っていることを確信した。例えば、環境問題を語る上で「SDGs」や「持続可能な開発」といった言葉は欠かせない。これらの言葉はまた、私たち一人一人がしっかり向き合って考えるべきテーマでもある。しかし、現在社会においてはこうした言葉が一人歩きしている印象が強く、真にこの言葉と向き合っている人は少ないのではないだろうか。「持続可能な開発」というフレーズを言語化できる(=「将来世代のニーズを損なうことなく、現在世代のニーズを満たすような開発」など。)人が現在社会にどれほど存在するのだろうか。こうした問題に関して個々人が少しでも自分で考える自分の言葉で説明できるようになるだけでも、人々の意識は大きく変わるのではないだろうか。今回は環境問題を例にしたが、感染症などの他の社会問題に関しても人々の言語化能力の欠如、すなわち当事者意識の欠如という問題は少なからずあるのではないだろうか。現在社会の問題の多く(特に環境問題)は、世界中の人々、特に先進国の人々が少しづつ努力することが極めて有力な改善手段になりうる。その努力を促すためには、自分の行動が社会の人々(自分含め)、さらには地球上の生物にプラスの効果をもたらすという他者への思いやりが必要で、そのためには他人に共感する力・他人を慮る力が不可欠であろう。しかし(ここからは完全に私の想像だが)、現在の言語表現の幅では環境問題におけるこうした「共感力」が十分に養われにくいのではないだろうか。だから何十年経っても依然環境問題は悪化する一方なのではないだろうか。だとすれば、社会問題を「自分ごと」として捉えられるような意識の転換をもたらす表現を模索することが極めて重要であり、その可能性を文学から見出せるのではないだろうか。社会問題に対して人々をエンパワーメントできる言語・文学の登場に期待してみたいと強く思ったし、改めて自分も言語というもののポテンシャルを再実感し、その可能性を模索することで、これらの問いに対して自分なりに考えてみたい。教養学部後期課程・4年以上








