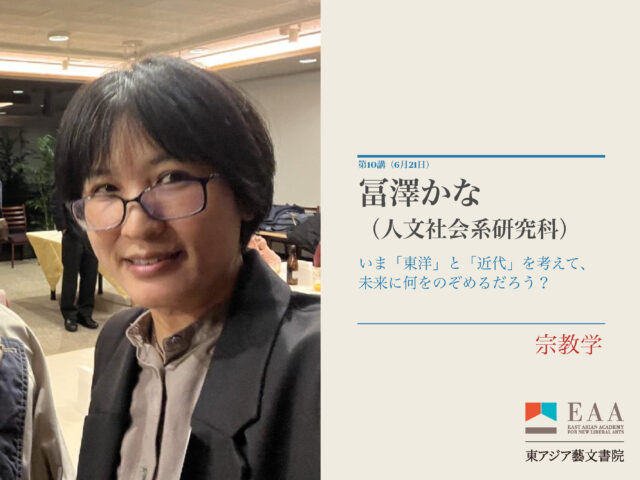
2024年6月21日(金)、EAAの主催で学術フロンティア講義「30年後の世界へ――ポスト2050を希望に変える」が駒場キャンパス18号館ホールで開催された。第10回となる今日は、冨澤かな氏(東京大学)が「いま『東洋』と『近代』を考えて、未来に何をのぞめるだろう?」と題した講義を行った。

まず、冨澤氏はオリエンタリズムについて、西洋が東洋に対して抱くステレオタイプとされており、西洋が自身の合理性や科学を強調し、東洋を非合理的で停滞した存在として描く場合は多いと指摘する。一方で、オリエンタリズムにはロマンティシズムの要素も含まれており、東洋への旅や冒険を通じて自己を再発見するという幻想も存在する。これに対して、オリエンタリズムを批判する研究では、このような二項対立が西洋の自己認識を強化し、東洋を従属させる仕組みとして機能していることが指摘されている。西洋が科学と合理性を象徴するのに対し、東洋は宗教と神秘主義の象徴とされ、東洋は停滞し、進歩しないものとして描かれる。このようにして、東洋は非合理的で停滞した古い存在とされ、西洋の優越性が強調される。

そして、冨澤氏はインドのヴィヴェーカーナンダの活動を事例として挙げる。ヴィヴェーカーナンダは西洋の物質主義に対抗する形でインドのスピリチュアリティを強調し、その価値を広めようとした。1893年のシカゴで行われた万国宗教会議でのスピーチは、その象徴的な出来事である。ヴィヴェーカーナンダは、この会議でインドの精神性が西洋文明のニヒリズムや物質主義に対する処方箋になると説いた。こうした活動は、オリエンタリズムの枠組みを逆手に取って、自国の文化を肯定的に打ち出す試みとして評価される。もちろん、これは単なる対立の構図を超え、東西の分断を超える普遍的な価値を模索する動きでもあった。
オリエンタリズムの研究は、近代の植民地支配の歴史を理解し、現代における文化間の対話を促進するために重要である。多様な文化がそれぞれの文脈でどのように影響し合い、どのようにより普遍的な価値を見出すかを考察することで、我々はより深い理解と共感を持って他者と向き合うことができる。オリエンタリズムの批判的研究は、過去の対立を乗り越え、新しい共存の形を探るための重要な視点を提供する。
報告・写真:張子一(EAAリサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)西洋が東洋を権力関係のもとで本質論的に一方向に語ることにオリエンタリズムの問題があるという考え方が大変興味深かったです。オリエントというのがオリエント化によって生まれた作られた概念でありそれが世界中に広まって実体となり、オリエントに関する個々の経験が実際は多様なものであるにも関わらず「オリエント」にまとめられてしまうというのも重要な視点だったと思います。また二元論的枠組みとしてのオリエンタリズムを批判することでむしろその再生産と固定化が引き起こされ、西洋が加害者で東洋は被害者という構図が固まってしまうという事態には考えが至っていなかったので、とても新鮮でした。
質疑応答の中でカレーについてのお話がありましたが、その中で「語彙は伸び縮みする」とおっしゃっていたことが印象的でした。私とあなたは違うから分からない、ということが尊重から分断に変わることを、自分が異物や他者についての経験を取り込んでいくことで止めることはできるかもしれないと思いました。
死生学の紹介で、近年は死が生活の延長線上から外れた病院という外部で起きることに変化した、という指摘にとても納得がいきました。死が疎外されタブー視されていくことが社会と私たちに及ぼす影響についても考えていきたいです。(教養学部(前期課程)文科三類・1年)(2)相対主義を乗り越えるためにはどうすればいいのかということを考えさせられる講義だった。
日々の生活の中においても、「あの人はあの人だから〜」といって、自分と他人の間に線を引っ張ってしまう面がある。しかし、それは他者理解には程遠い。
机上の空論的な議論にはなるが、相対主義がこの頃楽だとして蔓延っているというような構図は、ある特定の価値観を普及させようとしていたという点でヴィヴェーカーナンダがスピリチュアリティに普遍性を与えようとしていたことに似ている。そして、人との交わりの中で見出される新たな共作性などといったものが新たに普遍性を帯び始めると、何かまた違う問題が起こってしまうのではないかと思ってしまう。普遍性というものは、他者を圧迫してしまうほどの力があるのではないか。
これらを踏まえると、普遍性を求めるのは良くない気もしてくる。この世で普遍的なものというのは、自由を大切にする気持ちであろうか。しかし、必ずしもそれが普遍的である必要もないであろう。特定の人や集団との間の、そこでしか成り立つことのない共同性のようなものを大切にしていく必要があると思った。(教養学部(前期課程)文科一類・1年)








