2024年5月31日(金)、共同研究会「雑種文化論の可能性――加藤周一、芥川龍之介、アナトール・フランス」は対面(東京大学駒場キャンパス101号館EAAセミナー室)とウェビナーのハイブリッド形式で開催された。本イベントは立命館大学加藤周一現代思想研究センターとEAAの共同主催で、上廣倫理財団の協力を得て実現したものである。鷲巣力氏(立命館大学)が司会を務め、宮坂覺氏(フェリス女学院大学)が基調講演を行い、半田侑子氏(立命館大学)と伊達聖伸氏(東京大学)が報告を行なった。
共同研究会の冒頭では、司会の鷲巣氏より趣旨の説明がなされた。「雑種文化」論とは加藤周一がフランス留学(1955)から帰国後に発表した一連の論考であり、戦後日本の代表的な論考でもある。従来、加藤周一の「雑種文化」論をフランス留学中に得た発想とみなす意見が多いが、実はより古いルーツが芥川龍之介の文学、とりわけ「切支丹もの」にあると考えられる。本イベントはこの点を踏まえつつ、芥川が愛読し、加藤にも影響を与えた作家アナトール・フランス(Anatole France, 1844-1924)との関わりも視野に入れて、雑種文化論の可能性を問うという趣旨だと述べた。
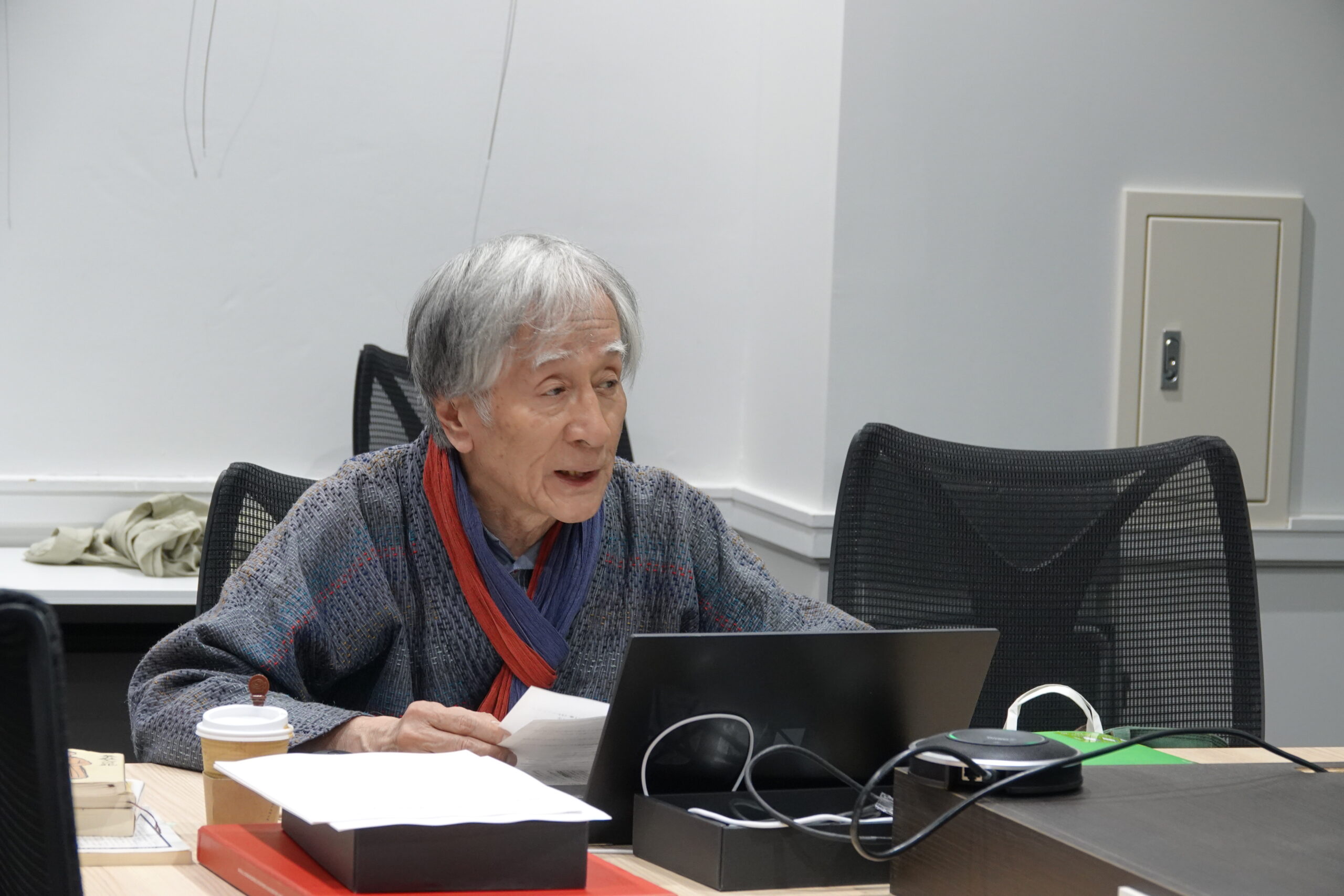 鷲巣氏
鷲巣氏
宮坂氏の講演「芥川の〈切支丹もの〉の世界——その多層的意味の一考察」は、芥川の家庭状況と生活環境を手がかりに、芥川文学を支える美意識の出自を幼少期に経験した「東京に忽然と出現した小さな西洋」と「東京に残された最後の江戸」に求め、こうした経験は芥川文学における「西欧的なるもの」と「日本的なるもの」、もしくは「永遠に超えんとするもの」と「永遠に守らんとするもの」の緊張関係として現れると論じた。そのうえ、芥川の生涯におけるキリスト教との関わり、「切支丹もの」に対する彼の関心と「煙草と悪魔」(1916)をはじめとする創作の実践について、学生時代の資料に遡りながら跡づけた。さらに、韓国・中国と対照的に、キリスト教信者が1%にも満たさないという日本の状況に言及し、西欧からの文化が日本の「造り変える力」(芥川)あるいは「沼地」(遠藤周作)の作用で溶解していくという問題を指摘した。
 宮坂氏
宮坂氏
半田氏の報告「芥川文学と加藤周一の「雑種文化」論」はまず加藤周一『青春ノート』(1938)を取り上げ、加藤の「雑種文化」論の原点は芥川文学にあったのではないかという問いを立てた。そして、加藤が芥川を評価したのは「西洋」に対する「わからない」という自覚であって、加藤の『日本文学史序説』(1975)で述べられた「変化をひきおこした力」をもつ「土着の世界観」が芥川の「神神の微笑」(1922)で語られた「造り変える力」に通底するものであると論じた。また、加藤と似たような問題関心をもちつつ、「雑種性」に批判的な態度を示した丸山眞男も芥川に注目し、「造り変える力」を「雰囲気と情緒を通じての同化」と捉えたという。半田氏によれば、芥川文学は丸山・加藤にとって「共通の触媒剤」でもあるのである。
 半田氏
半田氏
伊達氏の報告「造り変える力の小さな希望——この国の霊と戦う相対主義」は芥川も含め多くの日本知識人に読まれたアナトール・フランスを切り口に、芥川文学と「雑種文化論」との関連性を考察した。伊達氏はまずA・フランスと芥川の間に「絶対的な固定した物の⾒⽅をしない相対主義」という共通点を見出し、次に加藤の芥川像を踏まえて、A・フランス、加藤、柳田國男の思想に反軍国主義的・反国家主義的・自由主義的な愛国主義を看取した。さらに柳田と林達夫を補助線にしながら、「日本的なもの」と「外来の普遍的なもの」の関係と相互作用を検討した。最後、普遍的なものの根づかない土壌にある抵抗の可能性、西欧近代との同質性にも「国体」にも回収されない雑種文化の希望について問題を提起した。
 伊達氏
伊達氏
質疑応答では、芥川における理知性に還元されえない側面、遠藤周作における芥川文学の受容、日本の作家とキリスト教の関係など、様々なテーマをめぐって議論が交わされた。
報告:郭馳洋(EAA特任助教)
写真:席子涵(EAAリサーチ・アシスタント)









