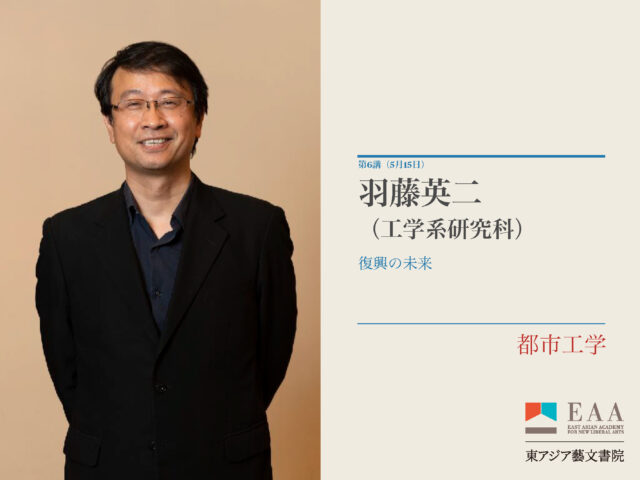
2024年5月15日(水)、EAA主催の学術フロンティア講義「30年後の世界へ——ポスト2050を希望に変える」が駒場キャンパス18号館ホールで行われた。第6回は、工学系研究科の羽藤英二氏(東京大学)が「復興の未来」という題目で講義を行った。

羽藤氏は、今年初めに発生した能登半島地震と台湾の花蓮地震を皮切りに講義を始めた。能登半島地震発生後、羽藤研究室のメンバーは被災地で現地調査を行った。花蓮地震と比べると、能登半島地震は初動の確認や処理速度が違っていた。そこには道路啓開やインフラ整備などの制約があり、また漁港の特性や地域資源の破壊も影響している。現在日本の国土では、2100年に予想される人口4000万人、巨大災害の可能性、そして失われた30年という3つの大きな危機に直面しており、東日本大震災後、持続可能性のためには地域の復興が重要な課題となっており、様々な対策が展開されてきた。
最後に羽藤氏は能登半島の復興の未来を展望した。能登半島は、富山湾に面する内浦と外浦を中心に、低山と浦浜が独自の流通ネットワークで繋がる地域である。昭和40年代に国鉄能登線が開通し、観光ブームが起こり、その後、道路整備や能登空港の開港で地域発展が進んだが、持続可能性が課題となった。これからも災害に備え、持続可能な国土を再構築し、この土地で生きたいと願う人々と共に未来を築くことが求められている。

報告・写真:席子涵氏(EAAリサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)今回の授業では能登半島の災害の現実を目の当たりにし、自ずと自分の中から湧き出るものがあるように感じました。授業では家屋が無惨に倒れているものや地震によって裂かれている地面の写真がありましたが、このような大震災に直面する当事者の心情に思いを馳せながら受講しました。このような甚大な被害を被った人々は果たしてまた希望を持てるものなのかについて考えました。 そこで、仮設住宅の話がありましたが、プレハブ型からまちづくり型、ふるさと回帰型への転換について考えることがありました。たとえ災害の中でも、その場凌ぎのものとしてではなく、災害が終わった後の復興を頭の中に入れている仮設住宅の設計に心を打たれました。このような設計があるからこそ、どれだけ甚大な被害を受けても必ず生活をやり直せる確信 と希望があるものだと思いました。そして、第二回の溝口先生の授業でも紹介されましたが、こういった人々の取り組みが「レジリエンス」なるものだと思いました。- 後期課程(教養学部(後期課程)・3年)(2)興味深いご講義ありがとうございました。私が興味を持ったのは仮設住宅についてのお話です。東日本大震災時のプレハブ型、熊本地震時のまちづくり型、能登地震時のふるさと回帰型があるとお聞きしました。仮設住宅が最低限の生活の場としてだけでなく、コミュニュティの確保やさまざまなサービスの場になりうるというのは初めて知りました。やりすぎではないかという意見もあるのは理解できますが、地域住民も参画して復興に参加していけるのであれば、とても価値のあることだと感じました。今日の講義で時々東京に住む私たちに関する言及がありましたが、大学進学で上京し、住んでいる地域周辺での交流もほぼないので、関東での災害にとても不安を感じました。能登などでの災害と、東京での災害対応では、全く違う問題が出てくると思いますが、どのような違いや共通点があるか考え、自分自身災害への考えを深めなければいけないと感じました。- 後期課程(教養学部(後期課程)・3年)








