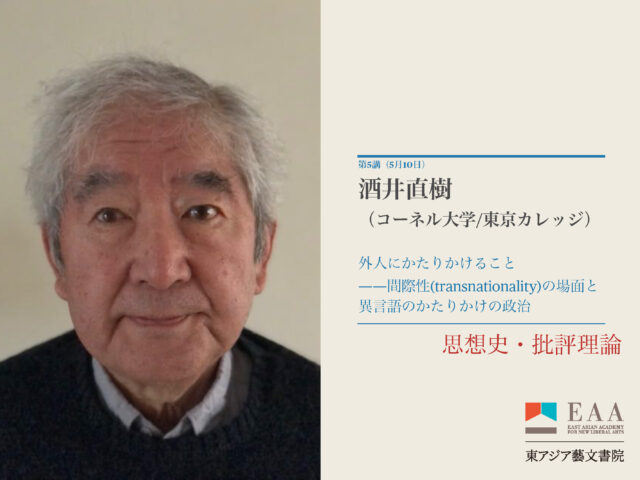
2024年5月10日(金)、EAA主催の学術フロンティア講義「30年後の世界へ——ポスト2050を希望に変える」第5回が駒場キャンパス18号館ホールで開催され、酒井直樹氏(コーネル大学/東京カレッジ)が 「外人にかたりかけること——間際性(transnationality)の場面と異言語のかたりかけの政治」というテーマで講義を行った。
講義の冒頭で酒井氏は、ポスト2050を希望に変えるための手がかりとして、「国際性(internationality)」と対比させて、「間際性(transnationality)」という考え方を提示した。現代社会において重視されるのは国際性であり、国際性のもとでは「自国民」と「外国人」を区別するのが当たり前とされる。これに対して、間際性は「自国民」も「外国人」も共に「外人」と捉えようとする態度である。

では、近代の国際社会において、なぜ「自国民」と「外国人」の区別がこれほど重視されるのだろうか。酒井氏はベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』に因りながら、国民国家の形成の仕組みに言及した。国民国家の成立には、「国民」が必要である。この国民共同体とは、もともとは「異人」あるいは「外人」である人々が、共同体への情緒的帰属を共有することによって作られる、つまり赤の他人との共感に基づいて作られる想像的な共同体である。この共感を生み出すのに最も有効な装置が、「外国人」と「同胞(自国民)」の区別である。
国際性という志向の出現は、17世紀のヨーロッパに遡る。ヨーロッパ公法が制定され、主権国家が領土を確定すると、ヨーロッパに初めて「国際世界」が出来上がった。当初ヨーロッパの中に限定されていた「国際世界」は、19世紀には東アジアなどの非ヨーロッパ世界に拡大してゆく。国際化しなければ植民地化されるという状況で、日本も含めた多くの国々が近代化(=国際化)し、国民国家を形成して、国際世界に参入していった。
本講義では時間の関係で、酒井氏の考える「間際性」の具体的なあり方まで伺うことができなかった。しかし、「国際性」の構造と形成過程を概観したことによって、現在の国際社会で当然視されている「国際性」の価値を、相対化して考え直すことができたのではないだろうか。

報告・写真:新本果(EAA リサーチ・アシスタント)
リアクション・ペーパーからの抜粋
(1)近代化というものがいかに私たちのアイデンティティや世界のあり方を規定しているのか改めて気付かされた。現代において激化する移民をめぐる問題にどのように対応するべきか。まずは「外国人」という概念を相対化する必要があると感じた。外国人とは、本来国内外に(国境という概念がない時代だが)存在する「外人」が、国境という想像物で同胞と区別されたものである。そのような想像の産物によって、国籍によって人を攻撃してしまうところに国民国家の恐ろしさを感じた。教養学部後期課程・3年(2)先生の意見の中の一つに、自分の所属しているのと同じ国の中にも外人を見出し(というより或る種の原点回帰を行う)ていくという物があったと思います。これは、人間を区別するメッシュを可能な限り小さくしていくということだったと思いますが、逆方向の発想として、メッシュを可能な限り大きくしてしまうというものがあると思います。もちろん、これは人間の差異を見ないふりすることに繋がっているので危険性を孕んでいますが、しかし、このようなアイディアが可能かどうか、つまり、境界を(先ずは)人類全体にすることによって排除をなくすという方針は可能なのか気になっています。教養学部後期課程・3年








