2024年4月30日(火)、東京大学駒場キャンパス18号館コラボレーション・ルーム3で、伊達聖伸氏(東京大学教授)の著作『もうひとつのライシテ――ケベックにおける間文化主義インターカルチュラリズムと宗教的なものの行方』(岩波書店、2024年)の合評会が開催された。渡辺優氏(東京大学准教授)の司会のもと、評者の増田一夫氏(東京大学名誉教授)と飯笹佐代子氏(青山学院大学教授)がプレゼンテーションを行い、著者の伊達氏が応答するという内容である。
渡辺氏による登壇者の紹介のあと、まずは伊達氏が本書の来歴について語った。伊達氏は2007年、19世紀フランスの宗教史にライシテを位置付ける博士論文をリール第三大学に提出した。その頃のフランスではライシテが社会的争点になっていたが、現実政治はイスラームを規制するための道具としてライシテを解釈する方向に傾いており、そうしたアクチュアリティに伊達氏の食指はあまり動かなかったという(とはいえ実際には、伊達氏はフランスのライシテに関するアクチュアルな論考を多数発表してきた)。そうしたとき、大西洋の向こう側のケベックでは、「ブシャール=テイラー委員会」をはじめ、ライシテをフランスとは異なる仕方で理解する動向があることを知り、ケベックのライシテに関心を抱いたという。伊達氏はその後、ケベックにおける間文化主義的とライシテの形成に関する研究を重ねたが、2010年代後半になると右派ポピュリスト政党ケベック未来連合が政権を取り、ライシテの名のもとにイスラームのヴェールを規制する法律が成立した。本書の用語を使えば、フランス流の「共和主義的ライシテ」が支配的になる一方、伊達氏が期待を寄せてきた「間文化主義的ライシテ」は「伏流化」したのである。
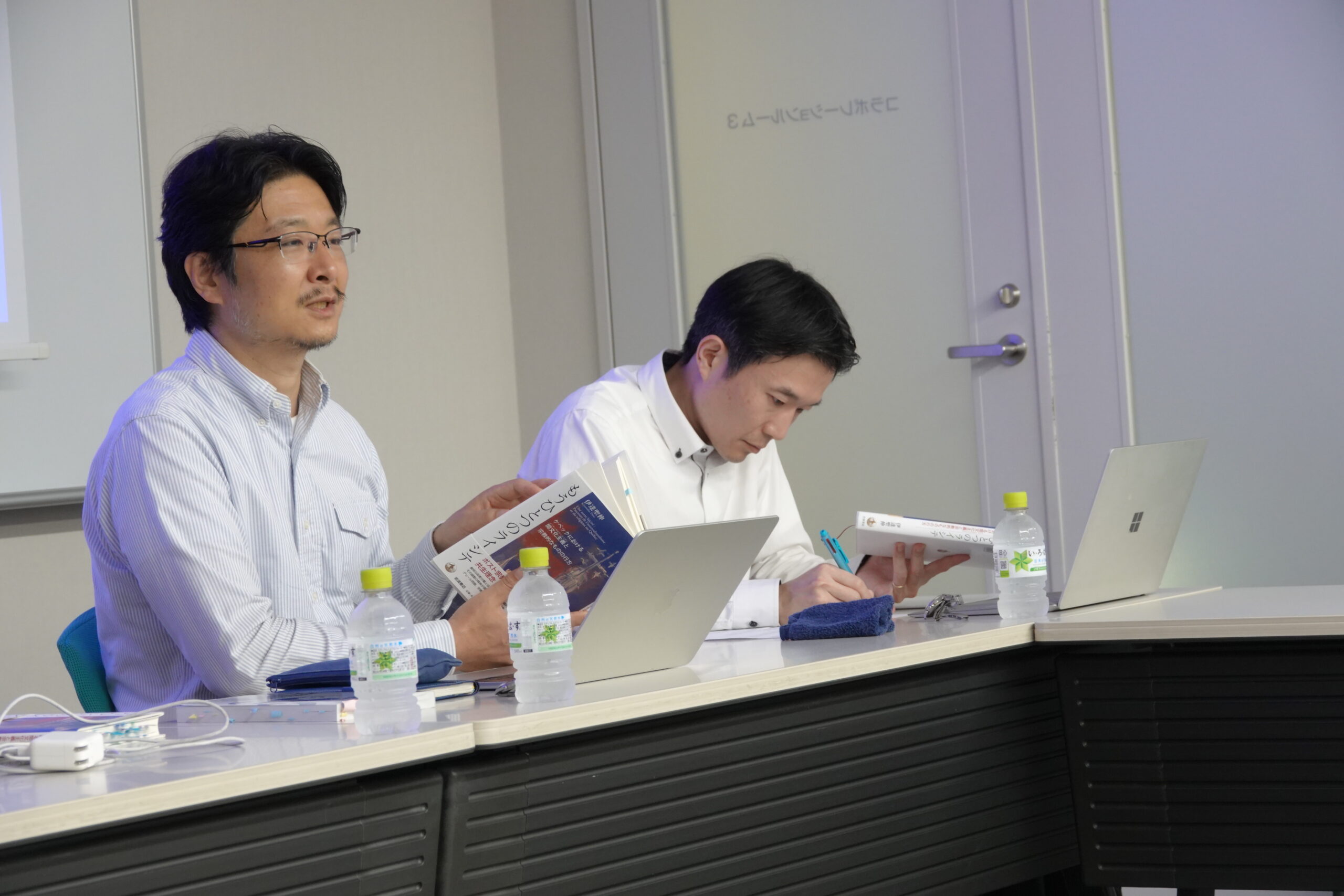
最初の評者を務めたのは増田氏である。伊達氏の最初の著作は上述の博士論文を元にした『ライシテ、道徳、宗教学――もうひとつの19世紀フランス宗教史』(勁草書房、2010年)だが、増田氏は本書が伊達氏による「もうひとつの」シリーズの続編であることに注意を促したうえで、本書がケベック現代史に関する「もうひとつの」見方を野心的に提示している点を高く評価した。すなわち、ケベック現代史の転換点とされる1960年代の「静かな革命」を「宗教」から「世俗」へという単線的な世俗化ではなく、「宗教」と「世俗」の再構成の過程として、哲学者の増田氏の言葉を使えば、「脱構築」的に捉え直している点である。「宗教からの脱出」(M・ゴーシェ)、「世俗化」と「ライシテ化」(J・ボベロとM・ミロ)に関する宗教社会学の理論を巧みに応用することで、本書はこうした新しい視座からケベックのライシテの歴史を描き直すことに成功している。増田氏はさらに、本書には二重の前提が通底していることも指摘した。ひとつは、制度的な「宗教」とは異なる「宗教的なもの」が現代にも存続しているとする見方である。「静かな革命」の後、フランス語がカトリシズムに代わって、ケベック社会の「代替宗教」となったとする本書の議論は、こうした前提に基づいている。もうひとつは、共生の原理としてのライシテを擁護する姿勢である。現代ケベックではライシテに関する複数の解釈が並列しているが、共生の原理としての側面に注目する伊達氏の解釈は、なかでもM・ミロのものに近いようにみえるという。
 (左から:増田氏、飯笹氏、伊達氏、渡辺氏)
(左から:増田氏、飯笹氏、伊達氏、渡辺氏)
増田氏の評に対して、伊達氏は規範性と記述性の間でのバランスの取り方の難しさに言及した。伊達氏が専門領域とする宗教学は、神学と異なる非規範的な学問という自己認識から出発したが、現代では研究者自身の持つ規範性を再帰的に認識する必要性が指摘されている。そうしたなか、多様性の承認と社会統合の実現という現代社会が直面する二重の要請を引き受けることも、伊達氏は重要であるという。
次に評者を務めたのは飯笹氏である。飯笹氏は、2000年代後半から2010年代後半にかけてのケベックの政治情勢に回顧的に言及しながら、本書が1960年代の「静かな革命」を契機とするケベック社会の争点とアイデンティティ・マーカーの変遷を見事に描き出していると高く評価した。そのうえで、英語圏の多文化主義に関する研究を重ねてきた飯笹氏は、間文化主義と多文化主義の関係性について注意を促した。本書でも紹介されているように、ケベックの間文化主義はカナダの多文化主義とフランスの共和主義の中庸を得たものとされる。だが、そうした語りでは、多文化主義はしばしば、個別文化の独立性を重視するあまり、社会統合を等閑視するものとして戯画化されている。しかし、飯笹氏によれば、英語圏の多文化主義は実際のところ、当初から社会統合を重視してきただけでなく、試行錯誤を繰り返すなかで、間文化主義の特徴とされていた文化間の対話の重要性も、最近では強調されている。間文化主義を多文化主義から区別しようとする語りとは裏腹に、現実には多文化主義と間文化主義は近いものになってきているという。とはいえ、こうした英米圏の多文化主義は、市場価値のある文化資源として宗教的な文化を積極的に利用する側面もあり、これは「ネオリベラル多文化主義」と呼びうる両義的な状況をもたらしていることにも飯笹氏は注意を促した。飯笹氏はそのうえで、伊達氏が「間文化主義的ライシテ」の「伏流化」を指摘しながらも、それが息を吹き返す可能性は高いと記した背景には、どのような考えがあったのかなどを尋ねた。

飯笹氏の評に対して、伊達氏は「もうひとつの」という言葉に込めた意味に立ち戻って応答した。伊達氏によると、この言葉はオルタナティヴや非主流派という意味だが、現在の趨勢だけにすべてが還元できるわけではないという思いも込めている。本書で示されているように、共生を可能にする「調整」の原理はケベックの歴史に深く根差したものであり、いまは「伏流化」しているとしても、簡単にはなくならないだろうと考えているという。

その後、議論はフロア全体に開かれて活発な質疑応答がなされた。今回の合評会では全体として、ケベックが近年経験しているライシテの硬直化と、そうした現実のなかでも伊達氏が「伏流」として注目し続けている「間文化主義的ライシテ」の行方が論点となった。社会の分断を養分として権威主義が幅を利かせ、ライシテが多文化共生のための原理から遠ざかるのは、ケベックにかぎらず観察しうる世界的趨勢である。この暗い世界で明るい展望を持つのは難しいかもしれない。しかし、伊達氏が合評会のなかで、本書の表紙に描かれたケベックは、闇が深まる夕暮れ時の姿ともとれるが、来るべき光を待つ夜明け前の姿ともとれると述べたことは印象深い。現代のケベックが直面するライシテの困難だけでなく、そうした現実を突破しうる可能性も感じることのできる合評会だった。
報告:田中浩喜(日本学術振興会)
写真:白尾安紗美(EAAリサーチ・アシスタント)








