8月4日に、にシリーズ講演・討論「東洋美学の生成と進行」第6回がオンライン開催された。塚本麿充氏(東京大学東洋文化研究所・教授)より、「東洋美学と美術史の対話―大正期の模索―」という題の講演をいただき、飛田優樹氏(黒川古文化研究所・研究員)よりコメントをいただいた。司会は本ブログの執筆者である丁乙(EAA特任研究員)が務めた。
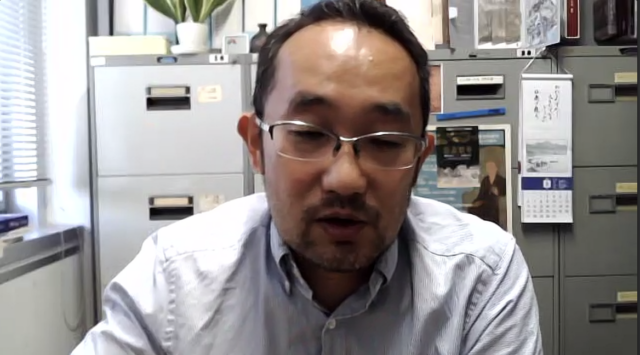 (講演者:塚本麿充先生)
(講演者:塚本麿充先生)
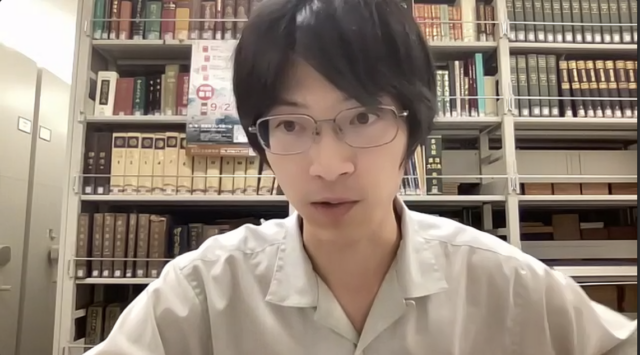 (コメンテーター:飛田優樹先生)
(コメンテーター:飛田優樹先生)
塚本氏の焦点は、「美術史」というディシプリンの東洋における近代的な設立過程であった。基礎的な背景として、美術史家という近代的な職業と対照的に、美術を担う者として「古筆家」ら鑑定家や画家などが前近代に存在したことが指摘された。およそ1914年頃から1930年にかけて、美術の主要な担い手は次第に大学の職業「美術史家」たちへと推移していったという。塚本氏は1914年に東京帝国大学の美学第二講座として美術史が置かれ、1930 年代以降はそれらの卒業生が「美術」業界の主流(博物館と文化財保護委員会等)の職域を独占していったことを考察した。
とりわけ重要なのが、瀧精一(1873-1945)という、日本における美術史学講座の実質的な開祖といえる人物であった。彼の美術史思想を特徴付けるのは、大量の部分図版を使った様式論の研究手法である。様式論の展開はハインリヒ・ヴェルフリンに代表される西洋思想の受容に始まり、1910年代に日本でも盛んに受容されたという。瀧のこのような様式論の方法は弟子を通して、京都帝大(1919)と東北帝大(1924)における美術史の講座の設立により広がっていく。
一方、金原省吾(1888-1958) のような、様式論ではなく、美術批評に中心を置いた記述を重視する美術史家も存在した。彼は1929年に帝国美術学校(現・武蔵野美術大学)を創設して教授となり、中国にいた傅抱石(1904-1965)は(東京帝大ではなく、)彼の方法論に惹きつけられその下に留学した。ここには、様式論と異なる、いわゆる美学に接近しうる美術史学の側面が示されている。
講演に対して、飛田氏はまず様式論の具体的なあり方を作品例を通して説明し、作品の記述において生じるモノと言葉の距離の問題や、その反省を美術史のなかに吸収していく動き、そして学問が制度的に細分化することの問題点を取り上げた。とりわけ書道の分野は西洋的パラダイムが不在であるゆえ、独特な展開を示せるものとして論じられた。また文人の文房の空間を含む一つの複合的な世界が提起された。
総合討論では、美術史に関する西洋からの受容や、方法論としての様式論と歴史学の手法との関係、現在の日本や中国大陸の状況の相違と類似について議論できた。今日のアカデミックでは、異なる傾向を持つ各分野・各地域間の対話可能性が重要であることが提起された。
報告者:丁乙(EAA特任研究員)








