鶴見俊輔については、この授業で昨年度までに『戦時期日本の精神史1931〜1945年』と『北米体験再考』を扱っているが、今回さらに『アメノウズメ伝』を取りあげることにした。本書は鶴見自身が「私は著作の中でこれがいちばん好きなんだ」、「ほかのはなくていい、これ一冊」と語ったこともある本である(『期待と回想』)。
アナキズムの系譜に連なる鶴見のなかに、「国家」対「性」という問題設定がなかったはずがない。だが、その問題は鶴見の著作であまり主題化されてこなかったのではないか。そう問いかける上野千鶴子に対して鶴見は、「ある時期までは、書き方が成熟していなかったから、書けなかったんですよ。だけど九一年に出した『アメノウズメ伝』は、その問題をまっすぐ出している」と答えている。それを聞いて上野は、「私は、タイトルにめくらましをくらわされて、『アメノウズメ伝』は『古事記』の話かと思っていましたから、読んでいません。読まなくちゃ」と応じている(鶴見俊輔・上野千鶴子・小熊英二『戦争が遺したもの』)。
「あとは、柳田國男の影響だね」と鶴見は柳田の名前を挙げている。『アメノウズメ伝』の冒頭は、たしかに『古事記』への言及からはじまるが、「日本の神話のなかには、小さい人が、何人もいる。そういう小さい人とじかにはなす道がひらけても、いいはずだ」というくだりがすぐに出てくる。このような箇所は、前回読んだ柄谷行人編の柳田国男『「小さきもの」の思想』とも響き合う。柳田と鶴見の共通点は、膨張し大国化しようとする男性的な日本に対し、日本における批判的な小国論の伝統を持ち出して抵抗の拠点にしようとするところにあると言えるだろう。その際、女性や女性的なものの力を評価する。
たとえば、柳田國男の『妹の力』には次のようなくだりがある。「過去の精神文化のあらゆる部面にわたって、日本の女性は実によく働いている。あるいは無意識にであったかも知れぬが、時あって指導をさえしている。これが一朝専業化の傾向を示してきたために、その特色は家庭の外に追いやられて、次第に軽しめられる者の列に入ってしまい、一度も試みられたことのない可能性が、今はまだ多くの柔らかなる胸のうちに睡(ねむ)っているかと思われる。この隠れたる昔を尋ね出し、それを新しい社会の力とするためには、ただ忍耐して多くの書籍を読んだり、暗記したりしていただけでは足りない。暗示はむしろ日常の人生の中にあるということを、実は私などもほんの偶然に心づいたのである。この経験だけは人に頒(わか)たずにはおられない」。
文彩は異なるが、『アメノウズメ伝』は鶴見俊輔が書いた『妹の力』と言ってみてもよいのではないか。鶴見は戦後の代表的知識人として政治的には左派的な位置を占めるが、彼のスケールは大きく、葦津珍彦のような右派的な論客とも信頼関係で結ばれていたことで知られる。「隠れたる昔を尋ね出し、それを新しい社会の力とする」のであれば、たしかに一国の伝統を軽んじるわけにはいかない。しかし、それは伝統の名において権威を誇示する行き方に賛同することではもちろんない。もうひとつの伝統を掴み出すことは、「一度も試みられたことのない可能性」を探ることに似ている。それには、忍耐強い学習に加えて、日常の人生の中にある暗示に、偶然に心づくことのできるような、柔軟で開かれた態度が求められるだろう。
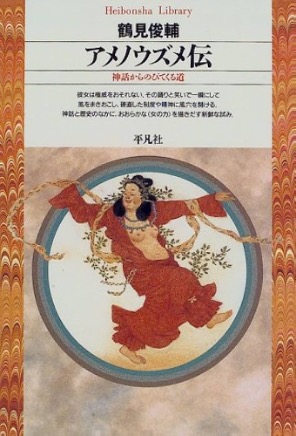
「国家のもとじめのうしろに立って、政府の方針にハクをつける役割をしてきた」のがアマテラスなら、アメノウズメは「どんなに小さな家、どんなにささやかな友人のあつまりにも、とまり木のようにかるくとまって、世界を再定義してみせる神」である。そのようなアメノウズメの役割は女性に限定されるわけではない。鶴見は「私にとってもっとも暗い日に、そこだけあかるい場所があるような人」として、乙骨淑子の父親・村谷壮平の肖像を描いている。裸一貫で、日米交流を「国際」ならぬ「民際」レベルで行なったラナルド・マクドナルドや中浜万次郎のような人物も、アメノウズメの系譜に連なる。
鶴見によれば、アメノウズメには、(1)美人ではないが、魅力がある。(2)世間体にとらわれず、自由である。(3)その気分に人びとを誘い込み、周りを楽しくする。(4)生命力に溢れており、それが周りの人たちの活気を誘い出す。(5)笑わせて、安心させる。(6)猥褻を恐れず、性の抑制を超える。(7)外部の人が入ってきても特別な警戒はしない、といった特徴がある。本書で論じられる戦後の日本の女性は、作家の瀬戸内寂聴、田辺聖子、「踊る宗教」で知られる天照皇大神宮教の教祖・北村サヨ、ストリッパーの一条さゆりなどである。
鶴見は、上野千鶴子と小熊英二との鼎談で、『アメノウズメ伝』は「一条さゆりというストリッパーの、私なりの伝記なんです」と語っている。「私は一条さゆりに会ったことはないんだけど、彼女についての情報を、偶然に私は彼女の弁護士の小野誠之から聞いたんだ。どういう生立ちであるとかね。彼女はけっこう経歴をつくってしまう人だと言われているんだけど、小野さんから聞いたところによれば、彼女の実母が、彼女の実父を殺してしまったんだ。そして母親は捕まって死刑になって、彼女は施設に入った。施設で成長して劇団に入ったら、その劇団の男たちに輪姦されて、そこからストリッパーになっていく。だから、私のテーマは、how could she live otherwise? だったんだ」。
一条さゆりは、1972年の興行で隠部を見せたとして公然猥褻罪に問われた。鶴見は、法廷に弁護側証人として立った東京大学講師で中国文学者の駒田信二の言葉を引いている。「彼女がひじょうに逆境に生まれたなかで、そして、ひじょうにたいへんな屈辱とか悲惨な目にあいながら、非常に正直に一生懸命に、まともに一生懸命に生きてきた、その真剣な生き方に感動したわけです。なぜ感動したかといいますと、私など一応社会的地位を築いておりますけれども、これまで生きてきた間に自分自身をふり返ってみて、自分自身をもそれから世の中をもしばしばごまかして生きてきたわけです。ところが、彼女の場合においてはひじょうに正直な性格で、世の中をごまかして生きていない」。
一条さゆりの正直な生き方には、駒田に自分の身を振り返させるだけのものがある。鶴見はそのことに感じ入って、彼の発言を引いたのだと思われる。一条には実刑判決が下ったが、鶴見は「そういう法の当否をこえて、ここには、まぎれようもなく、一個の心のひろい人がいる」と述べている。
一条さゆりの「伝記」という割には、『アメノウズメ伝』で彼女について述べられている実際の紙幅は少ない。服役後の後半生・晩年も描かれていない。小倉孝保『踊る菩薩――ストリッパー・一条さゆりとその時代』によれば、彼女が出所後に開いた店は繁盛したが、自分も飲んで気分が大きくなると客から金を取らないため、儲けが出なかったという。居酒屋の開店資金を出した倹約家の夫は、のちに自死している。経営者は向いていないと悟り、釜ヶ崎で雇われ身分で働くようになった彼女は、一緒に暮らしはじめた男が店に撒いたガソリンに放たれた火で、重体の火傷を負った。集中治療室で「ウ、ラ、ギ、ラ、レ、タ」と口にした彼女だが、男が4年の刑期を終えて出所してくると、屋台で一緒に酒を飲むなど、自分を傷つけた男さえも包み込んでいる。
鶴見の『アメノウズメ伝』が出た1991年、一条は出家しようと大阪府泉大津市の南溟寺を訪れている。住職の戸次公正はユニークな僧で、ジャズやビートルズを好んで聴き、現実社会でさまざまな課題に取り組んでいる人びととの交流を重視していた。1980年代には大阪湾泉州沖の関西新空港建設計画に地元住民として反対の声を上げ、警察の捜索を受けている。寺に警察が踏み込むケースは、信教の自由が保障されている戦後日本では極めて珍しい。戸次は、酒がやめられずに困っていると出家を仄めかす一条に、住職の自分が酒を飲むから断酒には向かないと彼女の希望をやんわりと斥ける一方で、人生経験をもとに講演をしてほしいと依頼した。「寺でストリッパーの話を聴かせるとは」との抗議の電話には、「職業で人を分け隔てすることこそ、仏様は悲しまれるのではありませんか」と応じた。1997年に亡くなった一条の葬儀を挙げ、戒名をつけたのも戸次である。戒名は、「さゆり」とも読める「釋優利(しゃくゆうり)」だった。「釋」は釈迦の弟子、「優」は優しさ、「利」は人を喜ばせることで、小倉は「優しさとサービス精神が彼女の真骨頂だった」と述べている(『踊る菩薩』)。
弱くて小さいはずの者がかえって人間のスケールが大きくて強く、大きくて強いはずの者がむしろ卑小であること。俗世に塗れた生きざまが、そのまま聖性を帯びる場合もあること。このような逆説は、宗教の論理にしばしば見られるが、いわゆる宗教とは異なる場所にも見出すことができる。
以上、報告者:伊達聖伸(総合文化研究科教授)

*
【受講者からの感想】
女性の「踊り」を当事者でない者が語るのは困難である。ここでの「踊り」は、性産業と密接な関わりを持つものとしての「踊り」を指す。例えば、森口岳は「女たちは踊ることができるか」(2018)において、「念頭に置いているのは、開発研究などにおいて繰り返し再生産され(かつ消費され)ている貧困女性たちの開発主体の物語についてである」と断りつつ、アフリカのバーガールたちの「踊り」に、性的シチズンシップを獲得する主体性が存在することを述べた。森口は、開発研究において貧困女性が客体化されてきたことに対する批判という文脈の中で、「踊り」を語ることを強調している。これは、抑圧の構造の中で自由な選択が許されない女性の行為に主体性を見出すことは、抑圧の構造を軽視していると批判されかねないからであろう。また、泉沙織は「戦後日本における『ストリップショー黄金時代』のバーレスク志向」(2022)において、ストリップに出演する踊り子が、これまでほとんどの研究の中で客体化されて語られてきたことを指摘した。しかし、踊り子は観客から見られるだけでなく、観客を自ら魅了する存在であるところが特徴だとして、踊り子の主体性が窺える文献調査の必要性を述べた。このように、女性の踊りは女性を抑圧する社会構造の産物でもあるために、その主体性はほとんど語られず、一般には語るのを憚られるものである。
一方鶴見は、ストリッパーである一条さゆりにアメノウズメ的態度を発見することで、「踊り」を語っている。これは、一条さゆりの主体性を語る試みである。しかし一条さゆりに会ったことすらない鶴見に、その主体性を語ることはできたのだろうか。鶴見はアメノウズメの踊りを、権威を崩し、異人との壁を壊す手段として、それ自体を支離滅裂な主張として捉えた。それは根源的な存在に立ち返る運動であり、国境、時代すら超えた普遍性があるという。舞台から降りた後も、ファンの男性たちに酒を振る舞い、「だるまさんのように生きたい」と言う一条さゆりには、「自分を人とわかちたいという気組み」があると、鶴見は指摘している。鶴見は一条さゆりの在り方に、アメノウズメ的な主体性を見てとったのだ。「踊り」にある主体性を、外部の者が語ろうとすれば、そこにある抑圧的な社会構造を暴力的に無視することになりかねない。しかしそれは、そこから主体性のみを取り出そうとするからではないか。主体の置かれた環境が無視されているのである。弱い者に見るべき主体性は、自由な選択のもとで、自覚的な意志を発揮する主体性ではない。強い者に脅かされかねない弱い者が、それでも自己の意志を保とうとする主体性である。女性の「踊り」を語るためには、主体性がその構造の中で持つ意味まで語らなくてはならない。鶴見は、アメノウズメにたとえられる、弱い者の主体性の思想を持っている。その主体性は、権威あるものや異人の前に立たされた弱い者が発揮する、権威を崩す働きである。鶴見は、弱い者が持つ主体性をアメノウズメ的態度としてその働きまで丁寧に語ってきたために、一条さゆりの踊りを、抑圧構造を内包しつつ語ることができたのではないか。
授業においては、アメノウズメの踊りはケアの倫理の体現であり、鶴見のやろうとしていることはケアの倫理の再評価であるとの意見が出た。また、アメノウズメとは「働きそのもの」である、権力に抗すると同時に、権力をケアする働きである、という見解も述べられた。ケアの倫理そのものが、既存の倫理、絶対的で論理的な倫理に抗するものである一方で、その働きは、分断ではなく、融和を目指すものである。つまり、アメノウズメの踊りは、ケアの倫理の行使そのものであると言える。
これを踏まえ、もう一度一条さゆりの踊りがいかに語られたかを考える。鶴見が一条さゆりの踊りを語ることができたのは、権威に相対する弱い者を前提とした主体性の思想を持っていたためである。しかしまた、鶴見の行ったことがケアの倫理を行使することの再評価であることも重要である。鶴見はこの働きの効果を讃えているのではない。これが権威を崩し、かつ寄り添うものでもある以上、その効果は両義的である。ただ、融和を目指す主体性に価値を置いたために、たとえ融和が権威を保存することになろうとも、鶴見はその主体性を評価できたのだ。一条さゆりの踊りは、理不尽な自身の境遇に対峙させられた彼女が、融和を目指した働きである。鶴見は彼女の境遇に対する評価を押し付けることなく、彼女のあり方そのものを評価したのだ。鶴見は、一条さゆりの踊りを外部からしか語ることができない。しかし、アメノウズメを評価することを通じて、彼女の働きを構造そのものの中で捉えた。それゆえ、鶴見は一条さゆりの踊りを語ることができたのだ。
(以上、Y・M)
*
鶴見俊輔の『アメノウズメ伝』では話題が多岐に渡り、様々な視点からアメノウズメ的な役割についての考察が繰り広げられていく。本書の中で、私はアメノウズメの物語を書く作家として田辺聖子の名が挙げられていたことに注目した。
古典のリメイクを数多く発表している田辺の著作には『春のめざめは紫の巻』という作品がある。源氏物語に登場する姫君やそのゆかりの女人の視点から光源氏を描き直す連作短編集であり、光源氏は一貫して時代遅れで自意識過剰な勘違い男として描かれる。この作品に登場する女性達は皆光源氏に靡かず、時に痛烈な言葉も浴びせるが、話のタッチは常に笑いに満ちている。これは光源氏のネガとして登場する、お調子者で口の達者な伴男というキャラクターが他の女人たちを巻き込みながら光源氏をいじり、からかい、ツッコミを入れていくからである。一人コテコテの京都弁を話し、女性に自身の理想を押し付ける光源氏像はそれだけでは苛立ちの対象にもなるが、そんな彼が伴男に茶化され、ものの見事に女性に袖にされる姿には一種の朗らかさすら感じる。源氏物語では社会的にも男女の関係においても不動の勝利者である光源氏を笑いの対象とすることは、権力におもねらない非攻撃的・非暴力的な道を示すと同時に、光源氏をもアメノウズメ的な賑やかで笑いに満ちた世界に引き込むことを可能にしている。
このように、笑いには風刺のように攻撃性のあるものだけではなく、その対象を拒絶することなく共同体の中に取り込むような働きを持つものもあると考えられる。この意味で、笑いには権力を揺るがすだけではなく権力の暴力性を和らげながら支えるような側面もあると言うことができるだろう。このことは、アメノウズメの踊りがアマテラスという傷つき、引きこもってしまった権力を癒し、再び神々の輪の中心に引き戻す役割を果たしていたことからも窺える。
権力と笑いの関係について、シェイクスピアの『ヘンリー4世』に登場する老騎士フォルスタッフの例を挙げてみたい。フォルスタッフは大酒飲みで好色、大口を叩くが実は臆病者というどうしようもないキャラクターではあるが、どこか憎めない魅力を持ち合わせている(実際に、女性には人気の様子だ)。フォルスタッフは次期国王であるはずのハル王子に馴れ馴れしく接し、共に悪い遊びを繰り返す。しかし、ハル王子は父王の死後にヘンリー5世として戴冠すると一転し、それまで交友を持っていたフォルスタッフを切り捨てる。その後、ヘンリー5世がフランスとの戦争へ乗り出し、冷酷で孤独な王としての道をひた走っていく様を鑑みると、フォルスタッフの存在は権力に人間性と親しみやすさを与え、民衆との間を取り持つような役割を持っていたのだと言うことができる。
鶴見は一般に左派知識人として捉えられている。一方で、『アメノウズメ伝』の中で彼はスターリンへの絶対的な追従の姿勢に警戒心を抱いており、革命が別の権力とそれへの従属を生み出す可能性を危惧していることが分かる。鶴見は既存の体制と革命の対立関係において絶対的に革命を支持するというよりは、二者の軋轢を解消しようとする立場にあるのかもしれない。そして反感を買わない形で権力の暴走を防ぎ、軋轢を解消するための手段として笑いが採用されていると考えることができる。
『アメノウズメ伝』の発表から30年経った現代において、批判対象をそのまま取り込むようなおおらかさを持つ笑いは果たして存在しているのだろうか。笑いを馬鹿馬鹿しいものとして一蹴してしまうことは簡単だが、効率が重視され、個人の思想同士がぶつかりあう時代の中で、共同体にしなやかさと寛容さをもたらす笑いの重要性を再考することにも意味はあるのではないだろうか。
(以上、M・Y)








