今年没後100年を迎える有島武郎は、宗教とジェンダー、小国論やアナキズム、またヨーロッパのテーマにもつながる人物で、今期の授業でぜひ取りあげようと前々から考えていた。
一冊に絞るとすれば、やはり足かけ9年をかけて書かれた代表作『或る女』だろう。男性作家が女性を主人公として書いたこの物語をどう読むか。「このテクストを読む行為は、決して読者をしてジェンダー的環境と無縁なままには置きません」と中村三春は述べている(中山和子・江種満子編『総力討論 ジェンダーで読む『或る女』』)。たしかに、このテクストについて論じることは、そうする者の立場をはしなくも露呈させてしまうように思え、そう考えると怖気づいてもしまうのだが、授業でさまざまな読みが試みられるのはテクストを甦らせることでもある。私としては、ひとまず前回読んだ内村鑑三との関係を意識して、自分の問題関心に引きつけた語り方を演じてみるしかあるまい――他のさまざまな読み方の在処を示唆するためにも。
内村鑑三の柏会に集った一高生たちは、校長である新渡戸稲造の薫陶を受けていた。彼らにとっては、内村が「父」に、新渡戸が「母」に比されたようだ。有島武郎にとっても、似たようなことが言えるだろう。内村と新渡戸の2人に遅れること約20年、同じ札幌農学校に学んだ有島は、新渡戸のもとに寄寓し感化を受け、級友森本厚吉の影響もあってキリスト教徒になることを決意した。内村本人とは1897年夏に初めて会い、1901年に札幌独立基督教会に入会したが1910年に退会している。
有島は、キリスト教を離れることになった理由として、1903年から留学したアメリカで迎えた日露戦争においてキリスト教国民の裏面を見せられたこと、キリスト教の罪という観念と贖罪論が自分の考えと相容れないと理解したことなどを挙げている。有島は米国滞在中、フレンド派の精神病院で看護師として勤務したが、それは内村が同じく訪米中に知的障碍児の養護院ではたらいたのに倣ったものだった。内村はその養護院で障碍児たちの心霊の開発が聖なる仕事であることを理解したが、有島の場合は患者であったスコット博士が自殺してしまった。
1923年6月に有島が軽井沢で波多野秋子と心中し7月に遺体が発見されてのち、内村は『万朝報』に「背教者としての有島武郎氏」を寄せた。内村は、一時は有島が自分の後継者になると思ったこともあったと言い、またアメリカ留学中の有島は信仰に燃えていたが、イギリスを回って帰国する際、ロシアから亡命中のクロポトキンに会い、そのアナキズムに感化されてキリスト教を棄てたという話を人伝えに聞いて、案外それが事実かもしれないと述べている。「神を馬鹿にすれば神に馬鹿にせらる。〔……〕私は有島君の旧い友人の一人として、彼の最後の行為を怒らざるを得ない」。最初の妻タケの異性関係を怪しんで「羊の皮を着た狼」と評した内村にしてみれば、「夫ある婦人」と「常倫破壊の罪」を犯した有島を許せなかったのかもしれない。
有島は1903年、渡米の前に内村からポール・サバティエ『フランチェスコの生涯』を借り出して読んでいる。サバティエはフランチェスコの宗教を、「神の方を仰ぐ宗教」ではなく「人の方を見る宗教」として描いている。これに有島は「所有財産に罪意識を持つ程の共感を示した」という。離教後もフランチェスコには敬意を持ち続け、クロポトキンに「フランチェスコを継承し実践する姿を見出していた」とされる(『有島武郎事典』)。
内村は、『或る女』に出てくる内田のモデルになっている。葉子が渡米の前日に訪れるが、会ってもらえない。また、物語の最後で葉子は、娘の定子を託す相手として内田がよいと思い、有島自身がモデルとされる古藤に呼びに行ってもらう。なかなかやって来ない内田を待ちながら、葉子が息を引き取ろうとするというのが最後の場面である。
表面的に一通り読むかぎり、物語のなかで内田が占める位置は、木部、木村、倉地に比べるとかなり周辺的である。だが、有島が古藤にも葉子にも自分を託しているとすると、葉子の謎は内田との関係において解明される部分も小さくないと思われる。
書き手としての有島は、男性的なのか、女性的なのか。男性的なところも多々あるが、内村に比べれば、よほど女性的であることは、一般論としても言えそうである。注目されるのは、「同性愛の要素が混入」していたという森本厚吉との関係を通して有島には〈脱男性化〉が進んでいたとの見方である(尾西康充『『或る女』とアメリカ体験――有島武郎の理想と叛逆』)。
足かけ9年にわたった『或る女』の執筆が、札幌独立基督教会を退会してからの時期に重なることも重要である。葉子のモデル佐々木信子が、木村のモデルで有島の友人でもあるクリスチャン森廣と結婚するために渡米し、結婚せずにそのまま日本に戻ってきたという1901年から翌年にかけて実際に起きた出来事を下敷きにしたこのフィクションは、明治の家父長制と闘い敗れた一人の女性の物語であるだけでなく、キリスト教が正しい顔をしているとき、あるいは欺瞞的であるとき、自分に信じられるものは何かを探す物語でもある――悪いのは、間違っているのは社会のほうだと思うが、あるいは自分のほうなのかもしれないという揺れ動く疑念とともに。
*
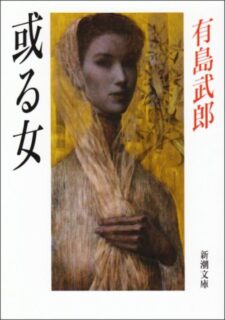
「葉子は他人を笑いながら、そして自分をさげすみながら、真暗な大きな力に引きずられて、不思議な道に自覚なく迷い入って、仕舞には驀(まっしぐ)らに走り出した。誰れも葉子の行く道のしるべをする人もなく、他の正しい道を教えてくれる人もなかった。偶ま大きな声で呼び留める人があるかと思えば、裏表の見えすいたぺてんにかけて、昔のままの女であらせようとするものばかりだった。葉子はその頃から何所か外国に生れていればよかったと思うようになった。あの自由らしく見える女の生活、男と立並んで自分を立てて行く事の出来る女の生活……古い良心が自分の心をさいなむたびに、葉子は外国人の良心というものを見たく思った」。
早月葉子が「新しい女」ならば、キリスト教婦人同盟の副会長として社会的に活躍する彼女の母・親佐も「男まさり」であった。父の影が薄く、「強い女」のもとで育った葉子は、母親と衝突を繰り返しながら、自分は母親に一番理解されているとの思いも抱いた。有島は男性作家でありながら、このような母―娘の愛憎関係の機微にも触れている。葉子は木部とのあいだに娘・定子をもうけており、ここにも母―娘関係がある。いや、定子がほとんど登場しないこの物語で葉子はむしろ二人の妹の愛子と貞世に対して家長のように振る舞っていると言うべきかもしれない。
ともあれ、葉子が木部と結婚したのは、親の反対を押し切ってであった。だが、結婚後に女々しく我儘に変貌した木部に葉子は耐えられなくなり、彼のもとを去る。木部孤笻のモデル国木田独歩は、妻の信子に去られて失意のうちにあった頃、同じく妻に去られた経験のある内村鑑三から旧約聖書のホセア書を読むように勧められている。
早月家に出入りし、親佐に気に入られ、親佐が亡くなるときに葉子との結婚の約束を取りつけた木村は、信仰熱心なクリスチャンである。「僕はあの女の欠陥も弱点も皆んな承知している。私生児のあるのも固より知っている。唯僕はクリスチャンである以上、何んとでもして葉子を救い上げる。救われた葉子を想像して見給え。僕はその時一番理想的なbetter halfを持ち得ると信じている」と語ったことが葉子の耳に入っている。だが、このような木村の考えとそれに支えられた振る舞いこそが、葉子がこの男をたまらなく嫌だと思う理由になっている。
思春期の葉子は、赤坂学院でキリスト教の教育を受けた。学校は葉子に「祈祷と、節欲と、殺情とを強制的にたたき込もうとした」。葉子はその型にははまらなかった。葉子には、学校の教えが正しいとは思えなかったに違いない。かといって、正しいのは自分だという確信が持てる地点まで行けたわけでもない。「なるなら何所かに大砲のような大きな力の強い人がいて、その人が真剣に怒って、葉子のような人非人はこうしてやるぞといって、私を押えつけて心臓でも頭でも摧けて飛んでしまうほど折檻をしてくれたらと思うんですの」。
葉子のこのような面に留意してこそ、彼女がどうやら内村鑑三がモデルの内田を心の拠り所にしていること、また木村に会いにアメリカへと行く船で倉地に出会い、「この人に思う存分打ちのめされたら、自分の命は始めてほんとうに燃え上がるのだ」という気になったこととの整合性が取れるのだと思われる。
受講生のH・Kさんは、葉子は男から独立しようとしているが、結局のところは男を頼りにするほかない矛盾を、登場人物の名前と関係づけてみせた。つまり、葉子は木部や木村から離れようとするが、木から離れた葉っぱが命を維持できないように、男から離れた葉子は女の身体を特徴づける子宮という器官の病に罹って息を引き取ることになってしまうと。
そう考えると、「或る女のグリンプス」では田鶴子だったヒロインの名前が、『或る女』では葉子になっていることの意味は小さくない。『或る女』のエピグラフとして引用されているホイットマンの詩のleavesを有島自身が「木の葉」と訳していることにも注目すべきだろう。葉子にとっては、倉地が木部や木村とは異なる男なのか、それとも同類の男なのかが死活的に重要な問題であったはずだ。倉地の字面に「木」を思わせる文字はないが、前編の最後は「木村」の文字がピラミッド状になる奇妙なエクリチュールのあとで、倉地を指して「男は材木のように感じなく熟睡していた」と言われてテクストが結ばれている。この点について、尾西康充は「木村」と「材木」のような男=倉地がイメージでつながると暗示している。
M・Yさんは、葉子が親佐や五十川女史や田川夫人に比べると「女性的」だが、内田の細君や倉地の妻と比べれば「男性的」であること、また、愛子や貞世に対して家長のように振る舞う点では「男性的」だが、倉地という男性を前にしては「女性的」たらざるをえなく、外部的な男性の闖入によって、それまで二人の妹に対して成立していた擬似的な家父長制のシスターフッドが壊れていくことになるのではと示唆した。
葉子の女性性や男性性は、関係のなかで転移したり反転したりする。葉子の揺らぎは、有島の揺らぎでもあっただろう。それは内村の堅忍不抜の信仰に比べると、いかにも柔弱であるように見える。しかし有島は、正しい義の人が救われるとも、悪人こそが救われるとも主張せず、自分の正しさに確信の持てない人間に、果たして救いはあるのか、ないのかという新しい問いを提起しているのではないかと思われる。
以上、報告者:伊達聖伸(総合文化研究科教授)

*
【受講者からの感想】
『或る女』を読んで一週目の正直な感想は「葉子に共感できない」だった。魔性の女性「葉子」が気まぐれの果てに自業自得で堕ちていく、という単純なストーリーだと読み取った私には、葉子に寄り添えるポイントはないように思えた。ジェンダーの観点から読み直そうと試みるも、結婚と離婚、女性性と男性性など、様々な「AとB」の境界線の中で揺れ動く葉子に、せっかちな私は「結局この人間は何になりたいのだろう」という感想を抱いた。
また、「葉子はその頃から何所か外国に生れていればよかったと思うようになった」という一節に示されるように、海外(米国)への漠然とした憧れがあるようだった。しかし許婚のもとに行く船の中で倉地と親しくなり、最終的には渡米をしないという選択をした。当時の許婚という制度がどれだけ拘束力を持つのか、またどれだけ自由恋愛が一般化していたのかははっきりわからなかったが、少なくとも自由恋愛が一般的ではないという先入観から読んでしまった私は、葉子を奔放な人間だと捉えてしまった。またそもそも、外国に行けば葉子の抱えるジェンダー的な迷いや苦しみは解決する問題なのか、という疑問を抱かせた。
したがって葉子が子宮の病に苦しむというラストシーンは、社会が期待するような古風な女性像に抵抗し、挫折や迷いのうちに(子宮に象徴される)女性性が傷つけられ、男性的にも女性的にもなりきれない葉子の苦しみを示しているのではないかと読み取った。つまり、「結局何がしたかったのだ」という筆者有島による葉子への問いかけと罰であると。後にこの読みは議論の中で揺らぐことになった。
議論の中で特に印象を受けた観点、それは、男性である筆者有島がなぜ、知る由もないはずの子宮の痛みを描けたのか、ということである。私の解釈では、それは有島による奔放な振る舞いをしてきた葉子への「罰」であった。一方で授業内の議論では、そのシーンは有島なりに子宮の病に象徴された「女性の苦しみ」に共感し、近づこうとしているのではないか、という解釈が出された。また、一方では、有島に内面化された女性性が葉子に投影されているのではないか、という解釈も出された。罰ではなく、有島自身の苦しみを葉子の病に象徴させたのだ、という読みである。葉子が最終的に米国に降り立たなかったことも、米国に象徴される「理想的な女性像」に葉子がありつけないことの暗示ではないか、という解釈も議論に挙がった。それはつまり、有島が米国留学の末にキリスト教国に失望してしまったときの感情が投影されているのではないか、という見方も可能になる。
このような見方に加えて、ある一つの語を挙げて報告を締めたい。葉子の抱えていた苦しみは、昨今認知され始めている“quarter life crisis”という語、すなわち、人生100年時代である現代における人生の4分の1(=25歳)あたりに抱える将来の悩みと質的に似ているのではないか。厚生労働省の統計では、葉子が生きていた明治大正時代の平均寿命は男女ともに45歳前後だが、モデルとなった佐々城信子が71歳まで生きたことを考慮すると、20代半ばの葉子がquarter life crisisに陥っていたことも十分考えられる。このように年齢的な補助線を引くと、単に男性性―女性性の揺らぎだけではなく、少女―大人の女性という境界や、若さ故の奔放さ―大人として期待される落ち着き、という別の境界も見えてくるのではないか。そしてこれらの境界をめぐる悩みの根底には、「男性/女性はこうあるべき」という社会に浸透したジェンダー観が関わっていることは言うまでもない。明治大正は家父長的で窮屈な時代だとか、自由恋愛ができる令和は良い時代だとか、そういう話ではなく、有島が葉子に投影した苦しみは性別関係なく、通時代的な若者の悩みを表現していると捉え返せるのではないか。あれだけ「共感できない」と感じていた葉子の姿は、今や24歳女性大学院生の私をそっくりそのまま映している鏡のようにも思えてくる。
(以上、E・Y)
*
このテクストを読む行為は、読者をジェンダー的環境と無縁なままにはしないというのなら、私は、ひとりの女性として、またフェミニストとしての立場から『或る女』というテクストの抑圧性について考えてみたい。
主人公の葉子は結婚による男性からの支配を厭い、女として自らの力量で生活できることを望む一方で、その美貌や才気によって周囲の男を誘惑し、そのことを「生の喜び」とまでいう。彼女は妹たちに対して家父長的に振舞ったり、男性たちに対してはサディスティックな面を見せたりするが、自らが男になろうとはしない。あくまで女でありながらも性に奔放で、支配的でもある自分のまま生きたい、認められたいと望んでいるような印象を受けるのである。しかしながらこの望みは、野性的で極めて男性的な身体性を帯びた倉地に出会ったことをきっかけに失敗することとなる。
最も象徴的なのは、葉子が子宮の痛みに苦しむラストシーンである。女であると同時に自立したいと願った葉子が最後に女の性器を奪われるという展開には、「処女か娼婦か」という女性のあり方に関する二元論的規範や、「(異性愛的)女性の魅力とフェミニズムは両立しない」というステレオタイプからの逸脱を懲罰するものとして解釈することができる。子宮をもたず男性であることを引き受けていた有島がこれを書いたということからは、「女は男になれない」、つまり男性的支配の特権的主体から女性を排除する動きや、女性の快楽を支配したいという欲望が見え隠れするようにも思われる。
この点に関して、有島の森嶋厚吉との同性愛的関係に触れ、その書きぶりを「女性的である」(または「脱男性化されている」)と評価し、葉子に同一化する形で書かれたクィアな実践として評価する見方もあるようだ。しかし男性同士の性的関係を単に異性愛関係に帰結させ、一方に「女性的」性質を担わせることは問題含みではなかろうか。また仮に森本との関係性において「女性的」立ち位置にあったとしても、少なくとも有島は男性のジェンダーを引き受け、男性作家として『或る女』を著したのである。
むしろここでは葉子に対する書き手の視点について、他者的なものについての興味や、性的対象としての女の魅力という点で考えたい。前編で葉子は船上の人々(男たち)の関心を一身に集めるが、若さや美貌と共にどこか神秘的で謎めいた雰囲気が強調されている。葉子自身も周囲から向けられるまなざしには非常に自覚的であり、ほとんど常に「自分の仕草がどのように(魅惑的に)見られるか」を念頭において演じるような形で振舞っている。その上で読者は、(葉子本人ではなく)書き手によって提供される、ひとりきりになった葉子の見せる行動や独白からその内面を「覗き見」するのであり、その際にも移り変わりやすく、ヒステリックにも感じられる心的描写と同時に、身体的魅力がきわめて断片化された形で描き出される。
最後に言及しておきたいのは、『或る女』における女同士の関係、およびそれに対する書き手の視線である。作中では葉子と他の女性たちとの関係にも焦点が当てられるが、ここでは葉子と女学校の少女たち、また妹の愛子と貞世とのシスターフッド的関係に注目する。これらは特に、他に男性が存在しない場のみにおいての関係が想定されており、ともに男性(的な存在)の介入によって崩壊し、それぞれ同性の恋→異性愛、姉妹間の保護/従属→家父長制と、前者が後者を代替/疑似するいわば「偽」の関係性として位置づけられている。女性を異性愛以外の文脈で強く描き出したという点では評価すべきかもしれないが、この意味では結局女性間の関係を軽視し抑圧する男性中心的なテクストとであると言えよう。
以上のように、書き手の視点は葉子に同一化するというよりもむしろ外部的な位置に留まっており、『或る女』におけるジェンダーの問題の一部は単に葉子というキャラクターのアイデンティティの揺らぎを示すものではなく、規範からの逸脱に対する抑圧という働きをもつものだと考える。
(以上、H・C)








