2023年2月22日(水)、第3回EAA「戦間期思想史を語る会」は対面(EAAセミナー室)とオンライン(zoom)のハイブリッドで開催された。本研究会は20世紀の第一次世界大戦と第二次世界大戦の間という時期(その前後の時代も含めて)に焦点をあてて、当時の東アジアないし世界諸地域の思想・言論を取り上げることによって、地域・ジャンルを横断する普遍的な問いを練り上げ、新しい学問を構築することを目指している。
今回の提題を務めた閔東曄氏(東京大学)は高坂史朗「歴史的意識と社会存在論」・米谷匡史「植民地/帝国の『世界史の哲学』」(『日本思想史学』37号、2005年9月)、趙寛子『植民地朝鮮/帝国日本の文化連環』(有志舎、2007年)の第5章と第6章、そして酒井直樹「パックス・アメリカーナの下での京都学派の哲学」(酒井直樹・磯前順一編『「近代の超克」と京都学派:近代性・帝国・普遍性』以文社、2010年)といったテクストの内容を踏まえながら発表を行った。閔氏はまず近代朝鮮の歴史・思想史的な流れを概観したうえ、植民地時代の朝鮮思想と1930年代以降の日本の思想状況とりわけ京都学派の哲学との連動を具体的に整理した。そして趙著に基づき戦時期の朝鮮知識人における植民地と帝国主義との「敵対的な共犯関係」を指摘するとともに、それを批判的に克服しようとする徐寅植(ソ インシク, 1906-?)の歴史哲学を丹念に説明した。最後に、「日本対西洋」という図式からはみ出るものの論じ方、「植民地」で普遍的に「哲学」することの意味、普遍的哲学の超越論的企てと帝国的国民主義/植民地主義との関係について問題を提起した。
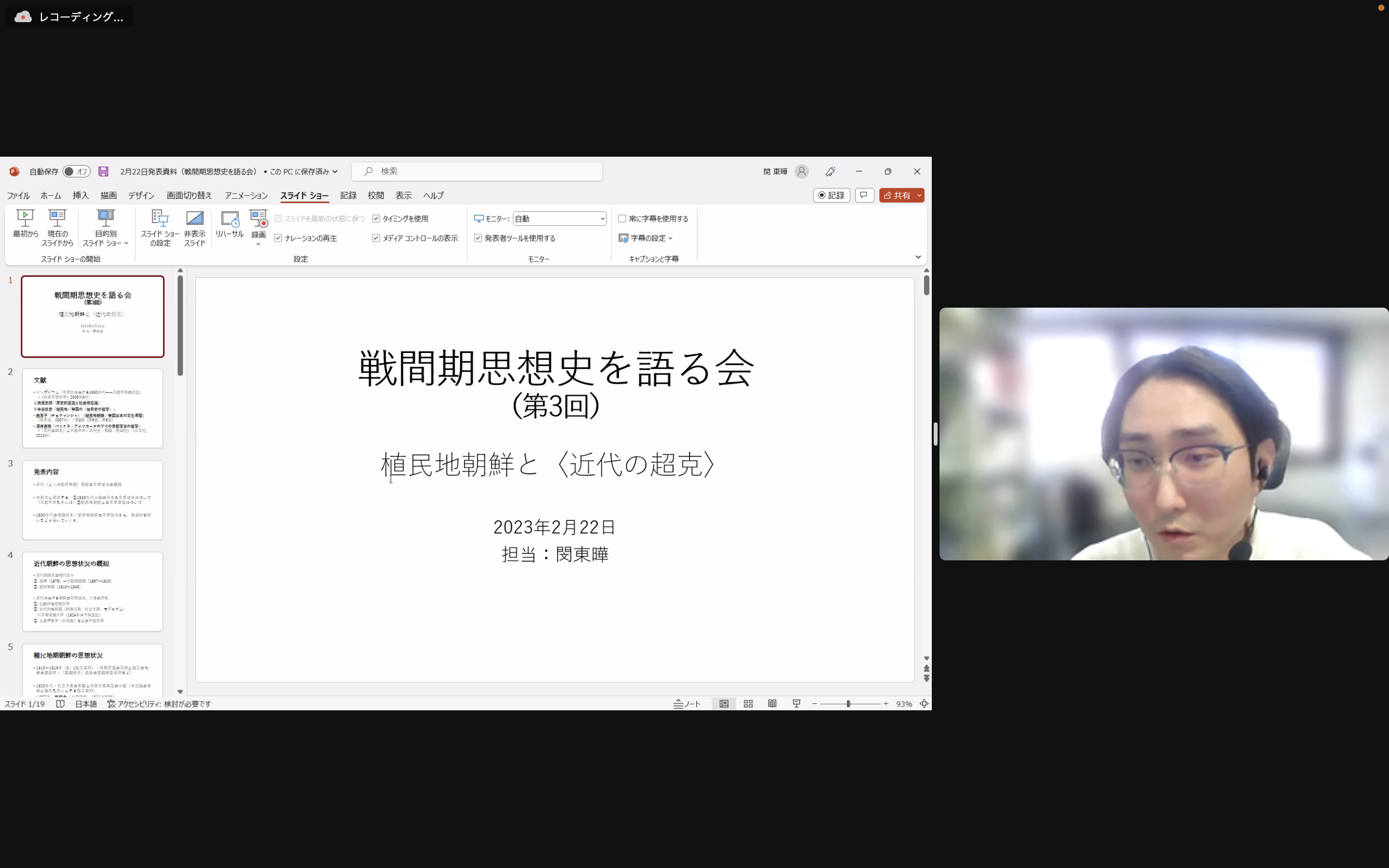
発表後の討論では、宮田晃碩氏(東京大学)はアーレントの議論を援用しつつ、徐寅植における「生」「生活」および「労働」の捉え方を問題にした。アーレントの『人間の条件』における「労働」(labor)は「仕事」(work)、「活動」(action)と区別され、複数性をもたざる動物としての生であるが、それと照らし合わせて、個別性・個性を重視する徐寅植の「労働」概念はどう理解すればよいかと問いかけた。
崎濱紗奈氏(EAA特任助教)は朝鮮の知識人がマルクス主義と京都学派を両方駆使して自身の思想を展開したのに対して、沖縄の思想家は京都学派への言及が少なく、むしろ柳田國男や折口信夫の「新国学」に関心を寄せたとした。そのうえで、戦後に分断の時代に入った東アジアにとって、1930年代から1940年代初頭の思想にはまだ複数の可能性があったはずであり、そこに戦間期の思想史を考える意義があると述べた。さらにそれと関連して、京都学派をめぐる議論は往々にして「抵抗の契機」の析出に止まるという現状のもどかしさを指摘した。
郭馳洋(EAA特任研究員)は、趙著における地域の共同防衛とその内部の抑圧性に関する論述に共感を示した。また、「歴史的現在」と「現代」を区別し、歴史の法則や「運命の同一性」に回収されえない個別性・「私の運命」を強調しつつも、労働の社会化や「原始運命」の共同性、「歴史のキマグレ」に抗う「理性」を語る徐寅植の言論に内在する緊張関係に留意した。1930年代の中国における「民主と独裁」論争、マルクス主義と民族主義の関係に新たな解釈を与えた毛沢東の「矛盾論」にも触れた。
危機と希望が同時に感じ取られた時代において、思想が現実を追い越そうとするような現象が一層顕著になっていた。それを学術的な精度で言語化して批評していくことは重要な課題であると思われる。
報告:郭馳洋(EAA特任研究員)








