2022年12月19日(月)、第2回EAA「戦間期思想史を語る会」は対面とオンラインのハイブリッドで開催された。本研究会は20世紀の第一次世界大戦と第二次世界大戦の間という時期(その前後の時代も含めて)に焦点をあてて、当時の東アジアないし世界諸地域の思想・言論を取り上げることによって、地域・ジャンルを横断する普遍的な問いを練り上げ、新しい学問を構築することを目指している。
第2回では宮田晃碩氏(東京大学UTCP特任研究員)が提題者を務め、マルティン・ハイデッガー「ヘルダーリンと詩作の本性」(濱田恂子、イーリス・ブㇷハイム訳『ハイデッガー全集第4巻 ヘルダーリンの詩作の解明』創文社、1997年)、轟孝夫『ハイデガーの超政治:ナチズムとの対決/存在・技術・国家への問い』(明石書店、2020年)の序論・第2章・結論について発表を行った。発表では言語がいかに「私たち」を作るか、そこに哲学がどう関わるかという関心から、ヘルダーリン(Friedrich Hölderlin, 1770-1843)と詩作に関するハイデガーの議論(1930年代半ば)が注目された。宮田氏は、「主体性の形而上学」とニヒリズムをともに乗り越えるために存在(zein)そのものを問い直したハイデガーがどのように詩作と言語への哲学的な省察を通じて「私たち」という共同性を改めて立ち上げようとしたか、その問題意識と論理を緻密に考察した。さらに石牟礼道子『苦海浄土』における共同性のイメージにも言及しながら、何らかの共通性(文化、言語、人種など)と異なる「私たち」のあり方、具体的な詩作と「私たち」の関係性、学問的な言説の(不)可能性について問題を提起した。
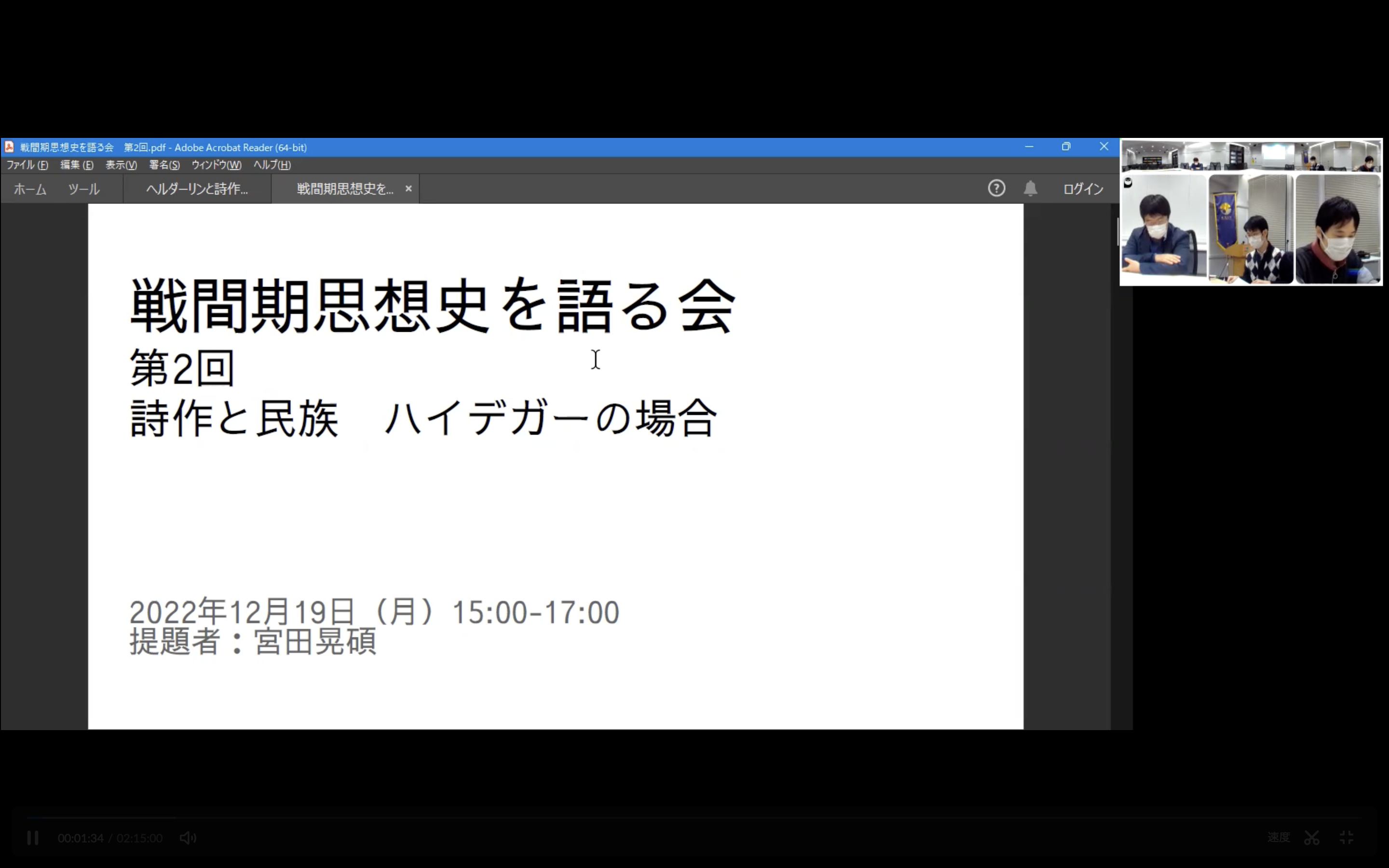
発表後の議論では、丁乙氏(EAA特任研究員)はハイデガーのヘルダーリン論における「留まるもの(was bleibet, das Bleibende)」の訳し方、ハイデガーがヘルダーリンに強く惹かれ、詩を特権化する理由について質問した。高原智史氏(東京大学)は詩人と言語の問題についてエマーソンの影響を受けた北村透谷における「元気」という概念およびその変遷を確認しつつ、言語と異なるような仕方で共同性を考えることに関心を示した。郭馳洋(EAA特任研究員)はハイデガーにおけるピュシス論と作為性批判が「自然」「作為」および「古層」に関する丸山眞男の議論と対照的なものであることに留意したほか、ハイデガーに用いたれた「Volk」概念の理解や、哲学の問いそれ自体の政治性に迫ろうとする轟著の問題意識にも注目した。
閔東曄氏(東京大学)はハイデガーに師事したこともある三木清の人間主義と詩作問題の関連性、1930年代から展開された三木の「自然」「作為」をめぐる議論および技術論、同時代の日本における民族論の流行ないし高坂正顕の『民族の哲学』(1942)について述べたうえで、ハイデガーの民族主義をその哲学の必然的な帰結とみなすべきかという問いを投げかけた。崎濱紗奈氏(EAA特任助教)は純粋無垢なものを保存する媒体としての「歌」を重視する伊波普猷と、言語の純粋さを語幹に遡って求めようとする折口信夫(伊波と親交あり)のことを取り上げ、1930年代の思想史における詩歌の位置づけの重要性を指摘した。さらに、哲学者の政治性に対する単なる擁護/糾弾ではないアプローチの可能性と意義、戦争に関わる責任、哲学言説がその根幹部で戦争に結びついてしまう原因といった問題関心を共有した。
今回では詩的言語と共同性(「私たち」)、原初性と作為性、哲学と政治をめぐって議論が白熱化していた。こうした討論を通じて、研究対象となる地域・ジャンルを異にする参加者たちの間から新しい学問をするプラットフォームが少しずつ形成されることを願う。
報告:郭馳洋(EAA特任研究員)








