2022年12月5日(月)、立命館大学加藤周一現代思想研究センターとの共同主催により、また上廣倫理財団の協力を受け、共同研究会「日本の知識人、その宗教と周辺——鶴見俊輔・加藤周一・林達夫」が対面とウェビナーのハイブリッド形式で開催された。
第一部は鷲巣力氏(編集著述業、立命館大学加藤周一現代思想研究センター顧問)による「林達夫と聖フランチェスコ、加藤周一とカソリック」、第二部は伊達聖伸氏(東京大学教授)による「鶴見俊輔における宗教——はみだしの技法」である。冒頭、第一部の司会を務める半田侑子(立命館大学衣笠総合研究機構研究員)は全体の導入を行ったのち(内容は事前の概要に準ずる)、鷲巣氏の紹介を行った。

鷲巣氏は『加藤周一著作集』(平凡社)、『加藤周一自選集』(岩波書店)の編集者としてよく知られていたが、近年は『加藤周一を読む――「理」の人にして「情」の人』(岩波書店、2011)や『「加藤周一」という生き方』(筑摩書房、2012)、また『加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか――『羊の歌』を精読する』(岩波書店、2018)などの著作群において、綿密な調査と分析によって加藤研究を牽引する第一人者となった。2022年も『書く力――加藤周一の名文に学ぶ』(集英社)を世に問うたばかりであり、加藤周一の残したテクストを詳細に読み解いている。
その一方、氏の編集者としての最初の仕事は『林達夫著作集』(平凡社)であり、林達夫と久野収による対談『思想のドラマトゥルギー』(平凡社、1974)も氏の編集によって成り立った。鷲巣氏は、加藤周一研究の傍ら、雑誌『イタリア圖書』52号(イタリア書房、2015)において「林達夫への精神史的逍遥」という連載を開始し、連載は第7回まで続いた。その第1回は「出発点としての『イエス』」であった。
鷲巣氏によれば、林と加藤を理解するうえで宗教の問題を避けて通ることはできない。「林達夫と聖フランチェスコ、加藤周一とカソリック」は、このような問題意識から生まれた主題である。

林達夫は「戦闘的無神論者」か?
半田によるこうした紹介を受け、鷲巣氏が報告を行った。林達夫といえば「無神論の立場から宗教批判を展開した思想家」という印象が強く根付いている。これは、林が自らの思想を「戦闘的無神論」と表現したことがあり、久野収が林を「戦闘的無神論者」と評したことに負うところが大きい。しかし、鷲巣氏は林が自宅玄関に飾ったジオットの聖母子像や、『聖フランチェスコの小さき花』やグレゴリオ聖歌を好んだことを理由に「果たして「戦闘的無神論」だろうか?」という疑問を抱く。
鷲巣氏によれば、19世紀末から20世紀初頭にかけて欧米では聖フランチェスコ研究が進み、多くの著書が刊行され、そのうちのいくつかが日本でも翻訳されていた。なかでも久保正夫による翻訳がもっともよく読まれていた。久保は谷川徹三、林達夫、三木清らのグループのリーダー格だった人物である。久保の翻訳による『聖フランチェスコの小さき花』は、谷川、林、三木がいずれも久保正夫訳で読み、いずれも感銘を受けたと書き残している。
その影響もあって大正年間は一種の宗教ブームが起きて(例えば、聖フランチェスコに題材を採った菊池寛の「真似」、芥川の切支丹物、倉田百三や有島武郎の作品)、林の青春時代はこの宗教ブームの時代と重なっていた。
林が若い頃に影響を受けた人物について、波多野精一、深田康算のふたりを鷲巣氏は挙げる。波多野に翻訳することを勧められ、ブセット『イエス』を1923年に岩波書店より翻訳出版し、1932年に文庫化された。この両書に書かれる林の見解は大きく異なっている。単行本の『凡例』には、キリスト教に対する強い共感が述べられるが、文庫版の凡例では、翻訳当初の自分の立場と現在の立場とは大きく変わっていて、いまでは「戦闘的無神論の陣営に」属していると断っている。1930年代初頭は林がマルクス主義にもっとも近づいた時期だったのである。林の思想的遍歴のなかではむしろ例外的な時代だったと鷲巣氏は考える。
1923年9月1日、関東大震災によって林の自宅は崩壊し、林の家族は近所の知人宅の炭置き小屋でしばらく過ごした。この辛い日々に、林は毎晩サバティエの『アッシジの聖フランチェスコ伝』を読み、癒されたことを『増補 思想のドラマトゥルギー』(平凡社、1974)で語っている。聖フランチェスコは、林曰く「僕という不信者にとっての守護聖者としか言いようがない」存在となっていたのだ。1971年林が初めてヨーロッパ旅行に出かけ、アッシジに行ったとき興奮のあまり眠れぬ夜を過ごし、自分の唯一の「感情旅行(センチメンタルジャーニー)」だといった。
林が聖フランチェスコを心の支えにしたのは、関東大震災の時ばかりではない。太平洋戦争が勃発したのち、1942年頃の日本のキリシタン研究には見るべきものがあったのだが、林はそれら文献を所蔵していた。おそらく、戦時下において独りキリシタン研究をすすめていたと推測できる。戦時下の林達夫には、心を支える拠り所として、「隠れキリシタン」への共感があり、自らも「隠れキリシタン」として生きようと考えていたのだろうか、と鷲巣氏は指摘する。
戦後、「共産主義的人間」を書いてスターリニズムを批判したとき、「ボス型政治家」に対置したのは「聖者型政治家」であり、その祖型としたのが「聖フランチェスコ」であった。鷲巣氏によれば、林の思想の原点にあったのは「聖フランチェスコ」への共感、聖なるものへの共感であった。林は「キリシタン」だと言わなかったが、限りなく「隠れキリシタン」に近かったと鷲巣氏は主張する。

鷲巣力氏
加藤周一の受洗の意味
林達夫と異なり、加藤周一は若いときからカソリックやその理論的書物についての共感を隠そうとしなかった人物である。加藤の親族には、母や妹をはじめとしてカソリックが多く、しかも最晩年にカソリックに入信する人が三人もいた。また、加藤の高校から大学時代にかけて影響を受けた人物として、垣花秀武、岩下壮一、吉満義彦を鷲巣氏は指摘する。一高時代の友人である垣花は核物理学の研究者であると同時に、トマス・アクィナスの研究者でもある。垣花にカソリック神学を学び、その論理整合性に共感を覚え、岩下壮一の著作を読むようになる。鷲巣氏によれば当時の学生のあいだでは岩下に対する関心が高く、一高の寮報『向陵時報』にはたびたび岩下に関する記事が掲載されていたという。加藤が1937年から1942年にかけて書いた『青春ノート』8冊(「加藤周一文庫デジタルアーカイブ」において公開)のうち、最後のノート『青春ノートⅧ』に「岩下師の言葉」を綴っている。吉満は岩下との出会いによってプロテスタントからカソリックへ改宗した人物であり、フランスへ留学しジャック・マリタンに師事する。加藤は吉満に仏文研究室で出会い、彼の講義を受講、のちに「吉満義彦覚書」を吉満著作集へ寄稿した。
加藤はカソリックへの共感をしばしば表明したが、一方で、自伝的小説『羊の歌』(岩波書店、1968)「あとがき」において「宗教は神仏のいずれも信ぜず」と述べるなど、無宗教であることをいいつづけた。科学ですべてを説明することはできないが、それでも宗教には帰依しない、という加藤の姿勢は著作にも反映されていた。そのため加藤は「無宗教者」である、という認識を多くの読者が共有していた。ところが、最晩年に加藤はカソリックへ入信した。
加藤の歿後、彼の入信は信仰のまぎれもない証左として語られ続けている。しかし鷲巣氏は、入信する5日前の2008年8月14日、加藤から電話を受けた。加藤が語った内容を、鷲巣氏は『加藤周一を読む――「理」の人にして「情」の人』に以下のように書き留めている。
「宇宙には果てがあり、その先がどうなっているかはだれにも分からない。神はいるかもしれないし、いないかもしれない。私は無宗教者であるが、妥協主義でもあるし、懐疑主義でもあり、相対主義でもある。母はカトリックだったし、妹もカトリックである。葬儀は死んだ人のためのものではなく、生きている人のためのものである。〔私が無宗教では〕妹たちも困るだろうから、カトリックでいいと思う。私はもう死んだのです。「幽霊」なんです。でも化けて出たりはしませんよ」
加藤は一度も教会に足を運ばず、説教を聞いたこともなく、自宅にて入信の儀式を行うという異例の方法をとっている。加藤が「私はもう死んだのだ」と話したことの意味を、鷲巣氏は、加藤が「カソリックを信じたわけではない」といいたかったのだと理解する。ではなぜ入信したのか。加藤の思想の中核には、身近な人への愛があった。加藤は妹に対する愛のため入信を決めたのだろう。残された妹が、もう兄には会えないと思いつつ生きるのと、いずれ天国での加藤との再会を信じつつ生きるのとでは大きな違いがある。妹が安寧に老後を過ごすために加藤は入信したのだ、と鷲巣氏はいう。実際、102歳になった妹は、加藤と天国で再会することを楽しみに今も元気に生きつづけている。
このように林、加藤は生涯のほとんどを「無宗教者」として過ごした。しかし、その内実はどうであろうか、と鷲巣氏は問いかける。「無宗教をつらぬいた」「戦闘的無神論」と言われた林は事実上「隠れキリシタン」ではなかったか。最晩年に「カソリックへ入信した」加藤は事実上「無宗教」をつらぬいたのではなかったか。これまでの認識を覆す、極めて重要な報告である。

左より鷲巣氏、伊達聖伸氏、片岡大右氏
休憩を挟んで第二部が始まった。冒頭、司会を務める片岡大右(批評家)が講師の伊達聖伸氏の紹介を行った。といっても、伊達氏の宗教学者としての活躍については多くを述べるまでもないとして、片岡が強調したのは、近代フランスの非宗教的な秩序構築の努力のうちなる逆説的な宗教性に注目した博士論文以来、氏の研究上の関心が、いわゆる実体宗教にとどまらず「世俗的」と称されるような社会秩序さえもが、何らかのかたちで「宗教的」と呼びうるような性質を帯びざるをえないという点に向けられてきた、という事実だ。こうした問題意識は今回の話にも通底していることが感じ取れるはずだという片岡の導入を受けて、伊達氏は報告を行った。
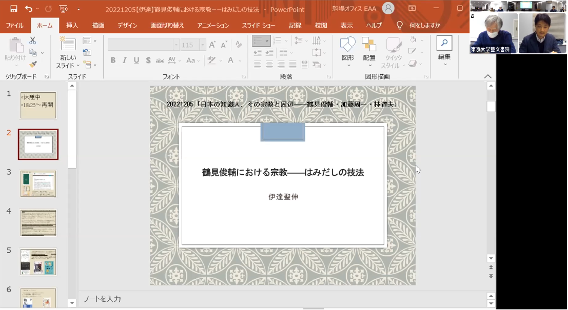
編集者として林達夫や加藤周一と親しく接してきた鷲巣氏と異なり、自分は鶴見とは面識がなく、しかも以前から継続的に読んできたわけでもない。そのように振り返る伊達氏が鶴見への関心を新たにしたのは、フランス研究に進み博士論文を仕上げたのち、ケベック研究を手掛けるようになってからだという。ケベックの研究者とともに「小国論」の研究に乗り出すなか、1979年から1980年にかけての鶴見のモントリオール滞在に関心を持ち、論文を1本書いた。それと並行してEAAの授業でも鶴見を取り上げ、その面白さ、奥深さを発見しつつある。
従来、鶴見が宗教という角度から語られることは少なかったが、そうしたアプローチは必要であり、鶴見の重要な部分に触れることができるはずだ。そのように述べる伊達氏は、『不定形の思想』(1968年)所収の「退行計画」(同年)に注目する。「はじめに思いちがいがあった。思いちがいは神にまつられた。思いちがいが神だった」という一節をはじめとして、重要性を予感させながらも、一義的な読解の困難なエッセイである。
93歳で没した鶴見が45歳の時に書かれ、彼の人生のほぼ折り返し点に位置するこのテクストの特徴を、伊達氏は3点に整理した。第一に、それは生い立ちの方へと線が伸びていくテクストであり、上流階級の出自を誇ろうとする鶴見に鉄槌を喰らわせた母の記憶に立ち返ることで、鶴見は「貴種を折る」(村瀬学氏)という自らの経験を風化させないようにと試みたのだと言える。第二に、「退行計画」はベ平連の裏側で書かれたテクストであって、戦争反対という「正しい」活動をする自らの姿に耐えられない、そんな彼の別の側面をここで表現し、バランスを取りたいという意志がうかがえる。第三に、これは老いの方へと線が伸びていくテクストだ。当時、ベ平連に参加した哲学者であり僧侶の橋本峰雄が、これはまったく仏教的だと読後の印象を語ったけれども、実際ここには、最晩年の『かくれ佛教』(2010年)に結実する鶴見の宗教観をうかがい知ることができる。
伊達氏はこうして、「退行計画」を起点として、鶴見の宗教論の輪郭を描き、その特徴を捉えるべく、(1)生い立ちから思想形成期、(2)戦後から壮年期、(3)晩年の3段階に沿って報告を展開した。
(1)出発点:幼年期〜⻘年期 ⽣い⽴ち〜思想形成期
(1)ではまず、「退行計画」以後に公言されてきた母親への「悪口」に注目しながら、かつて母が体現した「正しさ」や「正義の道」への反発が鶴見に「悪人」感覚を植え付けたこと、そこからキリスト教やマルクス主義、さらにはウーマンリブへの同調しがたさが帰結したことが確認された。それらは「You are wrong」の思想であるのに対し、鶴見は「I am wrong」を出発点とする(『かくれ佛教』)。
思想形成期に関しては、一方では、ハーヴァード大学留学期の鶴見に影響を与えたユニテリアン派とプラグマティズムの思想が取り上げられた。鶴見は前者からはキリスト教のうちにありながら正統教義に反逆し逸脱するものへの眼差しを、後者からはカトリックの無謬性(infallibilism)への対抗として捉えうるパースの「マチガイ主義」(falibilism)――絶対的な正しさへの到達可能性を退けつつも、「マチガイを何度も重ねながら、マチガイの度合いの少ない方向に向かって進む」(『アメリカ哲学』1950年)という立場――、実証困難な事柄については自らが正しいと感じるものを信じることができるとするジェイムズの「信仰の権利」、そしてキリスト教その他の宗教にも様々な非宗教的経験にも見出しうる「宗教的なもの」に注目するデューイの宗教論を学ぶことができた。
しかし他方では、思想形成期の鶴見が戦時期の日本の論者の宗教論に影響を受けたことも忘れてはならない。『かくれ佛教』の鶴見は、留学からの一時帰国中に柳宗悦と面会した際の「不思議な経験」を回想している。キリスト教神秘思想を研究していながら、柳は仏典を根拠に自己の思想を語ったのだという。この回想の紹介に続けて伊達氏は、石川三四郎、木下尚江、辻潤らの系譜を取り上げ、彼らに共通して見出しうる、不安定さに身をさらしつつ既成宗教を相対化する宗教的境地は、鶴見のものでもあったと評した。氏によれば、こうした通宗教的な感覚は、大正教養主義の地平に属していると同時に、ユニテリアン的なものでもある。鶴見は自己の育ってきた環境をそれなりになぞりながら、宗教をめぐる意識を形成してきたのだという。
(2)広義の「宗教」論とライフワークとしての転向論:戦後〜壮年期
(2)に関して、伊達氏はまず、鶴見の全業績のなかで戦争体験と並び大きな位置を占める転向論に注目し、それを広義の「宗教」論として捉え直すことを提案した。この点で意義深いのは、マギル大学での講義に基づく『戦時期日本の精神史1931~1945』(1982年)を、氏が英語版と比較して行った指摘だ。日本語版では、「国家権力のもとに起る思想の変化」として定義される「転向」は、「個人の選択と決断による思想変化」として定義される「改心」と別物のように見える(転向≠改心)。しかし英語では、いずれもconversionの一形態として説明されており、政治的な転向と宗教的な回心のあいだに一定の連続性を読み取ることができる(転向≒改心=回心)。日本語への翻訳によって見えにくくなっているが、転向は鶴見にあって、一種の宗教性の問題として論じられていたのだ。
実際、伊達氏によれば、思想を「信念と態度の複合」として捉えるという、転向研究の前提をなしていた鶴見の着想は(『期待と回想』1997年)、宗教を信念と儀礼の複合体として定義するデュルケムの立場を想起させる。鶴見は、戦前の「国体」それ自体を、『古事記』に見られるような「多神教としての神道」と異なる一神教的な国家宗教とみなしており(『戦時期日本の精神史』)、実体的な宗教よりも広い意味で宗教の問題を考えていた。「まちがいを通して得ることのできた真理への方向性の感覚」(同)を重視する鶴見の転向論は、先ほど触れたパースの「マチガイ主義」とも、晩年の宗教論とも響き合うものだ。

伊達聖伸氏
そのように指摘したのち、伊達氏は鶴見の絶対主義批判へと議論を進めた。鶴見は「ファナティックなもの」の持つエネルギーを認め、それを全否定することはないが、やはり「一つクッションを置きたい」という立場を強調していた。しかし逆に言えば、疑いによって抑制されうる限りにおいて、一神教的な普遍主義が退けられることはない。一神教であっても疑いを伴うなら、鶴見の評価は高くなる。揺れを支えるのが宗教、ということだ。
同じ両義性は、しばしば一神教的不寛容との対比において称揚される日本的寛容についても認められる。伊達氏によれば、日本的な「家」の問題点を自覚しながらも、それを背負いながら多少なりともよい方向へと道を切り開いていく、というのが鶴見の考えだった。鎖国性についても、彼はそれを日本が抱える困難の根源とみなす一方、孤立し小さく閉じることの意義を積極的に評価する面もあった。
ここまで見てきたことから了解されるように、鶴見の宗教的探求においては、何か特定の宗教形態が正しいものとみなされることはない。問題となるのは、目指すべきまたは避けるべき方向性をめぐる感覚である。伊達氏はこの点に関し、まずは鶴見のオーウェル論(「オーウェルの政治思想」1970年)から、侵略性を帯びた「ナショナリズム」ではなく防御的にとどまる「愛国心」への志向性を取り出したのち、それを「小国」論的発想と関連付けて、カナダやメキシコの先住民の小さな社会を擁護する鶴見の姿を浮き彫りにした。
しかし伊達氏によれば、鶴見は「精神の傷」を受けた者へと共感を寄せながらも、支配・被支配の関係性を絶対的なものとはしなかった。例えばメキシコのヤキ族には、「キリスト教をうけいれてからもそれを在来の宗教によってうらうちしてつよい合板をつくる動き」が認められる(『グアダルーペの聖母』1976年)。上からかぶさってくる力を巧みに受け止めて、生き延びる道を切り開くこと。こうした方向性に期待をかける鶴見は、褐色の肌をしたグアダルーペの聖母や五島の隠れキリシタンによる口伝の福音書といった「合作」の諸例のうちにこそ、意義深い宗教性を見出していた。
こうした探求の方向性は、さらにユーモアや漫画を重視する姿勢へとつながっている。キリスト教徒にならなかったのも、その正統な後継であるマルクス主義者にならなかったのも、漫画の影響だと振り返る鶴見は(「漫画の読者として」1980年)、1997年の自伝的回想でも改めて、キリスト教のような権威的宗教に対して「漫画的に対抗したい」という意志を表明し、「そこにこそ宗教性がある」と続けている(『期待と回想』)。国家の強大さと政府の統制力に立ち向かう思想としてのアナキズム評価もまた、こうした観点から理解できるだろう(「方法としてのアナキズム」1970年)。
(3)到達点:転向論以後 晩年
(3)について、伊達氏はまず、『期待と回想』の鶴見がかつての転向研究の意義を相対化し、より重要なテーマとして「生きていていいのか」「なぜ自殺しないのか」という問題に向き合うようになったことを指摘して、それと鶴見の繰り返された鬱病経験(12歳、29歳、38歳の3度)を関連付けた。ついで氏は、同じ『期待と回想』から「偽善とあいまいさを恐れるな」というメッセージに注目し、同様の主張がすでに70年代にもなされていたことに注意を促したが(「世界の偽善者よ、団結せよ」1976年)、ここで重要なのは、氏が親鸞の悪人正機説への鶴見の一貫して高い評価を確認したうえで、この偽善の再評価のうちにその向こう側へと突き抜ける姿勢を見定めていることだ。曖昧さについては、鶴見は『期待と回想』でパースに立ち返りつつ、「ぼんやりしているけれども遠くまでいく」ことの可能性を示唆している。
こうした曖昧さの評価を、伊達氏は言葉で過不足なく言い表せるものの手前あるいは向こう側に位置する宗教的なものの探求と結びつけつつ、晩年の鶴見にあってはそれが、耄碌を支えるものとしての宗教という発想を引き寄せていたのだと指摘した。それはまた、柳宗悦における「南無阿弥陀仏」、さらにはただ「南無」のみの重視という宗教観とも(『かくれ佛教』)、神を信じてはいないが自己条件づけのために近所の長谷八幡宮に参拝し賽銭をするというプラグマティックな信仰のあり方とも関わっているだろう(笠原芳光との対談、笠原『宗教の森』1993年)。「タヌキの方がキリスト教よりもはるかに深い重大なもの」だと断じ、「私は疑いの守り神としてのタヌキを信仰しているんです」と打ち明ける『期待と回想』でのいかにも人を喰った発言も、こうした文脈のなかで発せられたユーモアとして理解できるだろう。
鶴見は長谷八幡を、天皇制と強く結びつきつつも、それに完全には囲い込まれていない場所だとみなしていた。同じ姿勢で書かれたのが『アメノウズメ伝』(1991年)で、彼は権威を笑いのめすこの女神のうちに、軍国主義日本のイデオロギーに奉仕するのではないような神話の可能性を見ていた。「ユーモアが宗教だ」という立場が世界の伝統となることに期待をかける鶴見は、自らそのような宗教性を体現すべく、以下のように述べる。「アメノウズメから「鳥獣戯画」を通ってタヌキの伝説があって、そっちの方から私は影響を受けてるねえ。私はアメノウズメとタヌキを信仰してる(笑)」(『期待と回想』)。
鶴見はまた、ある宗教を受け入れながらも、「そこから少しはみ出す」ことの意義を強調し、「それぞれの宗教の流れのなかでちょっとはみ出したもの、それが世界的宗教の形成の場だと思う」と説いていた(『宗教の森』)。この観点からすると、長谷八幡はもとより靖国神社でさえも、ある種の両義性をもって捉えられることになる(「神社について」2006年)。こうした両義性をはらんだ伝統を伊達氏は「はみだす伝統」として定式化し、それと対をなす「したがう抵抗」にも目を向けた。政府公認の仏教から迫害された岩手県の「かくれ仏教」または「かくし念仏」と隠れキリシタンとのつながりに関する鶴見の示唆に触れつつ、氏はこうした宗教形態のうちに見られる「はみだし」のありようを、「「隠れ」のエキュメニズム」と名付けた。鶴見自身が自らの立場だと称する「仏教アナキズム」(『かくれ佛教』)にしても、クロポトキンらのアナキズム、さらにはユニテリアン神学といった異質な諸伝統とつながっているのだという(『期待と回想』)。
最後に伊達氏は、「鶴見俊輔における宗教——はみだしの技法」という報告タイトルに立ち返りつつ、こうした「はみだし」は鶴見の生涯と思想を語る際のキーワードとなりうると示唆した。親の期待からはみだした鶴見は、諸宗教の相互的な「はみだし」を前提とする「「隠れ」のエキュメニズム」のうちに人びとの連帯や社会の可能性を見たのだし、また彼は中年期の「退行計画」でも70歳になる1992年以降に書き継がれた『もうろく帖』でも、「わたし」の輪郭からのはみだしを生きていたと言える。
この最後の点は、松村圭一郎『はみだしの人類学――ともに生きる方法』(NHK出版、2020年)が主題化しているものだ。この松村氏の著作や山口昌男『はみ出しの文法――敗者学をめぐって』(平凡社、2001年)を参照しつつ、この言葉に着目することで伊達氏は、鶴見の宗教観――実体宗教にとどまらない宗教的なものをめぐる思索――が彼の思想全体において中心的な位置を占めていたことを鮮やかに浮き彫りにして見せた。

いずれも充実した2つの報告を受け、質疑応答ではいくつもの質問が提出された。ここでは、鶴見にとっては「揺れを支えるのが宗教だ」という伊達氏による定式化に関連して、「能動的」と「受動的」のあいだでの揺れ、アナキズムにも通じ、今日「ネガティブ・ケイパビリティ」として論じられるこうした態度を鶴見自身がどの程度自覚していたのか、という小川公代氏の問いに対し、伊達氏が「マチガイ主義」やタヌキの偏愛のうちにそうした両面性の自覚を認めたこと、そして三浦信孝氏が加藤周一と林および鶴見の関係をめぐる問いを投げかけたことを取り上げておきたい。
林達夫の「共産主義的人間」(初出は『文藝春秋』1951年4月号)を加藤周一が読んだのはいつかという三浦氏の疑問(1971年の「林達夫とその時代」には言及がないが、1980年の『日本文学史序説』下巻ではそのスターリニズム批判が「反共」的立場とは一線を画したものとして評価されている)を受け、鷲巣氏は2人の関係を振り返った。鷲巣氏によると、敗戦後の1940年代後半に両者は交流を持っていた。林から「ぼくは加藤さんを発見したひとなんだよ」と聞かされたことがあったといい、この時期に林が加藤を高く評価していたのは間違いない。1948年に中央公論社から加藤の『文学と現実』が刊行されたが、当時林は同社の出版部長だったので、林の意見で出たことが推察される。「共産主義的人間」について言うなら、加藤がどのように評価していたのかは十分にはわからない。『林達夫著作集』第1巻の解説として書かれた「林達夫とその時代」に言及がないのは、日本の知識人と西洋との関係をたどり直すことで林の歴史的位置を確定するという主題との適合性の問題もあっただろう。林が発表した当時は加藤のフランス留学(1951年11月)の半年ほど前であり、資金作りのための翻訳作業などで加藤は多忙だった。その時点で十分に読み得たかは疑わしく、少なくとも林の「共産主義的人間」に反応した批評は当時には書いていない。しっかりと読んだのはかなりのちのことだろうと鷲巣氏は述べた。
三浦氏のもう一方の問いかけ、加藤と鶴見の交流の始まりやその密度をめぐる質問に対し、鷲巣氏は戦後初期の鼎談(南博・鶴見・加藤)に言及しつつ、そこでの鶴見は加藤をそれほど評価しているようには読めないし、以後もそれほど親しくしてきたわけではないだろうと証言した。『思想と科学』に加藤は一度しか書いておらず、おそらく依頼がなかったのだろう(「「テレビ」一千台万歳」1962年7月号。なお、寄稿以外には1961年8月号に久野収との対談があるのみで、ほかには思想の科学研究会編『共同研究 転向』のための座談会に参加している)。互いに多少の違和感を抱いている仲だったはずで、ずっとのちの1999年の『潮』誌の連載対談(『二〇世紀から』潮出版社、2001年)は面白いが、それはまさに両者の立場が違っており、その違いについて語られているからだ。それは「二重唱」であって、斉唱ではない。鷲巣氏によると、1999年の時点では、2人はそうしたことができるだけの関係になっていた。
伊達氏もまた、鶴見と加藤の関係について応答し、前者のメキシコ行きが後者の示唆によりなされたことに触れたのち、『加藤周一著作集』第8巻(平凡社、1979年)の月報として書かれた鶴見の「加藤周一の流儀」を取り上げて、そこから頻繁な交流の印象を受けることはできないが、「読書案内人」としての加藤に鶴見が受けてきた恩義はよく伝わってくると評した。
閉会にあたり、2人の司会がそれぞれ簡単なコメントを述べた。半田は上述のやり取りを受けて加藤と鶴見の初期の関わりについて補足し、1949年に南博および鶴見との鼎談(『人間』9月号)を行った際、加藤が当時の日記(加藤周一文庫デジタルアーカイブで閲覧可能な《Journal Intime 1948-1949》)において南に言及しつつも鶴見についてはひとことも触れていないという事実を紹介した。やはり加藤と鶴見の付き合いは、次第に親密さを増していく、というかたちでなされたのだろう。
片岡はまず、「宗教の破片」を拾い集める者としての知識人を語る林達夫「邪教問答」(1947年)に言及し――なおこのテクストは落合勝人『林達夫 編集の精神』(岩波書店、2021年)において印象的に論じられている――、特定の宗教が社会生活を律しえなくなったあとになお残る宗教的なものの探求という観点が林と鶴見に通底するものであることを示唆した。伊達氏は短く応答し、鶴見は『柳宗悦』(1976年)において柳の民芸品蒐集を宗教的関心と結びつけていたと指摘することで、片岡の示唆を直ちに裏付けた。
最後に片岡は、伊達氏が繰り返し強調した鶴見のタヌキ愛好からの連想で、大童澄瞳『映像研には手を出すな!』第4巻(小学館、2019年)所収の作中作品『たぬきのエルドラド』を紹介した。環境保護を志向する人びとと開発の自由を求める人びとの対立という構図を「たぬきの意思」によってユーモラスに突き崩してみせるこうした現代の才能のうちに、鶴見的なものはしっかりと受け継がれているのかもしれない。
報告者:半田侑子(立命館大学衣笠総合研究機構研究員/第一部担当)・片岡大右(批評家、東京大学非常勤講師/第二部以降担当)








