今学期最後の課題本には加藤周一『三題噺』(ちくま文庫、2010年)を選んだ。これはある意味で変化球である。加藤の半生を知るのに有用で手に取りやすい本としては、まずは『羊の歌』(岩波新書、1968年)に指を屈するのが順当だろう。だが、正続二巻ある分量なのと、この「半自叙伝」にはかなり「フィクション」が混ざっていて、上手な距離感で読み解くのは案外難しい。主著『日本文学史序説』(1973〜74、78〜79)も文庫になっているが上下二巻本で(ちくま学芸文庫、1999年)、これも1、2回の授業でこなすのはハードルが高い。今学期の後半は、戦後を代表する知識人として鶴見俊輔の『北米体験再考』、竹内好の『日本とアジア』を読んできた流れでの加藤周一なので(なお丸山眞男はこの授業ではまだ読んでいない)、『中国・アメリカ往還』も候補に考えたが、平凡社の『加藤周一著作集9巻』(1979)として出ているこの本は、文庫や新書の形では刊行されていない。
そこで、手頃な厚さで文庫化されている『三題噺』を選んでみたのである。変化球だというのは、加藤自身は「あとがき」で「この本は短編小説集ではない」と述べているのだが、普通は「評論家」と目される加藤周一の「短編小説集」(鷲巣力による「解説」)という珍しい部類の本だからである。それをあえて取りあげるのは、風狂と言えば風狂だが、最近の加藤周一研究の流れに沿う部分もある。実際、これまであまり光が当てられてこなかった「小説家」としての加藤の側面に注目する必要性も認識されつつある(岩津航『レトリックの戦場——加藤周一とフランス文学』丸善出版、2021年)。
加藤の本としては珍しい部類とはいえ、鷲巣力の周到な「解説」が指摘するように、最初は1965年に筑摩書房から単行本として出版された『三題噺』は、「加藤周一の七十年にわたる執筆活動の「転換点」に位置する重要な作品」と言える。鷲巣によれば、加藤周一(1919〜2008)の著作活動は3つの時期に分けられる。第1期は旧制高校時代から『羊の歌』が出る1968年頃まで、第2期が1980年代末頃まで、第3期が1990年代以降である。そして第1期には3つの「出発」があったという。「いくさの日々」のなかで戦争に疑問を抱き、医学を学び、文学を志して作家となったのが「第一の出発」。フランス留学(1951〜55)に出かけたのが「第二の出発」。そして「第三の出発」は、カナダのヴァンクーヴァーにあるブリティッシュ・コロンビア大学で日本の文学と美術を研究し教えるようになったことである(鷲巣力『加藤周一を読む――「理」の人にして「情」の人』岩波書店、2011年)。「フランス文学研究」中心から「日本文学史研究」中心へと軸を移した加藤がヴァンクーヴァーに過ごした1960年代の約10年間は、「蓄積の時代」と言われる。その移行期にあって、初めから「青雲の志」を持たなかったという加藤が、こう「あり得たかもしれない三つの人生」を、石川丈山、一休宗純、富永仲基の3人に託して書いたのが『三題噺』なのである。
考えてみれば、鶴見俊輔(1922〜2015)の『北米体験再考』(1971)も、著者の人生のほぼ折り返し地点で書かれた著作で、かつての自分には見えていなかった米国の側面を、社会主義と同性愛についてはマシースン、ネイティヴ・アメリカンについてはスナイダー、黒人についてはフェザーストーンとクリーヴァーの目を通して描いたものと言える。加藤の場合も、キャリアの転機において「日本文学史」を構想するに当たり、日常生活は石川丈山、情愛生活は一休宗純、知的生活は富永仲基においてそれぞれ最も徹底していたと見定め、各人の伝記的事実を踏まえつつも、残る謎は想像力も交え、3人について語ることを通して自分のなかの鼎立する傾向を、確認しながら開発している。小説として書いたのは、3人の伝記的事実には不明な点も多く、また加藤自身も研究途上にあったからではないかと鷲巣は述べている。3つの章の文体が互いに異なっていることは一目瞭然で、加藤の力量と教養と精神の自由自在な様子に瞠目せざるをえない。
さらに言えば、詩仙堂を造営した石川丈山、破戒僧と言われた一休宗純、儒教・仏教・神道を比較の観点から論じた富永仲基の3人は、宗教学の観点からもそれぞれ関心を引く。特に仲基は、19世紀の西洋において成立する宗教学に先駆けて、比較宗教学的な研究を行なったことでも知られ、その人物を加藤が高く評価していたことも興味深い。
*
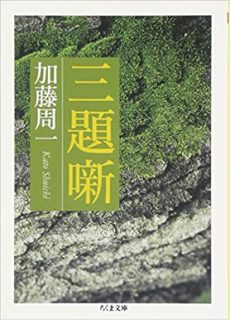
加藤周一『三題噺』ちくま文庫、2010年。
「詩仙堂志」は、加藤自身と思しき人物が詩仙堂を訪れ、そこで出会った老人と石川丈山について議論をする筋書きで、最後に消えたその老人が石川丈山その人ではなかったかという述懐で終わる不思議な話である。文体は漢文を基調とした日本語で、森鴎外を思わせる叙述が出てくる。槍の名手として家康に重んじられた三河武士である丈山は、大坂夏の陣で軍律を破って先駈けを企て、その後は槍を筆に持ち替えて庵を結び詩作に耽るも、詩を作ること自体が目的とはならず、庭を掃くことも詩作に匹敵するような、豊かな日常を静かな時間とともに生きた。
「狂雲森春雨」は、一休宗純と情愛で結ばれていた森という盲目の女性の語りを通して、官能の世界に生きる禅僧の姿が描かれる。『源氏物語』から谷崎潤一郎までを思わせる和文を基調とする文体によって息の長い語りのなかで描かれる情景は、男女の視点が一文のなかでも入れ替わり立ち替わりして、二人の孤独が溶け合い、語り手が強い個として析出してくる契機は弱い。それは五感では最も知的とされる視覚を奪われた女性による語りという設定とも関係していて、感覚的で官能的な情愛を通して身体の境界も揺らいでいるようである。加藤がここで描くのは「頓智の一休」でも「高僧の一休」でもなく、「情愛の一休」である。僧でありながら罪の意識のない彼の情愛に触れて、最初は有徳の人を罪深くしてしまうのではと恐れていた森も、次第に今ここの命が彼とともにあることを、ありがたく思うように変容を遂げていく。
「仲基後語」は、加藤自身に相当する人物が東京の記者という触れ込みで、京都タワーと思しき塔から霊媒師に富永仲基および彼の周辺にいた人物を次々と呼び出してもらい取材するという設定で、大坂の町人に生まれて学問に身を捧げた富永仲基の人物像をモンタージュの技法で浮かびあがらせようとする。弟の仲重が兄である仲基のことを「一種の怪物でした」と評したかと思えば、この兄弟にとって異母兄である長兄の吉左衛門は商家に学問は不要と厳しい。妹は「ほんとうは優しい兄だった」と言い、現代に伝えられていない著作『説蔽』について仲基は「焼かれた」のだと説明するが、その処分に関係したと思われる大坂奉行所の役人は役所対応で責任を取らない。農民の生活に心を砕いた同時代人の安藤昌益は富永のことを「要するに大坂町人」と決めつけ、自然哲学の体系を組み立てた三浦梅園は「あの男には天地自然の構造をあきらかにするということがなかった」とにべもなく、加藤の分身が反論する。身体を持たない霊ゆえに精神が知的に純化される方向でやりとりが進む工夫が凝らされているのがポイントである。
3つの話はそれぞれ日常・官能・知性を徹底させた人物についての物語という理解で基本構図は押さえられるが、少し視点をずらすと、「詩仙堂志」における父子関係の葛藤、「狂雲森春雨」の時代背景が応仁の乱という「いくさ」であることなども読みどころである。「仲基後語」にも仲基と関係のあったという想定の女性を登場させるなど一休的なモチーフが見られる一方で、「詩仙堂志」では丈山が女性を近づけた一休を批判するなど、話が入り組みながら糸でつながる線も見える。
*
フランス文学研究から日本文学史研究へと軸足を移した時期の作品だけあって、本書にはフランス文学研究に負っていると思われる見方も、ところどころ顔を出している。「仲基後語」で明示的に言及されるヴォルテールやド・ラ・メトリだけでなく、「詩仙堂志」で相手の老人が「できあがった詩はどうでもよかった、誰がよんでもよまなくてもよかった、読者は要らない……」と言明するのは、ヴァレリーの「テスト氏」はもちろん、ベンヤミン「翻訳者の課題」の冒頭も髣髴とさせる。富永仲基の霊が「詩は文字でつくるものだ」と述べるのに反応して、「あっ、それはそのまま……」と反応する加藤こと東京の記者の念頭に浮かんだのはマラルメの名だと思われるが、そこを仲基は「徂徠学でしょう」と切り返す。「人生の歓びというもの、これはあなたの小指の先が膿んで傷めばそれだけで崩れ去るものです」と仲基に語らせる加藤からは、たとえばアランの『幸福論』の一節を想起することができる。もはや「身体」を持たない霊として「純粋な精神」において語る富永仲基との対話は、ヴァレリーの対話篇『エウパリノス』を思わせる。
感覚的な知性も尊重し、官能を認識から排斥しない態度。死者との対話も含めて、人間の世界を拡張する方法。これらは、ヴァレリー的と形容することができるだろう。加藤周一におけるヴァレリー的傾向は、なにも『三題噺』にかぎらないが、この本において特に色濃く観察できるようにも思われる。また本書は、加藤の作品として必ずしも広く知られているわけではないが、前後する世代の日本の作家の作品とも相通じる面が認められる。たとえば、旅先で日常生活を語るうちに幽境に遊ぶ「詩仙堂志」の展開は、同じくヴァレリーの影響を受けた加藤よりも年長である吉田健一(1912〜77)の『金沢』(1973)や『怪奇な話』(1977)と似ているところがある。加藤より年少で親交もあった辻邦生(1925〜99)は、『嵯峨野明月記』(1973)では3つの異なる文体の語りを駆使して戦国の世と美の物語を紡ぎ、『西行花伝』(1995)では語り手が霊媒を通して呼び出された死者との対話をも含む形で、すでにこの世にいない西行の姿をモンタージュ形式で立ちあげていく。
*
『三題噺』で最も多くの紙幅が割かれているのは富永仲基で、加藤が3人のなかでも特に高く評価した様子が窺える。文庫本に収められている湯川秀樹との対談「言に人あり」(初出は『図書』1966年12月号)も、おもに仲基をめぐってのものである。その後、加藤は『日本の名著18 富永仲基・石田梅岩』(1972)を編み、さらに戯曲『消えた版木――富永仲基異聞』(1998)を書くなど、入れ込みようが伝わってくる。
富永仲基が考案した「加上」という方法は、後説が前説に対してどのように出てきたかを記述するもので、これは各宗教においてどの経典が最も権威を持つかという正統性をめぐる論争にも、自分にとってはどの経典が最も必要かという実用的で主観的な態度にも、抜き難く潜んでいる神学的で絶対主義的な姿勢を批判し乗り越えようとしたものである。また、富永は「くせ」という言葉で、仏道(インド)の特徴は幻術、儒道(中国)の特徴は文辞、神道(日本)の特徴は神秘であることを示そうとした。日本の特徴とされる神秘とは、ものを隠そうとすることで、言い得て妙である。「加上」は思想史や系譜学のアプローチに、「くせ」は文化人類学や地域間比較研究に道を開くものであると言える。対象との向き合い方や議論の立て方が斬新で、近代の学問の流儀を先取りしている。加藤周一にとっても、富永仲基の「発見」は驚嘆すべきことだったようで、学問を修めた大坂の町人が短い生涯のうちに新しい学問の地平を切り拓いたことに瞠目している。
加藤は『日本の名著18 富永仲基・石田梅岩』において、「仲基の立場は江戸時代においてまったく例外的であり、梅岩の態度は〔……〕江戸時代において典型的である」と二人を対照させている。劉争は『「例外」の思想――戦後知識人・加藤周一の射程』(2021)において、「例外」の概念に注目して加藤の『日本文学史序説』を読み解いているが、仲基を「例外」と見る加藤の視座は劉の議論に通じる。仲基は儒・仏・神の三教それぞれの思想史的発展を加上の原理で説明しようとしたが、梅岩は三教の共通点を「心」に還元して三教一致を説いた。仲基は夭逝した孤高の天才だが、梅岩は60歳まで生きて多くの弟子を育てた。
ところで、仲基の「加上」も「くせ」も記述的な学問のあり方に関わっているものだとすれば、彼が規範的な実践の道として説いたのは「誠の道」である。それは次のように説明される。「今の習慣に従い、今の掟を守り、今の人と交際し、いろいろな悪いことをせず、いろいろとよいことを実践するのを誠の道ともいい、それはまた、今の世の日本で実践されるべき道だともいえるものである」(『翁の文』)。世の習慣に倣うよう勧めるこの教えは、『出定後語』を読んだ本居宣長をして「見るにめさむるここちする事ども多し」と評さしめた仲基にしては、平凡であるようにも見える。この点をどう考えればよいのだろうか。
日本の宗教学は、この記述的な仲基と実践的な仲基の関係を、どのように評価してきたのだろうか。宗教学者の脇本平也は、『近代の仏教者』(1967)において、次のように述べている。「仲基は、あらゆる既成の伝統的権威から自由であった。いかなる宗教的ドグマも、思想的イデオロギーも信じなかった。儒・仏・道の三教を論ずる場合にも、そのいずれか一つを絶対的によしと信じて弁証論を展開するのではなかった。これらを、いわば傍観者としてながめる。そこに仲基の理論の基本的性格があった」。とはいえ、このように「特定の思想や宗教から超然たる仲基のこの立場」は、「それらの意味や価値を全的に否定してしまう虚無主義のそれではなかった」。むしろ「あらゆる思想」に「相対的な位置を与え価値を認めよう」とする「ヒューマニスティックな立場」であると脇本は言う。
島薗進は『宗教学の名著30』(2008)において、『翁の文』と『出定後語』は「東アジアにおいて宗教学的な思考のある種の側面が世界に先駆けて発達していたことを教えてくれている」と述べている。その一方で、「誠の道」については「理を超えたものではなく、理の内にあるもの」と指摘し、「現代において宗教を問う者」にとっては「「誠の道」の提唱で足りるかどうか、強く肯くこともできないだろう」と、一種の物足りなさを表明しているようにも思われる。
加藤周一は戯曲『富永仲基異聞――消えた版木』(1998)において、仲基の知的ラディカリズムと平凡な常識を説く態度のあいだの齟齬について謎解きをしている。仲基の『説蔽』は現在に伝わっていないが、それはたんに歴史に埋もれて発見されていないのではなく、検閲や言論弾圧によって歴史の舞台から姿を消したのではと加藤は想定している。仲基のいた懐徳堂は、官許の儒教の学問所で、『説蔽』は徳川の体制イデオロギーである儒教を批判するものだったから、当局から睨まれて出回らなかった。一方、『出定後語』において展開される加上は、仏教批判だったから見逃してもらえた。自分に残された命がそう長くないことを悟った仲基は、『出定後語』の出版に続けてぜひとも『翁の文』を出版したいと考えていたが、そこへそれまで保管されていた『説蔽』の版木が盗まれたらしいとの情報が入る。『翁の文』には「加上」の原理が儒教にも仏教にも神道にも適用されることが書かれている。『説蔽』の版木が消えたことは、『翁の文』を出すなという「脅し」に相当する。そこで仲基は用心から、『翁の文』に工夫を凝らすことにした。つまり、自分の見解をそのままの形で発表するのではなく、ある翁から聞いた話として、フィクション仕立ての距離を設けたのである。そして、翁の三教批判は舌鋒鋭いが、仲基は三教にはそれぞれよいところもあり、「三教の道」も「誠の道」にはかなわないと述べる役回りを演じさせている。
『日本文学史序説』において加藤周一は、「徳川体制の武家独裁の下に、富永仲基の他の学者に対する影響が極めて限られたものであったことは、あらためていうまでもない」と述べている。ここには、徳川政権が独裁的であったこと、富永が孤高の天才であったことが示唆されている。これに対し、宮川康子は『富永仲基と懐徳堂――思想史の前哨』(1988)において、「仲基が生きていたのは、商業中心地大坂の都市空間であり、そこには身分的な枠をこえて話し合うことのできる知識人のネットワークがあった」と述べ、彼を当時の知的文脈のなかに置きなおして天才仲基の「偶像」を相対化している。「誠の道」についても、加藤はそれを特権的な知性の持ち主である仲基の言論弾圧回避のための方便と見ていたとすれば、宮川は仲基には誰でもが知る「あたりまえの理」に道を求める態度があったとし、「万人」が「理性」によって「活発」な「議論」を交わす「社会的公共性」の方向性でこれを考えている。
*

受講生のS・Nさんは、富永仲基が「誠の道」を説いたことについて、思想を突き詰めることと実践的な格率としての「常識」は両立するのではないかと述べた。その際、今学期の鶴見俊輔の回で紹介した『たまたま、この世界に生まれて』(2007)を参照して、「狂った人間が集まって狂ったことを話し合っている」なかから「穏当な思想」としてのプラグマティズムが析出してきた事実を鶴見たちが評価していることを指摘してくれた。
S・Kさんは、『三題噺』で取りあげられる石川丈山、一休宗純、富永仲基の3人は、いずれも権力や権威から距離を置く生き方をしたことから、今学期の前半で取りあげた出口なお、金子文子、茅辺かのうの3人の生き方にも似ており、アナーキズムと結びつけて考えることもできるのではないかと述べた。加藤周一をアナーキストと見なすのは一般的とは言えないが、たしかにアナーキストの要素を加藤に見出すことも不可能ではないだろう。
N・Mさんは、加藤の晩年の著作『日本文化における時間と空間』(2007)において提示される3つの異なる時間の型、すなわち第1に始めも終わりもない円周上の循環としての日常的時間、第2に始めと終わりを持つ人生の不可逆性に特徴づけられる普遍的時間、第3に始めも終わりもない直線としての歴史的時間を提示し、その観点から『三題噺』における時間の分析を試みた。石川丈山の人生において支配的なのは日常的時間、一休宗純の場合は一回性を重んじる普遍的時間、学問の発展に期待をかけた富永仲基の場合は歴史的時間と整理するとすっきりしそうだが、そう単純に言えるわけでもなさそうだ。しかしそれはN・Mさんが『三題噺』をよく読み込んだからでもある。『三題噺』における3人についての叙述を『日本文学史序説』における叙述と比較する発表なら想定範囲内だったが、加藤の「到達点」と言える著作から「転換点」をなす著作に光を当て、その特徴を掴もうとする発想はこちらの想定を超えていた。
学期の最後を飾るにふさわしく、これまで読んできたものとのつながりを意識したり、別の著作まで読んできたりと、力のこもった発表が多かった。
報告者:伊達聖伸(総合文化研究科)








