2021年12月27日(月)13:00より、「部屋と空間プロジェクト」シンポジウムが行われた。司会は田中有紀(東洋文化研究所)が担当した。
最初に、大石和欣(総合文化研究科)氏が「詩学としての都市空間と家、そして室内空間」として基調講演を行った。本講演では『家のイングランド:変貌する社会と建築物の詩学』で取り上げられなかった家や空間に関する様々な理論を紹介した。「イングランドといえばコテッジ」という表象が形成された背景には、19世紀後半頃のイギリス農業および農村風景の衰退に伴い、文学で農村を理想化して描かれるようになったことがある。大石氏は、ブルデューの「構造化された構造」には含まれない、日常的な詩学としてのハビトゥス論を考える。

日常性の詩学としてのハビトゥスを考えるために、多木浩二『生きられた家:経験と象徴』(青土社、1984)も参考になる。そこに見えるのは、「生きられた」、つまり無意識でありながらも実存的に生きられた空間としての家、さらに私たちがそれをどう経験するかがトポスとして見えてくるという哲学である。この哲学を、文学や歴史、建築学の中でどう消化していくのか。家に関する「夢想」がどう私たちの思考を形作っていくかというガストン・バシュラールや、手触り・においなど感覚で構成される空間認識を論じたイーフー・トゥアンなど詩学的な空間論も参考になるが、より実存的に論じたのがメルロ=ポンティである。彼は「空間の知覚とは、特殊なクラスの〈意識状態〉とか作用ではないのであって、そのさまざま諸相は、つねに主体の全生命を表現し、主体がその身体及びその世界をつらぬいて未来へ向かうためのエネルギーを表現している」(モーリス・メルロ=ポンティ『知覚の現象学』竹内芳郎・小木貞孝・木田元・宮本忠雄訳、みすず書房、1967-74)と述べる。大石氏はこの「エネルギー」をめぐり、家への自身の強い興味は、幼少期に家族と過ごした家屋の匂いや感覚がエネルギーとなって、無意識に自分を動かしていたことによるのではと言及した。マルティン・ハイデガーは「空間」と「存在」について、「気遣い」という言葉で表現する。ある空間があったとき、それは単にハコモノでしかないが、そこに人が入り、手を施すことによって(=気遣う)、空間に意味をもたらす。そして今度は空間が人に意味をもたらす(=気遣う)。ハイデガーはこれを家にも応用し、家を建てることは、天と地の間に自分の存在を位置づけることだと考えた。
そもそもハビトゥスとは何か。もともと「持つ、所有する(habēre)」に由来するラテン語“habitus”は、『オックスフォード・ラテン語辞典』によれば、1)存在のあり方、状態、2)立ち居振る舞い、表現、態度、マナー、3)着こなしや生活様式、4)身体的性質、5)身体構造・体格・姿という複数の意味を持つ。また“habēre”からは、「住む、居住する」を意味する“habitāre”も派生し、英語ではすべて“habit”のなかに流れこんだ。つまり“habit”とは、存在のあり方、立ち居振る舞い、着こなしやどういう衣装をきるか、生活スタイル、体格など全てが含まれ、それは文学作品という表象の中にも現れてくるのである。そのため、空間に対置した人間の身体的性質、その性質の延長で建築物や空間を捉える必要がある。エドモンド・フッサールのいうような、心にこびりついたハビトゥスを、文学作品から、どう読み解き、言語であらわすかが課題であるが、文学は言葉によって時間・空間を著すという前提も持つ。たとえば夏目漱石の『門』が描く空間と家の構造の中には、罪悪感にさいなまれながらひっそり生きる夫婦の苦悩が見いだされる。サラ・ウォーターズの『寄宿人たち』には、19世紀のロンドン郊外にいる女性が、確固たる生活を支えている家が崩れ、親しみのある空間が不気味な空間に変わる様子が描かれる。また、時間と空間の関連についても注意する必要がある。マルセル・プルースト『失われた時を求めて』は、11世紀から存在する村の小さな教会の歴史性を描写しながら、主人公の過去から現在に至る想念を描き、建築物や空間にハビットとして埋め込まれたものを、フランス語ならではの繊細な時間感覚で描写する。
『家のイングランド』で論じた、多層的時間が共存する複合混成態(コングロマリット)としての空間は、ヴァルター・ベンヤミンの複合形態(コンフイグラツイオーン)という概念から借用した概念である。ヨーロッパでは古い家が好まれるが、家は手をかけることによって、前に住んだ人の時間の上に、新しい、異なる時間が積み重ねられていく。ロラン・バルト『記号の国』が描く上野の地下街は、「ローマの建築物が地方に根付き、その土地の文化に触れてヴァナキュラーな形で変質していく」というロマネスクという語の本来の意味が示すように、表面的には西洋化している上野の地下街にいるホームレスの人々にこそ、そのロマネスクな本質が具現しており、そのヴァナキュラーな形態の中に、上野の本質が浮かび上がっている。
続いて、田中有紀が「森本厚吉の住宅論:「実行」と「信仰」の偉人リビングストンと文化アパートメント構想」として報告を行った。消費経済学者として知られ、女子経済専門学校を創立した森本厚吉(1877-1950)は、1920年に「文化生活研究会」を設立し、日本初の鉄筋コンクリート5階建ての「文化アパートメント」を建設した。彼が目指したのは、アメリカ式「文化生活」の普及であり、中流階級が、優れた技術で支えられた「能率的」共同生活を送り、社会全体を導くことだった。本報告では、森本と有島武郎の共著『リビングストン伝』を再読する。彼らはリビングストンの人生を「煉獄」「実行の苦痛多き生涯」と捉え、最終的に「信仰の生涯」へと入ったと考える。報告では、このようなキリスト教的価値観が、のち、住宅論という生活における具体的な実践として、森本の中でどのように結びつくのかを考察した。

最も身近な生活、住宅に目を向けた森本は「習慣性」が形作る人間の思考や行動に注目した。高遠な道徳、理想を語る前に、まず生活を改善することを考えた森本は、自身とリビングストンを重ねる。森本にとっての天職とは経済問題の解決であり、リビングストンにとってのそれはアフリカ探検である。仕事を全うしたのち、やっと道徳の段階に進む。森本は中流階級がリードする国民全体の福利増進を目指し、リビングストンはキリスト教伝導へと進むのである。森本が目指す生活では、「自分もなまけてはならないし、他人もなまけてはならない。」彼は中流階級にも、それぞれが天職を全うするため、合理的生活を送りつつ、日々努力を続けることを求め、それによって、社会全体の改善をはかる。彼の住宅論では、仕事の空間と家庭の空間が連続しているのだ。彼が構想する文化アパートメントでの、アメリカ式共同生活の背景には、北海道での、共同体の中にある信仰・西洋文化がある。森本の住宅論とそれを支える消費経済学には、札幌農学校時代の経験が生かされているのではないか。「家」という人間を取り囲む身近な存在から、習慣を改め、ひとりひとりを目覚めさせ、世の中を改革するという理想は理解できる。しかし、札幌農学校での経験はあくまで森本個人のものであり、彼が主導した「空間」「住宅」に住んだとしても、人は「なまけ」て、「非能率的」な生活を送るかもしれない。そこでの生活では、森本の経験とは別の、新しい経験が積み重ねられていくのだろう。
前野清太朗氏(EAA)は「台湾「うた」空間の再脱日本化とノスタルジアの変容」として報告を行った。イーフー・トゥアンが『個人空間の誕生』で論じたように、近現代社会では公的生活からの引きこもりが追求され個人化が進んだ。しかし現在、世界的に引きこもることが求められる中、公ないし共への再接続の欲求が生じている。そこで注目されるのが「声」によって他者と世界を共有し、身体的に他者と共鳴することである。空間を超越する「うた」から、身体的に隔離された状況において社会的につながり続ける糸口を探ることはできないだろうか。前野氏は、国歌や唱歌など国民統合を目指す大きな「うた」に対し、小さな「うた」(俗謡)としての台湾語演歌に注目する。
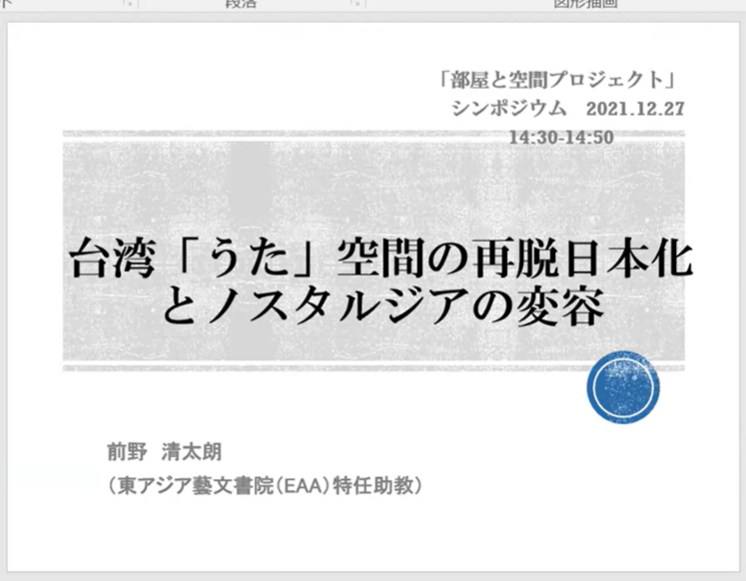
日本植民地期には、伝統的な「歌仔」に対し、日本の唱歌や流行歌の影響を受け、自由律化し、音の間がつながる非歌仔風歌が出現した。戦後、1945-1950年代に国民党による権威主義的統治と弾圧が行われた際、民族融和を訴える隠喩歌が流行する。それらが緩和される1950年代中頃に、中国的台湾民謡の採集が行われた際、元来の歌仔のみならず、日本統治期の台湾語歌謡曲も混ざりこみ、1960-70年代になると最新の日本の曲を用いた台湾語カバー曲(替え歌)が続々と発売されるようになる。また、日本の演歌の「こぶし」が取り入れられ、戦前曲と戦後曲がいずれもカバー後に「こぶし」入りとなり、日本風台湾語「演歌」が完成・定着すると、今度は祭囃子が挿入されるなど、原曲にない「日本風」を加味してカバーされていく。1970-80年代には俗謡としてマスなTVメディアから排除されLPベースで聞き、歌い継がれていった。1990年代以降は、戦前の「歌仔」でなく、日本風台湾語演歌がノスタルジアの対象になっていく。このような「うた」は歌謡教室や村の廟の前で行われる宴会・カラオケなど、人々が限定的ながらも身体的・主体的に参加し、日本人がいないことが前提の小さな共通性の空間で歌われ、新たなノスタルジアの対象になっていく。このノスタルジアで想起されるイメージは、「演歌」を好む田舎の父であるが、その父はもはや戦後生まれで、歌っているのも日本風台湾語演歌、さらには廟の村内放送が盛り込まれる曲もあり、もはや日本人に通じない「日本風」となっている。この戦後に生まれた「台湾語演歌」ジャンルは、国(民)歌のような「大きなうた」ではなかったが、1990年代以降、人々のノスタルジアを伴うようになることで共通記憶的な「大きなうた」の性格をもつ曲も現れた。しかし「大きなうた」は公的空間でのみつながる孤独な個人を生み出す。「公的につながる孤独な個人」の近代的矛盾を克服するため、いまメディアツールを飼いならす必要があるのではないか。身体のあいだ(intercorporeity)が隔離された状況で身体的に「小さなうた」を「うた」いながら小さな「(共)空間」を再建する。コロナ禍のオンライン上で行われた様々な「うた」に関する試みも、この矛盾を克服するための一つの動きであるといえるだろう。
最後に白佐立氏(教養教育高度化機構)が「暮らしと住まいの「弁証法」:ある戦後台北への都市移住者の聞き取りから」として報告を行った。戦後台湾では急速な都市への人口移動が発生した。地方から大都市に移住する人びとは身一つで都市にたどり着き、寄寓や借家住まいなどを経て、自身に適した住まいを選び、整えながら定住に至った。本報告は1930年代に台北州深坑に生まれたある女性(ハナ)の生活史を取り上げ、彼女の住まいの変遷と暮らしの関係に着目する。彼女の住まいと暮らしの「弁証法」を考察することを通じて戦後台湾の都市移住者が都市で生き抜いてきた過程を描く。

1931年に台北州深坑の農家に生まれたハナは、成績優秀で、国民学校卒業後さらに教育を受けることを希望したが、母の反対にあい、十代半ばに、単身台北へ移った後、ずっと台北で暮らしている。仕立を生業とし誇りをもって営んでいる。細身・小柄で、少しせっかちではあるが、陽気でおおらかな性格であり、人に借りを作ることに強く抵抗感がある。活動的で、その元気さは近所の人からも一目置かれるという。
独身時代は最低限の住まいしか必要とせず、寄寓し、部屋借りして暮らしていた。結婚後、兄と合資だが、ハナ名義の非合法建築を購入し、兄に借りを作ってしまった。そこにはリビングルームのような空間と3つの部屋と半楼(ロフト)があった。リビングのような空間には仕立屋をかまえた。2部屋を間貸し、その収入は兄に渡した。1960年代半ば、政府が道路を拡幅するため、非合法建築群を撤去し、そこに住んでいた人々の定住先として「整建住宅」を建設し、低金利住宅ローンで提供した。ハナは「整建住宅」である南機場アパートメントのⅡ期の竣工時(1968年)に入居した。家族5人と住み込みの職人が暮らし、6.8坪の狭い面積で仕立屋を営んだ。竣工当時、南機場アパートメントⅠ期は台湾における最大規模かつ最先端の集合住宅であり、全ての住戸に専用台所・トイレ・シャワー、各フロアにダストシュートが備えつけられていた。住戸内は間仕切りがされず、すまい方は入居者に委ねられていた。
ハナは店の上部に半楼(ロフト)を設置し、さらにⅡ期の中に部屋を借り、家族の生活空間を確保したが、借りた部屋が店と離れていたので不便であった。店の真上の住戸が購入できるタイミングを狙いつつ、兄に借りた「情」を「返済」するために、自分の家を買い増やす前に、Ⅱ期の中の1つの住戸を田舎にいる兄の名義で購入し、兄の代わりにその住戸の貸し出しを管理した。真上の住戸の売り出し情報が入ってくると、すぐに近所や知人にお金を借りて頭金をつくり、住戸をおさえた。互助会を立ち上げ、住戸の資金を調達して購入した。2階の住戸で広い室内面積を確保するため、1階の庇を床として利用し、2階の住戸に2部屋増築し、1階の台所とトイレを撤去して店として使用できる面積を拡大した。また、スラブを抜き、1階と2階をつなぐ内階段を設置することで、アパートの共有階段を経由せず、直接店と家を移動できるようにした。増改築には近隣住民との折り合いは必要だが、ハナはしっかり自分の考えを持ち、よりよい住環境を構築できるよう不断に工夫してきたのである。人は住まいにあわせてどのような暮らしを送り、また自らの暮らしを築くためにどのように住まいを整えてきたのか、ハナの人生は我々に大きな示唆を与えてくれる。
前野氏が論じた、日本風台湾語演歌が作り出す、独特のノスタルジアが共有される小さな空間は、居住空間ではないが、大きな「うた」が作り出す空間から距離を置き、自らの意思で生まれていった、小さいながらも力強い空間である。こぶしあり、祭囃子ありの混沌とした空間は、客観的には理解しがたいが、歌謡教室や廟の前といった場の記憶とともに形成された、複合混成態としての空間といえるのではないか。また、森本厚吉が理想とした「なまけてはならない」文化アパートメントは、一見最先端の技術に支えられた合理的な集合住宅であるが、これもまた、彼の札幌農学校時代の思い出やアメリカ式生活への思いが、奇妙に絡み合って形成された混沌とした空間である。森本自身を取り囲んでいた札幌農学校の雰囲気が、彼にエネルギーを与え、お茶の水に独特の空間を生み出してしまった事例といえるだろう。そして、ハナが住んだような、近隣住民と折り合いをつけながら増改築を繰り返し、生活を展開していく狭小住宅には、一見私的な空間を築くのは非常に難しいようにみえる。白佐立氏はしかし、ハナにとっては、個人的な干渉はあったとしても、公的権力に介入されず自分の意思でコントロールできる場所であれば、それは私的空間なのであると述べる。1階の店舗と2階の住居をつなぐ階段の出来にこだわり、満足した表情を見せるハナにとって、家はまさに、天と地との間に自分自身の位置を定めていく手段であり、ハナが居住空間を気遣い、居住空間自体がハナを気遣う姿を、私たちは強く感じることができる。
このように、本シンポジウムで大石氏が提示した理論および田中・前野氏・白氏が提示した事例を関連付けてみると、特定の空間に取り囲まれている人々が、自らの生をよりよいものにするため、さらに新しい空間をかたちづくろうとするエネルギーを、無意識のうちに働かせていることに気づく。日本風台湾語演歌による小さな空間も、文化アパートメントも南機場アパートも、私たちにとってはなかなか理解しがたい、独特の空間であるからこそ、そこで人々がもがき、自らの理想を空間に託して形作り、その空間がまた自らを形作っていく様子が、よくわかる。その様子を、今度は私たちが客観的に眺めることでやっと、実は私たち自身もまた、空間を気遣い、空間に気遣われていることに気付くことができるのだろう。
報告者:田中有紀(東洋文化研究所)








