2021年6月21日、28日の東アジア教養学「世界歴史と東アジアIII」は、EAAセミナーとのコラボレーション開催という形式で、報告者(崎濱紗奈:EAA特任研究員)が発表を担当した(過去の講義については以下を参照:中江兆民『三酔人経綸問答』を読む、幸徳秋水『廿世紀之怪物帝国主義』を読む、鶴見俊輔『戦時期日本の精神史1931〜1945年』を読む)。
今回題材としたのは、近代沖縄を代表する知識人である伊波普猷(1876-1947)が1912年に行った講演「古琉球の政教一致を論じて経世家の宗教に対する態度に及ぶ」である(併せて、サブテクストとして『古琉球の政治』(1922)も参照した)。本講演は、1912年、第二次⻄園寺内閣内務大臣・原敬の主催で開催された、「三教会同」という宗教者会議に対する伊波普猷の私見を述べたものである。
日露戦争直後の当時の日本社会は、都市/地方、資本家/労働者といった種々の格差が発生するなど、急速な資本主義の浸透や富国強兵路線の遂行による歪みが各所で露呈していた。これを背景に社会主義思想も流行を見せた。その主導者と目された幸徳秋水が1911年、大逆事件で処刑されたことは周知の通りである。「三教会同」は言わば、こうした社会不安への対抗措置として画策された。この政策の中心人物は内務次官・床次竹次郎と宗教学者・姉崎正治であった。彼らは、宗教が、社会統合のための新たなメディアとして機能することを期待したのである。
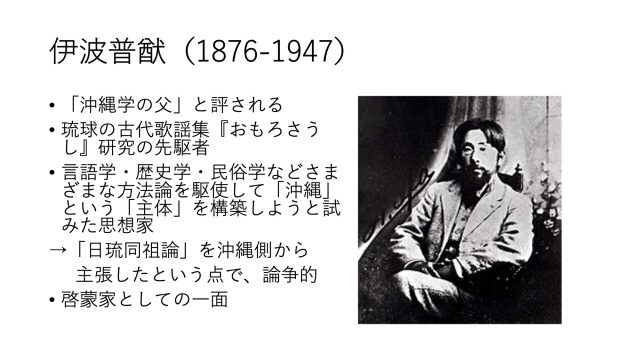
発表者スライドより
「三教会同」の結果は、床次や姉崎が期待したように芳しいものではなかった。しかし、帝都から遠く離れた沖縄で、伊波普猷はこの政策を高く評価した。ただしそれは、為政者の意図をそのまま受け容れるというよりは、中央の視点を自らの側に簒奪し利用する、戦略的な態度であったと言えよう。伊波の意図は次の点にあった。「進歩せる宗教」を普遍的理念として設定することによって、記紀神話によって日本民族を規定し、帝国の新たな参入者(「沖縄」「朝鮮」「支那」「アイヌ」「馬来」)を劣った存在と見做す自民族中心主義を批判すること。これにより、各々の「個性」(伊波の言葉で言うところの「無雙絶倫」=ユニークネッス)を尊重し、統合・包摂する新たなネイションとしての「大国民」を構成すること。言い換えれば伊波は、為政者の言説を借りながら、大日本帝国を、自らが理想とするところの普遍的な空間として書き換えようとしたのだ。
このような伊波の戦略的態度は従来の研究では肯定的に評価されてきた。しかし、本セミナーでは、次のような限界も指摘した。伊波の態度は、自民族中心主義から多文化主義へ、というより洗練された統治の言説を先取りすることによって、帝国日本という空間それ自体を補強してしまうという限界を内包していた。伊波が唱える「進歩せる宗教」というものも、あらゆる宗教を包摂する、言わばメタ宗教としての国家神道のあり方を、青写真として描き出してしまったと見ることもできよう。
だが、宗教に賭けた期待は、伊波普猷自身によって手放されることとなる。1910年代後半から1920年代にかけて沖縄を襲った経済危機である「蘇鉄地獄」がその大きな転機となった。資本主義の行き詰まりを目の当たりにした伊波は、もはや宗教によってこれを克服することはできない、と痛感した。そこで伊波が新たに踏み出したのが、郷土研究という領域である。柳田國男、そして折口信夫の手引きを得ながら伊波は、琉球の古代歌謡集『おもろさうし』をはじめとするウタの世界に沈潜していく。
しかし、ここでもやはり伊波の関心は宗教にあったと言えよう。なぜなら伊波は、資本主義に対するオルタナティブとして古代琉球の共同体を眼差す際、その共同体の核心にあったのは神への信仰であった、と考えたからだ。ただしここで言う宗教とは、制度化された宗教ではない。伊波によれば、制度化された宗教は、王の権威を担保するものとして利用され、奴隷(王の民として稲を納める者)を生む。伊波はこうした王と奴隷の関係性を「政治」と呼んだ(『古琉球の政治』)。伊波が理想としたのは、このような「政治」が生まれる以前の純粋無垢な共同体、すなわち神と人とが一体となった生活である。言ってみれば伊波は、より純粋な宗教のあり方を追い求めたのだ。

以上の議論を踏まえた上で、伊波の思想的な限界はどこにあったのか、というテーマでディスカッションを行った。参加者からは、「アイヌ」に対する伊波の眼差しから窺い知れる進化論的発想にまつわる問題点や、「ノロ(祝女)」や「ユタ」についての伊波の論じ方についてジェンダー論的見地から見た場合の限界が指摘された。また、本講義の主宰者である伊達聖伸氏(総合文化研究科)は、近代主義者でありつつも、資本主義への対抗として土着的な価値を評価するという伊波の態度は、ナショナリズムに関する議論で有名なエルネスト・ルナンにも通じる、と指摘した。また、国家以前の社会に関するピエール・クラストルの一連の議論と併せて検討する可能性についても言及された。発表者は最後に、資本主義の克服、という一大テーマに向き合いつつも、「政治」を徹底的に外部化し、「政治」なき共同体を理想化したロマン主義的な態度に伊波の限界があったのではないかと指摘し、セミナーを締め括った。拙い発表に耳を傾け、ディスカッションに参加してくださった皆さまに、改めて感謝申し上げたい。
報告者:崎濱紗奈(EAA特任研究員)








