2020年8月26日の昼下がり、一日で最も気温が高くなる時間帯に、わたしたちは東洋文化研究所大会議室に集まった。もちろん、適切な社交的距離を保ち、感染予防のためのアルコール消毒なども徹底した中での開催である。集まった目的は、いつものEAAの研究イベントや教育プログラムとはちょっと別の趣であったので、わたしは開催前から不思議にワクワクしていた。
EAAは、東京大学とダイキン工業株式会社との産学協創プロジェクトの一環に位置づけられている。いや、それ以上に、EAAが北京大学との東アジア学ジョイントプログラムとして発足することができた直接の原動力はダイキンの力強いサポートにほかならなかった。今回は、東大の人文系学問との協働を強化したいというダイキン側からのありがたいご提案を受け、いったいどのような協働のあり方が望ましいかについて、中島さんとわたし、そしてダイキンの東大産学協創スタッフとの間で議論してきた。わたしたちいわゆる「人文系」の諸学は、一般的に産学協同という場合にイメージされる、技術開発を目的とした研究協力はできないだろう。しかし、大学が大学であることの強みは、専門研究だけではなく、さまざまな分野の専門研究が、未来社会に活躍するべき人を育てる教育の場において束ねられていることにある。わたしたちは、ただ専門的な研究をし、そのための人材を育てるのではなく、人とは何か、人が人として生きる世界とは何かということ考える。それは、人と人、人と社会、人と技術、人と自然、人と世界などの諸関係について、さらには人とそれらを結びつける人を超えた何ものかについての、不断に答えのない問いを問いつづけることである。そして、こうした問いの中で共によりよき人になっていくために、大学という場を欲し、そこで研究と教育を行っている。これらの「人」をめぐる諸関係の問いのベースにこそ、人文学は存在し、その役割がある。
「科学」という近代的なことばは、「分科の学」という意味で言えば、個別の専門知とその体系を表している。人文学は、そのような専門知の体系の中でこそ「人文科学」と呼ばれるが、本来、人の学問は「分科の学」には収まりようがない。だから「人」とそれをめぐる諸関係に関する問いは「科学」の名にそぐわない。「人文科学」というより「人文学」とわたしが呼んでいる所以だ。そうすると実は、人文学はリベラル・アーツと言い換えてもいいものかも知れない。実際、中国語で「文学院」という場合、それは「リベラル・アーツ学部」を指す場合がある。
東大にも駒場のリベラル・アーツがある。わたしたちはそこで、問うことを学び、共に学ぶことで自分と周囲が変わっていく悦びを知る。それは、単に専門的な知識を消費する行為ではなく、共有の課題に共同で取り組む過程を通じて、自らが新しい価値を生産していく行為であるとも言える。これは「人」のあり方を示し、創造していくプロセスであり、とても人文学的な行為であり、同時に大学という場のほかに代えがたい魅力でもある。そうした共同行為をこの産学協創の中で実践していくことができれば、わたしたちは、大学と企業が社会に対して共同して追うべき責任の新しいかたちを世に示すことができるだろう。両者が協力の中で互いに変化し合いながら、人と社会に対して新しい価値のあり方を提示し、よりよい未来に向けた社会の変化を促していくのだ。

つまり、人の学としての人文学は変化を促すための智慧の実践(そう言えば「知の技法」というベストセラーが昔あった)をリードするものである。そこで、ダイキンと東大人文系研究のコラボレーションは、変化を促す学問の実践を参加者みなで実際に「やってみる」ことしかないということになった。やり方はシンプルだ。折しも院長の中島隆博さんがマルクス・ガブリエルと行った対談が書籍化されようとしていた。対話こそ哲学の原初形態であり、したがって人文学に共通する基礎であるが、世界でいま最も注目されている哲学者との対話がこんなに身近なところにあるのだから、これ以上の教材はない。そこで、参加者はこの『全体主義の克服』(集英社新書、2020年8月)を事前に読んだ上で、半ページ程度の感想を事前に提出し、それを踏まえてディスカッションすることになった。
当日のディスカッションは、中島さんとダイキンからの参加者13名、それにEAA東アジア教養学プログラム生4名が集まって(一部はオンラインからのリモート参加)、対話を行うかたちで進められた。しかし、その対話はわたしたちがともすればふだん注意することなく使ってしまっている言語や、あたりまえだと思ってしまっている思考の回路が、実は当たり前ではないかも知れないということを気づかせるようなスリリングなものだった。そのごく一部をかいつまんで紹介しよう。

参加者(以下P)「対話によってあたりまえだと思うことを疑うことが大切だと思います。」
中島(以下N)「では、対話って何ですか?対話によって何が開かれるんですか?」
N「実は哲学は対話的なものです。哲学者にあなたの思想はどんなものですかと聞いても気の利いた答えは返ってきません。なぜかというと、哲学というのはさまざまに異なる状況の中で対話することだからです。」
P「哲学を学ぶことで考え方の幅を広げることができそうです。哲学にはまるきっかけが生まれるといいです。」
P「哲学は距離が遠くて畏れおおいです。」
N「哲学にはいろいろなものがありそうですが、そうすると、哲学でないものはあるでしょうか?」
P「まったく哲学でないものはなさそうです。数式でしょうか。」
N「でも近代哲学は数学と切り離せませんね。」
P「そうするとやはりすべてのことが哲学ですね。」
N「歴史学は歴史を研究する、文学は文学作品を研究する、では哲学は何を研究するのでしょうか?」
P「哲学が哲学を研究するというのはおかしいと思います。」
P「わたしは工学専門ですが、それでもPhD、つまり哲学博士です。」
N「どうも哲学はほかの学問とちがってインチキな感じがしてきましたね。」
P「もしかすると、わたしも哲学をしているのかも知れません。」
N「そうすると、先ほど哲学にはまると言いましたが、ロックミュージックにはまるとか、源氏物語にはまるというのとはちょっとちがって、何か生活の態度とか、ものとの関わり方のことが哲学なのかも知れませんね。」
P「倫理的な価値を企業として訴えていくのは難しいと思います。」
N「では、倫理とは何かを考えてみましょう。みなさんはよりよく暮らせるような製品を提供したいと思っていますね。この〈よりよく〉というのが倫理です。倫理は名詞ではなく副詞で説明すべきものです。」
N「でも〈よりよく〉を説明するのは難しいことです。なぜならそれはものごとへの関わり方そのものだからです。それを経済的価値とどうやって結びつけましょうか?」
P「企業でも倫理的な価値を目指し始めていると思います。」
N「そうですね。単によりよい製品を作る競争だけではもう限界ですからね。だから〈よりよく生きる〉ためにどうすればいいかを考えるのは当然ですし、そのためにはおカネとは何かということについても考えていく必要がありそうです。」
N「民主主義とか価値と言われているものはいったい何種類のものがあるのでしょう?来たるべき価値とは何でしょうか?これも同様に〈よりよく〉のように副詞的に考えられないでしょうか。」
P「価値相対主義は困ると思います。子どもを虐待する自由はないので、その良し悪しを人に任せることはできません。」
N「しかし、それをどうやって説得力を持って説明しますか?」
P「子どもの人格にも尊厳があるからというと思いますが……。」
N「しかし、人格とか尊厳という哲学的なことばはよくわかったようなわからないようなことばですので、口ごもってしまいますね。むしろ、直観に信頼を置いたほうが腑に落ちる感じがします。そして、直観こそはいまの哲学の話題です。」
思いがけない問いであり、答えのない対話ではある。だが、一時間半の予定時間はあっという間に終わり、参加者各人はこのレッスンを受けて、再度コメントを提出することになった。それを中島さんは「あとがき」と呼んだ。「あとがき」という唐突なことばにみなが一瞬戸惑ったようだった。しかし、今回のレッスンはわたしたち参加者相互の哲学の実践であり、それ自体がある状況を背景に行われた豊かな対話のテクストだと考えると、「あとがき」という言い方も素敵な響きを持つようになる。「あとがき」は本の作者に与えられた特権である。だから、このように呼ぶことによって、わたしたちは、共同作業としての哲学の「テキスト」を共に編み上げた共著者になるのだ。しかも、そのプロセスでは、わたしたち自身のものごとに対するかまえ方が、何か別のものへと変わっていく感覚を味わったはずである。そういう経験を共有することが今回の目的だったのだと、中島さんと参加者一人一人との応酬の中からは浮かび上がってくる。もちろん、このような協働の積み重ねこそが、スローガンでも知識でもなく、わたしたち一人一人が「全体主義の克服」を実現するための具体的な実践であることは言うまでもない。
知識を消費するのではなく、世界の想像と創造に具体的に関与すること、それは哲学のみならず人文学全体が本来もっているはずの尊い意味であろう。大学と社会との新しい協働のかたちをここから作っていきたい。
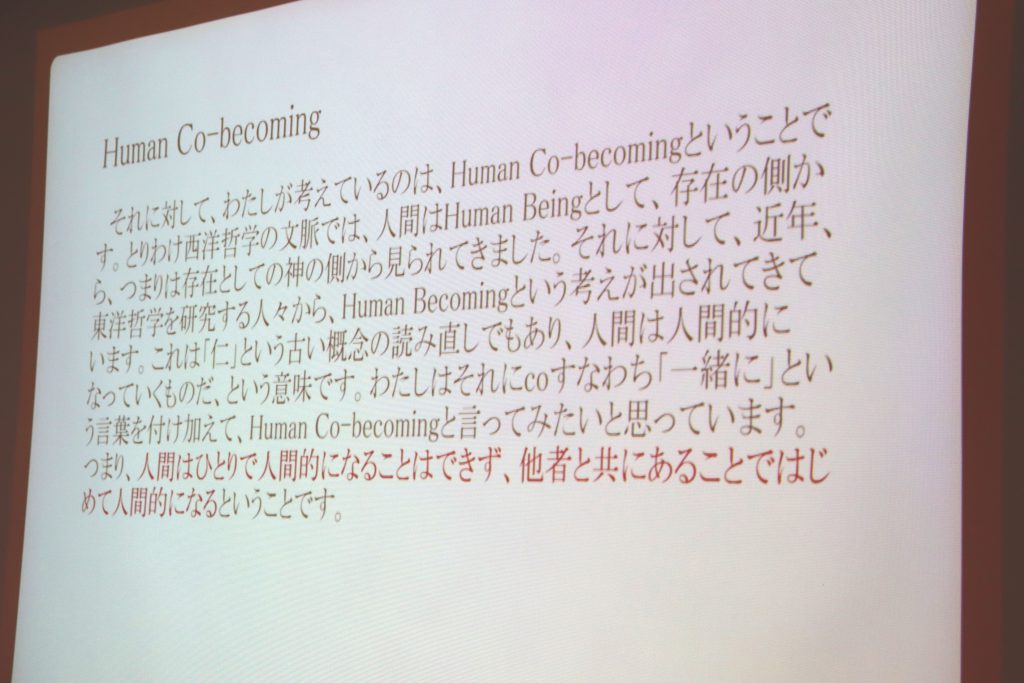
報告:石井剛(EAA副院長)








