2020年8月17日(月)15時より、第5回目の石牟礼道子を読む会が開催された。発表担当者は本ブログの報告者でもある建部良平(EAAリサーチ・アシスタント)で、石井剛氏(EAA副院長)、鈴木将久氏(人文社会系研究科)、前島志保氏(総合文化研究科)、張政遠氏(総合文化研究科)、佐藤麻貴氏(ヒューマニティーズセンター)、宇野瑞木氏(EAA特任研究員)、髙山花子氏(EAA特任研究員)、宮田晃碩氏(総合文化研究科博士課程)、田中雄大氏(人文社会系研究科博士課程)、の計10名が参加した。前回に引き続き『苦海浄土』の第二部「神々の村」の読解を行なった。サブテクストは以下の通りである。
・渡辺京二「解説 『苦海浄土』三部作で要の位置を占める作品」、『新版:神々の村』藤原書店、2014年、pp.395-404。
・「絶対負荷をになうひとびとに」、『石牟礼道子全集』第三巻、藤原書店、2004年、pp.431-444。
・「『苦海浄土』来し方行く末(上野英信との対談)」、同上、pp.511-531。
・「玄郷の世界(中村了権との対談)」、同上、pp.559-570。
発表では「神々の村」というテクストにおいて、「狂い」と「救い」が重要概念になっている点が考察された。最終章である第六章では、1970年11月に大阪で行われた、新日本窒素肥料株式会社の株主総会での場面が際立っている。それは水俣病患者の方々と支援者たちが、壇上で話す社長に一斉に詰め寄り、それぞれの叫びを発するという場面であった。発表者(建部)はその場面において、人々が共に一心不乱に狂うという状況が発生し、それが患者の方々の内面における「救い」の様なものに繋がったのではないかと想像した。それは株主総会の翌日を描いた場面で、患者の方々が「思う存分、狂うた」(『神々の村(新版)』藤原書店、2014年、pp.388-389)と吐露しているその情景に、一種の清々しさを感じたからであった。また、第二章において子をなくした母が、葬儀において見せた振る舞いに対して、「今日どもは、狂え、あんたも」(同上、p.75)とそれを見た人々が内心で発したこと。さらには、石牟礼道子自身が後の対談で、株主総会は一種の晴れの場であった(「『苦海浄土』来し方行く末(上野英信との対談)」、『石牟礼道子全集』第三巻、p.527)と述べていることも、発表者の想像を支えている。そしてこの様な集団的な「狂い」とその後の「救い」の様なものを成立させたものとして歌の意義を考えた。
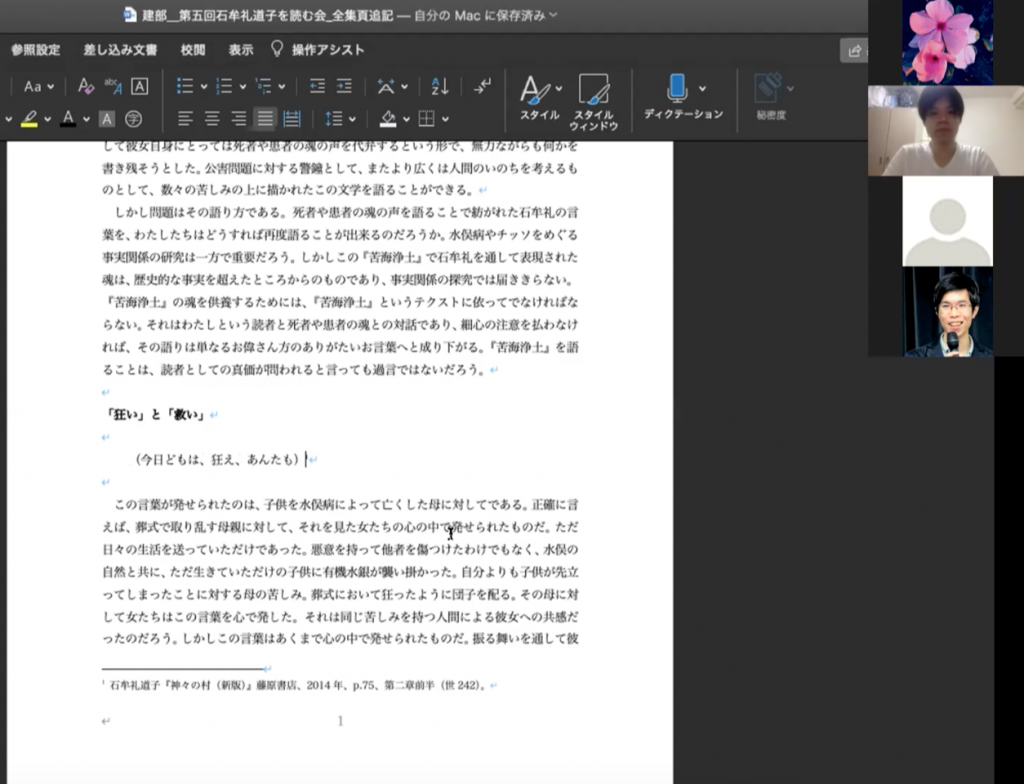
株主総会での詰めよりが始まる前、患者の方々によって歌が詠われた。「人のこの世はながくして…」と始まる歌は、株主総会に来る前に患者の方々が練習していたものであった。その練習は必ずしも順調に進んだわけではないが、歌の旋律や歌詞が持つ力、患者の方々が心のそこに蓄えていた声、そして株主総会の会場というみやこの建物。この三つが複合的に組み合わさることによって、非常に大きな反響と効果をもたらした。書中において度々現れる歌について、発表者は以上の様な解釈を試みた。もちろん、これによって患者の方々が回復し、一切の問題が解決したわけではない。会社側から誠意ある謝罪を受けたわけでもない。その意味での「救い」は起こっていない。これは、「神々の村」というテクストにおいて示された僅かな希望を考えるとするならば、この小さな「救い」しかあり得ないのではないかという考えである。
活発な質疑応答も繰り広げられ、株主総会の場面が持つ芝居的な側面についての指摘や、芝居に伴う人々の振る舞いの持つ力。石牟礼の患者に対する、或いはわたしたちの患者に対する、或いはわたしたちの石牟礼に対する「近さ」や「遠さ」。そして本読書会で度々議論となっている、石牟礼がこのテクストを書いたことそれ自体の意味など、様々な視点がもたらされた。
いずれにしても、『苦海浄土』を語ることは非常に困難な試みである。これまで十分に確認されてきた様に、石牟礼は極めて繊細且つ独特な手法で言葉を紡いだ。それを現在に生きるわたしたちが如何に語るのか。その挑戦にこそ目指すべきところがあると考える。
報告者:建部良平(EAAリサーチ・アシスタント)








