2020年4月1日、本年度第1回目となるEAAイベント、Roundtable Discussion “World Kyōyō-gaku (世界教養学) and Future Liberal Arts”が開催された。COVID-19(新型コロナウイルス)の流行に伴い、東アジア藝文書院(EAA)にとって初の試みとなる、Web会議サービス「Zoom」を使用したオンラインでの開催となった。
実験的な試みということもあり、本イベントはクローズドで行われた。7名の登壇者とEAAスタッフ8名の合計15名がディスカッションに参加した。冒頭で、この4月より新たにEAA院長に就任した中島隆博氏(東洋文化研究所教授)より、本イベントの趣旨についての説明がなされた。「世界教養学」とは、EAAが昨年度より模索してきた新しい学問の形——「世界哲学」「世界文学」「世界人間学」——の変奏形である。「世界」と「教養」、そして「学」という概念を複合(compound)することによって、わたしたちはどのように既存の近代的な学問の枠組みから脱出し、ともに自由に思考することができるようになるか。ラウンドテーブルでは、専門分野の異なる6人の発表者(石井剛氏・大石和欣氏・渡邊雄一郎氏・Jonathan Woodward氏・岡田泰平氏・井上彰氏)がこの挑戦的な問いに対して、各々の見地から応答した。分野横断的な会議が、果たしてオンライン上で可能なのかどうかという不安を皆抱えていたが、結果から言えば、画面越しの関係性は思った以上にフラットかつオープンなものであると感じた。
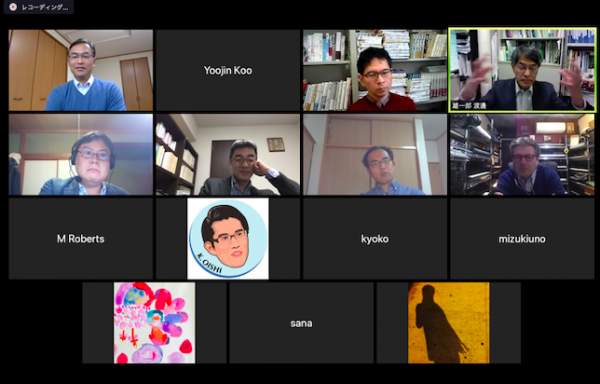
Web会議サービス「Zoom」上に集った参加者たち
まず、石井剛氏(EAA副院長/総合文化研究科教授)が”A Place for Promoting Hope: Redefining Komaba’s Kyōyō”と題した発表を行った。日本の敗戦後、1949年に東京大学教養学部が設置された。戦前の第一高等学校の「教養」精神を引き継いだこの学部は、「駒場」の愛称で親しまれ、1990年代に全国各地の大学で教養課程が廃止されたのちも、個別の専門領域を横断するリベラル・アーツの在り方を模索する最先端の現場たることを目指してきた。1949年の設置当時、教養学部は College of General Educationと英訳された。その後1983年にはCollege of Arts and Sciencesと名称を変えたが、日本語名である「教養学部」は変更されず現在まで維持されている。石井氏は、このことを受けて「教養」という概念によって意味されるものは固定されておらず、それ自身が”develop”(展開)するものであると述べた。さらに、中国哲学で議論されている「野」から「文」へ、あるいは「人」から「仁」へ、という変容のプロセスについて触れた上で、「教養」もまた、ある状態から別の状態への変容を可能にする場として捉えることができるのではないか、と提言した。この変容は、ジャック・デリダによる“Professor”の定義に見られるように、世界に向けて発信する(profess)という意思こそが重要であり、その意味において、変容とは決して独りきりで成し遂げうるものではなく必ず他者を必要とする(co-becoming)と石井氏は述べた。
続いて発表した大石和欣氏(総合文化研究科教授)もまた、石井氏と同様、日本における「教養」概念の変遷に言及しつつ、その新たな展開の可能性を探った。「教養」とは1900年代、主に高等教育の現場で西洋から輸入された概念である。しかし、駒場の教養教育で追求されている「教養」とは、決して西洋における「教養」概念(例えばドイツ語における“Bildung”)を無批判に前提としているわけではない。グローバル化する社会において、わたしたちは複数の困難な課題に晒されている。このような状況下で「教養」を考える際、従来の人間中心主義は再考される必要がある。しかし、このことは人文学(humanities)の遺棄を決して意味しない。より重要なのは、社会科学や自然科学といった、他領域の学問との組み合わせである。これについて中島氏は、“personal”という概念の重要性を主張した。中島氏によれば“personal”とは、public(公)とprivate(私)という二項対立に属しない領域のことを指す。「このもの性」(今、ここにあるということ)に立脚しつつ、世界と関わる在り方を模索することこそが、「世界教養学」に求められているのではないかと述べた。
次に渡邊雄一郎氏(総合文化研究科教授)が、自身の専門分野である植物分子生物学の見地から、「世界教養学」の展開とその可能性について述べた。渡邊氏は人間と自然界という二項対立に疑問を投げかけた上で、生物学における還元主義(複雑な構造を、分解可能なレベルにまで還元して考える態度)の限界を指摘した。例えば、ヒトは約2万個の遺伝子を持つことが明らかにされたが、そのことによって、人間はなぜこのような構造を持っているのか、という問いに答えることはできない。より重要なのは、得られた膨大なデータを用いて何をどのように考えるかということであり、そのためには、分子・個体・生態系という、別の階層とされるもの同士をまたぐ視点が必要であると渡邊氏は論じた。こうした視点の獲得は、人間と自然界を二項対立的に捉える西洋近代的な発想からの脱出を伴う。これに対し中島氏は、哲学者のトマス・カスリス氏による“detached knowledge”(観察者が観察対象を自らと切り離し、客観的な分析を試みることによって得られる知識)と、“engaged knowledge”(観察者と観察対象という二項対立ではなく、事象そのものの中に自ら飛び込み、巻き込まれることによって得られる知識)という概念を紹介した。渡邊氏の目指すものは、カスリス氏で言うところの“engaged knowledge”であり、自然科学と人文学を同時に考えるような試みであると指摘した。
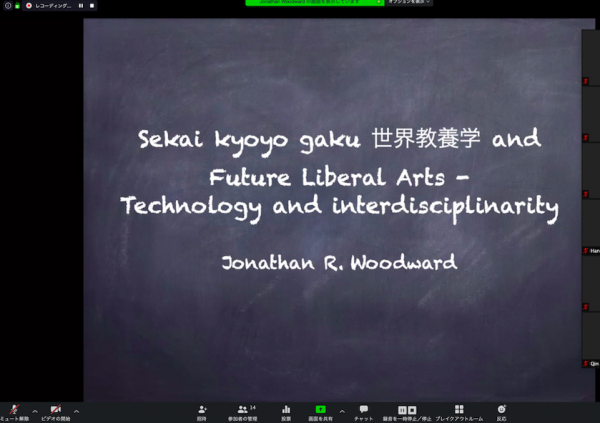
発表者のスライドを画面共有しながら議論するシーンも。画像はウッドワード氏の発表スライドから。
コーヒーブレークのあと、まずジョナサン・ウッドワード氏(総合文化研究科教授)が技術(Technology)と領野横断性(interdisciplinarity)をキーワードとした発表をした。自分自身がDr. Philを取得するまでに化学を中心に受けた高等教育の経験を語ったあとで、ウッドワード氏はイギリスでの分野横断型プログラム(i-science)の取り組み、そして現在PEAKで、化学を通して様々な学生の研究指導をしている状況を説明した。質疑では、科学技術の時代に、未来の可能性ではなく希望をどう豊かにできるのか、といった問いや、方法論に基礎を置いた教育とどのような学生を育てたいのかといった事柄についてやりとりがなされた。
それから、岡田泰平氏(総合文化研究科准教授)が発表をした。エドワード・ハレットの『歴史とは何か』(1961)の引用からはじめた岡田氏は、「近代の超克」とは違う形での「普遍」の可能性を探る中島氏の姿勢にも言及しつつ、「普遍」を考えるために、まず実際の現場や具体的な事例に目を向けることの意義と、様々な差異に目を向ける重要性を、地域研究を専門とする歴史学者の立場から主張した。これについては、現実の複雑さに具体的にどう対応するのかといった問いや、AIのシンギュラリティが到来した後に誰が歴史を書くのか、といった問いが投げかけられた。
最後に、井上彰氏(総合文化研究科准教授)が発表した。井上氏は新しい教養学のために必要な視点として、個人中心ではなく、チームのためのリベラル・アーツ教育の必要性と、人文学でも共同研究をとおして共同論文を執筆する形を提案し、知識中心の教育からの転換と、異なる人たちとの共同が求められていることを述べた。これに対しては、具体的な組織の実現可能性や、人文学におけるチーム型研究の前例について質問があがり、関西人のノリのよさやUKでのティータイム、パブ文化といったものの果たす役割が言及された。

登壇者7名によって、画面越しに活発なディスカッションが繰り広げられた
おおよそ定刻になったあと、参加者が一言ずつコメントを述べ、閉会した。全体として、「世界教養学」というよりも「教養学」をめぐる議論になっていたことが印象的であり、それは駒場の現在の状況を反映していたからではないかと思う。
EAAではじめてZoomを用いたイベントだったが、発言者以外はミュート機能を用いるといったこともスムースに準備された。終始画面に自分自身を映している人もいれば、発言するときだけ顔を出す人、終始顔を出さない人もいた。途中で中座する人もいた。機材的に大きなトラブルはなかったように感じたが、画像や音声から判断するかぎり、それぞれの機材動作環境はそれなりに異なっていたようだ。物理的におなじ空間に一緒にいないため、自分の声が相手にどのように伝わっているのかわからず、また相手の声の聴取に集中する必要があり、かぎられた情報から相手の気配を読み解くために、独特の緊張感や疲労感もあったと思う。休憩がもうすこしあってもよかったかもしれない。Zoomにかぎらず、遠隔でのコミュニケーションについては、試行錯誤を繰り返し、よりよいかたちを手探りすることになりそうである。しめくくりに中島氏が言ったように、生のかたち(form of life)を変える次元から、こうした探求をするための(ときにはお茶を飲みながらゆっくりと語る)プラットフォームは今後いっそう必要となるだろう。
報告者:崎濱紗奈・髙山花子(EAA 特任研究員)








