さる2019年12月18日、駒場キャンパス101号館11号室で、EAA招聘教授(北京大学歴史系準教授)昝涛氏を迎え、「近現代中国人のみたトルコ」を題として講演を行なった。EAAの石井剛氏(副院長、総合文化研究科教授)がモデレーターを務めた。
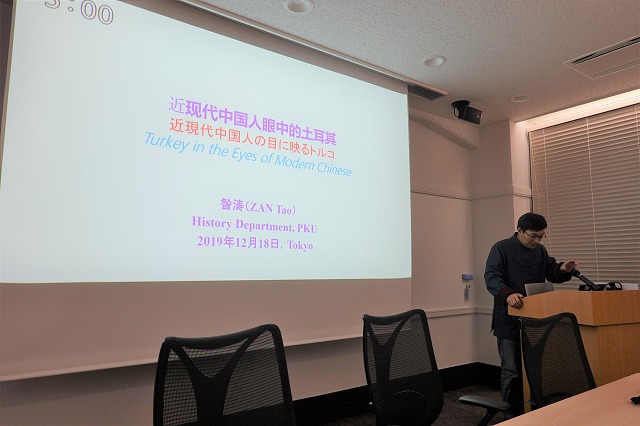
はじめに、昝氏は今回の講演は具体的な歴史的事実に基づく近代以降中国のトルコに対する認識が主題となると説明した。現代トルコの源流とされる「突厥」は、元来ある部族政権の呼称であったが、突厥可汗国の影響の大きさと情報の不足のためか、ペルシャ・アラブ人の認識において「突厥」はインナーアジア(Inner Asia、内陸アジア)遊牧諸民族の総称となり、さらに西欧へと広がった。その後、いわゆるチュルク系の各部族や民族の自己認識もかなりこれに影響された。しかし、古代中国王朝は突厥各部族とより頻繁に接触し、情報システムもより発達していたために、古代中国語で書かれた史料には精確な記録が残されており、19世紀末期以来解読されるようになった古代チュルク語資料と互いに証明し合えるものも多いが、残念ながら現在の学問界に十分に反映されていない状況である。
近代になると、オスマン帝国は1789年から一連の近代的改革を行なったが、世界情勢の変動も背景に衰退を示し始め、帝国の支配力の弱体化から領土問題や民族問題が相次いだ。19世紀末の康有為などの中国知識人はこの状況にいたく同情した。時代が下ると、中国では1905年に日露戦争があり、対してトルコでは1908年の青年トルコ人革命が起こりオスマン帝国の憲政民主制度が復活したことを受け、中国人にとってオスマン帝国としてのトルコは政治改革と排満革命の参考にもなった。1920年代、ムスタファ・ケマルによる革命を経たトルコはまた、後進民族が帝国主義に抵抗し、独立を成し遂げ、近代的国家を建設する典型として見られた。トルコは中華民国の知識エリートの政治言説によく取り上げられ、近代化(modernization)の視点からのトルコ研究も始まりを告げた。一方、階級分析を堅持する左翼知識人はトルコ政権のブルジョワ階級性と世界範囲内の共産主義革命の情勢から出発し、トルコに対して選択的に肯定し、批判した。
昝氏は、このような経緯で近代以降の中国におけるトルコのイメージの大半は、相手との直接な経験と了解がない状況で形成されたと指摘した。しかしそこから同時代の中国人の民族国家や世界情勢への問題意識、個人の意見と立場が見られる。今回の講演で氏はいくつかのテキストを精読を通じ、その特徴を明らかにした。さらに昝氏は改革開放以来のトルコ研究、特に近年のトルコやオスマン帝国に関する翻訳書や一般向けの本の流行を顧み、その背後に中国の国力の上昇、西欧ではない世界への関心の高まり、営利目的のプロモーションなどの思想史的原因があると説明した。
質疑では参加者からコメント・質問が寄せられ、特にトルコの近代化におけるイスラム教の役割について議論が活発に行われた。昝氏は近代トルコのイスラム教問題と、近代中国における儒教を含む「伝統」問題との間に類似点が存在すると見て、具体的に三つの傾向性があるとした。ムスタファ・ケマルなどの近代トルコ国家の指導者は基本的にイスラム教を近代化の反対側と見て、宗教を政府の管理の下に置いたが、イスラム教は国民アイデンティティーにもつながるため、トルコとギリシャとの住民交換の際も民族を決める基準(反面では浄化でもあるが)として機能した。さらにイスラム原理主義的思想も消えておらず、近年も保守思想の台頭が目立つようになっている。それに対しては石井氏が日本近代の国家神道問題を提起し、世界の(非西洋の)知識人は類似した問題に直面しているのではとコメントした。
昝氏の講演でも触れたように、中国のトルコ研究は「近代化」という目標から始まったものである。これには時代的制限がある一方、「近代化」そのものへの追究は今でも意義が大きい。東アジアの諸文明の近代化に対する比較研究は豊富な成果を出しており、トルコという「非西洋」かつ「非東洋」的ケースは近代化の多様性や未来の可能性を提示してくれるものといえよう。
報告:胡藤(EAA RA)








