2019年7月26日、東洋文化研究所にて、EAAフォーラム「世界文学としての東アジア文学」が開催された。来日中の張旭東氏(北京大学・ニューヨーク大学教授)のほか、武田将明氏(東京大学総合文化研究科准教授)、鈴木正久氏(東京大学人文社会系研究科教授)が登壇し、魅力的なプレゼンテーションを行った。EAAフォーラムは、東アジアにおける新たな「知」の模索と発信を目的として、新しい「東アジア学」を徹底的に議論する場を創出することを目指して開催されている。去る23日に開催されたEAAフォーラム「東アジアから考える世界文学と世界哲学」に続き、今回のフォーラムにおいても、登壇者および参加者の積極的な参加を得て、上述の目的を果たすことができた。

三氏はそれぞれ、“Remarks on the End of Modern / National Literature and the Rise of World Literature in East Asia”(武田氏)、“How or Why are Bei Dao’s poems World Literature”(鈴木氏)、《“编年”与“诗史”——鲁迅晚期杂文再解读》(張氏)と題して発表を行った。武田氏は、日本の近代化と文学の関係を参照しつつ、英語やフランス語といった「ユニバーサル」な言語からの翻訳作業を通して、「日本語」という言語が「ローカル」なものから「ナショナル」なものへと変容していったことに言及した。また、近代小説という文学形式が、ナショナルな言語としての「日本語」と相補的に発展してきたことも指摘した。しかし昨今、こうしたナショナルな言語、あるいはナショナルな文学というものは衰退傾向にある。では、文学は「世界文学」へと移行していくのだろうか?ここでまず考察すべきなのは「世界」とは何を指すのか、という問いである。武田氏は小説家のAlpana Mishra氏を例に挙げつつ、事態の複雑さを例示した。Mishra氏は、ヒンディー語で小説を執筆し、デリー大学で教壇に立つ際には英語を使用し、さらにロシア語で書かれた文学に親しんできたという言語経験を持つ人物である。文学の「世界」性とは、Mishra氏に見られるような、言語経験の多重性・多数性から考察する必要があるのではないか、と武田氏は指摘した。
続く鈴木氏の発表では、現代中国の詩人Bei Dao(北島)の「世界」性が論じられた。Bei Daoの作品(詩)は、世界的に広く読まれている。しかし、中国内部の読者を通して見えるBei Dao像と、中国外部から見るそれとの間には、ズレが生じているということを鈴木氏は指摘した。その最大のポイントは「政治」である。Bei Daoの詩には、自身の中国における「政治」経験(とりわけ文化大革命の経験)が、深く刻印されている。しかし、こうした経験を翻訳する際には、必ず困難が伴う。場合によっては、こうした経験は翻訳されず、結果としてテクストが「脱−政治」化されてしまうこともあり得る。しかし鈴木氏は、Bei Daoにとって言語とは、「政治」とは切り離すことができないものとしてあることを指摘する。したがって、Bei Daoの作品の「世界」性を考える際、翻訳され得ない、いわば翻訳の「剰余」(あるいは「はみ出し」)を考える必要がある。
続く張氏の発表では、晩年の魯迅に焦点が当てられた。張氏は、この時期の魯迅が執筆した「杂文(雑文)」という形式に着目した。「杂文」は、「文学」なのかそうでないのかというカテゴリ化、あるいは境界線を引こうとする欲望そのものを拒否する。「杂文」は、個人的なことから社会的なことまで、あるいは、実存主義や存在論といったあらゆる哲学的な視点を複雑に抱え込んでいる。また、そこにはブルジョワ的であるとか、プロレタリアート的であるとか、はっきりと階級的に定められた視点はない。しかし、その複雑性ゆえに「杂文」は、政治的であり、歴史的であり、なおかつ美的であることが可能である。張氏は、「杂文」とは、魯迅が「世界」という現実そのものと格闘した結果生み出された「世界文学」であると指摘する。それは、「世界文学」たろうとする自己意識によって実現されるのではなく、結果として「世界」性を帯びるということである。こうした複雑性を、張氏は「詩史」という概念で言い表した。

三氏の発表を受けて、会場からは以下のような多岐にわたる質問が提起された。「東アジア文学」という時、その内部にある個々の経験を、どのようにすればつなぎ合わせることができるのか?英語帝国主義的にではなく、なおかつ「東アジア」を本質化する形ではなく、いかに「世界文学」を語ることができるのか?また、「世界文学」を語る際、「歴史」はどのように関係してくるのか?あるいは、「文学」において「政治」とは何を指すのか?これらの質問に対する三氏の応答からは、次のような暫定的な答えが見えてきた。「世界文学」という潮流、あるいはそこにおける「東アジア文学」への注目は、文学作品が資本主義市場における「商品」であるという側面を映し出してもいる。しかし、そのように制度化された「文学」というあり方そのものを打ち破る可能性も、同時に内包されている。その際重要なのはやはり、定義不可能な領域への着目である。「文学」とはこうでなければならない、あるいは「世界」とはこのようなものである、といった思考法によっては捉えることのできない領域こそが、「文学」を解放する鍵を握っている。それは例えば、“minor literature”(「小説」=小さなお話)と呼ぶことができるかもしれない。言語が無効化されつつある(あるいは無効化されて久しい)昨今、「文学」を再考することが極めて困難であるなか、それでもなおその「解放」の可能性を多方面から模索する濃密な時間となった。
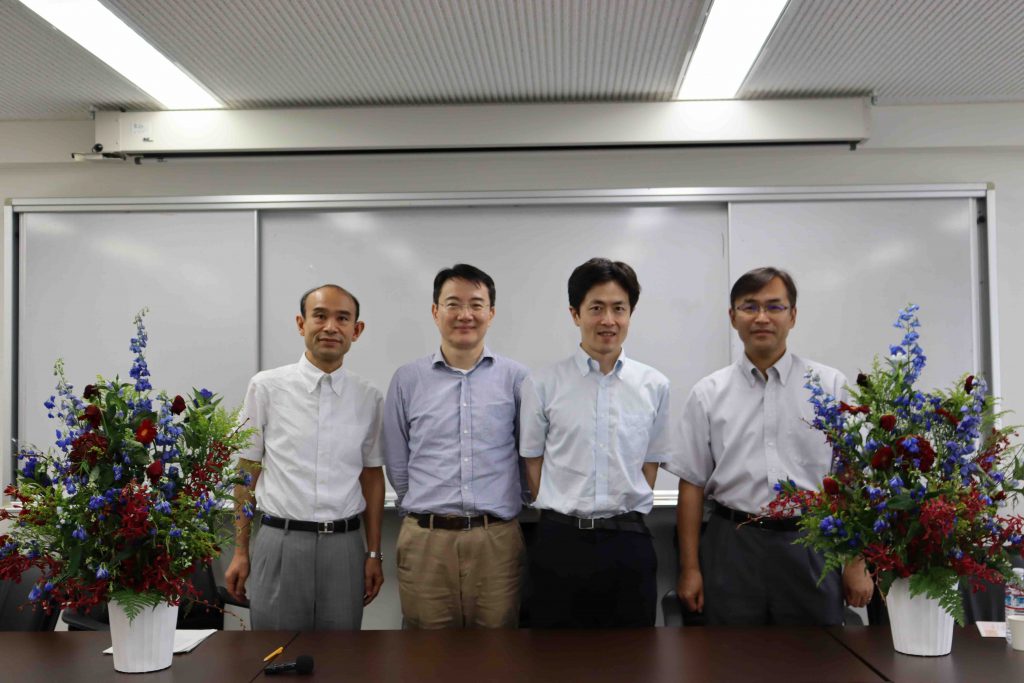
報告者:崎濱紗奈(EAA特任研究員)








