2020年12月11日、国際シンポジウム「ライシテから「分離主義」へ——1905年12月9日法問題からみるフランス社会と共和主義」がオンラインで開催された。本シンポジウムでは、伊達聖伸氏(東京大学准教授)、エマニュエル・オーバン氏(ポワティエ大学公法学教授)がパネリストとして登壇し、ピエール=イヴ・モンジャル氏(トゥール大学公法学教授)が司会、金塚彩乃氏(弁護士・慶應義塾大学法科大学院非常勤講師)が通訳兼解説を務めた。なお、オーバン氏を招いたEAAでの学術企画は今回で2度目となる。2019年12月の1度目の様子については、白尾安紗美氏による「EAAセミナー『フランスの公共空間における宗教的中立性の拡大:新しいライシテに向かって?』報告」を参照されたい。
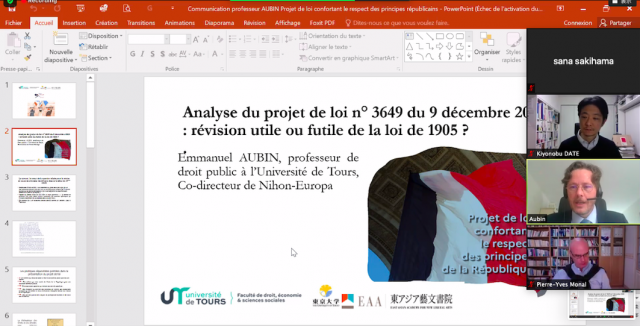
本企画の趣旨は、2020年12月9日にフランスで閣議提案された「共和国原理強化」法案に、宗教学と公法学の観点から分析を加えることにあった。フランスでは1905年12月9日に「政教分離法」が成立し、共和国は以後「ライシテ」を国是に掲げてきた。特に1990年代以降、ムスリムの社会統合が課題になるにつれ、ライシテは共和国の原理として一層強く意識されるようになっている。だが近年では、フランスがテロの標的となり「過激派」の台頭が問題視されるなか、共和国の原理や統合が「分離主義」に脅かされているという見方が広がっている。そこで、マクロン大統領は2020年10月2日、政教分離法が制定された12月9日に新しい法律を提案すると発表し、今回の閣議提案に至ったのである。
シンポジウムでは、宗教学者の伊達氏が最初に登壇し、「1905年12月9日法——フランスのライシテの功罪」と題した報告を行なった。この報告の目的は、1905年法と2020年法案の文脈と特徴を比較することにある。第一に、伊達氏は1905年当時と2020年現在では、ライシテの課題が変化していると指摘した。1905年当時のライシテは、私的領域での宗教の自由の保障を重視していたが、20世紀後半以降は、むしろ公的領域での宗教の役割の承認に焦点が移動している。また、1905年当時にはカトリシズムとの関係が争点だったが、今日のライシテはイスラームとの関係において語られている。さらに、1905年当時のライシテは左派の原理だったが、1990年代以降は右派の原理としても機能しているという。
伊達氏は第二に、最近のライシテは、20世紀初頭の政治家コンブの戦闘的なライシテに近似しているのではないかと指摘した。10月16日の教師斬首事件の後、ダルマナン内相は「分離主義」の温床とされる施設や団体に閉鎖や解散を命じたが、コンブも1902年から1904年、修道会を「共和国の敵」として、大規模な修道会の解散や修道士の追放を行った。宗教施設の閉鎖という国内政策に加え、置かれた外交状況においても政教分離法制定当時と現在には類似点が見られるという。実際、コンブは司教任命権と「ローマ問題」をめぐって教皇庁と対立し、1904年には外交関係を断絶しているが、マクロン大統領も近年、イスラーム保守層を支持基盤とするトルコのエルドアン大統領と対立を深めている。
最後に、伊達氏はマクロン大統領のライシテの二面性を指摘した。たしかに、マクロン大統領のライシテには「自由」を尊重するところがある。例えば、フランスでは従来、特殊な共同体への帰属は共和国の普遍主義と相容れない「共同体主義」として批判されてきたが、マクロン大統領は特殊な共同体への帰属意識と共和国への帰属意識は両立可能としている。しかし、マクロン大統領のライシテには「管理」を重視するところもある。実際、マクロン大統領は「共同体主義」に代えて「分離主義」を敵と名指し、共和国の統合を目指して教育への公的管理を強めようとしているし、国内における外国のイスラーム指導者の影響力が懸念されるなか、「フランスの」イスラーム指導者を養成しようとしている。
次に登壇した公法学者のオーバン氏は、「2020年12月9日法案の分析--1905年法の改良か改悪か」と題した報告を行った。この報告の目的は、2020年法案の内容と成立過程の検討にある。オーバン氏は第一に、2020年法案が近年の共和国原理の問い直しの延長線上にあることを指摘した。フランスでは2000年代以降、特に「過激派」に対する危機意識の高まりとともに、共和国原理の再認識が生じている。例えば、2003年の「スタジ委員会」ではすでに、「共同体主義」により個人の自由や男女平等が侵害されているという認識が示されている。この文脈の延長で、現在では「分離主義」が共和国の脅威として名指されているのであり、ライシテを権利だけでなく義務も与える共和国原理とする見方も広がっている。
オーバン氏は第二に、2020年法案の内容を紹介した。まず、この法案自体には「分離主義」や「イスラーム主義」の文言が含まれていないことが指摘された。ただし、法案に添えられた事前評価書にはこれらの文言が含まれている。次に、この法案ではライシテに関連する既存の法律が修正されていることが指摘された。例えば、法案の第30条では1901年の結社法、1905年の政教分離法、1907年1月2日法に修正が加えられているし、宗教社団の地位を定めた1905年法の第19条は、法案の第35条などにより大幅に書き換えられることになる。これらの修正では、宗教団体の財源の透明性を高め、国外からの不透明な資金流入を防ぐなどして、国家による宗教団体の管理を強化することが目指されているという。
最後に、オーバン氏は2020年法案の成立過程における国務院の役割を強調した。2020年法案はたしかに、戦闘的なライシテを掲げる政治の主導で作成されたが、その成立過程では国務院という法の機関が介入しており、法案の当初の戦闘的性格を幾分か和らげる役割を果たしている。例えば、当初の法案では犯罪の「教唆」や「人の尊厳」の侵害に対する罰則が定められていたが、国務院はこれらの曖昧な概念を刑罰の法的根拠とするのは不適当と判断して修正を求めている。また、当初の法案は在宅教育(ホームスクール)を「分離主義」の温床として禁止しようとしていたが、国務院はこれを教育の自由という憲法原理に反すると判断し、法案では最終的に特定の理由があれば在宅教育を認めるとしている。
伊達氏とオーバン氏の報告には、共通点と差異の両方をみることができる。まず、2020年法案の分析を同じ目的に掲げながらも、伊達氏が1905年当時と2020年現在を比較し、政治の次元での言説や政策を分析したのに対して、オーバン氏は2020年現在に焦点を絞り、法の次元での法案解釈や法案成立過程の分析を行った。次に、この観点の違いに加えて、強調点の置きどころにも違いが見られた。実際、マクロン大統領のライシテは「戦闘的なライシテ」に近づいており、そこでは「自由」と「管理」のうち後者が前景化していることを強調した伊達氏に対して、オーバン氏はむしろ、政治の掲げた「戦闘的なライシテ」が、国務院の冷静な法的判断により穏健化するかたちで法案にまとめられていることを強調した。
登壇者の報告後には、フロアからいくつかのコメントや質問が寄せられた。例えば、増田一夫氏(東京大学名誉教授)は、フランスは普遍主義的な「国民」概念を、ドイツは特殊で民族的な「国民」概念を伝統的に掲げてきたが、現在の移民政策や社会統合の様子をみると、逆説的にもドイツのほうが多宗派共存に成功しているように見えると指摘した。さらに、10月時点で複数の施設を閉鎖し、団体を解散することができたのに、2020年法案でそのような可能性を一層強化する必要はあったのか、2020年法案は欧州レベルの法規定においてどのように位置づけられるのかという質問を投げかけた。以上、2020年12月11日に開催された本シンポジウムでは、2020年12月9日法案というフランスのライシテに関わる最新の問題がいち早く議論された。
田中浩喜(東京大学大学院博士課程)








